神経心理学研究室
人間の心を、脳という視点からとらえる。それが神経心理学の原点です。
慶應義塾大学医学部精神神経科の神経心理学研究室の最初のテーマは、前頭葉機能障害と記憶障害でした。1980年頃のことです。
当時の神経心理学の中心であった方法論は、脳損傷者の臨床症状の精密な分析で、我々もこれを踏襲し、症状を客観的に評価する方法を開発し、さらにそれを活用したデータを分析することで、脳機能のメカニズムを探究してきました。現在、前頭葉機能検査として全国で広く活用されている「KWCST (慶應式ウィスコンシンカード分類検査)」は、当時我々が開発したツールの一つです。
1990年代に入り、functional Neuroimaging等の導入により、神経心理学の方法論は急展開し、対象もあらゆる精神症状に、さらには健常者の脳機能にまで拡大しました。そして我々もこのテクノロジーを最大限に活用しつつ、かつ、精密な臨床症状分析を軽視することなく、研究を続けています。
研究会は、原則第二、第四月曜日の夜に開催しています。
以下、我々の研究内容をご紹介していきます。(順次更新します)
伝導失語に認められるarticulatory-based phonemic paraphasia:交叉性失語を通して明らかになった音素から構音への変換の障害
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科)
Kawashima H, Funayama M, Inaba Y, Baba M. Articulatory-based Phonemic Paraphasia in Conduction Aphasia: A Dysfunction in Phoneme-to-Articulation Conversion Uncovered Through Crossed Aphasia. Cogn Behav Neurol. 2024. doi: 10.1097/WNN.0000000000000371.
【背景】Phonemic paraphasiaは伝導失語の特徴的な症状の一つです。従来, 日本語では音韻性錯語と訳されたように, 音韻表象の障害が原因とされてきました.たとえば, 伝導失語では「ゆきだるま」を「ゆきでるま」と言い間違えるだけではなく, 書字でも同様に書き間違えることが音韻表象障害説を支持してきました.しかし一方で, 伝導失語の特徴の一つである接近行為(たとえば, 「ゆきで, ゆきでる, ゆきでるま, ゆきだるま」)の存在は, 音韻表象が保存されていることを示唆しています.Luria (1976)やArdila(1992)は, 伝導失語に出現するphonemic paraphasiaには音韻表象の障害に起因する場合と, 音素を構音の変換する障害(articulatory-based phonemic paraphasia)に起因する場合があることを提唱してきました.後者の障害は観念運動失行の特性を有し、音の置換と正答へ至る接近行為が特徴であるとされています.また, 肢節運動失行と類似して音の歪みを特徴とする発語失行とは区別されています.しかし, 理論はあるものの, 実際の症例での記載はありませんでした.このギャップを埋めるために, 本報告では, 側頭-頭頂葉梗塞による交叉失語によりarticulatory-based phonemic paraphasiaを呈した61歳の右利き男性の症例を記載しました.
【方法】伝導失語におけるarticulatory-based phonemic paraphasiaの存在を確認するため, 本症例の失語が以下の条件を満たすことを諸検査で検討しました. すなわち, 1) 他のタイプの錯語が存在せずに phonemic paraphasiaが頻繁に出現する; 2)発話失行がない; 3) 口頭言語ではphonemic paraphasiaを認めるものの, 書字によって音韻表象が保存されていることを確認できる; 4) 音韻表象をあまり必要としない「か」や「ひ」など最小言語単位の反復においても口頭言語ではphonemic paraphasiaが出現すること, の4つの条件です.1) 2) は伝導失語であること, 3) 4) は音韻表象が保たれた中でphonemic paraphasiaが出現することを明らかにする条件です.
【結果】本症例に行った諸検査からは, 1~4の条件をすべて満たすことが確認できました.象徴的であったことは, 本症例はphonemic paraphasiaを呈したり, 発話が困難な音や単語に対して, ひらがなで正確に空書をしたり書き留めたりしていたことでした.本症例はこの症状を, 「頭では音は分かっているけど, 口の形にならない」と叙述していました.これらの結果は, 本症例では音韻表象がほぼ正常に保たれていることを示唆しています.
【考察】本症例のphonemic paraphasiaは音素から構音への変換障害を基本とするものであり, 音韻表象の障害や発話失行によるものではないと考えられました.交叉性の伝導失語においてこの特徴が明らかになったことは, 言語機能の通常ではない分離, すなわち, 右側頭-頭頂葉皮質での音韻表象機能と左半球の発話運動エングラム間の大きな分離に起因する可能性が考えられます.しかし, われわれは左半球損傷による典型的な伝導失語の症例においても, このタイプの音韻性錯語が存在する可能性があると考えています.
(船山道隆、2026.1.1.)
統合失調症における自己主体感の変容と心拍の関係:内受容感覚シグナルの視点から
是木明宏 (慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 特任講師)
Koreki A, Terasawa Y, Nuruki A, Oi H, Critchley H, Yogarajah M, Onaya M. Altered sense of agency in schizophrenia: the aberrant effect of cardiac interoceptive signals. Front Psychiatry. 2024 Sep 25;15:1441585. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1441585.
本研究は、統合失調症患者において循環動態が自己主体感(Sense of Agency)に悪影響を及ぼす可能性を示唆しました。
身体内部の情報処理に関わる内受容感覚は、感情形成のみならず、近年注目されるMinimal-self、すなわち自己主体感や自己所有感の形成にも深く関与していることが明らかになってきました。たとえば、先行研究(Koreki et al., Sci Rep. 2022)では、健常者におけるIntentional binding課題で測定された自己主体感は個々の内受容感覚の精度と関連し、特にその精度が高い人では内受容感覚シグナルの一つである心拍が自己主体感を増強させる可能性が示唆されました。
一方、統合失調症患者は内受容感覚の精度が低いことが報告されています(ex. Koreki et al., Schizophrenia Bulletin Open 2021)。また統合失調症の中核症状として自己主体感の異常が考えられており、これらの知見を踏まえると、患者における内受容感覚の低下は自己主体感に悪影響を及ぼしている可能性が考えられました。
そこで本研究では、Intentional binding課題を用いて自己主体感を評価し、心拍が自己主体感に与える影響を健常者と統合失調症患者で比較検討しました。その結果、健常者においては心拍が自己主体感を増強させる一方、統合失調症患者では悪影響を及ぼしている可能性が示唆されました。本知見は、統合失調症の病態生理解明の一助となると考えています。
(是木明宏、2025.12.1.)
反芻思考に関連する脳ネットワーク動態の変化
―― 認知行動療法と薬物療法の比較研究 ――
片山奈理子 (慶應義塾大学 保健管理センター 専任講師・医学部 精神・神経科学教室兼担講師)
Katayama N, Shinagawa K, Hirano J, et al.
Dynamic neural network modulation associated with rumination in major depressive disorder: a prospective observational comparative analysis of cognitive behavioral therapy and pharmacotherapy.
Translational Psychiatry, 2025; 15:267.
DOI: 10.1038/s41398-025-03489-y
■ 背景
うつ病の主要な認知的特徴である反芻思考(rumination)は、否定的な思考内容を反復的に想起し続ける傾向を指し、症状の慢性化や再発の重要な要因とされる。近年の神経画像研究により、反芻は自己参照的思考に関与するデフォルト・モード・ネットワーク(Default Mode Network: DMN)の過活動と密接に関連することが明らかになっている。しかし、主要な治療法である認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy: CBT)および薬物療法が、反芻関連の脳ネットワーク動態にどのように作用するのかは十分に解明されていなかった。
■ 方法
本研究では、うつ病患者79名および健常対照者56名を対象に、治療前後(16週間)の安静時機能的MRI(resting-state fMRI)を取得し、脳活動の時間的変動を隠れマルコフモデル(Hidden Markov Model: HMM)により解析した。うつ病群は、ベックのマニュアルに基づく16回の個人CBTを受けた群と、標準的な抗うつ薬による薬物療法群に分類した。反芻の重症度は反芻反応尺度(Rumination Response Scale: RRS)、抑うつ症状はGRID-HAMDを用いて評価した。HMMにより抽出された12の脳状態について、各状態の出現頻度、持続時間、遷移確率を算出し、治療法および時間の要因による変化を検討した。
■ 結果
うつ病群では、DMNの出現頻度および持続時間の増加、遂行機能ネットワーク(Central Executive Network: CEN)の活動低下が認められた。DMNの出現頻度はRRSスコアと正の相関を示し、反芻傾向が強いほどDMN優位の脳状態の発生頻度が高いことが示された。
治療効果の比較では、CBT群においてDMNの出現頻度の有意な低下とDMNからCENへの遷移確率の上昇が観察され、脳内ネットワークの動的柔軟性の回復が示唆された。一方、薬物療法群では、DMN活動が後部帯状回を中心とする後方領域へ再構成される変化がみられ、CBTとは異なる神経適応様式が確認された。
■ 考察
本研究は、反芻思考に関連する脳ネットワークの時間的動態(network dynamics)を定量的に検証した初の報告であり、CBTと薬物療法が異なる神経機構を介してうつ病を改善する可能性を示した。
CBTは、認知再構成や行動活性化を通じてDMNの過活動を抑制し、実行系ネットワークへの適応的切り替えを促進することにより、反芻傾向を軽減すると考えられる。これに対し、薬物療法は神経伝達物質レベルの調節を通じて、脳内活動の局所的再編成を引き起こすと推定された。
両治療の効果は臨床的改善としては類似していても、脳ネットワークレベルでは異なる経路によって達成されることが示唆され、この知見は、今後の個別化治療戦略および神経指標に基づく治療選択の発展に資するものであると考える。
(片山奈理子 2025.11.1.)
生体PETおよび死後脳サンプルにより明らかにされた老年期気分障害におけるタウ病理
黒瀬心 (国立精神・神経医療研究センター病院 臨床検査部 神経病理分野 上級専門修練医)
Kurose, S., Moriguchi, S., Kubota, M., Tagai, K., Momota, Y., Ichihashi, M., Sano, Y., Endo, H., Hirata, K., Kataoka, Y., Goto, R., Mashima, Y., Yamamoto, Y., Suzuki, H., Nakajima, S., Mizutani, M., Sano, T., Kawamura, K., Zhang, MR., Tatebe, H., Tokuda, T., Onaya, M., Mimura, M., Sahara, N., Takahashi, H., Uchida, H., Takao, M., Meyer, J., Higuchi, M., Takahata, K. Diverse tau pathologies in late-life mood disorders revealed by PET and autopsy assays. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. 21(6), e70915, 2025.
老年期気分障害は、認知症の前駆状態として発症する可能性が指摘されています。しかし、双極性障害やうつ病といった老年期気分障害の神経病理学的基盤はまだ十分に明らかになっていません。
われわれは、老年期気分障害がアルツハイマー病(AD)や非ADタウオパチーの前駆段階として現れるかどうかを、生体脳および死後脳を用いて検証しました。具体的には、2019年から2023年にかけて、52例の老年期気分障害患者と47例の年齢・性別を一致させた健常対照者を対象に、タウPET(18F-florzolotau)およびアミロイドPET(11C-PiB)を実施しました。さらに、208例の剖検症例を対象に、臨床病理学的関連解析を行いました。
解析の結果、老年期気分障害患者は健常対照と比べて有意にタウPETおよびアミロイドPET陽性率が高く、タウの集積パターンからは典型的および非典型的ADに加え、多様な非ADタウオパチーの存在が示されました。特にアミロイドPET陰性群においては、精神病症状を伴う患者で前頭皮質や線条体のタウ集積が有意に高く認められました。これらの所見は、死後脳解析においても裏付けられ、老年期に躁病やうつ病を呈した症例では、多様なタウオパチーを有する頻度が高いことが明らかになりました。
本研究は、生体PETで世界に先駆けて老年期気分障害患者の生体脳で多様なタウ病理を可視化したうえに、大規模な死後脳サンプルでも老年期気分障害とタウ病理との関連を示した点で重要な意義を有します。
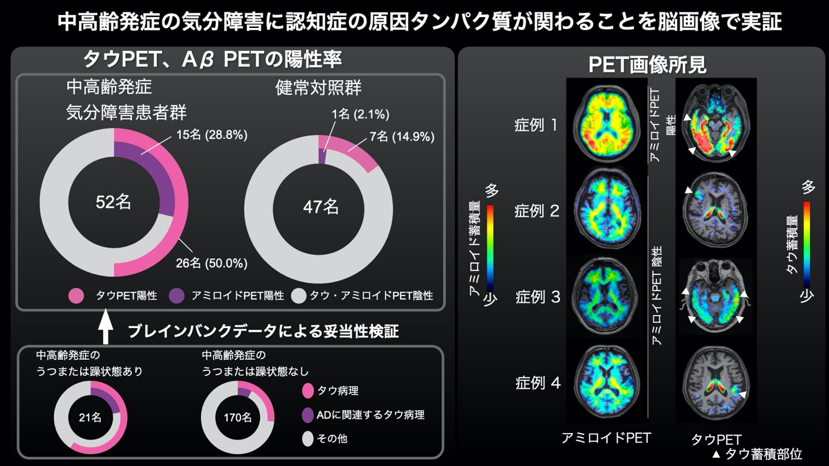
(黒瀬心、2025.10.4.)
背内側前頭前野損傷後の随意的な嚥下開始困難
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科)
Voluntary Swallowing Initiation Difficulty After Dorsomedial Prefrontal Cortex Damage: A Case Report.
Cogn Behav Neurol. 2025 Mar 1;38(1):9-15.
https://doi.org/10.1097/WNN.0000000000000383.
Motojima N, Funayama M, Nakajima A, Nakamura T, Baba M, Kobayashi S.
【背景】背内側前頭前野が運動の開始に重要な役割を果たしていることは、電気生理学の研究から明らかになっている。この領域が両側にわたって損傷されると、無動無言症(akinetic mutism)を呈し、随意的な運動が見られなくなることがあるが、これらの症例では重度のアパシーを伴う。一方、運動開始のみに限局した症状は、片側の背内側前頭前野の損傷後に上肢の運動開始困難や発話開始困難を呈した症例が数例報告されているものの、知見は十分に蓄積されていない。本報告では、同部位の損傷後に随意的な嚥下の開始困難を認めた症例を提示する。
【症例】 右背内側前頭前野の神経膠芽腫を外科的に摘出した直後から、液体の随意的な嚥下開始が困難となった60代女性である。頭部MRIでは右背内側前頭前野に腫瘍の摘出部位を認めたが、摘出前には midline shift を伴い、左背内側前頭前野にも広がる浮腫がみられた。左下肢を中心とする不全麻痺を認めたが、徐々に軽減した。吸引反射、左手の把握反射、本能性把握反応を認めたが、それぞれ2週間後、6週間後に消失した。一方、液体の嚥下開始困難は2か月後まで残存した。
本症例では嚥下反射は正常であり、咀嚼といった嚥下に対する外的な運動誘発要因が関与する固形物の嚥下には問題がなかった。一方、咀嚼を伴わない液体の嚥下では嚥下の開始が困難で、全く開始できないため口腔内に液体が留まり、吸引を要した。内服薬の嚥下も困難であり、経鼻胃管の留置が必要となった。液体嚥下の開始困難は、粘度、味、温度、指示の有無、随意嚥下か否か、体幹の角度調整による重力の補助といった条件の変化に関係なく出現した。一方で、液体の量が増加すると症状が悪化し、嚥下開始困難を強く意識することや、内服を伴うこと、さらに大きな薬剤の内服では一層顕著となった。これらの所見の多くは嚥下造影検査でも確認された。本症例には、嚥下失行と関連することが多い口顔面失行や発話失行は認められなかった。
【考察】本症例は、背内側前頭頭野の損傷後に液体の嚥下開始が困難となった症例である。われわれは、外的な運動誘発の有無、運動開始に関わる加速度の程度、認知機能あるいは情動による影響が、液体に限定した嚥下開始困難の背景に関与していると考えている。咀嚼運動を伴う固体では嚥下開始困難は認められなかったことから、外的な運動誘発が嚥下開始を促進していると考えられた。また、液体嚥下は固体嚥下と比較してより大きな加速度を必要とすることが示唆されている。液体の量が多くなると嚥下開始困難が悪化することも、嚥下に必要な力の影響を示唆している。さらに、嚥下開始困難を意識することが悪化を招いたのは、情動や行動の制御に高度なリソースが要求され、その結果、背内側前頭前野の機能の低下を引き起こした可能性がある。背内側前頭前野と運動開始との関係をより明らかにするには, 今後も類似した症例の蓄積が必要である.
(船山道隆、2025.9.1.)
自閉スペクトラム症の背外側前頭前野における長間隔皮質内抑制 -信号源推定法を用いた検討-
三村悠 (慶應義塾大学医学部 精神・神経科)
Yu Mimura, Shinichiro Nakajima, Mayuko Takano, Masataka Wada, Keita Taniguchi, Shiori Honda, Hiroyuki Uchida, Masaru Mimura, Yoshihiro Noda. Long-interval intracortical inhibition in individuals with autism spectrum disorders: A TMS-EEG study with source estimation analyses. Clinical Neurophysiology., 178, 2110936, 2025.
背景:
経頭蓋磁気刺激(Transcranial magnetic stimulation: TMS)はコイルを利用した電気刺激によりヒトの脳皮質を直接刺激し、その出力として得られる誘発電位から脳皮質の神経生理機能を評価することができる。TMSによる刺激には単発刺激と二連発刺激がある。脳皮質に磁気刺激を二連発で与え、二発目の磁気刺激で得られる誘発電位を測定する系を考える。この時、刺激間隔を100msに設定すると単発刺激時に比して誘発電位が抑制される現象が観察され、これはlong interval intracortical inhibition (LICI)と呼ばれる。LICIはこれまでの報告からGABA-B受容体を介した抑制機能を反映していると考えられている。自閉スペクトラム症(Autism spectrum disorder: ASD)者の脳皮質は興奮/抑制バランスの不均衡が病態として考えられており、GABA-B受容体作動薬が臨床症状を改善させるなどの報告から、LICIの抑制効果も減弱していると推定される。
目的:
本研究の目的は、経頭蓋磁気刺激-脳波同時測定法(TMS-EEG法)を用いて、ASD者の背外側前頭前野(Dorsolateral prefrontal cortex: DLPFC)におけるLICIの抑制効果を評価することである。先行研究においてはASDのLICIによる抑制効果は健常者と同程度に保たれていると報告されていることから、本研究においては解析方法を工夫して実施した。
方法:
ASD32名および健常対照者34名を対象に、左DLPFCに単発の磁気刺激及び100msの間隔で二連発刺激を与え、誘発脳波を得た。まず、すべての参加者のTMS誘発電位からLocal mean field potential(LMFP)を算出し、LICI効果を検討した。次に、体積伝導の影響を最小限に抑えるために、脳波データに対して信号源推定法を適用しDLPFCの電位を推定した。最後に信号源推定法で得られたデータに対して時間周波数解析を行い、LICI効果を周波数帯域ごとに検討した。
結果:
ASDと健常対象者を統合したLMFP解析では、刺激後165〜234msの間の皮質活動がLICIによって抑制されたことが示された(p = 0.024)。信号源推定法を用いても、同じ時間帯域においてLICIの抑制効果が確認された。さらに、時間周波数解析では、θからα帯域において刺激後30〜300msの間にLICI抑制効果が示された。しかし、各LICI効果においてASD群と健常対照群間で群間比較を行ったが、いずれも有意な群間差はみられなかった。
結論:
TMS-EEG法とLICIを組み合わせた方法のみでは、ASDにおけるGABA(B)受容体機能不全を検出するには不十分である可能性がある。これはASDの異質性や向精神薬内服などが影響していると考えられた。
意義:
本研究は、ASDにおけるLICI効果を信号源推定手法により検討した初めての研究であることに意義がある。今後は他のモダリティや刺激方法も組み合わせた解析が望ましい。
(三村悠、2025.8.6.)
メモリークリックにおける認知症類似の治療可能性のある精神疾患の分類
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科)
Identifying reversible psychiatric dementia mimics in new memory clinic outpatients.
Funayama M, Kurose S, Takata T, Sato H, Izawa N, Isozumi K, Abe Y.
J Alzheimers Dis Rep. 2025 Mar 21; 9: 25424823251329804.
https://doi.org/10.1177/25424823251329804.
[背景]仮性認知症のように認知症に類似する治療可能性のある疾患を診断することは、メモリークリニックの診療において極めて重要である。しかし、認知症に類似する神経疾患の分類は十分に研究されている一方で、精神疾患の分類については十分に研究されておらず、その実際の可逆性に関する詳細なデータも限られている。本研究では、この点を明らかにすることを目的とした。
[方法]足利赤十字病院のメモリークリニックを初診で受診した外来患者749名を後方視的に調査した。病因、進行速度、Mini-Mental State Examination(MMSE)による神経心理学的評価、認知機能が正常範囲か、Mild Cognitive Impairment(MCI)か、認知症のレベルにあるかといった認知機能のレベル、治療可能性について、精神疾患および神経疾患に分類して検討した。さらに、治療により認知機能が実際に回復した症例(MCIまたは認知症のレベルから正常範囲に回復した例、または認知症のレベルからMCIに回復した例)を特定した。
[結果]749名のうち121名(16.2%)が治療可能性のある疾患を有し、その内訳は精神疾患75名、神経疾患46名であった。精神疾患には、うつ病などの気分障害、統合失調症・妄想性障害、ADHD、アルコール使用障害、解離性障害、不安障害が含まれていた。治療可能性のない群と比較すると、これらの精神疾患群は年齢が若く、進行速度が速く、MMSEスコアが高かった。同様に、水頭症や慢性硬膜下血腫などの治療可能性のある神経疾患群についても、治療可能性のない群と比較すると年齢が若く、進行速度が速かった。MCIまたは認知症のレベルであった症例のうち6名(0.9%)が完全な改善(3例)または部分的な改善(3例)を示し、その中には精神病症状を呈した精神疾患の2例(妄想を伴う退行期うつ病および急性一過性精神病)が含まれていた。また、治療可能性のある疾患を有してMCIないしは認知症のレベルであった73例のうち14例(19%)は、すでにアルツハイマー病を中心とした認知症を合併していた。
[結論]治療可能性のある認知症類似疾患は稀ではあるものの、鑑別には注意が必要である。特に比較的年齢が高くなく、 急速な認知機能低下を示す症例では慎重な評価が望まれる。実際に改善した例の割合の低さは、これらの疾患が認知症のリスク因子と強く関連している可能性や、認知症の前駆状態であった可能性を反映していると考えられる。
(船山道隆、2025.6.1.)
中年期における緑茶およびコーヒーの摂取習慣は、将来的な認知症予防に寄与するか:長期縦断コホート研究
是木明宏 (慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 特任講師)Koreki A, Nozaki S, Shikimoto R, Tsugane S, Mimura M, Sawada N. A longitudinal cohort study demonstrating the beneficial effect of moderate consumption of green tea and coffee on the prevention of dementia: The JPHC Saku Mental Health Study. J Alzheimers Dis. 2025 Jan;103(2):519-527. doi: 10.1177/13872877241303709.
本研究は、国立がんセンターとの共同研究で、多目的コホート研究の一環として行われました。詳細は国立がんセンターの本研究の成果報告に関するHPをご参照ください。
https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/9527.html
今までにも緑茶やコーヒーの摂取が認知機能低下を予防する効果がある可能性が指摘されていましたが、研究期間が比較的短く、長期間の効果についてはよくわかっていませんでした。近年の研究から、認知症を引き起こす脳内の異常タンパクの蓄積や脳血管の老化は中年期から始まることが明らかになっていることから、中年期からの生活習慣の蓄積が後の認知機能低下に影響を与える可能性が考えられました。本研究では、中年期の緑茶やコーヒー摂取の習慣と、約20年後の認知機能障害との関連を検討した点が特徴です。
本研究からは、緑茶の習慣が1日1杯以下だった群を基準とした場合、緑茶を2~3杯飲んでいた群では、認知機能障害のリスクが44%低下していることが示されました。特に男性においてその傾向が顕著で、緑茶を2~3杯飲んでいたグループでは62%のリスク低下、緑茶を4~6杯飲んでいたグループでは61%のリスク低下が示されました。一方でコーヒーの影響は、より年齢の高い群では、コーヒー摂取が1日1杯未満の方を基準とした場合、コーヒーを1杯以上飲む群では46%のリスク低下が示されました。
今回の結果が得られた可能性として、緑茶の抗酸化作用、抗炎症作用、血管保護作用、異常タンパク質の蓄積阻害などの神経保護作用、またコーヒーではその抗酸化作用、抗炎症作用、血管保護作用などに加え、コーヒーの認知機能への刺激作用も重要な役割を果たしている可能性が考えられます。本研究の限界はあるため、さらなる研究が必要です。
(是木明宏、2025.6.1.)
ミレニアム精神医学辞典 三村將、村松太郎 編集
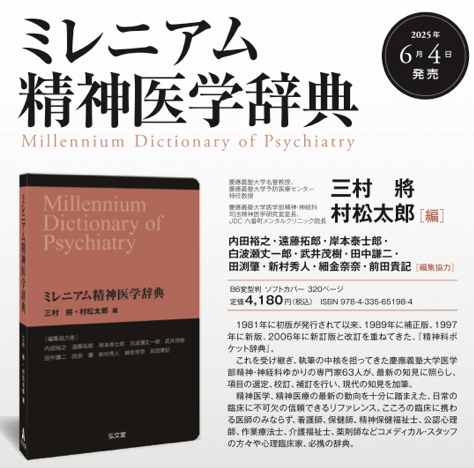
【序文(全文転記)】
スマホで簡単に、何でも、すぐに、知識を得ることができる時代に、紙の辞典の存在意義は何か。本辞典の発刊にあたって、プロジェクト開始時点からチーム内で常に自問自答し議論を重ねてきたのはこの問いである。精神医学の未来と過去を同等に尊重した現代を記述する。これが我々が到達した回答であった。収載語の選択、説明文の記述、そして『ミレニアム精神医学辞典』という書名、これらすべての中にその理念が凝集されている。
簡単に。何でも。すぐに。それは人間の限界を超えた利便性であり、正誤不詳の情報の氾濫を加速させている。そんな空間で重視されるのは正しいか誤りかではない。正しそうに見えるか、納得しやすいか、さらには特定のあるいは多くの人々にとって都合が良い情報か、こうしたものが拡散の推進力になり、真実はその拡散の中に雲散霧消する。20世紀初頭の哲学者ウィトゲンシュタインは、新聞が真実を報道しているかどうかを確かめようとしてその新聞を何部も買うという行動の愚を鋭く指摘した1)。コピーを膨大に重ねても真実性が増すことは一切ないのだ。21世紀初頭の現代でもてはやされるアクセス数や再生数は、いくら膨大であっても、真実とは無関係であることは言うまでもない。
では精神医学における正しい情報とは何か。正しい知識とは何か。精神医学の真実とは何か。ICDやDSMに刻まれた診断基準も一つの真実である。最新のニューロサイエンスのエビデンスに裏打ちされた疾病理解も一つの真実である。そして伝統的な精神医学が涵養してきた叡智も一つの真実である。それらは時に相矛盾し、不協和音を奏でながら、しかし予定調和としての真実を目指して前進を続けている。本辞典はそんな道の途中で立ち止まってみたスクリーンショットである。予定調和が現実になるのは百年後か、あるいは千年後かもしれない。ミレニアム(千年紀)のネーミングにはそうした意味もこめられている。
本辞典を形にすることができたのは、執筆者の先生方、そして精密このうえない編集作業をしていただいた弘文堂の世古宏さん、小林翔さんのご尽力のお陰であり、深く感謝してやまない。さらに、本辞典の前身である『精神科ポケット辞典』の執筆者・編集者の方々にも深く感謝したい。同辞典は1981年に初版が発行され、1989年に補正版、1997年に新版、2006年に新訂版が発行されたという歴史がある。その内容の一部は、本辞典にも当時のままの形で、あるいは現代の知見を加筆した形で、受け継いでいる。過去の執筆者の中にはすでに鬼籍に入られた先生もいらっしゃるが、そうした大先輩が本辞典をどう評価されているか、怯える気持ちも我々にはあることを告白しなければならない。
ミレニアムは過去だけでなくもちろん未来にも目を向けたネーミングである。一千年後の人々の目には、本辞典に映し出された現代の精神医学はどのように見えるのか。いささか誇大的なそのような夢を持って、『ミレニアム精神医学辞典』をここに上梓する。
2025年3月、桜の開花を目前にした日に
編者を代表して
村松太郎
JDC六番町メンタルクリニック
慶應義塾大学医学部 精神・神経科
1) Wittgenstein L: Philosophische Untersuchungen. Basil Blackwell, 1953. (邦訳. ウィトゲンシュタイン全集8. 哲学探究. 藤本隆志訳 大修館書店 東京 1976. 第265節 )
【解説】
弘文堂から、伝統ある精神医学辞典改訂プロジェクトのお話があったのは2018年であった。そして三村將教授室(当時)で、三村將先生、弘文堂社長、弘文堂ご担当者(世古宏さん)、村松のミーティングが行われた。そこでは、今という時代に辞典を発刊することの意味は何かということを中心とした議論が展開された。その回答が本辞典であり、エッセンスは序文に記された通りである。
その後、コロナ禍があり、また、ICD-11診断名の正式な訳語の決定を待ったことなどもあって、時が経過したが、このほど、ようやく発刊することができた。編集協力者、執筆者の先生方にはここにあらためて感謝申し上げます。
(村松太郎、2025.5.27.)
「遠隔記憶検査」更新版の開発
山本小緒里(千葉県千葉リハビリテーションセンターリハビリテーション治療部)
江口洋子(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室)
2010年以降の本邦の社会的出来事に関する「遠隔記憶検査」更新版の開発. 高次脳機能研究 44(3): 199-209, 2024
"Remote Memory Test updated version" for social events in Japan since 2010 using famous people photographs
山本小緒里1) 小西海香2) 江口洋子2) 田中春奈3) 佐竹祐人4) 池上正斗5) 葛西有代6) 菊地尚久1) 三村悠2) 穴水幸子2, 7, 8)
1)千葉県千葉リハビリテーションセンターリハビリテーション治療部
2)慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室
3)東京都健康長寿医療センターリハビリテーション科
4)大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室
5)伊那中央病院リハビリテーション技術科
6)総合リハビリ美保野病院リハビリテーション科
7)千葉県千葉リハビリテーションセンターリハビリテーション科
8)国立病院機構栃木医療センター精神科
9)東京都立大学人文社会学部
【概要】
「遠隔記憶検査」は,1970年代~2010年に活躍した有名人が写る社会的出来事の写真を用いて,人名の想起または再認,出来事に関するキーワードの想起を求め,得点化することにより健忘症患者の遠隔記憶を評価できる検査である。我々は2010年代の写真を用いて「遠隔記憶検査」の検査手法を踏襲した「更新版」を作成し,信頼性と妥当性を検討した。2020年時点で20歳以上の健常者183名に「更新版」を実施し,世代ごとの平均得点と標準偏差を求めた。再検査法を用いて級内相関係数を求めた結果強い相関が示され,本検査の高い信頼性が示された。また,健忘症と診断された15症例に「遠隔記憶検査」と「更新版」を実施し,各症例の偏差値を求めた。縦軸を偏差値,横軸を出来事の年代としたグラフで示した結果,症例の逆向性健忘の病態を検査結果で説明することができ,妥当性が示された。例えば自己免疫性脳炎後に過去10~15年の自伝的記憶(Autobiographical Memory)の逆向性健忘を呈した症例は,グラフ上で同期間の時間勾配が認められた。本検査は「遠隔記憶検査」と同様に,逆向性健忘の客観的指標として有用であることが示唆された。臨床における逆向性健忘の診断やリハビリ立案への活用が期待できる。
(山本小緒里、2025.4.1.)
解説 研究を繋ぐ
逆向性健忘の様態を明らかにするには、本人の遠隔記憶が欠損している期間や内容を明らかにする必要があります。しかし明らかにするには、記憶が欠損する以前に確かに「記憶されていた」ことの証明が非常に難しいために方法論的な困難が伴います。そのような条件下においても、1980年代後半から1990年代にかけて創意工夫された遠隔記憶検査が多く発表されました。当神経心理学研究室からも自叙伝的記憶検査(吉益ら、自叙伝的記憶と新しい検査法について.脳と精神の医学、1993)や、物品価格を解答してもらうプライステストの有用性(吉益ら、プライステストの有用性について-簡便な逆向性健忘検査のコルサコフ症候群への応用.精神医学、1997)が報告されました。社会的な出来事に関する遠隔記憶検査に関しては、検査項目が古くなることと、新しい検査項目を追加しなければならないという構造的な課題があり、1996年、次に2016年に報告しました(江口ら、視覚性遠隔記憶検査の作製とその妥当性の検討.神経心理学、1996;江口ら、有名人の顔が含まれる社会的出来事写真を用いた遠隔記憶検査作成の試み.認知リハビリテーション、2016)。初版は西の大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室神経心理研究室、次に東の当神経心理学研究室、さらに今回は東・西の研究室と新たに別の病院に所属する先生方と協働し、検査内容を更新しました。臨床で活用される検査は時代を経て、各所の研究者を繋ぎながら生き残っていくことを知っていただけたらと思います。
(江口洋子、2025.4.5.)
時間が100倍遅く進む:抗NMDA受容体脳炎の診断の鍵となる時間の変容
平田りさ, 和田央, 船山道隆, ほか(足利赤十字病院神経精神科)Time moving 100-fold slower: time distortion as a diagnostic clue in anti-NMDA receptor encephalitis. BMC Neurol. 2025 Feb 24;25(1):75.
https://doi.org/10.1186/s12883-025-04078-8.
Hirata R, Wada H, Yamamoto K, Sogi Y, Muzuta H, Isaka Y, Funayama M.
【背景】抗NMDA受容体脳炎は重篤で生命を脅かす疾患であり、約30%の患者がICUに入室し、5~11%が死亡すると報告されている。早期の免疫療法により、患者の70~80%が大幅に回復することが示されており、迅速な診断と治療の開始が予後を左右する。本疾患では、初期に患者の87%が急性の行動変化を示し、59%が初発症状として精神症状を呈することから、統合失調症などの精神疾患との鑑別が難しい。しかし、鑑別に関する報告は少なく、非定型精神病に最も病像が類似するという見解や、知覚の変容が特徴である可能性が示唆されているものの、十分な知見には至っていない。
ところで、ケタミンやフェンサイクリジンなどのNMDA受容体阻害薬によって生じる主たる現象は時間の変容であり、NMDA受容体機能と密接に関連していることが明らかになっている。本報告では、抗NMDA受容体脳炎の初期に顕著な時間の変容を呈した症例を提示し、この所見が本疾患の早期診断と治療の手がかりとなる可能性について考察する。
【症例】病初期に顕著な時間の変容を呈し、免疫療法によりほぼ完全に回復した抗NMDA受容体脳炎の2例である。いずれの症例も、精神症状の中で時間の歪みが主要な症状であった。
症例1: 中年男性。発症初期に「時間が100倍遅く進む」と感じる強い時間の変容を経験し、離人感や聴覚異常を伴った。他の症状が完全に回復した後も、この時間の変容は1年以上持続した。すなわち、意識障害が強い極期以前だけでなく、極期以後の回復期にも時間の変容が主症状であった。時間の変容が意識障害とは無関係であったことが特徴的であった。
症例2: 若年女性。発症初期に「時間が2~3倍遅く進む」と感じた。当初は自ら時間の変容を訴えなかったが、極期を脱した後、治療者が尋ねた際に確認された。本症例は発症初期に精神科病院に入院し、改善が乏しかったため電気痙攣療法のために紹介された。後方視的にみると、時間の変容が鑑別に役立った可能性がある。
【考察】本報告は時間の変容、特に時間が遅く進む知覚が抗NMDA受容体脳炎の初期に特徴的である可能性を示唆する。この独特な所見は、他の疾患では主要な孤立症状として現れることが稀であり、精神疾患における時間の変容と区別する上で有用である。本疾患は統合失調症との鑑別が困難だが、時間の変容が病初期から顕著に出現していたことから、鑑別に役立つ可能性が高い。さらに、一部の患者は時間の変容を自発的に訴えないため、初期評価時にこの症状を積極的に評価することが診断精度の向上に寄与すると考えられる。この点を明確にするには、今後多数例での研究が必要である。
(船山道隆、2025.3.6.)
91歳まで維持ECTをおこないその継続・終結の判断に苦慮した口腔内セネストパチーの1例
森山泰1), 高宮彰紘2), 横山照夫3), 増田万里亜1), 森山潔4)1)駒木野病院精神科
2)Neuropsychiatry, Department of Neurosciences, Leuven Brain Institute, KU Leuven, Belgium.
3)駒木野病院神経内科
4)杏林大学医学部麻酔科学教室
精神科治療学 39: 1395-1402,2024
電気けいれん療法(electroconvulsive therapy: ECT)は薬物治療抵抗性・不耐性を示す統合失調症・気分障害患者に対して高い有効性と即効性が期待される治療法である。急性期ECT後に再燃・再発を予防する一つの方策として、内服薬の調整に加えて維持ECT (maintenance ECT) がある。その施行間隔および施行期間について日本精神神経学会編集のECTグットプラクティスでは「うつ病および統合失調症患者において週1の間隔から2週毎、1カ月ごとの間隔に移行していき以後も徐々に間隔をあけていき3か月再発しなければ中止を検討」となっている。
ところで精神症状が活発な場合の維持ECTの終結過程についてはあまり検討されていない。今回我々は超高齢症例に維持ECTをおこないその継続・終結の判断に苦慮した口腔内セネストパチーの1例を経験した。
症例は不機嫌、拒絶、食思不良から口腔内セネストパチー、不食などに重篤化する精神症状のために、5-6週間隔でECTを継続しており、今回91歳時に:1)ECT後の血中酸素飽和度の低下、発作間せん妄といったECTの合併症;2)微熱、認知症といった身体併存症;3)本人のECT治療への拒否:を認めたためECTを中止したところ精神症状の明らかな再発を認めた。ECTを再開し精神症状が改善した時点でアドバンスドディレクティブ1)をおこなった。
その後も頻脈発作、上腕骨骨折といったさまざまな身体併発症を認めながらもECTを継した。代替療法として磁気刺激療法を考慮し専門外来を受診したが適応ではないとのことであった。最終的に低アルブミン血症に伴う胸水貯留のため麻酔科医判断でECTは91歳で終結となったが、その後は認知症が進行する一方で、精神症状の再燃は認めていない。
本症例のような超高齢症例のECT継続・終結に関しては精神症状、身体併存疾患、ECTの合併症、本人・家族の治療への動機づけ、内科・麻酔科との連携など多面的に判断することが重要であろう。
1)ある患者あるいは健常人が、将来自らが判断能力を失った際に自分におこなわれる医療行為に対する意向を前もって意思表示すること」と定義される。これには代理人表示と内容的指示がある。代理人表示とは事前指示をおこなうものが意思を表示できなくなった場合に決定をおこなう代理人を指名しておく事前指示である。
内容的指示は治療についての患者の望みを記録した事前指示で、当人が望んだり拒否したりする治療、ないし代諾者が医療の内容を決定する際に指針となる基準を指定しておくものである
(森山泰、2025.1.6.)
認知症の前駆状態における重症うつ病の人の臨床的特徴
西田晴菜(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)Hana Nishida, Akihiro Takamiya, Shun Kudo, Takahito Uchida, Bun Yamagata, Shogyoku Bun, Hiroyuki Uchida, Frank Jessen, Masaru Mimura, Jinichi Hirano. Characteristics of Severe Late-Life Depression in the Prodromal Phase of Neurodegenerative Dementia, The American Journal of Geriatric Psychiatry: OSEP, 2024, doi: 10.1016/j.osep.2024.10.003.
【背景】
老年期うつ病の一部は神経変性疾患と関連しているとされているが、認知症や軽度認知障害へ移行した人の臨床的特徴は十分に調査されていない。また、うつ病の重症度が神経変性疾患への移行に影響する可能性が示唆されている一方で、電気けいれん療法 (electroconvulsive therapy: ECT)が必要な重症のうつ病の人のうち、神経変性疾患に移行した人の臨床的特徴は明らかではない。
【方法】
2012年4月から2022年9月の間に、当院にてECTで治療された老年期うつ病の人のうち、一年以上当院で経過を追跡した人について後方視的にカルテ調査を行った。そして追跡中に老年期うつ病から神経変性疾患に移行した人と、移行しなかった人の臨床的情報を比較した。
【結果】
94名のうち12名(11%)はECT施行後平均20ヶ月後に神経変性疾患へ診断が移行した。神経変性疾患へ移行した人は、移行しなかった人と比較してよりうつ病の発症年齢が高齢(p = 0.01)で、メランコリーの特徴を呈した人が少なく(p = 0.03)、精神疾患の家族歴の既往を持つ人が少なかった(p = 0.01)。治療反応性に関しては両群で差は認めなかった。
【結論】
上記特徴を呈する重症の老年期うつ病の人に対しては、神経変性疾患への移行がないか特に注意して経過を追うことが重要である。
(西田晴菜、2024.12.19.)
電気けいれん療法と認知機能
髙宮 彰紘 (FWO special research associate (postdoctoral) KU Leuven, Leuven Brain
Institute, Department of Neurosciences, Neuropsychiatry, Leuven, Belgium)Electroconvulsive therapy and cognitive
performance from the Global ECT MRI Research Collaboration
Kiebs M, Farrar DC, Yrondi A, Cardoner N, Tuovinen N, Redlich R, Dannlowski U, Soriano-Mas C, Dols A, Takamiya A,
Tendolkar I, Narr KL, Espinoza R, Laroy M, van Eijndhoven P, Verwijk E, van Waarde J, Verdijk J, Maier HB,
Nordanskog P, van Wingen G, van Diermen L, Emsell L, Bouckaert F, Repple J, Camprodon JA, Wade BSC, Donaldson KT,
Oltedal L, Kessler U, Hammar Å, Sienaert P, Hebbrecht K, Urretavizcaya M, Belge JB, Argyelan M, Baradits M, Obbels
J, Draganski B, Philipsen A, Sartorius A, Rhebergen D, Ousdal OT, Hurlemann R, McClintock S, Erhardt EB, Abbott CC.
J Psychiatr Res, 2024 10.1016/j.jpsychires.2024.09.013.
近年、多くの研究領域において報告される論文数が増加の一途を辿っているが、再現されない散発的な報告も少なくない。一方、多くの領域において多施設共同研究が盛んに行われるようになり、大規模コホートによる信頼性の高い頑強な結果の報告や、複数コホートによる再現可能性の報告も増えてきている。ECTという領域においても多施設共同研究チームであるThe
Global ECT MRI Research Collaboration
(GEMRIC)が組織されている。GEMRICは元々ECT脳画像研究の国際共同研究グループとして開始されたが、最近では各種ワーキンググループの発足、参画機関による新しいコラボレーションの促進、ジャーナルクラブの開催などその活動内容は多岐にわたってきている。
本論文はGEMRIC Clinical and Cognitive Working GroupによるECTの縦断研究を行う際の認知機能測定に関する推奨事項を報告している。内容は以下のリンクから確認可能である。
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395624005351?via%3Dihub
論文の内容や、Working Groupで話し合われたことをまとめると、語流暢性課題 (verbal fluency test: VFT)
はECTに関する急性の認知機能変化を鋭敏に捉えられる可能性がある、全般的認知機能測定にはMMSEではなくMoCAを使うことが望ましい、自伝的記憶の測定に関しては3つの候補があるもののそれぞれ利点と欠点があり1つに絞り推奨することは難しいが今後行う前向き研究では各施設でデータを取得することが望ましい、ということである。
このような形で今後の研究に役立つ提言をまとめながら、各種ワークショップの開催などを通じて国際交流を深め、ECTに関する研究報告を行いながらこの領域の発展に寄与していくことが我々の目標である。
(高宮彰紘、2024.11.20.)
統合失調症におけるSense of Agencyの階層的解析:運動制御、制御検出、自己帰属
大井博貴(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)Oi H, Wen W, Chang AY, Uchida H, Maeda T.: Hierarchical analysis of the sense of agency in schizophrenia: motor control, control detection, and self-attribution. Schizophrenia. 2024;10(1): 79-79. doi: 10.1038/s41537-024-00512-x.
https://www.nature.com/articles/s41537-024-00512-x
統合失調症における自我障害は、主観的体験であるため、これまで自然科学の対象とすることはできなかったが、近年自我障害について神経科学的観点から捉えたSense of Agency(SoA)というパラダイムが注目されている。SoAとは、自己の行為と、それに伴って生じる外界の変化を自己の意志の通りに制御できるという感覚のことである。日本語では主体感などと訳される。この「行為に伴う自己意識」については実証的に評価できるため、統合失調症患者を対象とした行動実験が行われ、SoA異常が報告されてきた。脳内でSoA異常が生じるメカニズムについては、ベイズ推論を中心とした計算論的精神医学の観点からも考察されている。しかし、先行研究では、自他帰属課題等によって過剰な自己帰属(SoAの増大)が示される一方で、自己の制御に対する検出能力の低下(SoAの減弱)も示唆されており、統合失調症におけるSoA異常の全体像はいまだ不明である。このように統合失調症のSoA研究において一貫した結果が得られていない原因として、各々の実験系で扱う階層性が異なっている可能性が考えられる。SoAの生成過程においては、低次な感覚運動レベルから高次な認知レベルへと至る様々な階層における複数の要素が関わっているが、それらを包括的に評価した研究はまだ行われていない。そこで本研究では、同一の実験デザインの3種類の運動制御課題を用いて、SoAの生成に関わる様々な階層の複数の要素を包括的に評価した。
具体的には、統合失調症患者26名、健常者27名を対象として、reaching task、control detection task、control judgment taskの3種類の課題を実施した。3つの課題すべてにおいて、被験者は手元のマウスを動かして画面上のドットを操作したが、マウスの動きとドットの動きとの間にランダムな空間バイアス(事前に記録された他人の手の動きと、0度もしくは90度の角度バイアスを組み合わせたもの)が加えられた。Reaching taskでは、制限時間内にドットを画面上のターゲットにできるだけ多くタッチすることで、低次な感覚運動レベルにおける運動制御能力を評価した。Control detection taskでは、3つのドットの中から被験者のマウスの動きを一部反映しているドットを正しく選択することで、自己の制御に対する検出能力を評価した。Control judgment taskでは、被験者は画面上のドットを自分で制御できていると感じたか否かについて回答することで、高次な認知レベルにおける主観的な自己帰属判断を評価した。
マウスの移動速度を共変量として混合デザインANCOVAを実施したところ、reaching taskおよびcontrol detection taskにおいて、患者群の成績が有意に低かった(それぞれF(1, 47) = 39.46, p < 0.001, partial η2 = 0.456; F(1, 47) = 6.92, p = 0.011, partial η2 = 0.128)が、control judgment taskでは両群間に有意差を認めなかった(F(1, 47) = 0.02, p = 0.884, partial η2 < 0.001)。つまり統合失調症患者では、運動制御能力と、自己の制御を検出する能力が有意に低いことが示されたが、自己帰属判断は保たれていた。また、3つの課題の成績を用いて階層的クラスター分析を実施したところ、統合失調症患者と健常者を86%という高い精度で分類可能であった。
本研究により、統合失調症におけるSoA異常においては、感覚運動レベルにおけるSoAの感度の低下がより本質的であり、それを認知レベルにおける自己帰属バイアスによって代償している可能性が示唆された。また、3つの実験課題の結果によって、統合失調症患者と健常者を非常に高い精度で分類できたことから、今後さらに精度を高めていくことで、将来的にSoA課題が診断補助ツールとして有用となる可能性がある。このようなSoA研究を、計算論的精神医学や神経生理学的検査と組み合わせることで、より包括的な病態解明に繋がる可能性があり、そこから新たな治療法や認知リハビリテーション方法の開発へと発展していくことを期待している。
(大井博貴、2024.10.16)
身体化障害との鑑別を要したPainful legs and moving toes syndromeの一例Mimura, Y., Komatsu, K., Yasushi, Y., Seki, M., Nakajima, S., Uchida, H. and Mimura, M. (2024), A case of painful legs and moving toes syndrome mimicking somatic symptom disorder. Psychogeriatrics, 24: 1023-1029. https://doi.org/10.1111/psyg.13155
【概要】
Painful legs and moving toes syndrome (PLMT)は中年期以降の女性に多く、不随意運動及び“じんじん”、“ちくちく”としたしつこい痛みを足からつま先にかけて訴えることが特徴の疾患である.中枢性の疼痛処理経路障害及び末梢神経障害がその病態として推定されているが、診断に有用な検査もないため誤診されやすい。特に痛みの訴えが強く、その内容が独特であるがゆえに精神疾患に間違えられる可能性がある。
【症例】
症例は70歳代女性.X-6年に帯状疱疹後に陰部の疼痛を認め複数の病院を受診,鎮痛薬への反応性が不良でありうつ状態を疑われスルピリドを開始されたが振戦のためすぐに中止となった.翌年には外用薬で疼痛は改善.X-1年に体幹がねじれる現象が起こるようになり,クロナゼパム開始,症状は改善したが足の内側から引っ張られるような痛さを認めた.X年3月に他院脳神経内科を受診し検査の結果パーキンソン病関連疾患が疑われた.同年5月に当院に精査加療のため任意入院となった.入院時,左足趾から大腿の疼痛,不随意運動と腰の重さを訴えた.一方で、不釣り合いな身体症状へのこだわり、恐怖、不安は聴取されず、二次的な抑うつ症状も同定できなかったことから身体化障害らしさに欠けると感じた。その症候から神経内科医よりpainful legs and moving toesの可能性について示唆をいただき,ミロガバリンを開始,疼痛は徐々に改善し疾病教育をして退院となった.各種精査の結果、パーキンソン病と腰部脊柱管狭窄症が複雑に関与しPLMTを発症したと推定された. 今までの病歴から暗示に影響されやすく,疼痛を敏感に感じる身体化障害らしい背景もあったが,正確に訴えを聴取・診察することで鑑別できた1例であった.
【本症例から得られた教訓】
1 原因の特定できない痛みを安易に精神疾患としないこと
2 PLMTはミロガバリンなどを中心に薬物療法である程度コントロールできること
3 PLMTの病態が複雑であるがゆえ、症例ごとにケアプランを考慮するべき. 本症例で言えばパーキンソン病、腰部脊柱管狭窄症双方に対しての加療が奏功した可能性がある.
(三村悠、2024.9.1.)
脳卒中後の尿失禁は行動コントロールの障害と過活動膀胱に関連する
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Post-stroke urinary incontinence is associated with behavior control deficits and overactive bladder. Neuropsychologia 2024. 201, 108942. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2024.108942.
Michitaka Funayama, Akihiro Koreki, Taketo Takata, Yoshitaka Nakagawa, Masaru Mimura
【背景】脳卒中後には3割以上の患者に尿失禁が出現する.尿失禁は患者の生活の質を低下させるだけではなく, 介護者の負担を増やすために患者の介護施設への入所を余儀なくさせるなど, 患者の生活上での大きな支障となる.脳卒中後の尿失禁の機序は, 脳損傷後に反射の脱抑制として生じるBabinski反射と類似した機序である過活動膀胱(排尿反射の過剰な脱抑制)で説明されてきた.一方で, 症例報告からは前頭葉を中心とした大脳半球の損傷後に尿意に無関心となって尿失禁に至る例が記載されてきた.脳機能画像からも, 前頭葉を中心とした大脳皮質によって排尿のコントロールが行われていることが明らかになっている.しかし今まで, 脳卒中後の尿失禁の背景にある神経心理学的メカニズムとその神経基盤について, 包括的な研究は行われていなかった.今回われわれは, 脳卒中後の患者群を対象として, この点を明らかにした.
【方法】脳卒中後半年以上経過した71例に対して, 尿失禁の頻度, 過活動膀胱(尿の回数と尿意切迫感), 移動能力, 尿失禁に関連する身体疾患や薬物療法の有無, 神経心理学的所見(全般的認知機能, 見当識, 記憶, 注意機能, 遂行機能, 洞察力や衝動性を制御する能力などといった行動コントロールの程度)を評価した.統計手法としては, 尿失禁の頻度を被説明変数として, その他の因子を説明変数として, 尿失禁と各因子との関係を単回帰分析にて調べた.その後, 単回帰分析にてp値が0.1未満であった説明変数を用いて多重線形回帰分析を行い, 交絡因子をコントロールした.さらに, 尿失禁の神経解剖学的基盤を詳細に調べるために, MRIcronソフトウェアを使用してBoxel-Based Lesion-Behavior Mappingを実施した.
【結果】多重線形回帰モデルの結果から, 尿失禁の頻度は行動コントロールの障害と過活動膀胱の重症度に有意に関連していた。注意障害と尿失禁の頻度との関係は, わずかに有意な水準には達しなかった.Boxel-Based Lesion-Behavior Mapping からは, 右側を中心とした前頭葉腹内側部の病変が尿失禁の頻度と関連する可能性が示唆されたが, 統計学的に有意な水準にはわずかに達しなかった. 実際の患者や家族からは, 尿意が感じられる状況となっても”ヤバい”と感じず, テレビを見ている間に, 気づいたら失禁していたなどのエピソードが聞かれた.
【結論】脳卒中後の尿失禁は, 過活動膀胱と行動コントロールの障害といった2つの要因と密接に関連していることが明らかになった.また, 前頭葉腹内側部が神経基盤である可能性が示唆された.これらの結果より, 脳損傷後の尿失禁は前頭葉腹内側部損傷後の脱抑制行動と類似した前頭葉症状として捉えられる可能性が示唆された.
(船山道隆、2024.8.1.)
適応障害の背景にある高次脳機能障害を把握する必要性:右頭頂-側頭-後頭葉の心原性脳梗塞の1例
第120回日本精神神経学会学術総会 (札幌、2024.6.22.)中根弓那1)、滝上紘之1)、二宮朗1)、前田貴記1)、内田裕之1)、船山道隆1)2)
1) 慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 2)足利赤十字病院 精神神経科
【目的】高次脳機能障害は精神科を含めた医療現場で見逃されがちである.特に,右半球損傷は失語がないために,症状が分かりづらい.今回われわれは,長期に渡り社会的不適応を起こしていた背景に脳梗塞による高次脳機能障害が強く存在した1例を報告する.
【症例】68歳男性.発達の遅れの指摘はない.X-6年に物忘れを自覚し他院を受診したところ,右頭頂葉~側頭葉~後頭葉に心原性脳梗塞が発見されたが,無症候性と診断されていた.神経学的異常所見はみられなかったが,この頃より意欲低下や抑うつ気分があり,家族からも話のまとまりなさを指摘されるようになった.気分変調症と診断され,抗不安薬を投与されていた.X-3年,職場での異動を機に抑うつ症状が出現し,適応障害と診断された.休職や退職を勧められたが決断できず,方針決定と休養目的にX年より入院した.入院時,話が冗長でまとまりに欠ける,他者の反応に応じた言動の選択ができない,手を顔に持ってきづらいなど語用論の障害や身体空間の障害を示唆する症状が聞かれた.WAIS-Ⅳでは知覚推理(PRI)と処理速度(PSI)の低下が目立ち,神経心理検査では選択性注意の低下や,形の弁別や未知相貌の異同弁別の遅延,左半側空間無視,変形視が見られた.これらの機能の低下が職場での適応障害や気分変調症の背景にあることが明らかとなった.高次脳機能障害と診断し,訪問看護導入など社会調整をしたのちに退院となった.
【考察】右半球の脳梗塞後に諸機能低下が生じ,適応障害を起こした一例を報告した.本症例では特に話の迂遠さや他人の感情を察する能力の低下が所見として見られた.これは右半球が左半球と比較して優位に話の構造や一貫性,因果関係など話の全体像に関わる言語処理を行っていたり,情動認知の正確性に関係していたりするが,それが障害された結果を反映している.また,WAISと脳病変の部位の相関を示した過去の研究では,知覚推理(PRI)は右半球に,言語理解(VMI)・ワーキングメモリ(WMI)は左半球,処理速度(PSI)は両方に関係していることがわかっている.本症例は知覚推理(PRI)と処理速度(PSI)の低下が見られ,右半球の障害を反映したものとなっている. これらの指標の低下が本人の職場での不適応の一部に影響していた可能性が高い.右半球が左半球と比較して優位に担う機能は空間認知,顔の認識,情動の理解や表現,注意等,様々あるが,いずれの機能低下もその原因として右半球損傷があることに気づかれにくい.脳梗塞の部位に伴う症状を把握し,既往歴や症状出現の時系列,画像所見などに注意して診察することが診断上重要になると気付かされた症例であった.
(中根弓那、2024.7.11.)
軽度認知障害の背外側前頭前野における短潜時求心性抑制を用いた神経生理機能評価:TMS-EEG研究
三村悠 (慶應義塾大学医学部医学研究科 / 東京都立松沢病院 精神科 医員)Mimura Y, Tobari Y, Nakajima S, Takano M, Wada M, Honda S, Bun S, Tabuchi H, Ito D, Matsui M, Uchida H, Mimura M, Noda Y. Decreased short-latency afferent inhibition in individuals with mild cognitive impairment: A TMS-EEG study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2024 Feb 12:132:110967. doi: 10.1016/j.pnpbp.2024.110967.
【背景】大脳皮質の神経生理機能の評価法として経頭蓋磁気刺激(TMS)と高精度脳波計(EEG)を組み合わせたTMS-EEG法が知られている。TMS刺激法の一つである末梢感覚刺激とTMSによる中枢刺激を組み合わせた短潜時求心性抑制(SAI)は主にコリン作動性神経を介した抑制機能を反映する。これまで健忘型軽度認知障害(aMCI)に対してTMS-EEG法とSAIを組み合わせて評価した研究はない。
【目的】TMS-EEG法を用いてaMCIの左背外側前頭前野(DLPFC)における神経生理機能をSAI法で評価することを目的とした。
【方法】本研究は慶應義塾大学医学部倫理委員会の承認を得て実施した (承認番号: 20170152)。aMCI30例(年齢68.3±8.0歳, 女性11例)、対照健常(HC)30例(年齢67.4±6.9歳, 女性10例)を対象に左DLPFCに対して安静時運動閾値の120%強度で単発刺激80発とSAI刺激(刺激間隔=N20+4msec)80発をランダムに与え、各刺激後の誘発脳波の全電極平均電場(GMFP)、刺激部位局所平均電場(LMFP)、各周波数成分のTotal powerを群間比較した。【結果】GMFP解析では刺激後100msecにおいてaMCI群でHC群に比して抑制効果が低かった(p=0.034)。その抑制効果とMMSE得点に負の相関が認められた(r=-0.41, p=0.023)。一方LMFP解析では有意な群間差がみられなかった。トータルパワー解析においてMCI群ではHC群に比して刺激後200msecにおけるβ帯域の抑制効果が有意に減弱していた。
【考察】aMCI群では左DLPFCにおけるSAIによる抑制効果が低く、それは認知機能及びβ振動と関与している可能性が示唆された。これまでβ振動はコリン作動性神経の活動及び認知機能と関わることが報告されており本研究からSAIがMCIの早期コリン作動性神経低下を反映する神経生理学的マーカーになることが期待される。
(三村悠、2024.6.1.)
後天性脳損傷における主観的な奥行知覚の障害と客観的な立体視の障害をつなぐ
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Investigating the Link Between Subjective Depth Perception Deficits and Objective Stereoscopic Vision Deficits in Individuals with Acquired Brain Injury. Cogn Behav Neurol 2024. DOI: 10.1097/WNN.0000000000000369. Michitaka Funayama, Tomohito Hojo, Yoshitaka Nakagawa, Shin Kurose, Akihiro Koreki.
【背景】脳血管障害や外傷性脳損傷といった後天性脳損傷後において、主観的な奥行知覚の障害を呈する報告は以前から記載されている。しかし、それらの例では客観的な立体視の検査がほとんど行われていない。一部の報告では立体視の検査が行われているが、その場合は主観的な奥行知覚の訴えがない例であるか、病巣が明らかになっていない例であった。したがって、明確に特定化された病変を持つ後天性脳損傷の患者において、主観的な奥行知覚の損傷と客観的な立体視の損傷の関係を明確に示した報告はなかった。われわれはこのギャップを埋めるべく、明確な病巣を認めるなかで主観的な奥行知覚の障害の訴えがある後天性脳損傷3例(脳血管障害2例、外傷性脳損傷1例)にて、客観的な立体視の検査を行った。
【方法】「世界が絵のように平面に見える」「3本の物干しざおのどちらが近いか遠いか分からない」など奥行知覚の障害を訴える後天性脳損傷3例対して、神経学的、眼科的、神経心理学的検査を詳細に行った。次いで、2種類の立体視の検査を行った。右半球損傷と健常者の2つの対照群を用いて、これらの結果を比較した。
【結果】奥行知覚が障害されていた後天性脳損傷3例は、言語性IQにおいては右半球損傷群と違いを認めなかったが、視空間機能と関連する動作性IQでは右半球損傷群よりも成績は低下していた。2種類の立体視の検査においては、この3例の成績は2つの対照群と比較して大きく低下していた。この3例における主たる病巣は右半球を中心とする後頭葉の楔部(cuneus)から上頭頂小葉の後部であった。
【考察】本3例の結果は今までの動物実験での知見を補強するものであり、後頭葉から頭頂葉を経て前頭葉につながる視覚認知の背側経路(物へのリーチングや把握、特定の道具に対する手の形などと関連)が、その経路の初期段階で奥行知覚や立体視に深く関係することを示すものである。
(船山道隆、2024.5.8.)
ドーパミン関連タンパク分布とmRNA分布との関連
山本保天 (慶應義塾大学医学部 精神・神経科 特任助教)Yamamoto Y, Takahata K, Kubota M, Takeuchi H, Moriguchi S, Sasaki T, Seki C, Endo H, Matsuoka K, Tagai K, Kimura Y, Kurose S, Mimura M, Kawamura K, Zhang MR, Higuchi M.: Association of protein distribution and gene expression revealed by positron emission tomography and postmortem gene expression in the dopaminergic system of the human brain. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2023 Nov;50(13):3928-3936. doi: 10.1007/s00259-023-06390-2.
ドーパミン受容体、ドーパミントランスポーター、catechol-O-methyl transferase (COMT)などのドーパミン関連タンパクのトポロジカルな脳内局在は、ドーパミン神経伝達の恒常性だけでなく、ドーパミンに関連した認知過程においても重要である。一般に、脳内タンパク分布は、遺伝子の転写とその後のRNAプロセシング、タンパクの翻訳後修飾、タンパク輸送、タンパク分解など様々な段階で制御されている。生体脳PETと死後脳mRNAアトラス(Allen human brain atlas)を組み合わせることで、転写後の制御過程がタンパク分布に及ぼす影響が明らかになりつつある。これまでにドーパミン関連タンパクについての研究は乏しく、セロトニン関連タンパクについての研究が複数報告されている。それらによると、mRNAの発現レベルはセロトニン受容体密度と空間的に相関するが、セロトニントランスポーター密度とは相関しないことが報告された。このセロトニン受容体とトランスポーターとの差異は、シナプス前タンパクとシナプス後タンパクの転写後の制御過程が異なる可能性を示唆した。そこで、本研究では、ドーパミンD1、D2/D3受容体とドーパミントランスポーターに焦点を当て、mRNA発現とタンパク分布の関係を探索した。
本研究では、60名の若年健常者のPETデータを収集した。60人の被験者のうち、29人(女性4人、年齢32.3 ± 7.6歳)が11C- SCH-23390 PET、23人(女性4人、年齢29.7 ± 8.9歳)が11C-FLB457 PET、健常男性14人(年齢27.2 ± 6.1歳)が18F-FE-PE2I PETを撮像された。ドーパミンD1、D2、D3受容体、およびドーパミントランスポーターのmRNA発現マップは、www.meduniwien.ac.at/neuroimaging/mRNA. htmlから入手した。11C-SCH-23390 PETのBPND値とドーパミンD1受容体mRNA発現量との関心領域ごとの相関; 11C-FLB-457 PETのBPND値とドーパミンD2/D3受容体mRNA発現量との関心領域ごとの相関; 18F-FE-PE2IのVT値とドーパミントランスポーターmRNA発現量との関心領域ごとの相関をスピアマンの順位相関を用いて検討した。
11C-SCH-23390 PETのBPND値とドーパミンD1受容体mRNA発現量との間に有意な正の相関が認められた(r = 0.769, p = 0.0021)。ドーパミンD1受容体と同様に、11C-FLB-457 PETのBPND値はドーパミンD2受容体mRNA発現レベルと正に相関していたが(r = 0.809、p = 0.0151)、ドーパミンD3受容体mRNA発現レベルとは相関していなかった(r = 0.413、p = 0.3095)。ドーパミンD1受容体とD2受容体とは対照的に、18F-FE-PE2I PETのVT値とドーパミントランスポーターmRNA発現レベルとの間には有意な相関は認められなかった(r = -0.5934, p = 0.140)。
以上より、ドーパミンD1受容体およびD2受容体のmRNA発現量と、それぞれのタンパク分布との間には領域ごとの相関があることがわかった。しかし、ドーパミントランスポーターのmRNA発現量とそのタンパク分布の間には領域ごとの相関は見られず、シナプス前とシナプス後タンパクの局在には異なる制御メカニズムがあることが示された。具体的には、シナプス後タンパクは転写場所とタンパク合成(細胞体近傍)、分布部位がほぼ近接しているが、シナプス前タンパクは細胞体近傍で転写ならびにタンパク合成がなされた後に軸索輸送を介して細胞体から離れた軸索末端に分布している可能性が示唆された。これらの結果は、トランスクリプトームアトラスをドーパミン作動性神経系のニューロイメージング研究に応用するための、より広い理解を提供するものである。
(山本保天、2024.4.22.)
経頭蓋磁気刺激法を用いた非アルツハイマー型認知症及び軽度認知障害の神経生理学的バイオマーカー:レビューとメタ解析
三村悠 (慶應義塾大学医学部大学院博士課程)Mimura Y, Tobari Y, Nakahara K, Nakajima S, Yoshida K, Mimura M, Noda Y. Transcranial magnetic stimulation neurophysiology in patients with non-Alzheimer's neurodegenerative diseases: a systematic review and meta-analysis. Neuroscience and biobehavioral reviews. 155; 10545: 2023.
大脳皮質の神経生理機能の評価法として経頭蓋磁気刺激(TMS)と筋電図(EMG)を組み合わせたTMS-EMG法は、運動皮質の神経生理機能評価法として確立している。大まかに言えばTMSの刺激に対する応答をEMGで評価し、脳皮質機能を推定する方法である。特にPaired pulse paradigm(複数回刺激)では二回の刺激の組み合わせで得られる誘発電位を評価することでGABA-Aを反映した皮質の抑制機能 Short interval intracortical inhibition (SICI)、Glutamateを反映した興奮機能 intra cortical facilitation(ICF)、コリンを反映した抑制機能Short latency afferent inhibition(SAI)をそれぞれ計測できる。以前、我々はアルツハイマー型認知症(AD)及び軽度認知障害(MCI)に対して、TMS-EMG神経整理評価が有用であることを報告した。
今回、我々は神経変性疾患全体の30%を占め、単なる記憶障害にとどまらない認知機能低下を特徴とする非ADの神経変性疾患についても同様に調べた。結果として71本の論文がメタ解析に含まれた。TMS神経生理学的検査により、前頭側頭型認知症(FTD)患者ではグルタミン酸作動性機能の低下及びGABA-B作動性神経機能の低下が、FTD、レビー小体型認知症(DLB)、進行性核上性麻痺、ハンチントン病、皮質基底症候群、多系統萎縮症-パーキンソン型患者ではGABA-A作動性機能の低下が明らかになった。さらに、DLBや血管性認知症ではコリン作動性機能の低下が認められた。これらの結果は、NADを鑑別する新たな診断手段としてのTMSの可能性を示唆している。
(三村悠、2024.3.1.)
電気けいれん療法 (ECT) とケタミンの有効性は同等なのか?
髙宮 彰紘 (FWO special research associate (postdoctoral), KU Leuven, Leuven Brain Institute, Department of Neurosciences, Neuropsychiatry, Leuven, Belgium.)Ketamine or ECT? What have we learned from the KetECT and ELEKT-D trials?
Joakim Ekstrand, Akihiro Takamiya (co-first), Axel Nordenskjold, George Kirov, Pascal Sienaert, Charles Kellner, Pouya Movahed Rad
Int J Neuropsychopharmacol, 2023 doi: 10.1093/ijnp/pyad065.
電気けいれん療法 (electroconvulsive therapy: ECT) は重症うつ病に対して最も有効かつ即効性のある治療である。しかし、頻回な全身麻酔を要し、一過性の認知機能障害のリスクを有する。そのため、ECTと比較して簡便に施行可能で、副作用は少ないが高い有効性と即効性をもつ抗うつ治療が求められている。このような背景から、ケタミンの点滴投与とECTの治療効果を比較した非劣性試験がこれまでに2つ行われている。スウェーデンで行われたKetECT試験は、ケタミンの有効性はECTに劣ると2022年に報告した。一方、米国で行われたELEKT-D試験は、ケタミンの有効性はECTと同等だと報告した。
どちらの結果が正しいのだろうか?ついそう問いたくなってしまうかもしれない。しかしより有意義な問いは「どちらの結果を(自分のいる)臨床現場に適用できるのか?」だと思われる。正しいかどうかという点では、どちらの研究も適切な手続きで行われており、2つの相反する結論はそれぞれの場と条件*1においては正しいのではないかと思う。
この2つの臨床研究で最も注目すべき点は、ECTの有効性の違いである。スウェーデンの臨床研究ではECTの寛解率が63%である一方、米国では22%だった (ケタミンの寛解率はそれぞれ46%、38%だった*2)。そのため、ケタミンとの比較云々の前に、「なぜECTの有効性が2つの臨床研究でここまで違うのか?」という新たな疑問が出てきてしまう。ECTは標準的な治療として2つの非劣性試験において基準とされている。その基準がここまで違うと、その結果の解釈には慎重にならざるを得ない。
この2つの臨床研究の結果から得られる教訓は、「ECTに関して、過去90年近い歴史の中で蓄積されてきた臨床知と研究成果をもとに、適切な症例に適切な方法で施行することがその治療効果を最大限引き出す上で大切だ」ということである。ECTで最も改善が見込まれる患者像としてメタ解析で報告されている特徴は、高齢、精神病症状、エピソードの短さである。臨床的には不安症やPTSDなどの併存がなく、エピソード間に寛解期がしっかりとある、生物学的な要因が強いと考えられる症例の方がより改善しやすいと考えられている。スウェーデンでは入院環境でECTが行われ、米国では9割近くの患者は外来通院で行われたという違いもある。ECTの施行方法に関しては、右片側 (right unilateral: RUL) の電極配置かつ超短パルス波 (ultrabrief pulse: UBP) の刺激を用いたECTは寛解までのセッション数が短パルス波のECTと比較して多く必要であることが指摘されており、米国のELEKT-D試験における6〜9セッションでは十分な治療効果を得るには十分でなかったと考えられる*3。
2024年1月現在、ほぼ全ての症例が入院患者かつ90%以上が両側刺激という日本のECT臨床に、どちらの臨床研究に基づくエビデンスを適用できそうか、という問いに対する答えは自ずと出てくるのではないだろうか。一方、ケタミンの治療効果を最大限引き出す方法論や適切な患者像の探究も今後必要なのではないかと思う。
*1 ECTの対象患者や施行方法は、国や地域により異なることが知られている。筆者が専攻医オプション期間に米国にてECT臨床を学んだ際には、精神科医が適切でないとわかっていても患者の保険の制約によりECTを施行しないといけないという場面を目の当たりにし衝撃を受けた。逆に、外来での施行や片側ECTが普及しておらず、統合失調症患者への施行が多い日本の現状に関しては、「なぜ?」と問われ返答に窮することがしばしばである。
*2 米国の臨床研究 (ELEKT-D試験) の主要アウトカムは寛解率ではないが、比較のためMADRSで評価した寛解率を示している。
*3 本論文の共著者でもあるKellner先生が主導した米国のPRIDE試験においてもUBP RUL ECTが採用されているが、寛解率は62%だった。PRIDE試験は60歳以上の高齢者のみを組み入れているという対象者の大きな違いはあるが、いずれにしてもUBP RUL ECT自体に問題があるわけはない。しかし、UBPは非劣性試験で基準とされる標準的ECTと言えるかは疑問である。
(高宮彰紘、2024.2.1.)
脳画像研究の基盤整備
髙野晴成 (国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター National Center of Neurology and Psychiatry; NCNP 脳病態統合イメージングセンター Integrative Brain Imaging Center; IBIC 臨床脳画像研究部)
はじめに
国立精神・神経医療研究センター・脳病態統合イメージングセンター(IBIC)ではキャンパス内の病院や研究所との橋渡しをしつつ画像研究の推進を図っているが、IBICの重要な使命の一つとして、わが国の多施設共同画像研究の推進および研究環境の基盤整備も掲げられている。
近年の画像診断技術およびコンピューター技術、情報通信技術の発展により、画像研究は長足の進歩を遂げている。MRIでは臨床ではT1強調画像、T2強調画像、拡散強調画像等による構造・形態診断が行われるが、機能的MRI では安静時脳血流や課題負荷時の脳血流変化をみることができ、脳機能研究および精神神経疾患の病態研究に用いられている。PETやSPECCTなどの核医学では脳血流・代謝からアミロイド等の蓄積や神経伝達機能をみることができる。現在の画像はいずれもデジタルデータで保存され、解析はコンピューター上で専用のソフトウェアを用いる。結果として画像研究では大量のデジタルデータを扱うことになる。
多施設共同画像研究
施設の垣根を越えて広く症例を収集する多施設共同研究という手法は精神疾患に限らずいまや国内外でも臨床研究の標準となっている。多施設共同画像研究を推進するためには各施設から画像データを効率よく集積し、管理することが不可欠である。IBICでは2010年代前半より脳病態統合イメージングサポートシステム(Integrative Brain Imaging Support System; IBISS)を管理・運営している。IBISSでは各研究参加施設から国際標準規格であるDICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 形式の画像データを氏名等の個人情報を取り除いて、インターネットを介してアップロードし、クラウドサーバに保管・管理する。IBISSでは使用者のIDとパスワードの他に、あらかじめ各研究施設のグローバルIPアドレスをアクセス可能な施設として登録しておき、それ以外のIPアドレスからはアクセスできないことで安全性を保っている。IBISSはこれまで10以上の国内の多施設共同画像研究プロジェクトで使用され、MRI、PET、SPECT、CTのデータを収集してきた。
特に最近のAMEDの国際脳プロジェクトは多機種調和MRI撮像プロトコルと呼ぶ高品質・高分解能で標準化されたプロトコルを用いている。その分、データの種類が増えかつデータ量が大量化した。そのためIBISSは2022年にガバメントクラウドの一つである最新のクラウドに移行し、大幅な機能改修も行った。今日のクラウドではデータを保管するのみならず作業・機能する領域を持つことができため、拡張性が高い。そのおかげで利用者の要望に応じてプロジェクトごとに大幅なカスタマイズも可能になった。
画像データの品質管理
一つのプロジェクトではNCNP内の研究部と共同で大規模MRIデータの品質チェックを行っている。まずはDICOMタグ(ヘッダー)の自動チェックシステムを開発し、フォーマットや枚数、撮像シークエンスの不備を検出する。その過程でT1, T2強調画像などを自動抽出し、遠隔読影のサーバに転送、放射線科専門医に研究用の標準化された基準・手順に則って読影してもらう。たとえば、通常の放射線科読影では正常変異とみなされるものであっても、大脳皮質の容積測定に影響すると考えると除外すべきである。さらにわれわれがアーチファクトの確認を行い、研究利用の観点から解析に使用できるかの統合的な判断を複数人で行う。その質の担保として毎週ミーティングを行い、評価の共通化のトレーニングも行っている。この方法で現在、数千の画像の品質チェックを行っている。品質管理をシステム化することにより効率的になったが、人の目・判断も必要である。特に精神疾患の研究では微妙な差を検出する必要があるため、研究用画像の厳密な品質管理を行うことが不可欠であると考えている。
持続可能なデータ管理
今日では個人の日常生活でもクラウドを使用し、意識せずともクラウドとローカルのパソコンをシームレスに使用していることが多いと思われる。また、ほとんどの研究で何らかの形でクラウドにもデータを置いている。国内外でもクラウドに大量のデータを保持し、さらにそこにOSやアプリケーションを立ち上げ、クラウド内で解析を行う研究も散見される。とくに機械学習や人工知能を利用した解析に持ち込むためには大量のデータが欠かせない。また、近年はデータシェアリングが重要視され、クラウド上でデータが公開されている。しかしながら、研究用クラウドを維持していくことは簡単ではない。外部公的研究費は通常有期のものであり、それだけでクラウドを維持していくのは難しい。オンプレミス(ローカル)のサーバも併用しつつ、IBICの使命として継続的な運用と基盤整備をしていきたいと考えている。
(高野晴成、2024.1.5.)
統合失調症における自己主体感の変調は、予測シグナルの遅延から生じる:計算論的モデルによるシミュレーション研究
沖村宰 (昭和大学発達障害医療研究所 講師)Aberrant sense of agency induced by delayed prediction signals in schizophrenia: a computational modeling study
NPJ Schizophrenia 2023. DOI: 10.1038/s41537-023-00403-7.
Tsukasa Okimura, Takaki Maeda, Masaru Mimura, Yuichi Yamashita
【概要】
統合失調症の病態は未だ明らかにされていないが、自我障害が中核症状であると考えられている。近年、自我障害は自己主体感(sense of agency;SoA)の観点から実証的研究で調査されてもいる。SoAとは、自分自身が自分の行動やその世界への影響を引き起こしているという感覚である。統合失調症でのSoAの変調は、いくつかの行動実験研究で示されていて、その中の1つに、前田らによって開発されたKeio methodによる研究(Maeda et al., 2012, 2013)がある。前田らは、陽性症状優位の統合失調症ではSoA過剰(すなわち、物事の結果を自分の意図に結び付けやすいこと)、陰性症状優位の統合失調症ではSoA過小あることを示した。つまり、統合失調症でのSoAの変調とSoAの変調の2つのタイプを陽性症状と陰性症状に対応する形で示したことになる。統合失調症でのSoAの変調の機序は未解明であるが、「脳を情報処理システムとしたときに、統合失調症では予測機能の異常がある」という仮説が先行研究でなされている。そこで本研究では、「統合失調症では予測機能間での伝達遅延がある」と焦点を絞った仮説を立てた。その理由は、統合失調症におけるSoAの変調の脳基盤も未解明であるが、Whitfordらの研究(2011, 2012, 2015, 2018)をはじめとしてfrontoparietal networkの白質異常の知見がいわれているからである。
上記仮説を統合失調症患者を対象として実証するのは困難であるために、我々は、計算論的アプローチの1つである再帰ニューラルネットワークモデル(RNNモデル)でのシミュレーションで仮説検証をした。本研究のRNNモデルは、現時点での視覚・聴覚・固有受容感覚をうける入力層、次の時点でのこれらの感覚やSoAの判断を出力する出力層、現時点の入力とこれまでの入力の履歴から次の時点の予測の中心を担う文脈層からなる。
このRNNモデルを使って、まず、Keio methodの健常者の結果を学習させた。すなわち、Keio methodのタスクに限っては健常者と同じようなSoAの判断ができるようになったモデルを作成した。その後、「予測機能間での伝達遅延」の仮説検証をするために、文脈層内の伝達遅延をしたところ、前田らの行動実験(2013)のように、統合失調症パターンである2つのタイプのSoAの変調が再現された。本研究の仮説検証はシミュレーションできたが、他のRNNモデル障害実験でも統合失調症パターンが再現される可能性もあるので、比較実験として、文脈層内へのランダムノイズの追加、文脈層から出力層への伝達遅延、入力層から文脈層への伝達遅延のRNNモデル障害実験をしたところ、統合失調症パターンのSoAは観察されなかった。これらの結果は、「予測信号の伝達遅延」仮説を理論的に支持し、統合失調症におけるSoAの変調の病態を理解する手掛かりとなると考えられよう。
(沖村宰、2023.12.10.)
Steroid therapy and rehabilitation in the treatment in a patient with delayed
neurological sequelae due to carbon monoxide poisoning:A case report.
一酸化炭素中毒による遅発性脳症に対してステロイドパルスおよび後療法とリハビリテーションを行った1例
三村 悠1)2),大井 博貴1)2),高田 武人1)2),三村 將2),船山 道隆1)2)
1)足利赤十字病院神経精神科
2)慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室
中毒研究 36:32-37,2023
【概要】
一酸化炭素(CO)中毒による遅発性脳症(DNS)は、CO曝露による急性期症状が改善し、4-6週間の無症候期間を経て意識障害、失見当識、記銘力障害、失禁、失行、人格変化などの多彩な症状を呈する脳症である。その予後は決して良好なものではなく、治療法も確立されたものはない。今回我々はCO中毒によるDNSを発症したが3 回のステロイドパルスおよびステロイド後療法とリハビリテーションに反応し退院へつなげることができた症例を経験したので報告した。
【症例】
患者は30 代男性。CO曝露後第29 病日の朝に意識障害が悪化し,MRI所見もあわせてCO中毒によるDNSと診断した。同日より髄液中のミエリン塩基性蛋白(MBP)の推移をみながらステロイドパルス療法を行なった。反応は部分的で、第47病日から無動状態となり筋強剛も増悪した。ADLの自立度の指標であるFunctional independence measure (FIM、運動機能91点満点)は第53病日にかけて最低点である13点まで下がった。しかし髄液MBPは加療により減少しており、ステロイド後療法に切り替え継続的に介入したところ第75病日頃より徐々に意識レベル、ADL、認知機能が改善した。第108 病日にはMBP は検出感度以下となり,緩徐ではあったが意識レベルとADL は改善した。その後も積極的にリハビリテーションを行い第154 病日には自発語も認め,第190 病日にはADL は自立レベルへ改善した。認知機能はDNS発症前のWAIS-III: VIQ53 PIQ52 FIQ48 VC56 PO55 WM50未満 PS52→DNS発症直後:評価困難→DNS発症後半年のWAIS-III:VIQ 65 PIQ 69 FIQ 64 VC 73 PO 68 WM 58 PS 72と改善し退院となった。しかしながら、退院時まで「食事の際に醤油の袋がうまく開けられず何分も開けようとし続ける」、「部屋に閉じこもりタオルの糸屑を集め続ける」などアパシーや常同性は残存した。
【考察】
典型的な遅発性脳症の長期経過を追うことができた。継続的なステロイド加療およびリハビリテーションは脱髄の抑制に寄与し,髄液中のMBP に反映され,意識レベルの改善につながったと考えられた。本症例でみられたようにアパシーは重度でかつ遷延する可能性が高く、社会復帰の大きな障壁となる。薬物療法に加え、長期的にリハビリテーションにあたることが重要である。
(三村悠、2023.11.1.)
初期に行動異常型前頭側頭型認知症と誤診された神経梅毒:人生を大きく変える鑑別診断
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Neurosyphilis Initially Misdiagnosed as Behavioral Variant Frontotemporal Dementia: Life-Changing Differential Diagnosis.
Funayama M, Kuramochi S, Kudo S.
J Alzheimers Dis Rep. 2023 Sep 26;7(1):1077-1083. doi: 10.3233/ADR-230107. eCollection 2023.
【はじめに】
行動異常型前頭側頭型認知症(bvFTD)は変性疾患の中でも誤診されやすい疾患である。初期に他の精神疾患や神経疾患と誤診されているパターンはbvFTDと最終診断となった例の約50%に至る。逆に初期にbvFTDと診断された約50%は最終的に他の精神疾患や神経疾患の診断に至る。とりわけ、後者の中で、治療で改善が見込まれる治療可能な認知症(treatable dementia)との鑑別を誤らないことは極めて重要である。今回われわれは、初期にbvFTDと診断されていたが、後に神経梅毒であることが判明し、治療でほぼ完全に改善した例を報告する。
【症例】
症例は47歳の一人暮らしの男性である。仕事で大事な荷物を落とすなどの失敗から始まり、徐々に多幸的となるものの気に食わないことに対しては易怒的になるなど性格変化を認めた。意欲も低下し、自宅で尿や便にまみれるなどの衛生観念の低下を認めた。発症から6カ月後に精査のためにA 病院に入院したが、医師にかみつこうとしたり、他患の食事を盗み食いしたりするなどの脱抑制が目立った。また、常に周囲の患者の行動に気を取られるなど環境依存的な行動も目立った。MRIでは両側前頭葉に萎縮を認め、99mTc-ECT SPECTにおいても両側前頭葉と側頭葉の前方部に相対的血流量の低下を認めた。神経心理所見においてもWAISで測定する知能は正常範囲内であったが、Wisconsin Card Sorting Testの成績の低下を認めた。Clinical Dementia Ratingは2であった。bvFTDとして発症から7カ月後に当院に転院となったが、血清と髄液において梅毒に関するSTS、 TPHA、FTA-Absの全てが高値であり、 髄液の細胞数も3.3/mm3, タンパク47mg/dl, IgG 164mg/Lと正常上限から高値を示した。明らかな皮膚症状や神経所見は認めず、HIVも陰性であった。2400万単位のペニシリンを10日間、その後アモキシシリン1000mgを6カ月間投与した。治療開始から1カ月後には自宅での自立した生活が可能となり、治療開始から6カ月後には元の就労に戻った。その後10年間、再発は認めなかった。
【考察】
神経梅毒をbvFTDと誤診するという臨床では当り前のような症例であるが、画像所見、検査、症候をすべて丁寧に記述した報告例は、意外なことに今までに存在しなかった。類似症例は2例ほど存在したが、いずれも血液では梅毒検査が陽性であったが、髄液では梅毒検査は陰性であった症例である。本症例は横断的な症状と画像所見からはbvFTDが疑われたが、縦断的にみると変性疾患としては早すぎる進行であり、40代という若すぎる年齢とともに、典型的な経過とは異なった。神経梅毒をはじめとしたtreatable dementiaは、患者の後の人生を決定的に変えてしまうため、決して見逃してはならない疾患である。典型的な変性疾患との症候の違いが認められた場合は、適切に鑑別することが必要である。
(船山道隆、2023.10.23)
急速進行性認知症をきたした癌性髄膜炎の一例
三村悠 (慶應義塾大学医学部大学院博士課程)Crucial differential diagnosis of rapidly progressive dementia: A case of leptomeningeal metastasis.
Mimura Y, Oi H, Takata T, Mimura M, Funayama M.
Psychiatry Clin Neurosci Rep. 2023;2:e137. https://doi.org/10.1002/pcn5.137
【背景】
神経症状を伴わない急速進行性認知症(Rapidly progressive dementia: RPD)はしばしば精神疾患と誤診されることがある。癌性髄膜炎(Leptomeningeal metastasis: LM)は高い感度と特異度を有する検査に乏しく、診断そのものが困難なことで知られている。今回我々は精神症状を主体としたRPDを呈し、LMの診断に至った一例を経験したので報告した。
【症例】
症例は70代の男性。X-1年、胃癌と診断され化学療法中であった。X年、2週間の経過で易怒性、失見当、脱衣などの逸脱行為を認めた。症状は悪化し、名前も言えず、混乱し、空中に何かあるような仕草を繰り返す為心配した家族に連れられ当院外科を受診された。同日の頭部MRIでは特記すべき異常所見認めず、精神面の関与について当科へ紹介となり、精査目的に医療保護入院とした。
【入院後経過】
入院時、JCSI-3と意識障害を認め、何かをつかもうと手を伸ばす様子が目立った。それ以外に、明らかな神経学的巣症状を認めなかった。同日腰椎穿刺施行したところ、細胞数/蛋白の上昇を認めたためステロイド、アシクロビル、抗生剤にて加療開始した。第4病日には著明な改善をみせ、発語が見られるようになり歩行、摂食も自力で可能であった。HDS-R/MMSEは入院時評価不能であったがそれぞれ4点/9点と軽度改善した。同日、髄液細胞診からClass Vの報告を受け、癌性髄膜炎の診断とした。家族と相談の上、抗がん剤髄注療法は見送ることとした。第5病日から効果を認めたステロイドをハーフパルスで継続とした。第12病日に頭部MRIを再検したところ髄膜肥厚を認め癌性髄膜炎として矛盾しない所見であった。その後徐々に全身状態悪化し、経口摂食は困難となった。Best supportive careにあたったが、第73病日に永眠された。
【考察】
精神症状が目立ったLMの一例を報告した。これまでも精神症状をきたしたLMの報告は散見されるが、脳神経所見の異常や麻痺も同時に認めており、本症例は精神症状を主体としていた点で異なっていた。
LMの診断ゴールデンスタンダードは造影MRIだが、本症例は1回目のMRI検査で陰性であり、幻視が目立ったため精神疾患を疑われた。特にアルコール離脱、老年期精神病、せん妄が鑑別疾患としてあがっていた。MRI検査は感度が低いという問題があり、LMを疑った場合は積極的に髄液検査を行う必要がある。またMRI検査も髄液検査も単回の検査では見落とす可能性が指摘されており、どちらの検査も組み合わせて、疑わしい場合は複数回の施行を検討するべきである。
本症例はRPDを呈しており、幻視の性質について本人の訴えは聴取できなかったが、精神疾患に伴う幻視は複雑幻視でかつ本人にとってネガティブなものが多く、そういった性質を確認できない限り幻視を精神疾患由来と判断することには危険性を伴う。
LMはいまだに治療法が確立していないが、その予後を推定することは家族や本人にとって意義深い。癌を背景とした患者がRPDを呈したときに安易にせん妄と判断せず、正確な診断をすることは極めて重要である。
(三村悠、2023.10.1.)
シャドーイング行動は外界を認識できないことと関連しているかもしれない: posterior cortical atrophy (PCA)患者におけるシャドーイングの症例報告
工藤 駿(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)Shadowing Behavior may be Associated with an Inability to Recognize the External World: A Case Report of Shadowing in a Patient with Posterior Cortical Atrophy
Shun Kudo, Michitaka Funayama, Shin Kurose, Yusuke Shimizu, Taketo Takata, Masaru Mimura
J Alzheimers Dis. 2023. doi: 10.3233/JAD-230257.
【背景】
認知症などの変性疾患において、介護者や医師などを後追いする例は稀に経験されるが、その背景や機序は今までのところ明らかではない。今回われわれは、誰かの後ろをひたすらについて歩く「シャドーイング」が顕著であったposterior cortical atrophyの1例を報告し、その背景や機序を検討する。
【症例】
発症時年齢59歳。
59歳の夏頃から頻繁に道に迷い、自動車事故も起こすようになったが、エピソード記憶障害は明らかではなかった。61歳時には40年勤めていた会社のプレス機を上手く扱えなくなり近医を受診した。頭部MRI・SPECTでは右頭頂-後頭葉を中心とする萎縮/相対的血流量低下が認められた。63歳時には電化製品が使えなくなり、64歳時には自分の名前を書いても文字が抜け落ちる、途中で切れることがあった。不安が強く介護者である妻の後から離れようとしないこともあった。66歳時には、家族の顔を見ても誰だか判別することができなくなった。また、進行性の流暢性失語も目立ち、日常物品も使えなくなっていった。妻が体調を崩し自宅での生活が困難となり住宅型老人ホームに入所したが、特定の職員や入所者の後ろを常に付いて歩く「シャドーイング」が目立ち、入所者間で揉めることが多々生じた。施設側が対応に難渋し67歳時に精神科病院へ入院となった。
入院後の診察では、パーキンソン症状を含め神経学的には明らかな異常を認めなかったが、椅子には自分の体を合わせて座れず、物品を掴むのに時間がかかり、病棟内で見渡せる狭い範囲でも自室の位置を把握できないなど顕著な視空間障害が認められた。病棟内でも回診に無言で付いてくることが頻繁に見られた一方、原始反射や環境依存的な行動は見られなかった。MMSEは3/30(即時想起のみ可)であった。
【考察】本症例における「後追い」については、顕著な視空間障害、失行、失語のため外界の状況理解が困難であることが背景にあり、誰かの後ろを歩くことで自身を守ろうとする代償的な機序が考えられた。この患者の障害の重症度(MMSE 3/30)を考えると、この1症例から決定的な結論を導き出すことは困難であるが、周囲の環境を認識することの深刻な困難は、シャドーイング行動の発現に寄与している可能性がある。
(工藤駿、2023.9.18.)
症例! 失語症のリハビリテーション
中川良尚、佐野洋子、船山道隆著 新興医学出版社 2023
船山道隆 (足利赤十字病院神経精神科部長)
本書の特徴は、臨床現場で失語症者のリハビリテーションを行う言語聴覚士のみならず、失語にかかわる医師にとっても、失語症とそのリハビリテーションを理解する上で極めて優れた内容が記載されていることである。江戸川病院リハビリテーション科の言語室は、わが国における失語症のリハビリテーションにおいて最も正統な流れを持ち、また、リハビリテーションの質の高さのみならずリハビリテーションを施してきた失語症者の数においても、わが国では最高水準である。その江戸川病院で長年培われてきた貴重な知見をもとに、失語症のリハビリテーションの現場でそのまま役立つ実践的な内容が記載されている。さらに見逃してならないことは、失語症者とその家族を心理的に、さらには社会的に支える姿勢が本書に組み込まれていることである。わが国で失語症にかかわる医療従事者には、ぜひ本書から失語症とそのリハビリテーションを学んでいただきたい。
(船山道隆、2023.8.1.)
解説 「実践!」そして「症例!」
本書の「序文に代えて」の冒頭には次のように記されている:
筆者らが2022年3月に刊行した、姉妹書「実践! 失語症のリハビリテーション」と本書は、過去約40年にわたり江戸川病院で行ってきた失語症言語訓練の臨床で学んだ知見を書きとめたものであり、次世代の失語症の言語訓練発展に、何かしらお役に立つことを願ったものです。
この一文と上記船山道隆部長の紹介文をあわせれば、本書の解説としては完璧であるが、一つだけどうしても追記しなければならないのは、「症例!」というタイトルの通り、本書には実際の豊富な訓練映像のDVDが付けられているという大きな特長である。失語症という性質上、その症状も訓練も、文字情報だけから得られるものには相当な限界があるが、DVDを視聴することで格段に理解が深まることは言うまでもない。したがってこのような視聴覚資料が付されていることは失語症の書籍においては必須条件とも言えるが、現実には個人情報等のハードルがあり、「必須条件だが、達成困難な理想」であったところ、本書においては「本書に各症例の詳細な個人情報、そして言語訓練の詳細な経過を書くことやDVDによる訓練映像の提供にあたり、対象となる失語症者とご家族のすべての方から喜んで受諾していただくことができました」ということが「序文にかえて」に記されている。失語症者のための、著者らの40年にわたる並々ならぬ努力が、当事者の方々からの深い信頼を得ることで、本書の発刊が実現したことを、ここからも読み取ることができる。
1968年、失語症を中心とする高次脳機能をテーマに伊豆韮山温泉病院で開催された研究会「韮山カンファレンス」を母体として発足した「日本失語症研究会」は、1983年に「日本失語症学会」と名称を変更し、活発な活動が続けられ、2003年にはその名称が「日本高次脳機能障害学会 (旧 失語症学会)」に変更され、さらに2013年には「日本高次脳機能障害学会」となって「失語症」が学会名から消失した。(近い将来には「障害」が削除され「高次脳機能学会」への変更が予定されている)。高次脳機能に関する臨床・研究の範囲の発展は大変喜ばしいことで、社会に対する貢献も大きく拡大しているが、失語症の専門家の相対的な減少も憂えられているという現実がある。失語症は、臨床においては対象者が膨大に存在し、研究においては、人間の思考が言語を離れて論ずることが不可能である以上、脳機能のみならず人間そのものの理解に向かう深く広いテーマを内在している。「私たちも生涯をかけて、失語症の方のために頑張ってまいりたいと思います」(本書「序文にかえて」の結び)という決意から生まれた本書が、失語症の臨床にも研究にも、大きく貢献することは疑いない。
(村松太郎、2023.8.29.)
認知症に伴う日常生活上の困難さが肺炎の危険性を増加させる:口腔内不衛生と嚥下障害がその要因
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Pneumonia Risk Increased by Dementia-Related Daily Living Difficulties: Poor Oral Hygiene and Dysphagia as Contributing Factors.
Am J Geriatric Psychiatry 2023. doi: 10.1016/j.jagp.2023.05.007.
Michitaka Funayama, Akihiro Koreki, Taketo Takata, Tetsuya Hisamatsu, Jin Mizushima, Satoyuki Ogino, Shin Kurose, Hiroki Oi, Yu Mimura, Yusuke Shimizu, Shun Kudo, Akira Nishi, Hiroo Mukai, Riko Wakisaka, Masaaki Nakano
【背景】 肺炎は認知症患者の主要な死因であるが、その具体的な背景は十分には明らかになっていない。意外にも、今までに認知症に生じる肺炎の危険因子についての総括的な研究は行われておらず、高齢者に生じる肺炎からの知見を認知症の臨床で応用していただけであった。したがって、認知症に関連する要因がどのように肺炎に影響するかについては明らかになっていなかった。特に、口腔内衛生や移動能力の低下などの認知症に関連した日常生活上の困難さ、さらには認知症の治療の際に用いる身体拘束と肺炎の関連性については、ほとんどに研究されていない。
【方法】2011年から2022年の12年間に認知症の行動・心理症状により足利赤十字病院神経精神科病棟に入院した454例の認知症の入院例(複数回入院も含むため、336人の認知症を持つ患者)を対象とした。入院患者を、入院中に肺炎を発症した群(n=62)と発症しなかった群(n=392)の2群に分けた。最初に、肺炎の発症と関連する可能性のある合計24項目、すなわち、認知症の病因(アルツハイマー病など)、認知症の重症度(Clinical Dementia Rating)、身体状況(嚥下障害、意識障害、低栄養、脱水など)、身体合併症(糖尿病、COPDなど)、薬物療法(抗精神病薬など)、認知症に関連した日常生活上の困難(口腔内不衛生と移動能力の低下)、身体拘束の施行について、2群間の違いを調べた。次に、潜在的な交絡因子と繰り返しの入院をコントロールするため、mixed effects logistic regression analysisを用いて、肺炎の危険因子を明らかにした。
【結果】認知症患者における肺炎の発症は、口腔内不衛生を筆頭として、嚥下障害、意識障害と関連していることが明らかとなった(p<0.01)。身体拘束と移動能力の低下は、肺炎の発症と関連する傾向を示した(p<0.10)。
【考察】 認知症の肺炎の発症に影響する因子として、口腔内の不衛生による口腔内の病原性微生物の増加と、嚥下障害や意識障害による気道への嚥下物の除去の困難さの2つの要因が考えられた。身体拘束および移動能力の低下と肺炎との関係を明らかにするためには、さらなる研究が必要である。これら認知症と関連する要因が、一般的に多く報告されている身体合併症や認知症の重症度と肺炎の発症の関連よりも密接な関連があることは、注目に値すると思われる。すなわち、われわれの結果は、介入によって認知症に伴う肺炎の発生をある程度抑制できる可能性を示唆する。
口腔内の不衛生に対しては、口腔ケアの指導や援助が認知症に伴う肺炎に対する予防において有効である可能性がある。さらには、嚥下や歩行に関するリハビリテーションや身体拘束を減少させることが認知症の肺炎を予防する可能性もある。
(船山道隆、2023.7.1.)
うつ病の未来性思考に対する認知行動療法の脳機能アプローチによる治療機序の解明:ランダム化比較試験 (IMAGING study)
片山奈理子 (慶應義塾大学医学部精神神経科 助教)1) Katayama N, Nakagawa A, Umeda S, Terasawa Y, Kurata C, Tabuchi H, Kikuchi T, Mimura M. Frontopolar cortex activation associated with pessimistic future-thinking in adults with major depressive disorder. Neuroimage Clin. 23: 101877. 2019.
2) Katayama N, Nakagawa A, Abe T, Kurata C, Sasaki Y, Mitsuda D, Nakao S, Mizuno S, Ozawa M, Nakagawa Y, Ishikawa N, Umeda S, Terasawa Y, Tabuchi H, Kikuchi T, Mimura M. Neural and clinical changes of cognitive behavioural therapy versus talking control in patients with major depression: a study protocol for a randomised clinical trial. BMJ Open. 10(2): e029735. 2020.
3) Katayama N, Nakagawa A, Umeda S, Terasawa Y, Abe T, Kurata C, Sasaki Y, Mitsuda D, Kikuchi T, Tabuchi H, Mimura M. Cognitive behavioral therapy effects on frontopolar cortex function during future thinking in major depressive disorder: A randomized clinical trial. J Affect Disord. 1;298(Pt A):644-655. 2022.
4) Amano M, Katayama N, Umeda S, Terasawa Y, Kikuchi T, Tabuchi H, Abe T, Mimura M, Nakagawa A. The Effect of Cognitive Behavioral Therapy on Future Thinking in Patients with Major Depressive Disorder: A Randomized Controlled Trial. Front. Psychiatry. doi: 10.3389/fpsyt.2023.997154.
5) Katayama N, Nakagawa A, Umeda S, Terasawa Y, Shinagawa K, Kikuchi T, Tabuchi H, Abe T, Mimura M. Functional connectivity changes between frontopolar cortex and nucleus accumbens following cognitive behavioral therapy in major depression: A randomized clinical trial. Psychiatry Res Neuroimaging. 2023 Apr 11;332:111643. doi: 10.1016/j.pscychresns.2023.111643.
うつ病は未来に対する認知が否定的となることはAron T. Beckのうつ病における否定的な認知の3徴としても知られている。その未来性思考に関連するBA10の活動が健常者よりもうつ病では過活動になっていることを2019年に報告し本神経心理学研究のHPにも掲載していただいた(1)。
その後、うつ病群は週1回約45分間の認知行動療法を16回行う認知行動療法群(CBT群)と認知の変容を促さないいわゆるカウンセリングを行うtalking control群(TC群)にランダム化し、比較試験を行った(プロトコル論文:(2))。その結果、未来を想像している時のBA10の活動がCBT群では低下(正常化)し、TC群では変化がなかった(3)。将来について想像して回答するまでの時間を測った反応時間もCBT群では短縮したが、TC群では変化がなかった(4)。安静時の脳機能結合はBA10と側坐核と結合性の変化が両群で差を認め、その変化は治療終結1年後の臨床症状と相関があった(5)。
2019年に横断研究を発表した時はうつ病は将来を想像するときに努力が必要なのだなというくらいにしか考えていなかった。未来に対する認知の変容を促すCBTと認知の変容を促さないTCでは、未来性思考中の脳活動変化に差はあるのかに興味を持ちRCTを行った。その結果、CBT群では未来性思考を行うことに困難さが減ることが脳機能画像からも行動指標からも明らかになり、その変化は治療終結後の臨床症状とも相関していたことから、CBTの持つ長期的な効果にも関連性があるのではないかと考えている。認知行動療法では、うつ病の患者さんが抱えている現実的な問題を整理し、短期的及び長期的な目標をたて、それを実現するために必要なことをスモールステップで考えていく治療法である。私たちも2020年4月のコロナ禍初期は1ヶ月後、半年後、1年後の未来性思考が全くできなくなった。しかし、コロナウイルスの感染経路や症状、予防策や治療方法など現実の問題が整理されることにより、徐々に自分達のポジティブな未来を想像することが可能となった。私はCBTセラピーを受けているうつ病患者さんにはまさに同じようなことが起きているのではないかと考えている。自分のポジティブな未来を想像する能力は人間にとって非常に重要な認知であり、それが非機能的であるうつ病に効果がある認知行動療法の一つの治療機序の解明になったのであれば幸いである。参加してくださった被験者の方々、そして長きに渡りご指導してくださった多くの神経心理学研究室の先生方に心から感謝申し上げます。
(片山奈理子、2023.6.1.)
後部皮質萎縮症および皮質基底核症候群の患者に生じた道具の持ち方に限定した失行
大森智裕、船山道隆、穴水幸子、仁井田りち、田渕肇Omori T, Funayama M, Anamizu S, Niida R, Tabuchi H. A selective hand posture apraxia in an individual with posterior cortical atrophy and probable corticobasal syndrome. Cogn Behav Neurol. 2023 Mar 27. doi: 10.1097/WNN.0000000000000339
背景
近年の失行研究では、道具の操作方法と持ち方を区別して評価することが主流になってきている。しかし、道具の持ち方に限定した報告例は、脳血管障害で2例、低酸素脳症にて1例であり、世界でも極めてまれにしか報告されていない。ところで、変性疾患の中でも後部皮質萎縮症や皮質基底核症候群ではいずれも失行が頻繁に出現する病態である。しかし、変性疾患においては道具の持ち方に限定した失行例の報告例は皆無である。今回われわれは、後部皮質萎縮症および皮質基底核症候群の患者に生じた道具の持ち方に限定した失行症を詳細に検討した。
また、この症状を説明する理論的背景についても考察した。
症例
症例は66歳時に自家用車で駐車をする際の困難さと着衣の障害を呈し、徐々に道具の持ち方が分からなくなった女性である。他院では診断がつかず、68歳に当院に初診となった。その際には電車を乗り継いでひとりで都心へ出かけるなど、着衣と道具使用以外のIADLやADLは保たれていた。神経学的所見では、左上肢に筋強剛、無動、皮質性感覚障害を認めた。神経心理所見としては背側型同時失認が目立っていた。頭部MRIでは右側優位の両側頭頂葉の萎縮を、99mTc-ECD SPECTでも同部位の相対的血流量の低下を認めた。また、道具の持ち方に関連すると報告されている左頭頂間溝の前方部も相対的血流量の低下を認めた。ドパミントランスポーターイメージングにおいても右側優位で線条体での集積低下を認めた。これらの結果から、後部皮質萎縮症および皮質基底核症候群の臨床診断に至った。
道具使用については持ち方に限定した障害が目立った。例えば、自発的にはさみを使うとき柄ではなく刃の方を持ち、試行錯誤しても正しい持ち方には至らなかった。しかし、はさみを正しく持たせた後は、使用方法は正しかった。はさみに限らず、くし、歯ブラシ、スプーンなどの道具も同様に、患者の道具の持ち方は困難である一方で、正しい持ち方をした後の使用方法は常に正確であった。道具の機能に関する知識は保たれていた。患者は道具の機能を正しく口述し、さらにはコップとスプーン、マッチとろうそくなど、10個の道具を2つずつ組み合わせにする課題も全て正答した。さらに、コインや10000円札などの物品をつかむこと自体には問題はなく、それらの物品に対応する親指と人差し指の間の幅も正しかった。すなわち、本症例は、それぞれの道具に特有な持ち方に選択的な障害が存在すると考えられた。
この障害をさらに明らかにするために、本症例に加えて年齢と認知症の重症度をマッチさせた変性疾患6例を対照群とし、われわれは以下の3つの課題を行った。5つの道具に関して持ち方(持つ位置、持ち方)および操作方法(タイミング、上肢の位置、振り幅)を正しく行う課題、箸の柄を被検者の右側および左側に置いて正しい持ち方をみる課題、操作方法の知識を問う課題(のこぎり、アイロン、ジョウロの3つの道具の中から異なる操作方法を選ぶなど)の3課題を行った。本症例は最初の2つの課題の持ち方の課題にて対照群と比較して成績が低下していたが、操作方法と操作方法の知識を問う課題では差を認めなかった。すなわち本症例は、道具に関する操作方法、操作方法の知識、機能の知識のいずれも良好に保たれていた中で、道具の持ち方に関して選択的な障害を認めた。
本症例が示唆すること
本症例は右側優位の頭頂葉の萎縮/機能低下が認められたものの、道具の持ち方に関連すると報告されている左頭頂間溝の前方部も相対的血流量の低下を認めた。この脳画像所見は、本症例に出現した選択的な道具の持ち方の失行の存在を支持する。さらに本症例では、詳細な検査を基にして、道具に関する操作方法、操作方法の知識、機能の知識のいずれも良好に保たれていた中で、道具の持ち方に関して選択的な障害を認めたことを明らかにした。この両方の点をひとつの症例で示した報告は、本症例が世界で初めてである。
本症例に認められた選択的な道具の持ち方の失行は、Osiurakの提唱するreasoning-based hypothesisを支持する。この理論では道具の持ち方、道具の操作、道具の知識といった機能がそれぞれ独立して脳に存在するとされている。したがって、われわれの症例が呈した選択的な道具の持ち方の失行の症状は、この理論と合致する。一方でBuxbaumの提唱するmanipulation-based hypothesisは、操作方法の知識の低下が失行全体の基本であるとされる。本症例では操作方法の知識は保たれている中で、選択的な道具の持ち方の失行が生じたため、この理論とは矛盾する。
リハビリテーションの観点からは、目印などの工夫により、正しい道具の持ち方に至り、道具の使用が正しく行われる可能性が高い。したがって、本症例のように詳細な失行症の把握がリハビリテーションにおいても必要であると考えられる。
(船山道隆、2023.5.1.)
症例報告:ロゴペニック型原発性進行性失語を呈し、アミロイドPETおよびタウ PETを用いて非アルツハイマー病性タウオパシーと考えられた一例
百田友紀 慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程(精神・神経科学教室)Momota, Y., Konishi, M., Takahata, K., Kishimoto, T., Tezuka, T., Bun, S., Tabuchi, H., Ito, D., Mimura, M., 2022. Case report: Non-Alzheimer’s disease tauopathy with logopenic variant primary progressive aphasia diagnosed using amyloid and tau PET. Front. Neurol. 13. https://doi.org/10.3389/FNEUR.2022.1049113
【概要】
認知症(認知機能の障害)を呈する疾患群では、症候の類似性や非典型性により臨床診断が困難な場合がある。そのような疾患群の一つに、他の認知機能の障害が目立たず言語症状のみが進行する進行性失語が挙げられ、背景病理に概ね対応した3つの型[非流暢/失文法型、意味型、ロゴペニック(語減少)型]に分類される。近年の認知症診療では、アミロイドやタウなどのバイオマーカーが重視されつつあり、中でも、新たなタウトレーサーを用いた陽電子放出断層撮影 (PET) や血液バイオマーカーが早期診断および病理学的根拠の推定に有用とされる。
Eisai-Keio Innovation Laboratory for Dementia (EKID) の臨床研究「認知症の病態メカニズム解明と創薬標的創出のための臨床研究」でも、従来から行われるアミロイドPETに加え、新たに開発された18F-Florzolotau (18F-PM-PBB3) をトレーサーとしたタウPET、血液検査、ゲノム解析などを実施し、生理学、遺伝学、放射線科、神経内科、精神神経科などの領域横断的な研究が進められている。著者は言語聴覚士として大学院在籍中、本臨床研究のリクルート開始前の準備段階から関わった。本稿で紹介するのは、ロゴペニック型原発性進行性失語 (logopenic variant primary progressive aphasia: lv-PPA) を呈し、当初の臨床所見はアルツハイマー型認知症 (AD) に矛盾しなかったが、EKIDにおける諸検査の結果、ADとは異なるタウオパシー(タウ蛋白の異常蓄積を呈する疾患)が示唆された症例である。
失語症は言語聴覚士が主な専門領域とする症候であるが、変性疾患に伴う進行性失語、ことに本症例が呈した「ロゴペニック型原発性進行性失語」は比較的少なく、通常臨床ではあまり経験しない。本症例報告には、共同著者の各領域における新旧の知見が織り込まれている。患者さんご夫妻および本症例報告に関わった皆様に感謝し、関連疾患の病態解明につながることを期待したい。
【症例】
患者は60代女性で、2年前にアルツハイマー型認知症と診断されたが、明確な自覚症状はなかった。その後、徐々に言葉の出づらさを自覚し、精査のため当院を紹介受診となった。診察では明らかな運動症状、錐体路/錐体外路症状、および失行は認めなかった。日常生活に支障をきたす明らかな記憶障害は認めなかったが、言語性記憶の低下が示唆された。発話は概ね流暢であったが、呼称、語列挙、文の復唱において喚語困難および音韻的誤り[音韻の置換(例:「つめきり」→「きめつり」)、音韻の欠落(例:「おやゆび」→「おゆび」)]が認められた。これらの所見は、一般に背景病理がADであることの多いlv-PPAの特徴に合致した。前医で実施されたPittsburgh Compound-Bをトレーサーとした アミロイドPETの結果は「陽性疑い」であった。磁気共鳴画像法および単一光子放射型コンピューター断層撮影法では、ADを疑う所見が認められた。しかし、18F-FlorbetabenをトレーサーとしたアミロイドPETは陰性、18F-FlorzolotauをトレーサーとしたタウPETは陽性で、ADは否定的と考えられた。タウトレーサーの集積は、主に左半球の上側頭回、中側頭回、縁上回、および前頭葉弁蓋部に認められた。これらの結果から、本症例は前頭側頭葉変性症、中でも病理学的にタウオパシーに分類される前頭側頭葉変性症 [fronto-temporal lobar degeneration (FTLD)]-タウの可能性が高いと考えられた。
本症例では、アミロイドPET、タウPETを含む先端的な検査の結果、当初に想定されたADの臨床診断とは異なる病理背景が推定された。その一方で、すべての検査結果が必ずしも一貫した病理背景を支持しなかった点は、進行性失語を呈する疾患の多様性をあらためて示すものと考えられた。
(百田友紀、2023.4.19.)
精神医学研究の方法論
前田貴記 (慶應義塾大学医学部精神神経科 専任講師)
“こころ”を扱う難しさ
“こころ”というものは、実体としてとらえることはできない。そのような“こころ”に症状が現れてくる疾患について、いかに研究すればよいのであろうか?身体医学においては、身体という実体を客観的に扱うことができるため、身体の病理性については、自然科学に依拠して、また科学技術を駆使して診断し、研究することが可能である。脳科学は、この方法論で行うことが可能である。一方、精神医学においては、“こころ”の病理性については自然科学では扱うことができないため、固有の方法論が必要であり、その方法論が精神病理学である。神経心理学については、脳との関連で“こころ”について考える精神病理学の中の一領域であるが、“こころ”のしくみを理解するために脳を参照するのであって、脳の研究が目的なのではない。
精神医学に固有の方法論
精神医学も医学の一端を担っている以上、当然ながら、事実に基づいた実証的な方法論でなければならないが、精神病理学が基づく事実とは、患者さんの“こころ”の表現(Ausdruck)としての、語られた「ことば」と「行動」という事実である(1)。患者さんの語る「ことば」を大切に扱う姿勢が大前提であり、語られた「ことば」を漏らさず、逐語で、ありのままに記述すること、そして患者さんの「行動」を、定量的にも定性的にも丁寧に記述することが基本である。その上で、精緻な症状分析を行い、“こころ”のしくみの理解、そして精神疾患の病態仮説について考えるのが精神科医のやるべき仕事である。
“こころ”と脳の関係
精神医学において,精神病理学と脳科学とが連繋して研究を進めることができれば,大きな成果が得られることであろう。連繋のために、“こころ”と脳とを架橋する方法論が求められてきたが、いわゆる心身問題(心脳問題)があり、それは難問である。
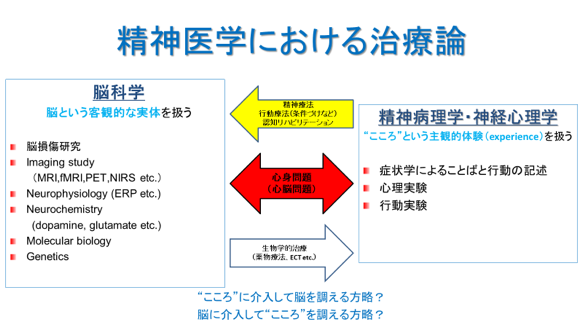
慶應の神経心理学研究室を創始した鹿島晴雄先生は、“こころ”と脳の関係について、“こころ”と脳とは重ね描きの関係であるとし、「見方あるいは方法論の違いであって、どちらが正しいということではなく、またどちらか一方に還元しうるものではない。本来、方法論の範疇が異なるのである」、「両者の連繋は治療的である限りにおいて意味があり、しかもそれは重ね描きの関係であり、すり合わせ対応させることであって、両者を統合することではない。またそれは論理的にありえないことである」(2)と述べている。その上で、“こころ”の現象や症状を脳に繋げ得る言葉で,脳の機能障害を“こころ”に繋げ得る言葉で表現することが大切であり、そのような言葉を共有することの重要性を述べている。
しかるに、今日,脳科学の隆盛によって,精神医学において精神病理学と脳科学との断絶が深刻になりつつあり、さらに精神医学が脳一元論的な思想になってきていることが問題となっている。脳科学については、能力のある神経科学者に大いに進めてもらいたく、我々精神科医を鼓舞していただきたい。神経科学者が精神科医との連繋において求めているのは、臨床における精緻な症状分析であって(特に内因性精神病の症状)、脳の研究ではない。精神医学の方から、“こころ”の現象や症状を脳に繋げ得る言葉で適切に表現をして、神経科学者に伝えることが求められているのである。そして、兄弟子の加藤元一郎先生は、神経科学との連繋においては、病名(疾患カテゴリー)ではなく、“symptom oriented”で連繋するようにと常々仰られていたが、箴言である。精神医学における病名は、いまだにカテゴリー診断かディメンジョン診断かと喧々諤々で混迷しており(3)、カテゴリー診断も、あくまでも操作的診断であり、定義や境界の変転が激しいため、病名のみでのインクルージョンでは、とても神経科学の土俵に乗せられる水準にはないことを、その炯眼で見抜いておられた。精緻を極める神経科学の知見に繋げるための、それに見合った精緻な症状分析、つまり精神病理学の実力が必要ということである。事実、加藤元一郎先生による症状の抽出とその分析は鮮やかであった。
精神科医自らが、安直にも脳科学一辺倒になってしまい、精神医学を草木も生えぬ焼け野原,すなわち、“こころを扱わぬ精神医学”としてしまわないようにしなければならない。精神科医が、内因性精神病についてよく分からない、しっかりと診て関わったことがないという、悪い冗談のような事態になることを危惧している。不毛になりつつある森に、若木を植えては、水遣りを続けているような心境であるが、再び巨樹の聳え立つ森へと再生させるには、長い時間を要するのである。
ありうべき治療論
精神医学には、大きく分けて二つの治療方略がある。一つは、“こころ” (体験)に介入して脳を調えるというアプローチであり(神経系の“再編成”)、もう一つは、脳に介入して“こころ”を調えるというアプローチ(いわゆる生物学的治療)である。内因性精神病においては、主として後者の治療方略がとられてきたが、内因性精神病においても、“こころ”に介入をして脳を調えるという治療方略があって然るべきであり、生物学的治療(薬物療法など)と相補的に進めることで、治療がより高い水準で実現できるものと考えられる。精神疾患は、薬物療法などの生物学的治療だけでは限界があるという臨床的事実もあり、今後、ますます、“こころ”に介入する治療の工夫が必要になってくるものと予測する。というよりも、精神医学はそうあるべきであり、それこそ精神医学にしかできないことであることを、肝に銘じて研究に臨むべきである。
<文献>
1. 前田貴記:“自我”体験の異常のとらえ方. 精神科治療学(in press)
2. 鹿島晴雄:“こころ”と“脳”-重ね描き-. 精神神経学雑誌 116 ; 316-322, 2014.
3. 前田貴記, 沖村宰, 野原博:統合失調症におけるスペクトラムというメタファーの導入の意義と問題点.「精神医学の基盤3:精神医学におけるスペクトラムの思想」, 学樹書院, 104-112, 2016.
(前田貴記、2023.3.21.)
高次脳機能障害の世界をかいまみる
先崎章 (東京福祉大学社会福祉学部教授 / 埼玉県総合リハビリテーションセンター神経科)高次脳機能障害の世界をかいまみる 四半世紀診ている外傷性脳損傷者4名から学んだこと、10年前とこの10年. 高次脳機能研究42: 251-257, 2022
https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbfr/42/3/42_251/_article/-char/ja/
本稿は、両親の故郷である福島県郡山市にて開催された、高次脳機能障害学会での教育講演の内容をまとめたものである。さらに1例、とりわけ思い出深い症例も提示したが、本人より印刷物としては掲載の同意が得られず、4例での構成となっている。本文に記したように、診ている患者さんから新たに教えられることばかりである。長くからの患者さんと話すと、いろいろな感情がわいてくる。初めて対面した時からの自分の歩みをふりかえる。還暦をすぎ、過去のすべてのことが懐かしく、愛おしく思い出される。
小生は20代半ばのかけ出しのころ、東京都下のある病院に外勤で出ていた。そこには東大デイホスピタルを創られた宮内勝先生や、2週に一日だが小木貞孝先生がいらして、若い時からずっと担当している患者さんを入院や外来で診ていた。20年前、いやもっと前からの患者さんたちである。当時、わたしはその意味するところがわからなかった。その後、小木先生の自伝本にも登場する村上医院の村上先生(先代)のところで、時々お手伝いをした。メンタルクリニックの黎明期、下町の医院で20年来の患者さんたちを大勢みていた。
その村上先生がある時、診療所の会報に自分の近況を載せた。その短い1頁の文章が今でも忘れられない。それは、自分は若いかけ出しのころは病気しかみえなかったが、だんだん生活もみえてきて、次第に生活だけしかみえない翁になってしまった、といった内容であった(正確には違っているかもしれません、うろ覚えですみません)。今ならわかる。ご家族やご本人の辛い日々、やるせない日々、あるいは希望をもった日々、そして人生そのものに対峙してきた先生の証だったのだ。
小生はその後30年前に、身体リハビリテーション病院に転勤になった。神経心理をやらなくてはならなくなった。今はなき別館一階の片隅での研究会。加藤元一郎先生はじめ諸先生方から脳損傷者の臨床や学問を一から教わった。そして今がある。と、ここまでの文章で登場した人たち。自分と症例の方々以外、みな鬼籍に入られてしまった。研究会の20代の若い大学院生らの発表を聞いては、その明晰さとスマートさに羨望を感じる今日この頃。さらに若い頭脳を取り込み、研究会がますます発展されることを願ってやみません。
(先崎章、2023.2.27.)
内受容感覚と自己主体感の関係性および心拍によるその調整:探索的研究
是木明宏(下総精神医療センター 精神科医長)Koreki A, et al. The relationship between interoception and agency and its modulation by heartbeats: an exploratory study. Sci Rep. 2022 Aug 10;12(1):13624.
【研究概要】
本研究は健常者のみを対象としているが、その研究背景には臨床がある。本研究のテーマの一つである自己主体感(Sense of agency)とは、何か出来事(身体運動も含む)が起きた時にそれを起こしているのは「自分」であるという感覚である。統合失調症ではこの自己主体感の障害が想定されている。また本研究のもう一つのテーマである内受容感覚(Interoception)とは、身体内部の感覚を意味し、そこには呼吸や脈拍などが含まれる。この内受容感覚も精神疾患全般で異常がよく報告されている。これら2つの領域が関連しうることを示したのが本研究の学術的価値である。これは精神疾患における多彩な症状の病態生理をより多角的に説明しうる可能性を生み出す。
具体的な研究方法は以下である。被験者の自己主体感をIntentional binding課題で評価、内受容感覚を心拍区別課題で評価した。いずれも代表的な神経心理学的課題である。結果は、両者は正の相関を示した、つまり内受容感覚が良い被験者は自己主体感も高く、逆に内受容感覚が悪い被験者は自己主体感も低かった。
さらに興味深いのは脈拍との関係である。ここでは心拍という内受容感覚のシグナルが圧受容体を通して脳に信号を送ることで脳機能(本研究では自己主体感)が変化するかという点を評価している。結果は、内受容感覚が良い被験者では収縮期で自己主体感は高く、逆に内受容感覚が悪い被験者では収縮期で自己主体感は低かった。
よって本研究では健常者の範囲ではあるが、悪い内受容感覚は全体的にみても脈拍との関係性で見ても低い自己主体感と関係していることが示された。今後はその因果関係や患者群での臨床的意味を検討していくことで、精神疾患の病態生理への深い理解や新たな治療法の開発につながる可能性が考えられる。
【将来的展望】
本研究のような心脳連関からの研究アプローチは脳のみの研究では未解明だった領域にメスを入れられる可能性がある。近年、脳機能は収縮期と拡張期で異なる可能性が示されてきている。大まかには運動機能は心臓の収縮期で強まり、感覚機能は拡張期で強まるとされる。ここには身体の内外からの感覚、つまり内受容感覚(ここでは心拍)と外受容感覚(視覚や聴覚など)とを脳がいかに適切に協働させ最適な脳機能を作り出しているかが反映されている。このような脳機能の側面が適切な自我形成にも関与していることが本研究からは示唆され、逆にその脳機能の変調は様々な未解明の症状を説明できる可能性がある。今後の研究に精進してまいります。
(是木明宏、2023.1.20.)
第1回 大学院生 Research Day
三村悠 (慶應義塾大学医学部 大学院博士課程)
去る2022年8月31日、慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室主催で「第一回 Research day」が開催された。発案者は同教室准教授の内田裕之先生で、先生が留学されていたトロント大学で毎年行われていた学内のポスドクや院生が一同に介して発表する同名称のプログラムから着想を得て、この度ご提案いただいた。教室内の教授以下助教の先生方まで参集いただき、総勢16名の大学院生が各々の研究内容を紹介し、コメントをいただいた。座長や司会も大学院生が担当し、機材トラブルなどもあったがなんとか乗り切ることができ、全体として非常に実りのある1日となった。
コロナ禍で大学院生同士の交流が極端に減った現在において、他院生の研究内容を知ること、発表を聞くことは非常に重要な機会となり切磋琢磨することができた。神経心理教室からは3名の院生が発表したため、下記紹介する。
(三村悠、2022.12.4.)
演題5 菅波 美穂 博士課程3年
「他者の罪に対する罰の評定課題を用いた脳損傷における道徳判断の検討」
博士課程3年の菅波は昨年度、精神神経科外来の患者様の協力を得て表題課題に関するデータを収集しその予備解析の内容について発表した。
脳損傷による社会行動障害は脳損傷者の社会復帰を妨げる大きな要因の一つとなっている。社会行動障害の要因の一つは道徳観であると考えられている。道徳観の変化により、してはいけないことをする、するべきことをしない、許されるべきでない行動を許容してしまう、責めを負わせる必要がない行動について必要以上に責めを負わせる、などさまざまな行動が生じる。後者2つは自分には直接影響のない第三者の行動についての道徳的判断をするという社会機能を維持する利他的他罰にかかわるものである。ここに本研究では注目した。
本研究では、第三者に対する道徳判断が脳損傷にどのように影響を受けるのかを検討するため、短いシナリオを読み登場人物がどの程度悪いと思うかを判断する道徳判断課題を作成し、脳損傷群35名と年齢・性別・学歴をマッチした健常対照群30名からデータを収集した。その結果、脳損傷群は健常群平均から有意に乖離する評価をする症例が多いことが分かった。また、行為者が意図を持ち不道徳な行為をするシナリオでは健常対照群に比しより悪くないと判断し、行為者が行動した結果意図していなかった他者への害を招いてしまったシナリオでは健常対照群に比しより悪いと判断する傾向がみられた。また、感情面ではどのようなシナリオを読んでも常に強い感情を覚える群とほとんどに感情が動かない群に脳損傷者が多く含まれていた。
今後はデータをさらに詳しく解析し脳損傷者の第三者に対する道徳判断の特徴を明らかにしていく予定である。
本研究は一般社団法人日本損害保険協会2021年度交通事故医療一般研究助成、および2021年度公益財団法人井之頭病院研究助成金のサポートを受けて実施した。
(菅波美穂、2022.12.4.)
演題6 三村 悠 博士課程3年
「健忘型軽度認知障害におけるコリン機能の評価:TMS-EEG-MRI研究」
博士課程3年の三村は、現在直接指導を受けている精神病態生理学研究室での研究内容より、表題の内容を発表した。
大脳皮質の神経生理機能の評価法として経頭蓋磁気刺激(TMS)と高精度脳波計(EEG)を組み合わせたTMS-EEG法が知られている。TMSによる入力に対する反応を脳波で評価する試みである。TMSによる入力時には単発刺激のみならず種々のプロトコルがある。今回は末梢感覚刺激とTMSによる中枢刺激を組み合わせた短潜時求心性抑制(SAI)を用いた。SAIプロトコルによる出力は大脳皮質のコリン作動性神経生理機能を反映していると考えられている。さらに近年、脳内のノルエピネフリン機能を非侵襲的に計測する手法としてneuromelanin(NM) -sensitive MRIが注目されている。NMは代謝産物であり、青斑核におけるノルエピネフリン機能指標と考えられている。青斑核はアルツハイマー病でも病初期に変性が起こることが知られており、その変性はマイネルト基底核のコリン作動神経へ影響を与えると考えられている。
今回、健忘型軽度認知障害(aMCI)21名と年齢・性別をマッチした高齢健常者(HC)23名に対してSAI法を組み合わせたTMS-EEG法による評価及びNM濃度の評価を行った。結果として、HCの左DLPFCにおいて、SAI法による平均電場の抑制効果が確認された一方で、aMCIの左DLPFCにおいては同様の抑制効果が確認されず、aMCIのDLPFCにおけるコリン作動性神経回路の障害がTMS-EEG法を通じて確認された。TMS-EEGは非侵襲的にコリン作動性神経回路の評価が可能であることが示唆された。一方でNM濃度については有意差が得られず、またSAIの抑制効果との相関関係もみられなかった。NM濃度についてはさらにサンプル数を増やして検討していく予定である。
同内容は解析結果をさらに整理して、今後投稿予定である。
(三村悠、2022.12.4.)
演題7 南 房香 「うつ病の母から未発症の娘への脳構造の世代間伝達」
博士課程3年の南は、Psychiatry and Clinical Neurosciencesに先日acceptされた学位論文の研究内容を発表した。
Minami F et al: Intergenerational concordance of brain structure between depressed mothers and their never-depressed daughters. Psychiatry and Clinical Neurosciences 76: 579-586, 2022.
親は子の認知、行動、脳に大きな遺伝的、環境的影響を与え、これを世代間効果という。世代間効果は気分障害患者においても観察され、特に母親と娘との間でうつ病の強い関連があることが知られている。本研究の主な目的は、うつ病患者とそのうつ病でない子孫の間で、ヒトの脳における女性特有の世代間伝達パターンを調査することであった。
うつ病の既往を持つ寛解期の親とそのうつ病の既往のない実子を含む34家族から78名を募集した。MRI画像データのsource-based morphometry解析およびsurface-based morphometry解析を用いて、4種類の親子間(すなわち、母-娘、母-息子、父-娘、父-息子)の脳構造の類似性の程度を検討した。
独立成分分析により、結果両側の前帯状皮質、後帯状皮質、楔前部、中前頭回、中側頭回、上頭頂葉、左角回などのデフォルトモードネットワーク(DMN)および中央実行ネットワーク(CEN)に位置する脳領域において、母-娘ペアでのみ灰白質構造の有意な正の相関をみとめた。同様の所見は、他の3組の親子ペアではみとめなかった。FreeSurferによる解析では各ROIの皮質体積、皮質表面性、皮質厚の相関係数をペアで算出したところ、右尾側中前頭回の皮質体積および左尾側中前頭回の皮質表面積において母-娘で有意に正の相関を認めた。同部位における相関係数を他のペアと比較した結果、母-娘間に有意に相関係数が高いことが示された。
本研究からDMNやCENといったうつ病に関与する脳ネットワークにおいて、寛解期の親とその高リスクの実子との間に女性有意な世代間伝達パターンを有することが示された。本研究の結果は、うつ病発症リスクの高い者への早期介入の視点につながることを期待する。
今後は、周産期の母親の脳機能の変化や精神症状への影響、さらに生まれてくる子供の神経発達への影響や、高リスク者への予防などに関する調査をしていきたいと考えている。
(南房香、2022.12.4.)
気分障害における寛解と回復に関連した神経回路基盤の解明に資する縦断MRI研究(通称国際脳研究)
平野仁一 (慶應義塾大学医学部精神神経科 専任講師)
近年大規模脳画像データを用いて、脳の発達障害、老化の制御、精神・神経疾患の病因解明・診断・治療法等に迫ろうとする国家プロジェクトが世界的に多く具体化されつつあり、本邦においても国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が「戦略的国際脳科学研究推進プログラム」(以下、国際脳)を推進しています。
国際脳は、本邦の多くの大学・研究機関が参画し、健常から疾患に至る脳画像等の総合的解析、AIによる脳科学技術開発、ヒトと非ヒト霊長類動物との神経回路比較研究等を目指すビックプロジェクトです。慶應義塾大学医学部精神神経科は、国際脳の中でうつ病の縦断脳画像データを取得し、その神経回路基盤の解明を目的とした「気分障害における寛解と回復に関連した神経回路基盤の解明に資する縦断MRI研究」を国立精神・神経センター、京都大学との共同研究として担当しています。
具体的には成人期から高齢期のうつ病に対する通常治療(薬物療法・認知行動療法・電気けいれん療法・経頭蓋磁気刺激)を受療するうつ病症例350例と健常対照例150例を対象として、MRI脳画像(構造画像、安静時脳機能画像等)、臨床データを取得し、機械学習を応用しうつ病における①寛解・回復に関連する神経回路基盤の解明、②症状ドメインと関連した神経回路基盤変化の解明、③各治療の寛解・回復の予測因子となる神経回路基盤の解明、という3つの研究課題について検証していきます。
うつ病はQOLや社会生活に与える影響が大きいとされ、その異質性の高さも指摘されています。本研究で神経回路基盤が解明され、各治療法に対する治療効果予測モデルやうつ病の層別化が実現できれば、うつ病の精密医療に繋がり、気分障害の実臨床にも資する結果が得られるのではないかと考えています。
(平野仁一、2022.11.26.)
オックスフォード便り
和氣大成 (オックスフォード・ウエヒロ/セントクロス 派遣研究員. オックスフォード大学哲学科ウエヒロ応用倫理センター)WAKE, Taisei. Oxford Uehiro/St Cross Scholar. The Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics
BEEEEEP! HONK! HONK!
イギリスで車を運転して気がついたことがある。やけにクラクションを多く聞くことだ。10分も走れば2、3回は鳴る。自分に向けられたものでなくても、いい気はしない。日本ではあまり鳴らされたことがないので、最初こそビクビクしていた。けれどそのうち、これは何も攻撃的なメッセージではなく、「以心伝心よりも言葉で伝えることを大切にする文化」なのかとひとり合点して、心を落ち着けた。
「人としてどうあるべきか」を言葉で根拠を持って説明するのが哲学の一分野としての倫理学である。印象論に過ぎないが、日本ではあまり倫理について積極的に話し合うことが好まれない。智に働けば角が立つ1)、100年と少し前に倫敦に滞在した小説家もそう喝破している。限られた医療資源を誰に割り当てるかという、倫理的には重要な議論も、議論自体が倫理的でないと嫌悪感を持つ人もいる。
言わなければ伝わらないが、言うことが許される文化。言わなくても伝わるが、言うことが許されない文化。
かたやここオックスフォード大学の Faculty of Philosophy は50名以上のフルタイム専任教員の他、150名以上の教員を要する世界でも類を見ない哲学の地だ2)。そして哲学は、当大学の学士過程で最も人気が高いそうだ3)。
この哲学科に、筆者が所属するThe Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics4)は設置されている。AI (Artificial Intelligence) 、パンデミック、医療倫理も含めた最新かつ伝統的な応用倫理学の議論が、医学や公衆衛生、人文科学の専門家とともに、時には統計学や実験心理学のアプローチとも接続しながら、ダイナミックな人的交流の中で行われている。
賛否は別の機会に譲るとしても私の興味を引いた議論の一例を挙げるなら、(当センターのサンプリングバイアスにならないことを祈る)、道徳性のbio enhancement 5)や、医療におけるAIと責任の帰属6)などである。
そのような環境に身を置くうち、以前から消化不良だった言葉がますます気になってきた。それは医療における「中立」という言葉である。文献に登場する頻度も2000年代に入ってから急激に増加している。使われる文脈の一つに、「意思決定支援」がある。
意思決定支援の背景にある考えは、医療倫理や生命倫理の中核となる原則の一つである「自律(autonomy)」の尊重である。その含意は自己決定にとどまらない広がりがあるにせよ、一人一人の価値観を重視した医療を目指すこと、それはとても重要な考えだ。
しかし当事者の価値観が、多くの人から見てその人の「最善(best interest)」を損なう可能性が高い場合、「自律」と「最善」をどのように調整するかについては多くの立場があり議論は続いている。
もしかしたら「医療に関わるものが自分の価値観を押し付けない」という最低限の矜持として「中立」という態度を取りたいのかもしれない。しかしこれまでも「中立」という概念を巡っては、多くの注意が喚起されてきた。例えば既存の権力関係の勾配や資源配分の不均衡を是認するだけになるかもしれない。
あるいは神は死んだ7)と言われて久しい現在、「エビデンス」や「科学的」 という「the view from nowhere」の“正しい”視点を欲しているのかもしれないと邪推さえしてしまう。現在使われるような意味での「客観性」概念ですら19世紀に「誕生」した歴史的経緯を指摘する研究すらある8)。ともかくも、目の前の人にとって最も善い選択肢を選ぶ支援をする際、「人間から完全に離れた」“正しい”視点というものがどれほど有効なのか、私にはまだわからない。
臨床の現場はひと呼吸も整える暇などないかのように次から次に対応に追われる。「患者中心」「尊厳」などそれ以上検討しにくい言葉の下、せかせかと進める歩みの先が間違った方向に向かわないように、深く吟味された“善い”目的地が必要ではないだろうか。現場と理論のギャップを少しでも埋める手がかりをこのオックスフォードで得られたらと願う。
というようなことを考えながらクライスト・チャーチ・カレッジに入ると、映画『ハリー・ポッター』で有名な食堂にふと迷い込む。紅や黄色の葉が眩しい秋の新学期が始まる。

1) 夏目, 1906, 草枕; 2) Faculty of Philosophy, University of Oxford website; 3) オックスフォード大学日本事務所代表アリソン・ビール氏インタビュー; 4) www.practicalethics.ox.ac.uk; 5) Savulescu, 2001, Bioethics; 6) Kiener, 2021, AI & SOCIETY; 7) Nietzsche, 1882, The Gay Science ; 8) ダストンら、2021, 客観性
(和氣大成、2022.10.20.)
解説 中立は何色か
実はイギリスから送られてきた上の写真を見たとき私は、ハリー・ポッターに出てくる講堂だと思った。そう思った方はほかにもいらっしゃるのではないかと推定しているが甘いだろうか。もちろんHPの原稿に和氣大成研究員 https://www.practicalethics.ox.ac.uk/people/dr-taisei-wakeが映画の写真を添付するはずはない。彼が記載しているとおり、これは和氣研究員が留学中のオックスフォード大学内にあるcollege のhttps://www.chch.ox.ac.uk/食堂である。写真で見るといかにもホグワーツそのものにみえるが、イギリスにはこういうハリー・ポッターゆかりの撮影場所があちこちにあるらしい。日本でいえば千と千尋の神隠しの金具屋のようなものにあたるのであろう。
和氣研究員のThe Oxford Uehiro Centre for Practical Ethicsへの留学が決定したのは2020年7月。実際に渡英したのは2022年4月である。もちろんこの時間差はコロナ禍の影響である。「オックスフォード便り」は、2022年9月12日の当学の研究会で和氣研究員の『「中立」であることの哲学』と題されたインパクトあるWeb講演内容に関連している。リモート会議が急速に普及し、地球のどこにいても研究会に参加できるようになったのは、言うまでもなくコロナ禍のもたらした大きな変化のひとつで、するとコロナも悪いことばかりではなかったという言葉が頭をよぎるが、次の瞬間、コロナに苦しんだ膨大な数の方々がいらっしゃるという事実に気づき、決してそんな言葉は口にせず沈黙する。こういうときは、中立を保つのが最も安全な態度である。
和氣研究員の講演テーマである中立は、そういう消極的な中立ではない。中立だから意見を表明しないということではなく、中立な立場から意見を表明するという積極的な中立を意味している。意見とは、それが中立な立場から表明されたときには普遍的な価値があり、常に正しいか、少なくとも逆に誤っていることはないという漠然としたイメージがあるが、では次のような場合にはどう考えるのかと和氣研究員は問いかける。
・虐待が発生しているとき。虐待者と被虐待者に対して、第三者が中立の立場を取るとはどういうことか? 虐待を容認することにならないか?
・兄弟喧嘩が発生しているとき。父親が中立の立場を取るとはどういうことか? 年長の兄が勝つことを容認することにならないか?
もし上の「中立」が正しい態度でないとしたら、では正しい態度とはどのようなものになるのか? 上の「中立」とは別の種類の「中立」があるのか? そもそも「中立」とは何か?
和氣研究員の解説文の中に、「それ以上検討が不可能な言葉」への言及がある。「患者中心」や「尊厳」がその例として挙げられている。こうした言葉は、いわば絶対に正しく、反論を許さないという性質を持っているが、「中立」もその一つかもしれない。そして「絶対に正しく、反論を許さない」とはすなわち、単にその言葉は「正しい」ということ以外には何ら具体的な意味を有していない。かつて、「意思決定支援」において望ましい態度として「中立」が提案され採用された時点では、「中立」はおそらく息づいているかのような瑞々しい言葉だったのであろう。それが急速に色褪せ、今ではただ「正しい」という白いペンキが全面に塗られた単なる記号と化しているのではないか。
「正しい」とストレートに言うと逆に胡散臭い空気が漂うが、それを別の言葉に言い換えると空気は強制正常化される。そういう言葉は便利で安全なので多く人が口真似し常套句になる。「寄り添う」もその代表的な一例であろう。「エビデンス」や「社会実装」も同類である。こうした言葉を口にし、自分はこの言葉にそった行動をしていると言えば、それは「自分は正しい」と宣言していることと同値である。だから「寄り添う」「エビデンス」「社会実装」などの言葉を人が発するのを聞くと、実に軽薄で、さらには醜いと私などは思うのだが、まあそこまではいいとしよう。醜さが本当に露わになるのは、こうした言葉の否定形が使われる場合である。「寄り添っていない」と言えば、それは強い批判の言葉になる。「正しい」が白だとすれば、「寄り添っていない」は黒なのである。もはや「寄り添う」が何を意味しているかは希薄化し、「あなたは寄り添っていない」とは、「あなたは正しくない」と批判していることに等しい。反論を許さない批判ほど危険なものはない。「差別」という批判も特に危険なものの一つで、「それは差別だ」と決めつければ、相手はそれ以上発言することを事実上禁じられ、その反対の「差別でない」とされた発言が常に正しいということになる。「寄り添う」も「差別」も、実に醜い言葉である。「中立」もそうした言葉になる危険を相当に孕んだ言葉であることを、和氣研究員の講演を聴いて理解することができた。「中立」などということがそもそもあるのか。「客観性」と同様、ただ理想的な「白」を意味しているだけで、実体はどこにもないのではないか。
「中立」も「客観性」も、非常に多くの知的活動のベースにある概念で、これらの言葉を出されると人はそれ以上考えることなくそれは正しいと納得するのが常である。だがその正しいと信じていることは正しいのか、正しくないのか。もし正しくないとすれば、あるいは、正しくない部分があれば、医療活動も科学もその土台を失いきわめて脆弱なものになる。こうした問題を追究できる学問は哲学以外にはない。哲学の牙城、オックスフォード大学哲学科ウエヒロ応用倫理センターで文字通り哲学に浸る日々を送っている和氣研究員の次のレクチャーに大いに期待したい。
(村松太郎、2022.10.31.)
拒食タイプと感染症の合併が摂食障害のリフィーディング期の血球成分の最低値を予測する
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Funayama M, Koreki A, Mimura Y, Takata T, Ogino S, Kurose S, Shimizu Y, Kudo S. : Restrictive type and infectious complications might predict nadir hematological values
among individuals with anorexia nervosa during the refeeding period: a retrospective study. Journal of Eating Disorders (2022) 10:64 https://doi.org/10.1186/s40337-022-00586-x
【はじめに】摂食障害において血球成分が低下することは報告されているが、その機序は明らかではない。特に入院後のリフィーディング期には血球成分が更に低下し、1~2週間後に改善することが多い。したがって、この時期の血球成分の最低値に関係する因子を明らかにすることは臨床上重要である。今回われわれは、摂食障害のリフィーディング期の血球成分の値に影響を及ぼす因子を求めた。
【方法】1999年から2018年までに足利赤十字病院神経精神科病棟に入院した摂食障害の101入院例(複数回の入院例を含む55名)を対象とした。ヘモグロビン、白血球、血小板といった3つの血球成分について、入院時、リフィーディング期の最低値、その2時点での減少割合といった3つの値を求めた。これらの値への説明因子として罹病期間、性別、拒食/過食嘔吐タイプ、body mass index、BUN/Cr比、感染症の有無、カロリー摂取量、慢性腎臓病(ヘモグロビンのみ)、ALT(血小板のみ)を用い、一般化線形混合モデルにて統計解析を行い、多重比較補正を行った。
【結果】入院時のヘモグロビンは12.1 ± 2.7 g/dlから22.3% 減少して9.4 ± 2.5 g/dlに低下した。赤血球の輸血を必要とした12入院例のうち5入院例(41.7%)においては、入院時のヘモグロビン値は正常範囲内であった。白血球は5387 ± 3474/μlから33.6%減り3576 ± 1440/μlに、血小板は226 ± 101 ×103/μlより24.3%の減少を認めて171 ± 80 ×103/μlと低下した。これらの血球成分の最低値は入院5~10日後に出現した。ヘモグロビンの最低値と白血球の最低値など、3つの血球成分の間では最低値や減少割合を中心に有意な相関を示した。一般化線形混合モデルからは、拒食タイプは白血球の最低値に関連し、感染症の合併(主に誤嚥性肺炎とカテーテル関連の尿路感染症や敗血症)はヘモグロビンの最低値と低下割合、さらには赤血球の輸血の必要性と関連していた。
【考察】摂食障害入院例のリフィーディング期の血球成分の低下は、拒食タイプと感染症の合併といった因子によって予測できる可能性がある。特に、感染症のコントロールは重要であろう。誤嚥性肺炎やカテーテル関連の感染症は、寝たきりを防いだり不必要なカテーテルを抜去したりすることである程度予防できることができる。また、入院時にヘモグロビン値が正常範囲内であっても赤血球の輸血を必要とした例が少なくないため、拒食タイプや感染症の合併を有した例を中心として、摂食障害の入院後1~2週間の間は入院時のみならず入院後に追加の血液検査が必要であろう。
(船山道隆、2022.9.1.)
初期のPosterior cortical atrophyにおける視空間ワーキングメモリの低下はタッピングスパン課題で捉えられる
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Michitaka Funayama, Taketo Takata, Yoshitaka Nakagawa, Kosaku Sunagawa, Asuka Nakajima, Hiroaki Kawashima, Masaru Mimura.
Visuospatial working memory dysfunction from tapping span test as a diagnostic tool for patients with mild posterior cortical atrophy
Scientific Reports. 11, 10580. https://doi.org/10.1038/s41598-021-90159-w, 2021
【背景】Posterior cortical atrophy (PCA) は50~65歳といった比較的若年に発症する変性疾患のひとつの形である。しかし、初期段階のPCAを診断することはしばしば困難であり、診断までに時間がかかったり誤診されやすかったりすることも知られている。その理由は、症状面において視空間障害が典型的であるが、その他の言語、記憶、行動のいずれの側面もほぼ正常に保たれることが最も大きな要因である。さらに、神経心理検査においてもMini Mental State Examination (MMSE)の図形模写課題を除いて、臨床現場で簡便にできる検査法が知られていないことも一因である。実際に初期のPCAにおいては、MMSEやHasegawa Dementia Scale-Revised(HDS-R)といった簡易な認知機能検査では正常値になることがほとんどである。しかし、多くのPCA例で若年発症にもかかわらず発症から数年のうちに就労が困難となり、家庭生活でも車の運転、電化製品の使用、料理や食器の片付け、金銭の支払い、着衣、入浴など日常生活に欠かせない能力の低下が目立つようになる。典型的なアルツハイマー病よりも日常生活での問題が多いともいわれるが、PCAの患者を支援する際にもまずは適切な診断と症状のメカニズムの把握が必須である。今回われわれは臨床現場で極めて手軽なタッピングスパン課題が初期のPCAの診断の補助になり得るか、また、タッピングスパン課題の成績がPCAで視空間ワーキングメモリの成績を表しているのかどうかについて調べた。
【方法】対象はClinical Dementia Rating (CDR) 0.5の段階のPCA 8例(61.5±5.6歳)と年齢を合わせたCDR 0.5の健忘型アルツハイマー病(AD)9例(61.4±6.3歳)。両群にMMSEとHDS-Rに加えて、標準注意検査法のタッピングスパン課題と数唱課題を同順と逆順で行った。視空間ワーキングメモリに関して遅延マッチング課題と移動するドットで結ばれる図形組み立て課題を行った。これらの検査の前提として、2つの物(2つ条件)と3つの物(3つ条件)の間の位置関係を問う位置関係課題を行った。
【結果】PCA 8例とも、目的のものに視線を向けることができない精神性注視麻痺と視覚のもとでものをつかめない視覚失調は認めず、同時に複数のものに視覚で注意を向けることが困難である背側型同時失認(視覚性注意障害)が視空間障害の中核症状であった。位置関係課題は2つ条件でPCA8例とも全問正答したが、3つ条件ではPCA8例中2例において誤答を認めた。両群間でMMSE, HDS-R、数唱課題の成績では差を認めなかったが、タッピングスパンの成績は同順(PCA 2.1±1.1, AD 4.2±0.7, p<0.01)、逆順(PCA 0.9±1.2, AD 3.1±0.8, p<0.01)ともにPCA群が低かった。数唱のスパンからタッピングスパンのスパンを引いた差分は同順(PCA 3.5±0.9, AD 0.7±1.1, p<0.01)、逆順(PCA 2.0±1.1, AD -0.1±0.6, p<0.01)ともにPCA群で大きく、数唱と比べてタッピングスパンの成績の低下がPCA群において目立った。PCA群におけるタッピングスパン課題の成績は、視空間ワーキングメモリ課題と強い相関を示した(r=0.64~0.93)。
【考察】PCA群では数唱課題は健忘型アルツハイマー病と同程度の成績であったが、タッピングスパン課題の成績は極めて悪く、同順で2桁程度、逆順ではほとんどできないレベルであった。実際、PCAの視空間障害はBálint syndromeの中でも精神性注視麻痺や視覚失調といった症状は最重度になるまで出現せず、初期から中期までは同時に背側型同時失認が主症状である。したがって、初期のPCAでは、精神性注視麻痺がないので検査自体は実施が可能であり、さらに視覚失調がないので手を使うタッピングスパン課題であっても視空間ワーキングメモリの低下を反映できると考えられる。したがって、視空間障害を中核症状とするPCAにおいてタッピングスパン課題は診断の補助となる可能性を示している。 本研究からはタッピングスパン課題の成績が視空間ワーキングメモリの能力を反映していることが明らかになった。以前よりPCAではその主症状である視空間障害のベースとなる視空間ワーキングメモリが低下しているという報告が数例の研究で言われていたが、本発表では今までよりも多い例数でそれを明らかにした。
(船山道隆、2022.8.1.)
初回エピソード精神病の中での自己免疫性脳炎と統合失調症スペクトラム障害との鑑別
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Michitaka Funayama, Akihiro Koreki, Taketo Takata, Shin Kurose, Tetsuya Hisamatsu, Atsushi Ono, Tatsuhiko Yagihashi, Jin Mizushima, Yoshikazu Yagi, Satoyuki Ogino, Hiroki Oi, Yu Mimura, Yusuke Shimizu, Shun Kudo, Akira Nishi, Hiroo Mukai.
Differentiating autoimmune encephalitis from schizophrenia spectrum disorders among patients with first-episode psychosis. Journal of Psychiatric Research151, 419-426, 2022
https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.05.008
【はじめに】初回エピソード精神病の原因の多くは統合失調症を中心とする精神疾患であるが、まれではあるものの自己免疫性脳炎の症例が初回エピソード精神病の中に紛れてくることがある。自己免疫性脳炎は精神疾患とは治療法が根本的に異なり、さらに早期の治療介入によって良好な予後が得られるため、両者の鑑別は臨床上極めて重要である。ところが、この2つの疾患の精神症状に関する相違点は今まで明らかになっていない。例えば、抗NMDA受容体脳炎を中心とする自己免疫性脳炎の精神症状は、統合失調症様の症状、幻覚・妄想、類循環精神病(非定型精神病)などと記載されているのみである。今回われわれはこの両者を比較するcase control studyを世界で初めて行った。対象を初回エピソード精神病の症例として、後方視的にこの2つの疾患の精神症状の違いを調べた。
【方法】足利赤十字病院神経精神科病棟に2001年から2021年の期間に初回エピソード精神病のために入院した症例の中の、自己免疫性脳炎10例と統合失調症スペクトラム障害177例を対象とした。精神症状を中心に、神経症状、神経心理学的所見、既往歴、病棟生活の自立度(看護必要度)についてもカルテ調査を行い、両群で比較を行った。精神症状としては幻覚全般、幻視、幻聴、シュナイダー一級症状の中の言語幻聴(自己の行為に随伴し口出しする形の幻聴など)、知覚変容、妄想全般、シュナイダー一級症状の中の妄想性自己体験(させられ体験など)、シュナイダー一級症状全般、妄想性誤認症候群、緊張病症候群、連合弛緩を取り上げた。統計学的手法としてはフィッシャー正確確率検定を用い、精神症状に関してはボンフェローニ多重比較検定も用いた。
【結果】自己免疫性脳炎の精神症状には知覚変容が(p=0.019)多く、一方で統合失調症スペクトラム障害に多い精神症状にはシュナイダー一級症状全般(p=0.017)、 妄想全般(p=0.014)、連合弛緩(p=0.003)が挙げられた。特に、シュナイダー一級症状と連合弛緩は統合失調症スペクトラム障害のみに出現した。また、けいれんや言語症状は自己免疫性脳炎のみに、ARMS(精神病発症危険状態)の既往は統合失調症スペクトラム障害のみに出現した。病棟生活の自立度は統合失調症スペクトラム障害の方が高かった。
【考察】自己免疫性脳炎の初期においては、けいれんや不随意運動などの神経症状が出現する前に精神症状が前景に立つことが多い。また、MRIや髄液検査といった検査がその場で行うことができない治療環境であることも少なくない。すなわち、精神症状を元に自己免疫性脳炎と統合失調症スペクトラム障害の鑑別を要求される場面がある。本研究で明らかになった知見が、鑑別の一助やMRIや髄液検査などの詳細な検査の必要性の有無の目安になるかもしれない。
(船山道隆、2022.7.1.)
アパシー、脱抑制、精神疾患の併存が外傷性脳損傷後の就労状況に関係する
船山道隆 (足利赤十字病院神経精神科部長)Funayama M, Nakagawa Y, Nakajima A, Kawashima H, Matsukawa I, Takata T, Kurose S.
Apathy level, disinhibition, and psychiatric conditions are related to the employment status of people with traumatic brain injury.
Am J Occup Ther 2022 Mar 1;76(2):7602205060. doi: 10.5014/ajot.2022.047456.
【背景】
高次脳機能障害を起こす疾患の中でも外傷性脳損傷は脳卒中と比較すると若年に出現する割合が多い。したがって、外傷性脳損傷後に就労につなげることはリハビリテーションにおいて極めて重要なテーマである。過去の研究からは、外傷の重症度、損傷前の就労状況、就労を目的とするリハビリテーションへの参加、身体機能、認知機能、情動面の安定性などが就労への予測因子として挙げられている。しかし、外傷性脳損傷後にしばしば出現するアパシー、脱抑制、精神疾患の有無といった要素は、過去の研究において包括して取り上げられることはなかった。今回われわれは(Funayama et al 2022)これらの因子を考慮して外傷性脳損傷後の就労状況を調べた。
【方法】
われわれが対象とした例は、2015年から2020年までに足利赤十字病院と江戸川病院の高次脳機能外来を受診した18歳から65歳までの外傷性脳損傷例110名である。就労状況は3段階(一般就労、福祉的就労、就労なし)に分類した。就労状況を説明する因子として、患者背景(年齢、性別、教育歴、損傷からの経過年数、損傷前の就労状況、外傷の重症度、てんかんの有無、精神疾患の有無)、運動機能(FIMの歩行・車いす評価項目)、認知・精神機能(知能をWAIS-Ⅲの言語性および動作性IQ、エピソード記憶をリバーミード行動記憶検査の成績、遂行機能をウイスコンシン・カード・ソーティング・テストの達成カテゴリー数、アパシーを標準意欲検査法の面接による意欲評価スケール、脱抑制をBADS質問紙の脱抑制に関係する5項目を用いて評価)を用いた。統計手法には線形判別分析を用い、有意水準をp<0.05と設定した。
【結果】
良好な就労への関連因子として、精神疾患を認めないこと(p<0.01)、アパシー(p<0.01)や脱抑制の程度(p<0.05)が軽いこと、若年であること(p<0.05)が挙げられた。本研究の問題点は病識、性格傾向、就労を目的とするリハビリテーションへの参加、経済状況を考慮に入れていないことである。これらの問題点はあるものの、外傷性脳損傷後の就労状況には、精神疾患の併存、アパシー、脱抑制といった精神症状が大きく関連する可能性が示された。
【本研究が示唆すること】
この結果がリハビリテーションの現場へ示唆する点は以下のようであろう。外傷性脳損傷後の個人に出現するこれらの症状を軽減するため、リハビリテーションに関わるわれわれは、その人その人にあったテイラーメイド的な対応をする必要がある。もちろんこの点は、上記に挙げた並存した精神疾患のみを対象としているわけではない。例えば、アパシーが強い状況であっても、本人のやる気がでるような就労内容や就労訓練内容を提供することで就労や就労訓練につながる場合が少なくない。脱抑制に関しては、精神科や心理系からのアドバイスが有効である。例えば、福祉的就労に関わる福祉分野の職員は、利用者に優しくすることだけが重要であると考えていることが多い。しかし、脱抑制が顕著な利用者に関しては、これらの職員の関わり方によってむしろ利用者の脱抑制を悪化させることが少なくない。もちろん優しく接することは基本中の基本なのではあるが、その一方で適切な限界設定を定めることが重要であり、その方法によって利用者の脱抑制の軽減につながることが多い。あるいは、集団のリハビリテーションの場を利用して脱抑制の強い個人が周囲からフィードバックをもらうこともひとつの方法であろう。
本研究の結果をひとつの踏み台として、外傷性脳損傷後の就労に対してよりよいアプローチが次々に開発されることを強く切望する。
(船山道隆、2022.6.1.)
MRI-SPECT-EEGで同時に認めた異常所見が虚血への脆弱性を示唆した一過性全健忘症の一例
三村悠 (慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)Yu Mimura, M.D. 1)2), Michitaka Funayama, M.D., Ph.D. 2), Masaru Mimura, M.D., Ph.D. 1).
Combined abnormal findings of MRI-SPECT-EEG suggest vulnerability to ischemia in transient global amnesia.
Journal of the Neurological Sciences Volume 438, 15 July 2022, 120273.
https://doi.org/10.1016/j.jns.2022.120273
【概要】
足利赤十字病院で経験した一過性全健忘症(Transient global amnesia: TGA)の症例報告である。TGAはその派手な臨床像に比して一般に検査所見が目立たないことが特徴とされた。しかし近年MRIやSPECTを中心に異常所見の報告が集まっている。とはいえ、まだ病態解明は十分ではない。今回我々は複数の異常所見が同時にみられ、一つの病態を示唆する症例を経験したため報告した。
【症例 40代女性】
[現病歴]某日朝(発症前8時間)は普段通りに過ごしていた。平時と同様に仕事をこなし、夜フラダンススクールへいった。ダンスの練習中に突然”同じ質問を繰り返す”ため、友人が夫へ連絡し迎えにきてもらった。迎えに来た夫に対しても「誰に言われて迎えに来たの」「なんで迎えにきたの」と繰り返し、夫は繰り返し同じ内容を返答したが依然として同様の質問を繰り返すため夫に連れられて救急外来を受診した。
[入院後経過]
入室時(発症後3時間程度)、身体所見・神経所見には特記すべき異常所見を認めなかった。日付を2日間違えており軽度の見当識障害は続いていたが、同じ質問を繰り返すなど混乱されている様子はなかった。入院時点で簡易的に認知機能検査を行ったところ3単語の即時再生は可能だったが、遅延再生では1単語カテゴリーに関するヒントを要した(乗り物です→電車と正答)。Serial7は初診担当医が施行した際には「97、あれ3を引くんですよね?」と混乱したようだが、筆者が到着後施行した際には問題なくできていた。髄液検査、頭部CT/頭部MRI検査、一般採血検査で異常はなかったが、本人と相談の上経過観察目的の入院とした。入院後健忘症状は改善したためTGAと診断した。第2病日Wechsler memory scale-revisedを評価したところ遅延再生は84と明らかな低下は認めなかった。同日、ちょうど発症後48時間頃経過したタイミングで頭部MRI画像を再検したところ左海馬CA1領域に拡散強調像で高信号が確認された。脳血流ECD-SPECT検査では楔前部から後部帯状回にかけて血流低下を認めた。頸動脈および頸静脈エコー検査では異常を認めず、内頸静脈逆流所見も認めなかった。入院中の脳波で安静閉眼時にSubclinical rhythmic electroencephalographic discharge of adults (SREDA)を認め、さらに過換気条件で背景脳波の徐波化と振幅の増大を認め、過換気終了後1分程度まで持続した。発症後9日目の時点で頭部MRIの海馬における高信号は消失した。
【考察】
症例は典型的なTGAの経過を示したが、その経過の中でMRI/SPECT所見に加えて脳波でSREDAを認めたという点で貴重な症例である。現在のところ、それら3つの所見を同時に認めたという報告はない。
海馬では連合野で処理された情報が嗅内皮質を介して歯状回→CA3→CA1とシナプスを形成し伝達され(いわゆる三シナプス回路)、さらにCA1から嗅内皮質へと出力され記憶が形成されると考えられている。その回路の構成要素であるCA1の一過性の障害によりTGAの健忘が生じることが想定されMRI所見はそれを支持する。なぜCA1なのかは結論が出ていないが、MRIの検討からTGAの時系列に伴う拡散強調像の信号変化は虚血モデルと一致していることから、血行力学的な機序が想定されており、CA1は特に低酸素状態による代謝ストレスに非常に弱い部位であるため、TGAの病巣として画像所見が得られやすいと報告されている。
本症例ではCA1病変に加えてSPECTにて楔前部の血流低下が示された。これまでも22例のTGA症例で左楔前部の血流低下が有意であること、さらに6ヶ月のフォローアップで同部位の血流が改善することが報告されている。楔前部と後部帯状回はDefault mode networkの一部のPosterior medial episodic network (PM network)の構成要素として海馬とともに記憶を支える。具体的には楔前部と後部帯状回は海馬に入力する聴覚的・視覚的に処理された自己や周囲の空間に関する記憶をさらに精緻な記憶に強める働きをもっていると考えられている。海馬はPM networkの最重要なhubであり、楔前部との連携で自己に関連づけた記憶が整理され、後部帯状回との連携で自身の知識やスキーマとの統合がはかられる。このような関係から、海馬の機能異常はTGAの病態の本態でありそこから機能的に連合している後部帯状回や楔前部の血流低下が引き起こされたと考察される。
SREDAは4-7Hzの高振幅徐波が周波数を変えながら律動的にあらわれるパターンであり、一般人口の0.06%程度にみられる。かなり稀だが、病的意義については不明であり正常亜型と考えられている。TGAとの関連についてはないという報告と、関係を示唆する報告がある。関係を示唆する報告においても明確な関連性は指摘されていない。しかしSREDAは過換気中に現れることも多く、血管攣縮及びそれに伴う虚血・低酸素と関連するという報告がある。実際に本症例も背景脳波でSREDAを認め、さらに過換気条件での徐波化もみられ過換気時の脆弱性が示唆された。フラダンスという呼吸数が上昇することをきっかけに発症したのも関係が深いように見える。これまでの議論を総合すれば、SREDAの出現は過換気時における神経の血行力学的な虚血への脆弱性を示し、実際にストレスがかかったときに虚血の影響を受けやすいCA1領域の機能が一過性に低下し、海馬を中心としたPM network全体の機能も障害されることで特に自身に関連したエピソード記憶の記銘・保持が著しく障害されるが、そのストレスが解除されると自然に改善していく、というTGAの病態仮説が浮かび上がってくる。そして本症例はその仮説を支持する所見を示してくれる貴重な一例といえる。
(三村悠、2022.5.13.)
解説 海馬の扉を開く
突然発症する。目立つ症状は当惑である。何度も同じ質問を繰り返す。いま自分がおかれている状況が認識できていない様子である。しかし神経学的所見を含め、他には症状は全くない。そして24時間とたたないうちに、きれいに正常に戻る。ただしエピソード中の記憶は失われている。これがTGA (Transient Global Amnesia)である。
TGAの最初の報告は1956年、Benderの”episode of confusion with amnesia” であるとするのが一般的だが、1882年、RibotのDisease of MemoryにもTGAと思われる症例の記載がある。以後、この特異かつ派手な症状は精神科医や神経内科医の注目を集め続けてきたが、メカニズムはなかなか解明されなかった。海馬領域の何らかの異常であろうということまでは誰にでも推測でき、かつ、それがいかにも納得できる説明であったが、「何らかの異常」では何の説明にもなっておらず、かつ、「納得できる説明」であることは「正しい説明」であることを意味しない。
そんな状況の中、実際に海馬領域の異常が可視化される研究は徐々に蓄積されてきた。だがそれは文字通り「徐々に」であった。最初の報告から少なく見積もってもゆうに50年が過ぎているにもかかわらず、今なお機序が解明されていないことの背景には、TGAが一過性の症状であるという特性がある。しかもいつ発症するかは予測できないから、いつ出会うかはわからない。TGAについて研究しようと考えても、その具体的計画を立てることは事実上不可能なのである。
このような状況の中、TGAの一症例からMRI、SPECT、EEGという三つの検査で結果を得た三村悠大学院生の仕事は非常に貴重である。これを可能にしたのは、三村院生の臨床への熱意と、迅速に次々に検査を施行した行動力に尽きる。三村院生の紹介文の結びに記されている通り、本症例はTGAの病態仮説を支持する所見を示した貴重な一例である。だが本研究の真価はさらにその先にある。それは海馬についての研究への新たな扉が開かれることへの期待である。
神経心理学では、文字通り限局された脳領域の局在損傷例についての綿密な研究が、大いに発展に貢献してきた。記憶に関していえば、Scovilleが1957年に報告した両側頭葉切除の症例HM、Teuberが1968年に報告したフェンシングの事故による視床損傷の症例NAについての精密な検査データは、現代もなお研究史上に燦然と輝く地位を占めている。こうした例はしかし、非常に稀な症例であり、得られた所見を一般化することには限界がある。
それに対しTGAは、多数例を研究対象にでき、しかも可逆性であるから、同じ一例について、記憶障害ありの時期となしの時期の検査所見の比較も可能である。そしてその二つの検査所見の違いが海馬の機能障害を反映していることを実証したのがこの三村院生の仕事である。すなわち本研究は、TGAについての貴重な一例報告ということにとどまらず、TGAが海馬の機能を探究するための入り口の一つであることを確実に示したという意味で、海馬と記憶についての研究に新たな地平を開く可能性を秘めている。
(村松太郎、2022.5.30.)
自閉症スペクトラム者向けのバーチャルロボットを用いた集団型オンライン就職面接トレーニングプログラム
熊﨑博一 (長崎大学医歯薬学総合研究科未来メンタルヘルス学分野 教授)Group-Based Online Job Interview Training Program Using Virtual Robot for Individuals With Autism Spectrum Disorders
Hirokazu Kumazaki H, Yuichiro Yoshikawa Y, Taro Muramatsu, Hideyuki Haraguchi, Hiroko Fujisato, Kazuki Sakai, Yoshio Matsumoto Y, Hiroshi Ishiguro, Tomiki Sumiyoshi, Masaru Mimura. Group-Based Online Job Interview Training Program Using Virtual Robot for Individuals With Autism Spectrum Disorders. Front Psychiatry. 2022.12:704564. doi: 10.3389/fpsyt.2021.704564.
COVID-19の流行に伴い急増したオンライン就職面接は、流行が収まった後も社会に残ることが予想されている。オンライン就職面接は、ASD者にとって大きな障壁となっている。ASD者向けのオンライン就職面接のエビデンスに基づいたトレーニングは現在までほとんどなく、新たなトレーニングの開発が期待されている。ASD者個人のオンライン就職面接におけるスキル習得を促進するために、我々はバーチャルロボットを用いた集団型オンライン面接トレーニングプログラム(GOT)を開発した。GOTでは、面接官と面接受験者がそれぞれバーチャルロボットとして画面上に映し出されている。5人の参加者がグループとなり、面接受験者、面接官、評価者の役割を演じた。参加者はすべての役割を無作為の順序で行った。各セッションは、一次面接セッション、フィードバックセッション、二次面接セッションで構成された。参加者は計25回のセッションを経験した。GOTの前後には、GOTの効果を検証するために、人間のプロの面接官とのオンライン模擬就職面接(MOH)を実施した。計15人のASD者が本研究に参加した。GOTの前後で、自信、意欲、他者視点の理解、言語能力、非言語能力、面接のパフォーマンススコアの改善を認めた。また、面接官や評価者の視点の重要性についての認識も、1回目のMOH後に比べ、2回目のMOH後に有意に増加した。バーチャルロボットを使用し、面接官や評価者の視点という他者視点を体験することで、面接スキル取得の重要性を学び、モチベーションの持続と面接への自信向上につながったと考えられる。今後より大規模で多様なサンプルで、縦断的なデザインによるさらなる研究を進めていく必要がある。
(熊崎博一、2022.4.1.)
抱負
2022年4月1日,長崎大学医療科学専攻に「未来メンタルヘルス学講座」が設置され講座を担当させていただくことになりました。
メンタルヘルスの需要増加に伴い,初診までの待機時間も長くなり,医療資源までのアクセスも難しくなっている現実があります。さらに地域によっては医師不足による医療崩壊が進み,医療資源の不足は深刻な社会問題となっております。
最近の科学技術の進歩には目覚ましいものがあります。精神障害の診断は,客観的評価の担保が難しいことが一因で,医師により診断が異なるという問題がありました。この問題を解決するために患者様の診療情報や行動から診断,治療方針の決定を行う人工知能の活用が考えられます。またヒト型ロボットの技術進歩にも目覚ましいものがあります。ロボットは予めプログラムすることで人間同様の動作を行うことが可能であり,人間と比較して常に同一の動作が可能な正確性があります。この利点を利用して,精神科診療のエキスパートの面談技術をロボットのプログラムに組み込むことで,その面談を別のロボットで再現できる可能性があります。さらにこのロボットを患者様の面接や学生の教育に導入することで,全国各地で統一化した最先端の面接の提供,および面接法の教育が可能となります。またアヴァター技術の進歩にも目覚ましいものがあります。アヴァターを適切に用いることで遠隔医療の質の向上が期待されます。精神科医療には,病院,診療所,待合室,離島医療だけでなく,デイケア,訪問看護,グループホーム,作業所,学校,特別支援教育をはじめとした多様なフィールドでの展開が期待できます。このように人工知能,ロボット・アヴァター技術は医療資源の不足を補うだけでなく、高度で標準的な医療への貢献が期待されます。各地域の多様な領域で、人工知能,ロボット・アヴァター技術を適切に用いることで,高度な医療を全国各地にもたらすことにつながり,地域における医療の格差是正の効果も期待できます。
最新の科学技術との共生が課題となってくる一方で、従来先人たちが築き上げてきた伝統的精神科医療の功績が大きく、先人たちに敬意を忘れず,学びを続けていかねばならないと思っております。今回,長崎大学で新たに設置された未来メンタルヘルス講座では,既存の伝統的精神科医療と人工知能やロボットといった最新の科学技術の共生について研究を進めていきます。精神科医療の発展に寄与するとともに,増加するメンタルヘルス分野の需要にも対応できる次世代型の人材育成を目指していきます。本講座を発展させることでこれからお世話になる長崎大学、これまでお世話になった慶應義塾大学に恩返ししたいと思っております。
(熊崎博一、2022.4.9.)
COVID-19 パンデミック下での、既存の精神疾患を持つ患者の症状変化~女性と気分障害患者は精神症状が悪化しやすい~
黒瀬心 (慶應義塾大学医学部医学研究科 精神神経科博士課程/足利赤十字病院 神経精神科 非常勤医師)Kurose S, Funayama M, Takata T, Shimizu Y, Mimura Y, Kudo S, Ogino S, Mimura M. Symptom changes in patients with pre-existing psychiatric disorders in the initial phase of the COVID-19 pandemic: Vulnerability of female patients and patients with mood disorders. Asian Journal of Psychiatry, 2022. 68, 102966
https://doi.org/10.1016/j.ajp.2021.102966
COVID-19 パンデミックは未知の感染症というだけでなく、ロックダウンなどといった隔離措置、経済的な問題など様々な理由でメンタルヘルスに悪影響を与える。精神疾患を持たない健常者を対象とした、メンタルヘルスに関わる研究は数多くあるものの、既存の精神疾患を持つ患者がCOVID-19 パンデミック下でどのような症状変化があるかについての包括的な研究は十分に行われていなかった。そこで、(1)COVID-19パンデミックの初期にどの精神疾患で症状が増悪しやすいか、(2)その交絡因子、を明らかにするため、日本での初回の緊急事態宣言前と緊急事態宣言下の2カ月間(調査期間:2020年4月8日~6月7日)に、足利赤十字病院の神経精神科外来患者1592人の精神症状についてGlobal Assessment of Functioning (GAF) を用いて前向きに評価した。診断カテゴリー(ICD-10でのF0〜9)と増悪の関係について、カイ二乗検定を行った。さらに、性別、年齢、診断カテゴリー、pandemic前のGAFスコアを独立変数としたロジスティック回帰分析を行った。気分障害(F3)および神経症性障害(F4)患者の増悪率はそれぞれ4.32%および5.37%であり,器質性障害(F0)および統合失調症(F2)患者のそれよりも有意に高かった(X2 (9, N = 1592) = 27.8, p < 0.01)。ロジスティック回帰分析の結果,気分障害患者および女性患者は、他の障害患者や男性患者よりもそれぞれ有意に高いことが明らかになった(オッズ比(95%信頼区間)=2.4(1.2-4.6),p<.01,F3:3.1(1.5-6.6),女性:p<.01)。これらの知見から、精神科医はパンデミック下において、気分障害患者および女性患者の管理に特に注意が必要であることが示唆された。
(黒瀬心、2022.3.11.)
解説 明るいMental Healthの暗い影
時流に乗っていること。身近であること。ふつうの人と関係が深いこと。こうした条件を遵守すれば、メンタルヘルスは明るく語ることができ、注目度の高い話題になる。COVID-19下でも同様である。コロナで生活が激変しています。こんなときこそメンタルヘルスに気を配りましょう。人とコミュニケーションを取りましょう。規則正しい生活をしましょう。バランスの取れた食事をしましょう。アルコールは控えめにしましょう。反論の余地はない。明るい。毎日の感染者数の数字を人ごとのように横目で見つつ、にこにこと笑って過ごせそうである。
COVID-19はもはや一つの災害であるが、災害時のMental Healthとは本来そんな気楽なものではない。そもそも日本語のメンタルヘルスは、Mental Healthから深刻な部分を切り取った特異な言葉である。たとえば米国のNIMH = National Institute of Mental Healthが、むしろ重篤な精神障害者を対象とする精神医学の研究所であることからも明らかな通り、Mental Healthはメンタルヘルスとはかなりニュアンスが異なる。決してふつうの人々だけを視野に入れたものではない。日本語のメンタルヘルスはMental Healthの明るい一分野にすぎない。その影には真に医療を必要とする人々が膨大に存在する。継続的な精神医療を必要とする人々が日本のあらゆる場所に存在する。東日本大震災のとき、日本精神神経学会が被災地のMental Healthの喫緊の課題として取り上げ実行したのが、精神科治療薬の安定供給であった。災害時に真に必要とされるのはそうした活動なのであって、時流に乗った、身近な、ふつうの人々に関係が深いメンタルヘルスが明るい冷酷さで社会を満たせば、その影にあるMental Healthは深刻さを増していく。
黒瀬心院生はそこに着目した。既存の精神疾患を持つ患者の症状変化を明らかにした本研究は、COVID-19下での真のMental Health研究と呼ぶにふさわしい。それは時流に乗っているとは言えず、多くの人にとって身近ではないかもしれないが、精神疾患を持つふつうの人々に関係が深い、貴重なデータを示したものである。
(村松太郎、2022.3.23.)
内因性カンナビノイド系の代謝酵素であるモノアシルグリセロールリパーゼ(MAGL)をヒトの生体内で初めて可視化することに成功
高畑圭輔 (国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 量子生命・医学部門 量子医科学研究所 脳機能イメージング研究部 研究員)Takahata K, et al: First-in-human in vivo undefined imaging and quantification of monoacylglycerol lipase in the brain: a PET study with 18F-T-401.
Eur J Nucl Med Mol Imaging 2022. https://doi.org/10.1007/s00259-021-05671-y
研究の概要
欧米諸国では、大麻が医療用だけでなく娯楽用にも開放され、巨大な市場を形成しつつあることが近年繰り返し報道されている。我が国では、大麻の所持や栽培は大麻取締法によって厳しい処罰の対象となっており、医療用大麻の合法化に向けた議論も検討がようやく始まった段階である。大麻に含まれる生理活性物質はカンナビノイドと呼ばれている。実は、ヒトを含む動物の体内にはカンナビノイドに類似した作用を持つ物質が複数存在しており、内因性カンナビノイドと総称される。主な内因性カンナビノイドには、2-アラキドノイルグリセロール(2-AG)とアナンダマイドがあり、神経伝達系の制御、炎症、疼痛、摂食、記憶、学習などの重要な生理現象に関連している。2-AGとアナンダマイドは1990年代後半に相次いで同定されたが、長らく、「どちらが真の内因性カンナビノイドか」という議論がなされてきた。多数の検証が行われた結果、2-AGがアナンダマイドの800倍の濃度を有すること、2-AGが記憶や学習に重要な役割を持つ逆行性シグナル伝達との媒介物質であることから、2-AGこそが真の内因性カンナビノイドであるとみなされている。そして、この2-AGの代謝を担う中心的な酵素がモノアシルグリセロールリパーゼ(MAGL)である。MAGLの阻害は、2-AGの濃度を上昇させることにより抗炎症作用、疼痛抑制作用、神経保護作用などをもたらすことが報告されている。また、MAGL阻害剤は、うつ病や不安障害、神経変性疾患、炎症性疾患などの病態修飾作用を持つことから、精神神経疾患領域における次世代の創薬標的となっている。しかしながら、これまでヒトの生体内でMAGLを非侵襲的に捉えられた例はなく、MAGLの生体イメージング技術の開発が望まれていた。
本論文の著者が所属する量研機構では、MAGLを標的としたPET薬の候補化合物群を武田薬品工業株式会社より提供を受け、動物実験での検証を重ねてきた。そして、候補化合物群の中からT-401という物質がPET薬として最も良好な性質を有することを見出した上で、18Fによって標識することにより新規PET薬である18F-T-401を開発した。本研究は、18F-T-401によるPET検査をヒトで初めて行った研究であるが、18F-T-401が良好な脳移行性と代謝的安定性を有すること、またMAGLに対して可逆的な結合を有することを示し、18F-T-401がPET薬として理想的な性質を有することを明らかにした。さらに、genomic plotと呼ばれる新しい手法を用いることにより、18F-T-401で測定した脳内MAGL密度がMAGLのmRNA発現量の脳内分布とも正確に一致していることを示した。以上の検討結果より、18F-T-401によるPETが脳内のMAGLを可視化できることを証明した。本研究は、ヒトのMAGLを生体内で初めて可視化した研究であり、内因性カンナビノイドおよびMAGLを標的とした創薬や、精神神経疾患の病態研究などに活用されうる成果であると考えられる。
余談
我が国では大麻取締法により栽培が厳しく制限されている大麻草(麻)であるが、合法的に栽培されるケースが存在する。私の生地である徳島県には、四国山地の山中に木屋平 (旧木屋平村、現在は廃村)という地域があり、古代から天皇家の祭祀に使用する麻を栽培してきた歴史を持つ。天皇即位の際に行われる大嘗祭では、麁服(あらたえ)という麻の織物が不可欠であるが、これには木屋平村で栽培された麻が使用されているのがしきたりである。2019年の天皇即位に際して行われた大嘗祭でも、木屋平で栽培された麻から織られた麁服(あらたえ)が供えられた。たまたま、私の母が木屋平村の出身であったことから、私も子供時代にはこの山深く自然豊かな木屋平村で夏休みを過ごしていた。そして、この地で古くから行われてきたという麁服(あらたえ)の作成や麻栽培の苦労についても祖父からよく聞かされていた。収穫前の時期になると、若い村民が24時間体制で見張り番を行って、麁服(あらたえ)となる麻を厳重に警備していたそうだ。昭和から平成に改元された1989年にも、この地で麻栽培が行われたことを記憶している。
実は、徳島県には大麻比古神社、大麻町、麻植郡といった「麻」に由来する地名が多数残されている。これは、古代、阿波国に入植した忌部氏が有する専門的技能であった「麻栽培」に関連しているとされる。阿波国一之宮である大麻比古神社で祀られている大麻比古大神は、古代に阿波国を開拓した忌部氏(いんべし)の祖先とされ、神武天皇の時代に忌部氏の子孫が阿波国に入り国土を開拓して麻の種を播いて麻布を作り、郷土の産業の基を開いたことがその名の由来とされている。また、「古語拾遺」では、郡名「麻植」は阿波忌部が麻を植えたことに由来すると記述されている。忌部氏は、元々古代朝廷における祭祀を担った氏族であるが、奈良時代に勢力を増した中臣氏に地位が押されぎみとなり、半ば迫害されるような形で朝廷を逃れ、その後は日本の各地に散らばり、地方氏族となっていったようである。阿波忌部氏も、日本各地に散らばった忌部氏の末裔の一つで、最終的に四国山地の奥深くである木屋平に入植したとされる。朝廷から遠く離れた木屋平の地にあっても麻の栽培を続け、天皇即位の祭祀に不可欠である麁服(あらたえ)を献上する役割を今日まで残しているという点は大変興味深い。なお、麁服(あらたえ)の麻が栽培される木屋平という地名は、この地にある森遠(もりとお)と呼ばれる場所から生まれたとされる。木屋平村では「安徳天皇の小屋の内裏」が森遠の位置に存在したこと、平は小屋平氏が平家であり、小屋に続けて平を加えたものであると伝承されている(木屋平村村史、昭和46年)。森遠は険しい四国山地の中でも、緩やかな傾斜地や窪地が広がる場所で絶好の日照条件をもち、数ヶ所から清水がわき、小川も流れていることから、入植者なら真っ先に居住する好条件の場所であるとされる。私も何度か森遠を訪れたことがある。付近一帯の山は大変深いが、森遠は見事な棚田に囲まれた平坦地であり、ここから見渡す四国山地の風景は大変美しい。日本で一番好きな場所はどこかと尋ねられたら、私は「森遠」と答えている。阿波忌部氏は迫害から逃れるためにこのような山中の地を選んだのではなく、彼らのアイデンティティでもあった麻栽培に最適な土地であったことからこの地を選んだのではないかとも想像している。
天皇即位という時代の節目に合わせて行われる麻栽培も、当然ながら大麻取締法にのっとって行われている。木屋平では、「葉っぱの一枚たりとも外に出さない」という合言葉のもと、厳重な管理で行われているという。我が国でも、大麻が医療目的で使用される日が遠くないうちにやってくると思われるが、内因性カンナビノイドを標的とする薬剤によって、大麻様の効果をより選択的で、副作用の少ない形でもたらすことが可能になるかもしれない。本研究では、ヒトの生体内に存在する内因性カンナビノイドの代謝酵素を標的とするイメージング技術の確立に成功したが、我が国の文化だけでなく、幼少期の記憶と結びつく「麻」に関連する研究を担う機会を得たことで、自分にとっても非常に感慨深い成果となった。
(高畑圭輔、2022.2.1.)

徳島県美馬市木屋平地区の麻栽培の様子(2019年5月 筆者撮影)
高齢者の同意能力 ―認知症高齢者の医療同意における能力評価と支援の試み―
江口洋子 (慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 訪問研究員) 臨床精神医学 51:49-56, 2022.
意思決定支援等に係る厚生労働省から出された各種ガイドライン(「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(2017年3月策定)、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(2018年6月策定)、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2018年3月改訂)、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(2019年5月策定)、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」(2020年10月策定)がある)は、高齢者あるいは認知機能が低下した者に対する意思決定支援について説明されており、定められている意思決定が求められる場面は異なるものの、いずれも対象者の意思を尊重するために繰り返し、本人の思いを聞いたり汲み取ったりすることの重要性が強調されている。
臨床現場では、個人の意思や尊厳を尊重したいという思いが強くある一方で、医療者が最善と考える治療を患者が選択しなかった場合、とりわけ患者の意思決定能力が十分でないと思える場合には難しい対応に迫られることも少なくない。本邦における高齢化による高齢患者の増加、さらに医療技術の進歩により治療の適用も高齢化がすすむ現在では、益々認知症高齢者の医療同意に関する知見の集積や議論が待たれるところである。
本論文では、医療同意能力評価方法に関する論文をレビューし、AppelbaumとGrissoが提唱した、治療に対する意思決定(医療同意)能力は、理解、認識、論理的思考、選択の表明の機能的能力が中核を成すという「4つの能力モデル」に基づき作成されたMacArthur Competence Assessment Tools for Treatment(MacCAT-T)を紹介した。他にも、4つの能力すべてを評価するものではないが、Aid to Capacity Evaluation (ACE)もについて説明した。
さらに4つの能力モデルの各能力と認知機能との関連についても概観した。軽度認知障害(MCI)や認知症発症初期の高齢者を対象とした研究では一貫した結果は得られていないが、概ねMCIや認知症が軽度の場合でも医療同意能力の低下は疑われるが、必ず低下しているとはいえない点で知見は一致するところであろう。したがって、患者に認知機能低下があったとしても同意能力は低下していないとの前提で、患者本人の意思が十分に尊重されるように、様々な場面で発せられる本人の言動や態度など医療同意能力評価と支援の資料となる情報収集を心がけなければならない。
最後に、本学の精神・神経科高齢者認知障害サポートチーム(Dementia Support Team: DST)が循環器内科のグループと協同した高齢者意思決定支援に関する取り組みも紹介した。認知症高齢者の医療同意評価や支援に関して、認知症をよく知る精神科のチームが果たせる役割は大きい。今後は医療同意の支援は専門家だけでなく,各職種が情報を共有することにより、診療科を横断して、かつ多職種で取り組むことが期待される。それが実現すれば、認知機能の低下があっても、本人の意思を最大限尊重した治療が迅速に可能になる。
(江口洋子、2022.1.16.)
高齢者の刑事責任能力 --- 脳画像の役割を含めて ---
村松太郎 (慶應義塾大学医学部精神神経科准教授)臨床精神医学 51:49-56, 2022.
法律は高齢者の犯罪に追いついていない。現行の刑法が制定されたのは明治時代、1907年である。当時の日本人の平均寿命は男女ともに40歳代であった。したがって高齢者の犯罪は想定外か、想定内であったとしてもきわめて例外的なものと見られていたはずである。また、アロイス・アルツハイマーがアルツハイマー病の最初の症例を報告したのが1906年だから、認知症という概念さえ当時は存在していなかったのである。そんな時代に作られた法律を、高齢者の犯罪が激増している現代に適用することの歪みが今、露わになってきている。
そこで刑事裁判の法廷はニューロサイエンスの知見に期待するのであるが、現代のニューロサイエンスは高齢者の犯罪を追い抜いている。「追い抜いている」というのは、良い意味で言っているのではない。伴走すべき立場にあるのにもかかわらず、その役割を放棄してはるか先まで走り去ってしまっているといった意味である。法律への応用を前提としないで進歩したニューロサイエンスを、法の世界に持ち込むことの歪みが今、露わになってきている。それは、脳画像検査所見や神経心理学的検査所見を、その適用範囲を大きく逸脱して適用するというBrain Overclaim Syndrome (脳過剰重視症候群)と呼ばれる事態として法廷に具現している。その顕著な例が、高齢者の刑事責任能力判断である。責任能力は精神障害と密着した概念であり、精神障害の概念は精神医学の誕生以来変遷を重ねてきているが、ニューロサイエンスの進歩によって、脳機能障害という視点を離れた精神障害というものはもはや考えられない時代になり、それに伴い必然的に、責任能力についても脳機能障害という視点で論ずることが必須になった。加齢や、あるいは認知症という疾患による脳機能障害の結果として犯罪が行われたとき、被告人を非難することができるのか。できるとすればその根拠は何か。逆にできないとすればその根拠は何か。そして非難できないのであれば、ではどうすればよいのか。
脳機能の解明は人間観を変えずにはいられない。倫理道徳機能、そして心と呼ばれるものが、脳機能の現れであって、したがって脳の病でそれらが崩壊することがあり得るという現実が、人々の常識にまで広まったら、責任非難という概念は新たな衣を纏って社会に迫ってくるであろう。高齢者や認知症の責任能力を問う刑事裁判は、その最前線にある。
(村松太郎、2022.1.20.)
解説 心と脳と司法精神医学
江口論文、村松論文はいずれも、臨床精神医学51巻1号(2022年1月)の特集『高齢社会と司法精神医学』に収載されたものである。司法精神医学とは、広義には、法と精神医学の接点にあるものすべてを指す。法は、人間が自由意思を持ち、理性的に行動することを前提としたうえで、社会を維持するために作られた壮大かつ緻密なシステムである。このシステムにおいては、心=精神機能に一定範囲からの逸脱がある対象者を前にしたとき、法が確立してきた精密さが急に通用しなくなり、人々は、何が正しく何が悪いのか、何が遵法で何が違法かの判断に困惑する。高齢者と認知症の数が膨大になった我が国では、この問題の発生件数は増加する一方である。その代表が、江口論文の認知症高齢者の医療同意であり、村松論文の高齢者の刑事責任能力である。いずれも、社会内に生きる人間の精神機能=心の評価を要求される領域であり、その評価は脳機能の評価に直結している。人間の心を、脳という視点からとらえる。本HP冒頭一行目に記した神経心理学の原点が現実社会にありありと展開されるのが、本特集『高齢社会と司法精神医学』の世界である。
最後にこの特集の全体像を示す。
高齢者犯罪の現状と課題 (五十嵐禎人・千葉大学)
高齢社会と法 (西山健治郎・二番町法律事務所)
高齢者の刑事責任能力 – 脳画像の役割を含めて -- (村松太郎・慶應義塾大学)
高齢者の刑事訴訟能力 (中島直・多摩あおば病院)
高齢者の同意能力 –- 認知症高齢者の医療同意における能力評価と支援の試み -- (江口洋子・慶應義塾大学)
受刑者の高齢化 – 超高齢社会における高齢受刑者の現状 – (小山田静枝・他・さいたま市保健福祉局保健部健康増進課)
高齢者の自動車運転 – 近年の道路交通法の改正について – (高橋信行・國學院大学)
高齢者による介護殺人の特徴 (田口寿子・神奈川県立精神医療センター)
(村松太郎、2022.1.21.)
アルコール性認知症と誤診されていた右側頭葉型前頭側頭型認知症
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Michitaka Funayama, Asuka Nakajima, Shin Kurose, and Taketo Takata.
Putative Alcohol-Related Dementia as an Early Manifestation of Right Temporal Variant of Frontotemporal Dementia. Journal of Alzheimer’s Disease 83 (2021) 531–537.
DOI 10.3233/JAD-210501
【背景】前頭側頭型認知症の初期段階での診断には、誤診の可能性が常につきまとう。前頭側頭型認知症の初期診断は約半数の例で後に変更され、主に精神疾患やアルツハイマー病などの他の変性疾患の診断に至ることが多い。反対に、最終診断が前頭側頭型認知症であった例の中で約半数は初期には精神疾患の診断を受けていたという報告もある。その前頭側頭型認知症のなかでも、右側頭極に変性の中心を持つ場合は特異的な症状に欠けることから、とりわけ診断が困難であると言われている。今回われわれは、初期症状としてアルコール依存症となりアルコール性認知症と誤診されていた右側頭葉型前頭側頭型認知症の1例を報告した。
【症例】
アルコール性認知症の診断
症例は、教育歴16年、家族で経営する材木店の社長として長年働いてきた、仕事熱心な真面目な男性である。60歳頃からきっかけなくアルコール依存症となり、会社は倒産に至った。同時期より他の人が話したことに注意を向けなくなったり仕事上のミスが多くなったりして、家庭内でも妻との口論が絶えず関係が悪化していった。発症から4年後(64歳)にはうっ血性心不全(アルコール性心筋症)により入院加療となったが、病室で喫煙をしたために強制退院となった。発症から5年後(65歳)にうっ血性心不全で再入院するも、他患者の部屋に入って冷蔵庫の中の物を食べたり(過食傾向も伴う)、他患者の静脈注射用のシリンジポンプの電源を切ったりしたため、アルコール性認知症の診断で神経精神科に転床となった。神経精神科病棟に入院中はさまざまな言動や行動の問題が目立った。人の話を聞かずに立ち去ってしまう一方で、自分の話は一方的に多弁に流暢に話し、しばしば話が脱線していた。肺炎球菌による肺炎に罹患したが、自室に留まる約束を守らずに勝手に他患者の部屋に入り込み、他患者2人にも肺炎球菌による肺炎をうつしてしまったり、勝手に冷蔵庫から食べ物を持ってきて食べたり、病棟共有である新聞や雑誌に落書きをしたりしていた。妻とは離婚に至り、施設に入所となった。頭部CTでは右側頭極に萎縮を認めたが、当時は注目をしていなかった。
前頭側頭型認知症の診断
施設入所となり65歳以降はアルコールを絶ったが、施設内の共有の雑誌へ落書きをしたり、他人の部屋に上がり込み人の食べ物を食べてしまったりする異常行動が続いた。当科で外来通院を継続していたが、診察室では医師が問いかけてもすぐに立ち去ってしまう立ち去り行動が目立った。67歳からは毎回同じ話をするオルゴール時計症状が、68歳からは決まった時間に食堂に入り、決まった時間に外出をする時刻表的行動を認めた。明らかな意味記憶障害も出現し、67歳時には施設の庭のナスを取ってそのまま生で食べ、68歳時には施設内の同居者を認識できなくなった。69歳からは表層失読を含む明らかな語義失語が出現した。この時点で撮像した頭部MRIとTc-99mECD SPECTでは両側側頭極に萎縮/相対的血流量の低下を認めた。この時点でようやく、アルコール性認知症ではなく、前頭側頭型認知症の診断に至った。アルコール依存症も前頭側頭型認知症の初期症状として時に出現する症状のひとつであることから、すべての病態を一元的に捉えることができた。
【考察】
誤診の背景
症状を詳細に診ていなかったのがもちろん原因であるが、一度アルコール性認知症と診断してしまったことで、異常行動をアルコール性認知症に当てはめてしまった点が挙げられる。しかし、後方視的にみると診断へのヒントは多い。立ち去り行動や他人の部屋への押し入りと勝手に人の食べ物を食べるなどの共感不全や顕著な脱抑制はアルコール性認知症では典型的ではなく、過食傾向やアルコール依存症自体を前頭側頭型認知症の食習慣の変化と捉えることができる。
アルコール消費量の増加と前頭側頭型認知症
食習慣の変化やアルコール消費量の増加は前頭側頭型認知症の初期症状のうちの1つであると考えられ、左側頭葉の萎縮が主体である意味性認知症よりも右側頭葉型前頭側頭型認知症に多いことも知られている。アルコール消費量の増加の原因として報酬系の異常が指摘されるだけではなく、右側頭極の萎縮による味覚の意味記憶障害も原因の1つと推測されている。しかし、実際にアルコール依存症となり、さらにはアルコール性認知症とまで誤診されていたというひとつの典型例の報告は今までなかった。本報告では、前頭側頭型認知症の初期症状としてアルコール依存症がありうることを明確に示すものである。
なお、右側頭型前頭側頭型認知症の症候は最近注目を集めてきている。前頭側頭型認知症の異常行動に意味記憶がどのように絡むのか、これを解く鍵が秘められている可能性がある。
(船山道隆、2021.12.1.)
アルコール離脱期の激しい発汗と発熱による循環血液量減少性ショック ~症例報告~
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Michitaka Funayama, Ryotaro Okochi, Shintaro Asada, Yusuke Shimizu, Shin Kurose and Taketo Takata.
Severe diaphoresis and fever during alcohol withdrawal cause hypovolemic shock: case report. BMC Psychiatry (2021) 21:387. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03393-x
【背景】疫学研究からはアルコール使用障害による入院を経験した患者は、一般人口よりも平均余命が24~28歳短くなることが明らかになってきている。この原因には主に長期にわたるアルコール使用による臓器障害(肝臓などの消化器、循環器など)が挙げられるが、アルコール離脱期にもけいれん、不整脈、たこつぼ心筋症など死に至る可能性のある身体合併症が出現することがある。これらの身体疾患には離脱に伴う中枢神経系の過活動やアドレナリン作用の増強が関連している。アルコール離脱期には他にも、発汗、発熱、振戦、幻覚や錯覚、精神運動興奮、不眠、不安などの症状が出現するが、過度の発汗と発熱は循環血流量の低下を引き起こす可能性がある。しかし、今までにアルコール離脱期に循環血流量の低下とそれに関連する身体合併症の報告はない。今回われわれは、食事はほぼ全量摂取していたものの、アルコール離脱期に生じた激しい発汗と発熱によって循環血液量減少性ショックとそれに伴う腎前性腎不全を呈した症例を報告する。
【症例】症例は20年来のアルコール依存症を伴う52歳男性である。アルコール性肝障害からChild-Pugh Bの肝硬変と食道静脈瘤を併発していたが、食道静脈瘤からの吐血にて入院加療を行っていた。緊急の内視鏡的静脈瘤結紮術と輸血によって身体的には改善傾向であったが、第4病日目から不眠、第5病日目には振戦、頻脈、意識変容、幻覚や錯覚に加え、激しい発汗を伴うアルコール離脱症状が出現した。第6病日目にも激しい発汗は続き、さらに38℃台の発熱も加わった。離脱せん妄が続いていた期間、患者は食事をほぼ全量を摂取していたが、第7病日目には血圧が75/48mmHgまで下降する循環血液量減少性ショックとそれに関連した腎前性腎不全(血清クレアチニン濃度3.4mg/dl)を呈した。細胞外液による多量の輸液療法によってこれらの病態は改善した。
【考察】本例は、アルコール離脱期の中枢神経系の過活動やアドレナリン作用の増強によって生じた激しい発汗と発熱が患者の必要水分量を増加させ、循環血液量減少性ショックに至ったものである。精神科領域において部分的に類似した病態は緊張病(ないしは悪性症候群)で認められる。アルコール離脱や緊張病はその精神状態のコントロール自体で十分に大変なのであるが、同時にそれに伴う身体面の病態把握も重要となる。われわれ精神科医には、精神面および身体面の両者に対する細かい管理が求められる。
(船山道隆、2021.12.11.)
解説 真に意義ある医学論文とは
医学論文を書く目的は何か。将来の症例の診断・治療・処遇に役立てるためである。将来の症例とは、臨床医の目の前に現れる個別の症例である。すると症例報告こそは医学論文の原点ということになるが、同一の症例は決して存在しないから、むしろ本質を共有する複数の症例を対象として一般化されたグループデータの方が、結局は個別の症例の臨床に資することになる。しかしながらここに発生する深刻な問題は、「本質を共有する」という点にある。精神科で扱う多くの疾患では、何が本質であるかはまだまだ不明のものが大部分だ。だから観察可能な症状に基づいた操作的診断基準が公式のものとして汎用されているが、すると診断名が同じでも本質を共有しているという保証は全くないから、グループデータにどこまで意味があるかについては疑問符がつく。同じ色、たとえば赤い色の花だけを集めて研究しても、得られるのは赤い色素についてのデータのみであり、それは科学的に正しい知見であっても、研究で求めるゴールからはかけ離れたものでしかない。
かくして精神医学は優れた症例報告の蓄積が切望される段階にあるが、他の医学分野と同列の評価基準が目指されるという事情もあって、グループデータの方が高い地位にあるというのが現実である。そんな逆風の中、船山道隆部長は、十三転び十四起き(本HP2020年4月参照)の不屈のエネルギーで、洗練された症例報告を発刊し続けている。前頭側頭型認知症の初期症状としてアルコール依存症が現れたという症例は(J Alzheimer dis 2021)、全経過から振り返ってみれば経過の初期に診断可能であったと指摘できても、リアルタイムでの診断は非常に困難であることは間違いない。アルコール離脱症状から二次的に脱水となりショックに陥るという症例は(BMC Psychiat 2021)、アルコール依存症の日常臨床で実は多数遭遇していると思われるが、指摘されなければ気づくことはきわめて困難である。どちらも将来の個別症例の診断・治療・処遇に大いに有用であるが、グループデータとしての論文として成立することはまず考えられない。順風に乗れば誰でも比較的楽に前進できる。逆風の中での前進こそが真の前進であり、真に意義ある医学論文である。船山部長が出版を続けている一連の症例報告がまさにそれであると言えよう。
(村松太郎、2021.12.29.)
線条体におけるドパミンD2受容体およびドパミントランスポーターの結合性と局所灰白質脳容積との関連性
黒瀬 心慶應義塾大学医学部医学研究科 精神神経科博士課程 / 量子医科学研究所 脳機能イメージング研究部 脳疾患トランスレーショナル研究グループ 実習生
Kurose S, Kubota M, Takahata K, Yamamoto Y, Fujiwara H, Kimura Y, Ito H, Takeuchi H, Mimura M, Suhara T, Higuchi M. Relationship between Regional Gray Matter Volumes and Dopamine D2 Receptor and Transporter in Living Human Brains. Human Brain Mapp, 2021. 42(12), 4048-4058 https://doi.org/10.1002/hbm.25538
線条体でのドパミン神経伝達は、皮質線条体ネットワークの強度、結合性、シナプス可塑性に、相互的、機能的に関連していると考えられている。統合失調症などの精神神経疾患では、ドパミン神経伝達および皮質線条体ネットワークの異常、脳構造の変化が、それぞれ繰り返し報告されてきた。しかし、ヒトを対象として生体でドパミン神経伝達と脳構造との関連を調べたものは報告が少なかった。ここで我々は、過去に量研機構で撮像されたPETデータを用いて、健常人の脳においてドパミントランスポーター、ドパミンD2受容体、局所脳容積の関連について調べた.
34人の男性健常者(平均年齢23歳)に対して、頭部MRI・T1強調画像, [11C]raclopride(ドパミンD2受容体)・[18F]FE-PE2I(ドパミントランスポーター)を用いたPET検査を行った。これらのリガンドの binding potentials (BPND) を定量化し、線条体の3つの機能的な領域(limbic, executive, sensorimotor)に分けてそれぞれのリガンドのBPNDの相関解析を行った。さらに, voxel-based morphometry (VBM)法を用いて、局所灰白質容積とそれぞれの線条体領域におけるBPNDとの相関を、年齢、MRI撮像プロコル、全脳容積を共変量として解析を行った。
[11C]raclopride の、limbic subregionにおけるBPNDは海馬鉤および海馬傍回とその隣接する側頭葉の脳容積、executive subregionにおけるBPNDは前頭前野とその隣接する領域の脳容積、 sensorimotor subregionにおけるBPNDは一次体性感覚野および補足運動野における脳容積、とにそれぞれ有意な正の相関を認めた。 これらは、皮質線条体ネットワークの機能的・解剖学的な繋がりに基づいたものであった。一方で、[18F]FE-PE2Iでは有意な相関はみられなかった。
これらの結果から、ドパミンD2受容体の密度が皮質線条体の機能的・構造的な関連に関与していることが示された一方で、これらの関連はドパミントランスポーター密度が反映していると考えられる黒質線条体経路とは独立していると考えられた。今後、統合失調症やパーキンソン病の患者を対象として同様の研究を行うことが、ドパミンと脳構造の観点における病態解明につながると考えられる。
(黒瀬心、2021.11.18.)
解説 360度の視点から精神をみる
本HP2020年6月「中枢性自律神経ネットワークを含めた脳全体での脳血流の亢進を認めた悪性緊張病の1例」(Schizophrenia Research 2019) の1st authorである黒瀬心医師がその後大学院に進学し、量子医科学研究所で行った仕事である。
20世紀半ばに統合失調症のドパミン仮説が提唱されて以来、ドパミンは精神医学研究における主役とさえ言える物質であるが、ヒトにおけるその役割については未解明の部分が大量に残っている。そんな状況の中、黒瀬院生の本研究は、ヒトの線条体におけるドパミンD2受容体とドパミントランスポーター の関係についての貴重なデータを報告するものである。
医師7年目の黒瀬院生は、慶應精神神経科入局後、足利赤十字病院を中心に、慶應義塾大学病院、下総精神医療センターで幅広く臨床、研究を行ってきた。特に関心を持って取り組んできたのは、脳損傷後や神経変性疾患の高次脳機能障害や精神症状、そして内因性精神疾患の中で特に器質因が想定されている病態で、上記本HP2020年6月に紹介した論文はそれが形になったものの一つである。同論文に代表される通り、これまでの彼の方法論は、神経心理学所見を詳細に検討するケーススタディ等であったが、本研究は、臨床の第一線から研究所に舞台を移しての、最新のイメージング技術を駆使しての仕事である。これは決して転身を企図してのことではない。精神科医として臨床を行なってきたことを最大限に生かした研究が彼の目指すところで、最近では神経病理学にも手を広げ、精神症候学、神経心理学、ニューロイメージング、神経病理学をダイナミックに繋ぎ、「精神」を360度のあらゆる観点からみるという目標に向けて歩み続けている。
(村松太郎、2021.11.29.)
失語症者の刑事裁判? --- 失語症者に裁判を受けることが可能なのか?
斎藤文恵 (慶應義塾大学医学部精神神経科特任助教、言語聴覚士)失語症患者による刑事事件の裁判
村松太郎、斎藤文恵
認知リハビリテーション2021年26巻1号 p.1-14
https://doi.org/10.50970/cogrehab.2021.001
【事件の概要】
70歳代男性A氏は、脳梗塞により失語症を患った後、被害者である妻との間に様々な行き違いが生じ、自ら離婚調停を起こしたが、弁護士との疎通が不良で調停の内容や経緯、見通しを十分理解できず、勝つつもりで始めた調停で負けてしまったと認識し、不可解さと悔しさで混乱していた。何とか気持ちを抑えていたものの、耐えきれずに自らの手で妻を殺害し、自首した。
【起訴から判決確定まで】
A氏は殺人罪で起訴されたが、裁判所による訴訟能力鑑定依頼を受け、我々が言語・認知機能検査および訴訟能力判定に特化した検査などを行った。その結果「訴訟能力あり、但し適切な援助を要する」という条件つきの判定となった。
裁判所は鑑定書に基づき、言語聴覚士である斎藤を「通訳人」と指名し公判での同席を認めた。さらに全文筆記業者を導入し、公判中の全ての口頭でのやり取りをモニター上で確認できるよう配慮した。
公判が始まる前に裁判所において8回の「公判前整理手続き」があり、斎藤は通訳人としてA氏に同席した。またA氏と弁護人との質問練習にも同席した。さらに週1回の通院リハを設定し言語訓練および質問練習の予習・復習を重ねた。公判までの準備期間は1年以上に及んだ。これらはA氏にとって有効なリハビリテーションの機会となり、コミュニケーション能力には改善をみた。
公判においてA氏は、モニター上に示される文によって裁判所内での他者の発言をおおむね理解していると推測された。しかし「被告人質問」において、とくに検察官の質問に対してA氏本人が答える際には、質問の理解は十分でなく、回答が適切でない場面もあった。すなわち、日常的なコミュニケーション能力は高くても、裁判という厳密に「ことば」でやり取りされる場面に十分なだけの言語能力は有していなかった。
一審判決は「懲役10年」であり、弁護側は控訴した。
二審は「控訴棄却」であり、上告せずに判決は確定した。A氏は現在服役中である。
失語症者A氏に訴訟能力はあったのか。通訳人としての支援は十分だったか。公判での質問は失語症者に対して適切であったか。そもそも今回の事件はなぜ起こってしまったのか。本稿ではこれら全過程を記し検証した。担当弁護士の方からもコメントをいただいた。
(斎藤文恵、2021.10.12.)
解説 刑罰という予定調和
人は回復を目指す。脳損傷者は回復を目指す。医療者は回復の支援に尽力する。だが、回復とは何か? 端的には機能の回復である。しかし機能が完全に回復することはない。それでも人は回復を目指す。何のために? より良く生きるため? しかしより良く生きるとはどう生きることか? そもそも生き方に良い悪いがあるのか? こんな問いを投げかけられたら人は立ち尽くす以外にない。それでも人は回復を目指す。すると回復を目指すこと自体がゴールなのか? そうでないとすれば、回復の先にはより良く生きられる世界があると信じるからこそ、人は回復を目指すのであろう。
例外というものがある。回復の先のゴールが誰の目にも明確な場合という例外がある。たまたまそれは殺人事件であった。夫が妻を殺害した。殺人事件としてはごく平凡な一例である。ただ夫A氏が失語症であるという点だけが違っていた。失語症患者による殺人。ここに、失語症の殺人犯の認知リハビリテーションという特殊な事態が発生した。裁判を受ける機能だけの回復をゴールとした、きわめて例外的な認知リハビリテーションを、我々は開始することになった。
リハビリテーション開始前には、評価が必須である。本事例ではそれは訴訟能力の鑑定であった。訴訟能力すなわち裁判を受ける能力の判定である。これは裁判所からの命令を受けた村松が行なった。そして訴訟能力ありと結論した。ただし支援が必要という条件をつけた。裁判所はこれを受けて公判に向けての準備を開始した。中心となったのは言語訓練であった。担当したのは斎藤文恵言語聴覚士である。1年以上、総計120時間に及ぶ訓練を経て、裁判員裁判の法廷で公判が開始された。法廷では斎藤言語聴覚士が、刑事訴訟法175条の「通訳人」として、常にA氏の横に座り、A氏のコミュニケーション全般についての支援を行なった。A氏逮捕から判決まで一貫してこの事件を担当された岡慎一弁護士は、本論文にお寄せいただいた担当弁護人コメントの中で、「こうした「支援」は、我が国で最初のものだったと考えられます・・・今回の方法は、現時点で考えられる最大限の支援だったと考えられます。」と述べておられる。振り返って見れば反省すべき点・改善すべき点は多々あったものの、リハビリテーション成否の指標をゴールの達成度とするのであれば、本事例の認知リハビリテーションは100%成功したと言えるであろう。
そのゴールは、懲役10年の判決であった。70代の失語症患者がこれから10年の歳月を刑務所で送る。それがこの認知リハビリテーションで到達したゴールであった。
もし村松が訴訟能力なしと判定すれば、彼は刑務所に入ることはなかった。
もし斎藤言語聴覚士が言語訓練をしなければ、彼は刑務所に入ることはなかった。
もし斎藤言語聴覚士が法廷で支援しなければ、彼は刑務所に入ることはなかった。
ゴールが懲役10年であることがわかっていたら、我々の行動は変わっていただろうか。どこかの時点で立ちすくんでいただろうか。
芥川龍之介の描いた河童は、この世に生まれてくるかどうかを本人が決定する。河童はなぜか、生まれる前に未来を知っており、意思決定をするのである。生きることがつらくて耐え難いと信じれば、生まれてこないことを選択し、その選択は尊重されて直ちに処分される。
人は河童ではないから、強制的にこの世に存在することを強いられる。そして生きることを強いられる。この先には良い未来があると信ずることを強いられて生きる。回復すればより良く生きることができると、本人も医療者も信ずることを強いられて今を生きる。未来を知らないからこそ、人は生き続けられるのであろう。
(村松太郎、2021.10.28.)
嫌悪感情に伴う心拍誘発磁場の変化について
島の活動を中心とした脳磁図研究
加藤隆 (つつじメンタルホスピタル認知症疾患医療センター長)Kato, Y, Takei, Y, Umeda, S, Mimura, M, Fukuda, M. Alterations of Heartbeat Evoked Magnetic Fields Induced by Sounds of Disgust.
Front Psychiatry 2020;11(0):683. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00683
【背景】
JamesやLangeに遡る情動の末梢起源説は、外界からの刺激に応じて起こる身体変化を脳の情動認知プロセスが感じ取り、自覚的な情動体験が構成される、というものである。情動はあくまで中枢で喚起され、身体状況の変化はそれらの結果に過ぎないとする中枢起源説との議論を経て、未だ結論には至らないものの、少なくとも身体とこころの双方向性の影響(Body-Mind Interaction)が存在することには間違いが無い。パニック障害などの精神疾患でみられるように、身体状況の変化は中枢における情動処理に影響を及ぼし、それが更なる身体状況の変化を生むことは、日常の診療場面でも良く目にする現象である。時間分解能の高いMEG研究にあって、この様な比較的長い潜時で見られる情動変化を捉えることはこれまで困難であったが、今回我々は心拍に同期したHeartbeat Evoked Magnetic Fields (HEFs)という新しい手技を用いて、心ー脳相関に関連する脳磁場応答を検討したので報告する。
【方法】
対象は健常被験者39例で、IADS-2 (International Affective Digital Sounds) から抜粋した嫌悪音声を、対照音声との比較で聴覚刺激として与えた。嫌悪刺激は子供の虐待やDV、嘔吐音など情景がありありと浮かぶ環境音であり、対照音の野球場の喚声やイノシシの鳴き声など音量や6秒間の構成が一致するものを選択した。刺激はそれぞれ2回ずつ15種類行い、対照ー嫌悪ー対照ー嫌悪の順番に1ブロックで3分、合計12分の検査とした(https://www.frontiersin.org/files/Articles/562066/fpsyt-11-00683-HTML/image_m/fpsyt-11-00683-g001.jpg)。この間全頭式の脳磁図計で応答を記録し、それぞれの条件において心電図のRピークを潜時0とした加算平均を行った。これら心電図に同期した加算平均波形から脳表におけるソース推定を行い、周波数帯域ごとの応答強度を条件間で比較検討した。
【結果】 心電図と同期した脳活動として、嫌悪条件下で潜時300ms付近に両側性右優位の島皮質の活動を認めた(https://www.frontiersin.org/files/Articles/562066/fpsyt-11-00683-HTML/image_m/fpsyt-11-00683-g002.jpg)。他の脳領域との相関関係や周波数帯域ごとの活動を見るために島皮質を後部・腹側前部・背側前部の3領域に分け条件間の活動を見たところ、嫌悪条件で右島領域の腹側前部においてのみ19および23Hzのβ帯域における有意な振幅増大を認めた(https://www.frontiersin.org/files/Articles/562066/fpsyt-11-00683-HTML/image_m/fpsyt-11-00683-g003.jpg)。これらの振幅増大は主に潜時500ms付近で見られたが、先行する潜時300ms付近で14Hzの振幅抑制も有意であった(https://www.frontiersin.org/files/Articles/562066/fpsyt-11-00683-HTML/image_m/fpsyt-11-00683-g004.jpg)。またこの右腹側前部領域と前脳の相関を見たところβ帯域での左側前頭前野腹内側部との有意な相関を認めた(https://www.frontiersin.org/files/Articles/562066/fpsyt-11-00683-HTML/image_m/fpsyt-11-00683-g005.jpg)。
【考察】
先行研究からは嫌悪感情と島皮質の活動の相関が示唆されているが、脳磁図を用いて心ー脳相関をみた我々の課題でも、島皮質とりわけ右腹側前部領域が嫌悪感情によりβ帯域にて賦活されることが示された。これらの活動は左前頭前野腹内側部との相互作用により発現されており、嫌悪感情により賦活された身体感覚情報が右腹側前部島皮質を介して左前頭前野腹内側部に至る経路で処理されている可能性を示唆している。前頭前野腹内側部は身体感覚を通じた認知処理にも密接に関連しており、身体感覚の求心性情報のエンドポイントであるのみならず、逆に身体感覚を変化させる起点としても機能する。今回の我々の報告は、情動負荷が心ー脳相関にもたらす変化が主に島および前頭前野腹内側部におけるβ帯域の活動と関連していることを示している。
(加藤隆、2021.9.1.)
解説 0.001秒の因果
緊張すると心臓がドキドキする。誰にでもあるごく平凡な体験だが、19世紀の哲学者・心理学者William Jamesによってこの平凡な体験は意味深長な体験に生まれ変わった。それがJames-Langeの感情の末梢起源説である。「緊張すると心臓がドキドキする」という文章は、時系列的には、まず緊張という感情が発生し、その後に動悸という身体変化が発生することを意味しており、それは人の自然な主観的感覚に一致しているが、真実は順序が逆で、身体変化が先で、緊張という感情はそれに反応して発生するというのがJamesの説である。「人は悲しいから泣くのではない。泣くから悲しいのだ」という、彼が言ったとされる有名な言葉にそれが象徴されている。これに真っ向から反対するのがCannon-Bardの感情の中枢起源説で、両説の争いは本HPに2020年10月に紹介した梅田聡教授監訳の『感情』に詳細に解説されている。
私には実体験がある。講堂で100人ほどの学生を前にして実習の説明をしていた時のことだ。学生の一部から始まった私語が、私が登壇した時点ですでに部屋中に広がり、大騒ぎといった様相になっていた。まあよくあることではあるが、この時の私は、それを大目に見てよい立場にはなかった。まもなく始まるその実習は多くの医療施設のご厚意・ご協力によって成り立っているもので、学生には緊張感を持って真剣に取り組むことが求められており、私の役割はそれを確実に学生に伝えることであった。
そこで私は、定められた事務的な話を始めつつ、この状態で私はどうすべきかと冷静に考え、喝を入れなければならないという結論に達した。この時、学生の騒ぎは相当な音量に達しており、喝を入れるとはすなわち怒鳴る以外になかった。
まあここまでは大学の凡庸な教員が考えそうなことである。興味深いのはここからだ。
私はこのように冷静かつ論理的に考えた末に怒鳴ることを選択したのであるが、怒鳴った途端に事態は急変した。学生は驚いて静まりかえった。それは別にいいのだが、急変は私の身体に発生した。激しい動悸と発汗である。
それまでは静穏であった私の身体が、怒鳴った瞬間から交感神経優位になった。さらには感情の昂りも感じた。動悸と発汗の突然の発生という予期せぬ事態に狼狽したのだ。いわゆる「自分の言葉・声に自分が興奮する」というパターンである。
リアルタイムで自分自身の反応をそう分析することまで私はできていたのだが、それでも自分の感情の昂りを抑制することはかなり困難だった。いま自分は、辺縁系から発生している興奮を前頭葉で抑制しようとしている、だがいったん暴れ始めたreptile brainを大人しくさせるのは容易でないようだ。そんなfolk neuroscience的なことまでそのとき考えていたこともよく記憶している。
客観的にはこのときの私は「キレて怒鳴った」と見えたであろう。だが実態は「怒鳴ったからキレた」のである。まさにJames-Langeの感情の末梢起源説の具現そのものの興味深い体験であった。
しかしこんな体験では決してJames-Lange説を証明したことにはならない。
「怒鳴ったからキレた」というのは、あくまでも私の主観であって、この主観は主観としてはどこまでも正しいが、しかし、「怒鳴る」という意思決定の直前に、実際には微細な、しかし有意な、感情の昂りがあったのかもしれない。つまり感情の昂りが私に意思決定をさせたのであって、冷静に意思決定したというのはみかけのことにすぎないのかもしれない。私の感情が昂ったのは私が「動悸と発汗の突然の発生という予期せぬ事態に狼狽した」からだと先ほど言った。私は確かにそう感じた。時系列としては動悸・発汗が先で、感情の昂りが後だった。しかしその逆の「緊張が先で動悸が後」という主観的体験は事実を反映していないというのがJames-Lange説なのであるから、同じ主観的体験である「動悸が先で感情の昂りが後」が、常識とは順序が逆でJames-Lange説に一致しているというだけの理由で正しいと考える根拠はない。「緊張したから心臓がドキドキした」というのが解釈であるのと全く同様に、「動悸・発汗が発生したから感情が昂った」もまた解釈にすぎない。どちらの解釈が正しいか、決着をつけるには感情と身体変化の時間的順序を測定しなければならない。その時間とはミリセコンド=0.001秒のオーダーである。
そこまでの時間分解能を持つ脳機能測定機器は、現代ではMEGしかない。MEGはJames-Lange vs Cannon-Bard以来続いている歴史的争いに決着をつける可能性を秘めた武器である。優れた時間分解能に加えて、きわめて微細な磁気活動も見逃さないという測定感度もMEGの持つ偉大な力である。この感度のためMEGは、近所を地下鉄が走っただけでノイズが入り測定値が乱れる。だからMEGで脳を究めんとする加藤隆博士は東京を離れ、群馬の地で研究を続けている。
もっとも、仮に時間的関係が証明されたとしてもまだ先がある。
たとえば昼は夜に先行するが、昼は夜の原因ではない。稲光は雷鳴に先行するが、稲光は雷鳴の原因ではない。時間的順序は、因果関係証明の、いわば必要条件にすぎない。Aが時間的にBに先行することを証明し、そしてAとBの時間差の間に何が起きているかを証明したとき初めて、原因がAで結果がBであると結論することができるのである。
本研究は、時系列の証明までには至っていないものの、ミリセコンドのタイムスパンにおける感情と身体変化の脳内ループが、すなわち脳内で何が起きているかが見事に示されている。これはもちろんMEGの偉力を駆使したものだが、実は時間分解能があまりに高いゆえに、潜時の長い情動変化を捉えることはMEGでは不可能ではないかと従来は考えられていたところ、心拍に同期したHEFsという画期的な方法を用いてその不可能を可能にしたのが加藤博士の本研究である。
そしてMEGがきわめて微細な磁場変化を捉えることができることの裏には、活動を繰り返し加算平均するという仕掛けがある。ということはつまり、講堂での私の体験の際、仮に何らかの方法で私の脳活動をMEGで測定できたとしても、その一回の体験を材料にして、感情の昂りと動悸・発汗の時間的順序を証明するのは不可能だということである。するとMEGでJames-LangeとCannon-Bardの論争に決着をつけることは不可能なのか。
いやしかし、ここにも不可能を可能にする方法はあるはずである。上州のMEG使い・加藤隆博士の叡智に期待したい。
(村松太郎、2021.9.29.)
Logocloniaはlogopenic型進行性失語の末期に出現する可能性
船山道隆 (足利赤十字病院神経精神科部長)Yoshitaka Nakagawa, Michitaka Funayama, Masahiro Kato. Logoclonia might be a Characteristic of Logopenic Variant Primary Progressive Aphasia at an Advanced Stage: Potential Mechanisms Underlying Logoclonia. J Alzheimers Dis. 2019; 70(2): 515-524. doi: 10.3233/JAD-190184.
【Logocloniaとは】
Logocloniaとは、「なかかかかかかか」「あまたとととととととと」などと語の途中や最後の音節を意味もなく流暢に繰り返す現象である。同じ語全体を繰り返す同語反復palilaliaや単語の最初の子音の繰り返しを特徴として緊張と努力を伴う発声である吃音stutteringとは症状が異なる。Logocloniaは1910年にKraepelinによって提唱され、まれにアルツハイマー病を中心とした変性疾患で報告されてきたが、その機序は明らかではなかった。今回われわれはlogocloniaを呈する患者を全体の失語症者から取り出し、その言語面の特徴と脳機能画像からlogocloniaの機序に迫った。
【Logocloniaはlogopenic型進行性失語の末期に出現する可能性】
2008年1月から2017年12月までに江戸川病院リハビリテーション科と足利赤十字病院高次脳外来に通院した914名の失語症患者(脳血管障害や頭部外傷といった高次脳機能障害の患者と変性疾患による進行性失語を含む。logopenic型進行性失語は16名)の中で5名がlogocloniaを呈した。いずれの5例も初期にはlogopenic型進行性失語を呈し、臨床的にはアルツハイマー型認知症と診断した例である。Logocloniaを呈した時点ではいずれの例も重度の認知症に至っていた。
Logocloniaを呈した時点の5例の言語面は、流暢性は保たれていたものの呼称能力と音韻想起能力が著しく低下していた。脳機能画像からはブローカ領域が比較的保たれていた一方で左側頭葉から頭頂葉の言語野の相対的血流量が大きく低下している所見であり、言語所見を支持するものであった。すなわち、logocloniaは流暢性が保たれている中で語や音韻の想起が著しく低下している中で、音韻のバリエーションが少なくなり、同じ音の繰り返しに至ったものではないかと考えられた。ところで、logopenic型進行性失語は、もともと音韻性進行性失語と呼ばれていたように、構音といった運動面の流暢性は保たれているが、初期から喚語困難や音韻の想起の問題が出現することが特徴である。Logocloniaとlogopenic型進行性失語の背景には、類似した機序があるかもしれない。
(船山道隆、2021.8.1.)
慢性期の外傷性脳損傷における広範な白質構造異常と語頭音の流暢性障害との関連
山縣 文 (慶應義塾大学医学部精神神経科専任講師)Yamagata B, Ueda R, Tasato K, Aoki Y, Hotta S, Hirano J, Takamiya A, Nakaaki S, Tabuchi H, Mimura M. Widespread white matter aberrations are associated with phonemic verbal fluency impairment in chronic traumatic brain injury. J Neurotrauma. 2020, 37(7):975-981. doi: 10.1089/neu.2019.6751.
受傷直後よりごく軽度の意識障害である「もうろう状態」が短時間だけ続き、かつMRI上も脳損傷の所見がないケースでもその後に認知機能障害を呈する報告が相次いでいる。軽度外傷性脳損傷(mild traumatic brain injury; mTBI)の「軽度」とは、意識障害が軽度であることから付けられた名称であるが、実際の臨床症状は軽度とは限らない。Diffusion Tensor Imaging(DTI)を用いた最近の脳画像研究によると、頭部外傷後の意識消失が0~20分、外傷後の健忘が24 時間以内、グラスゴーコーマスケールスコアが13~15で定義されるmTBIにおいても、「脳梁や内包などの白質線維において微細な白質構造異常が生じる」という結果が報告されている(Aoki et al., 2012; 2016)。つまり、MRIでは脳損傷を確認することはできないが、白質における微細な構造異常とそれによる構造的結合の損傷がTBIにおける潜在的な神経病理と想定されており、外傷後の高次脳機能障害やびまん性軸索損傷の発生機序や診断概念の根幹を覆す可能性がある。本研究では、TBIにおける認知機能障害に関する潜在的なメカニズムを調べるために、慢性期のTBI患者にみられる白質線維の損傷と認知機能障害との関連性について調査した。
慢性期の軽度から中等度/重度のTBI群18名と年齢の一致した健康対照群17名を対象とした。DTI解析において広く使われているTract-Based Spatial Statistics(TBSS)という解析ソフトを用いて、TBIの白質構造異常のパターンを特定した。具体的には、拡散異方性の指標としてfractional anisotropy (FA)値とaxial diffusivity (AD)値、radial diffusivity(RD)値の3つを算出し群間比較を行った。さらにTBSSのthreshold-free cluster enhancement correctionを使用して、白質線維束の損傷と認知機能障害との関係性を調べた。
TBSS解析により、TBI群は健康対照群と比較し広範な脳領域でFA値が低下しており、白質構造異常を有していることが示唆された。興味深いことに、それらの領域の大部分で、FA値が減少している領域とRD値が増加している領域が重なっていた。一方で、AD値では群間差はみとめなかった。これらのDTIパラメータの組み合わせから、神経病理所見として脱髄をみている可能性が示唆された。次に重症度をmTBI群のみに限定し、サブグループ解析を行ったが、そこでも健康対照群と比較し、多くの白質線維でFA値が有意に低下していた。語流暢性課題(verbal fluency task: VFT)において、語頭音VFTはTBI群で有意に成績が低下していたが、意味性VFTでは差を認めなかった。FA値と語頭音VFTの成績が広範囲な白質線維において正の相関を示した。これは、白質構造に異常があるほど、語頭音VFTの成績が低いことを示唆している。一方で、FA値と意味性VFTでは相関をみとめなかった。
本研究では、様々な重症度のTBIを対象としており、個々の症例で脳損傷の大きさや位置、程度にばらつきがあるにも関わらず、慢性期TBI患者は広範な領域で白質構造異常を示した。これは、すべての重症度を通してTBIでは健康対照群と比較し、白質線維の統合性が低下しているという過去の研究報告を確認するものとなった。また、側頭葉ではなく、主に前頭葉に投射される半球内および半球間をつなぐ前視床放線、小鉗子、脳梁のFA値と語頭音VFTの成績に相関をみとめた。前視床放線は、内包の前脚を通り前頭前野(主に背外側前頭前野)と視床をつなぐ白質線維であり、実行機能と複雑な行動計画に関与している。また小鉗子(脳梁の前方投射線維)と脳梁は、前頭領域の半球間の接続を持ち、これらの領域の損傷は前頭葉機能の障害に関与している(Paul et al., 2007; Edwards et al., 2017)。以上より、語頭音VFTは、意味性VFTと比較して、TBIにおいて、前頭葉を中心とした白質構造異常による実行機能障害をより鋭敏に反映する認知機能検査である可能性が示唆された。
(山縣文、2021.8.3.)
解説 心の隠蔽説を実証する
人は発語する前に、自分が何を発語するかを知っている。知っているが一語一句まで意識しているわけではない。それでも意図した通りに正確に発語することができる。
ここで「知っている」という言葉にこだわると、迷路に迷い込むことになる。意識していないのに知っているというのは一体どういうことなのか、という問いがその第一歩になる。哲学者の一部はこの問いを追究し(この追究自体は興味深い作業ではある)、いわゆる「心の隠蔽説」否定という結論に達している。「心の隠蔽説」とは、「心はその人の内部に隠されている」という、いわば常識に合致した考え方で、脳科学的な言葉に言い換えれば、「人間の精神機能は必ずそれに対応する脳内の活動がある」ということになろう。その脳内の活動が、さしあたって今のところはいかなる検査機器を用いても全貌までは見ることができないから、たとえば発語されるまでは、その人が何を意図しているかは他人にはわからない。だが本人だけは発語する前に自分が何を意図しているかを「知っている」。つまり意図は、発語されるまでは本人の中に隠蔽されている=脳内の活動として隠蔽されているというのが「心の隠蔽説」である。
このとき本人は、これから発語することを「一語一句まで意識していない」が「知っている」のはパラドックスであるというのが、「心の隠蔽説」を否定する哲学者の論考の出発点である。そして、「心の隠蔽説否定」は、論理的には、「人間の精神機能は必ずそれに対応する脳内の活動がある」ことの否定に直結する。
船山道隆部長によるlogocloniaの精密な解析に基づく推定が正しければ、「心の隠蔽説否定」は旗色が悪くなる。「logocloniaは、流暢性が保たれている一方で語や音韻の想起が著しく低下しており、音韻のバリエーションが少なくなった結果、同じ音の繰り返しに至ったものである」という船山部長の推定は、語や音韻として脳内に存在するもの(それらが存在することを本人は「意識していない」が「知っている」)を取り出す「想起」という機能の障害が、「流暢性」という機能の維持によって発生したと言い換えることができる。いま「推定」と言ったが、この推定以外には、「なかかかかかかか」「あまたとととととととと」などと語の途中や最後の音節を意味もなく流暢に繰り返すlogocloniaという現象を説明することはほぼ不可能であることに加え、ブローカ領域が比較的保たれている(流暢性の保持に対応)一方で左側頭葉から頭頂葉の言語野の相対的血流量が大きく低下している(語や音韻想起の障害に対応)という脳機能画像所見がこの推定の説得力を非常に大きくしている。
脳内に存在する語を取り出す機能に着目し、臨床所見と脳画像所見に基づき説得力ある論を展開しているという意味では、山縣文講師の論文も同様である。そして山縣講師は、この研究結果に基づき、語頭音VFTと意味性VFTといういずれもシンプルな検査の持つ深い意味を指摘している。この指摘は脳機能障害の適切な評価を通して、当事者にとっての大きな恩恵に繋がるものである。
言語機能にかかわる研究はこのように、脳と心の根本的な関係にかかわる重要なデータをしばしば提供してくれる。他方、哲学的思弁は、透徹した論理の追究という意味では非常に興味深いものであるが、どこか一箇所で事実から外れると、奇妙な結論にたどり着く。「心の隠蔽説否定」は、人が発語する際に、「一語一句まで意識していない」が「知っている」のはパラドックスであるとした段階に深刻な瑕疵がある。本人が自分の発語内容を発語する前にすでに「知っている」のは、それが脳内に存在していることを指しているのであって、意識とは無関係である。そして発語という行為が、脳内に存在するものを取り出す作業であることは、今回の船山部長、山縣講師の研究が雄弁に示している。もはや哲学は脳機能についての事実を離れた思弁として成立する学問ではなく、今のところNeurophilosophyと呼ばれている分野こそが、哲学の本流になっていくことは否定できまい。
(村松太郎、2021.8.28.)
中年期における魚食・多価不飽和脂肪酸摂取量と老年期の認知症の関連
野崎昭子 (下総精神医療センター医長)Shoko Nozaki, Norie Sawada, Yutaka J. Matsuoka, Ryo Shikimoto, Masaru Mimura, Shoichiro Tsugane :
Association Between Dietary Fish and PUFA Intake in Midlife and Dementia in Later Life: the JPHC Saku Mental Health Study
J Alzheimer’s Dis. 2021;79(3):1091-1104. doi: 10.3233/JAD-191313.
【背景】
高齢化の中、認知症の予防や進行の抑制は国民的な関心事となっている。特に食事内容や生活習慣(喫煙、飲酒、運動など)など、自らの取り組みで改善可能な危険因子を明らかにすることは非常に意味があると考えられる。食事については、地中海食(野菜や果物、全粒粉、魚、オリーブオイル、ナッツ類を多く摂取する食習慣)や魚食について検討がなされており、魚食が多いと認知症のリスクが下がるとの報告が多いものの、地域差があるなど一定していなかった。一定しない理由としては、過去の研究は魚食量がもともと少ない文化圏で行われており、差が出にくいといった可能性が考えられる。また、脳の神経細胞の変化は認知症発症の何年も前から起こっていることが分かっており、魚食量を測定した時期と認知症を観察した時期が近すぎると差が出にくいといったことも考えられる。日本は世界的にも魚食量が多いことで知られており、本研究では日本における老年期の認知症リスクと中年期の魚食量の関連を検討した。
【方法】
1990年に長野県佐久保健所管内の南佐久郡8町村(1990年時点)に居住していた40~59歳の約1万2千人のうち、1995-96年の健診データがあり、かつ2014-15年に行った「こころの検診」に参加した1127人のデータにもとづいて、魚食量、魚に多く含まれる不飽和脂肪酸摂取量とその後の軽度認知障害・認知症との関連を検討した。食事については、147品目の食品(魚介類と魚加工食品は19品目)の過去1年間の摂取状況を尋ねる食物摂取頻度調査票を1995年、2000年に行い、平均値を用いて魚食量と多価不飽和脂肪酸の摂取量を推定した。軽度認知機能障害・認知症については、2014-2015年に神経心理検査、抑うつ症状の質問票を用いた検診を行い、精神科医が各研究参加者を診察して、認知症、軽度認知機能障害、うつ病の診断を行った。認知症に関連する他の因子を調整するため、1995年に得た喫煙、飲酒、身体活動量、教育歴のデータを、2014-2015年に得た糖尿病、がん、心筋梗塞、うつ病既往に関するデータを用いた。
このように得られたデータを用い、魚食量・不飽和脂肪酸の摂取量と認知症、軽度認知機能障害の関連について、ロジスティック回帰分析を行った。魚食量、それぞれの多価不飽和脂肪酸摂取量については、低い方から4分位のグループに分けて解析した。Model1として性、年齢、教育歴を調整、Model2として性、年齢、教育歴、喫煙歴、飲酒歴、身体活動量、既往歴(がん、心筋梗塞、糖尿病、うつ病)を調整し、Model2を最終モデルとした。
【結果】
こころの検診参加時の対象者の平均年齢は73歳、6割が女性であった。研究参加者1,127人のうち、380人が軽度認知障害、54人が認知症と診断された。認知症については、魚食量が一番低いグループ(Q1)を基準とした場合、Q4ではリスクが0.39倍と61%の低下が認められた。また、それより魚食量が少ないQ2、Q3でもリスクはそれぞれ0.43倍、0.22倍となり、魚食量が一番低いQ1と比べるとリスクは低かった。魚に多く含まれる多価不飽和脂肪酸であるドコサヘキサエン酸(DHA)についても、一番摂取量の少ないQ1を基準とした場合、Q4の認知症のリスクは0.28倍となり、72%のリスクの低下が認められた。また、魚食量と同様にQ2、Q3でもリスクはそれぞれ0.39倍、0.30倍と低かった。同じく多価不飽和脂肪酸であるエイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサペンタエン酸(DPA)について、Q1と比較した場合、Q4のリスクはそれぞれ0.44、0.22となり低下が認められたが、低下が認められるのはQ3からであった。軽度認知機能障害についても同様の検討を行ったが、魚食量、多価不飽和脂肪酸摂取量とも、認知症のリスク低下のような強い関連は認められなかった。
【考察】
魚食量やDHAについては、過去の報告でも認知症予防に効果がある可能性が示唆されているが、魚食量を調べた時期と認知機能を調べた時期の間隔が短いことが多く、研究の限界の一つとして指摘されていた。今回の研究では中年期の魚食量が約20年後の認知症リスクと関連があることが示され、魚に多く含まれる多価不飽和脂肪酸であるDHA、さらにEPA、DPAの摂取量でも同様の効果が観察されていることから、中年期から長期に魚を多く食べるよう心がけることで、認知症を予防する効果がある可能性が示された。魚食や多価不飽和脂肪酸の摂取は認知症と関連が深い脳卒中や心血管疾患のリスク低下にも関連しているとされ、今回の研究ではこれらの要因を調整した上でも認知症のリスク低下に関連していることが示された。世界的に魚食量が多い日本でも、魚食量の「天井効果(一定以上魚食量がある場合は効果が観察されなくなること)」ではなく魚食量が多いと認知症リスクが低いことを観察できたことは、大きな成果と言える。今回の研究では、中年期に認知機能を評価しておらず、もともと認知機能が良好な人がたまたま魚食量が多いという可能性は否定できないため、魚食や多価不飽和脂肪酸の効果を結論付けるためには、さらなる研究が必要である。また、軽度認知機能障害では魚食や高価不飽和脂肪酸の摂取の明確な効果を観察できなかったため、この点に関しても今後の研究が必要である。
(野崎昭子、2021.7.20.)
解説 予防の科学と哲学
予防ビジネスには常に最大限の警戒が必要である。
第一は真偽の問題である。すなわち、「〇〇で予防できる」と示された〇〇に、本当に予防効果があるのかは疑ってかからなければならない。予防ビジネスは、「それを予防したいと人は強く願っているが、今のところ有効な予防法はない」という状況において自然に発生する藁をも掴む気持ちを利用するもので、つまり「〇〇で予防できる」という情報に接したとき、人には疑うより先に信じるという心理的構えが形成されているのが常である。詐欺師にとってはこれほど騙しやすいカモはいない。
治療ビジネスもそれは同じだが、治療の場合は効果の有無が比較的短期間に明らかになるのに対し、予防では効果の有無の判定には長い期間を要する。それどころか長い期間を経ても効果が本当にあったかなかったかはわからないことの方がむしろ多い。認知症はその最たるものの一つであろう。
こうした事情に乗じて有象無象のフェイクが世の中に出回っている。何の科学的根拠もないにもかかわらず、認知症を予防できると喧伝される。そして人は長期間にわたってそれを摂取し続ける。それはサプリであったり食べ物であったりする。おそらく最も蔓延しているエセ予防ビジネスはこのパターンであると思われるが、たとえ科学的根拠があっても、予防できるという話にはなお警戒が必要である。
それが第二、データレベルの問題である。
データレベルというと、専門家の間ではエビデンスレベルという概念がすぐに浮かぶが、実社会ではそれ以前に、基礎研究で得られたデータがそのまま臨床レベルの効果の証明になるかのように誤解されているという問題の方がむしろ大きい。細胞レベルや動物レベルのデータは、それらがいかに信頼できるものであっても、臨床応用までにはまだまだ長い道のりがあるという事実が無視されるのである。
それがクリアされたとしても、第三として、量の問題がある。
認知症の予防に有効であることが科学的に証明された物質はいくつもある。するとそれを受けて(それに「乗じて」と言うべきかもしれない)、その物質が含まれている食物が紹介される。「認知症予防に有効なことが科学的に証明された成分が含まれている食物」は、通常とは異なる意味での食欲をそそることになる。
だが「認知症予防に有効なことが科学的に証明された成分が含まれている食物」を食べるように心がけても、認知症予防には決して繋がらない。
たとえばチーズの成分の中には認知症予防効果がある物質が含まれているが、予防の有効量を摂取するためにはチーズを何十個も食べることが必要である。そういう重要な情報をスキップして、「認知症予防のためにチーズを食べよう」と薦めるのであればそれもまた詐欺である。
量については逆の問題もある。これまでに認知症予防効果があることが示された物質の多くには、至適な量の範囲というものがあり、その範囲を超えて摂取し過ぎると逆に効果が落ちるというパターンになっていることが大部分であり、したがって過剰摂取によるデメリットと常に背中合わせである。「○○には予防効果がある」「○○は体に良い」などといったとき、それは「○○を摂取すればするほど良い」ということには決してならないのである。
最後に、第四として、哲学の問題がある。
ある食べ物が予防に有効なことが科学的に証明されたとする。しかもその有効量は日常的に摂取できる常識的な量だったとする。
だがそれが嫌いな食べ物だったらどうするか。普通はあまり食べない物だったらどうするか。それでも食べ続けるか。もしそうするなら、それは食事を認知症予防に特化した目的とすることにほかならないが、では毎日の食卓を予防専用の場にしようというのか。
認知症は予防したい。だが認知症の予防は人生の目標ではない。
さらに言えば、健康の維持も人生の目標ではない。
毎日決まった物を食べ、決まった生活をし、我慢の日々を送る。その結果、健康が維持される。認知症にはならずに人生を終える。そんな人生を、人は良かったと思えるのか。臥薪嘗胆はその後の何らかの高い目的のために行うものであって、臥薪嘗胆そのものは目的にはなるまい。いや、なる人もいるのかもしれないが、それは各人の哲学の問題になる。体に多少悪いことをしたとしても、その方が人生が楽しいのであればそちらを取るという哲学もあろう。あろうというよりその方がむしろ普通かもしれない。さらにはその方が健康な考え方とさえ言えるかもしれない。
認知症の予防に有効とされているものはたくさんある。しかし真に有効とするためには、以上のような問題がクリアされなければ実用にはならない。
かくして、野崎昭子博士の本論文の偉大な価値が見えてくる。テーマは魚を食べることである。魚が認知症予防に役立つのではないかというのは、昔から言われていたことではある。科学的データもあった。しかし野崎博士が論文内で指摘しているような様々なデータ解釈上の問題があり、本当に有効がどうかには疑問符が付けられ続けてきた。
そんな状況にあって、JPHCコホートの活用を通して野崎博士がまとめた本研究は、画期的な意味を持っている。JPHCコホート https://epi.ncc.go.jp/jphc/は、10都府県総勢14万人の地域住民から構成され、様々な病気の発症と生活習慣の関わりを明らかにすることを目的にした長期追跡プロジェクトである。本研究はその中の佐久コホート(長野県)から生まれたもので、1990年から20年間追跡して得られたデータに、精密な統計解析を行った成果である。
したがって先に挙げた第一と第二の問題は確実にクリアされている。すなわち、データには十分な科学的根拠があり、実臨床に適用できるエビデンスとなっている。
そして得られた結果は人々が十分に実施可能な予防法であった。本論文からのメッセージは「一日に魚80グラムを食べることが認知症予防に効果がある」という単純明快なものである。ポイントは80グラムという数字である。魚80グラムとはほぼ魚の切り身一切れにあたる。日本人の平均的な食生活を考えると、これを毎日食べるというのは多数派とは言えないが、やろうと思えば十分に実行可能な範囲である。そして、逆にこの量を超えて食べる習慣というのはなかなか得られにくい。したがって過剰摂取によるデメリットを気にする必要はほぼない。ということは、現実的には、魚は食べれば食べるほど良いという単純な食習慣が推奨されるということになる。これはかなり画期的なメッセージである。あまたある予防法とされているものの中で、この野崎論文が示唆する「一日に魚80グラムを食べる」という予防法は、科学的根拠、データレベル、そして量的に実行可能という意味で、比類なき実用性を持った方法だと言える。
では最後の第四、哲学についてはどうか。魚が嫌いな人には、この予防法は役に立たないということになりそうである。だが魚がさほど好きではないが嫌いという程ではないというレベルの人については、工夫すれば行動変容の余地はある。工夫とはたとえば、魚が好きな人が増えるように、魚料理を発展・洗練させていくことが挙げられよう。認知症予防のためにそうしたことを推進することの適不適もまた哲学の問題、と呼ぶのは少々大袈裟であって、美味しい魚料理を食べて認知症が予防できるのであれば、健康と生活謳歌の両方に資する名案ではないかと思うが如何でしょうか。
(村松太郎、2021.7.30.)
Parkinson病に対する電気けいれん療法:システマティックレビューとメタ解析
髙宮 彰紘(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 特任助教)Takamiya A, Seki M, Kudo S, Yoshizaki T, Nakahara J, Mimura M, Kishimoto T.
Electroconvulsive Therapy for Parkinson’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Mov Disord 2021 Jan; 36 (1): 50–58.
電気けいれん療法 (electroconvulsive therapy: ECT) は精神疾患に対して効果が確立された治療である。Parkinson病は運動症状のみならず精神症状も出現する。しかし、Parkinson病における精神症状の治療において、抗精神病薬の使用に伴う運動症状の悪化など副作用もあり十分量使用できないというジレンマが生じうる。ECTはParkinson病の運動症状と精神症状の両者に効果が見込める可能性が示唆されてきた。このような背景をもとに、精神・神経科と神経内科の両者で、過去に行われたParkinson病に対するECTの有効性を調べた研究のレビューを行った。
14の研究(129名)のデータを解析し、治療前後の各種症状評価尺度の変化量を算出した。ECTは運動症状、うつ症状、精神病症状、Wearing-off現象に対して有意は改善効果が期待でき、認知機能は悪化させないという結果で、出版バイアスの影響を考慮してもこれらの結果は変わらなかった。ECTの運動症状に対する改善効果は、精神症状がないParkinson病の患者のみを対象とした研究のサブグループ解析においても有意であった。
ECTはうつ病や統合失調症におけるうつ症状、精神病症状に対する効果のみならず、Parkinson病におけるうつ症状、精神病症状に対しても有効である可能性が示唆された。Parkinson病に伴う精神症状に対して有効性が示された薬物療法の選択肢は少なく、運動症状を悪化させる懸念もあり治療に難渋するケースも少なくない。ECTは認知機能への悪影響の懸念があるが近年の方法論の改善(電極配置やパルス幅の調整など)により認知機能への影響を最小限に抑えることが可能である。ECTの運動症状への改善効果は精神症状の改善とは独立している可能性があるが、その機序は不明であり今後の研究が必要である。これまでにParkinson病に対するECTのランダム化比較試験は1つしか行われていなかったため本研究では主に観察研究の結果をもとにしており結果の解釈には注意が必要である。今後の質の高いランダム化比較試験が望まれる。
ここまでが学術論文としてのお作法に則って淡々と記載した内容で、ここからはこのレビューをした際の個人的な感想である。論文を網羅的に検索すると、エビデンス至上主義において最下層と位置付けられる症例報告が多く目に止まったが、ルールはルールとして全て除外させていただいた。しかし、治療歴が長く、疾患の進行と薬物療法の副作用の影響が複雑に絡み合い、脳外科治療含め他の治療法ではどうしようもない難治例においても、ECTで運動症状と精神症状の両者が改善したという報告は確かにされてきている。それでも神経内科領域ではこれまでECTにスポットライトが当たることがなかったということは驚きであり、両科の風通しを良くすることの必要性を感じるきっかけにもなった。また、なぜECTはParkinson病の運動症状症状に有効なのか、なぜECTは抗精神病薬と異なり運動症状を悪化させずに精神病症状を改善させることができるのかと様々な疑問が噴出し、パンドラの箱を開けてしまったような妙な感覚にもなったが、そこに希望があると信じ今後の研究につなげたいと思う。
(高宮彰紘、2021.6.1.)
解説 封印された希望
慶應精神神経科の医局の先輩に、昭和の時代から、筋萎縮性側索硬化症ALSに対する電気けいれん療法(ECT)の有効性を強く主張しておられた先生がいらっしゃる。阿部正先生(昭和22年慶應医学部卒26回生、平成8年他界)である。
『知情意集中病』と題された阿部先生のご著書には、ECTで改善したALSの実例がいくつも紹介されている。同書のはしがきには、「知(観念)に集中しすぎが分裂病、感情に集中しすぎが躁うつ病、行動に集中しすぎがてんかん。そして、この集中の正反対の負集中病というのがあって、観念の負集中病が痴呆症、感情への負集中病が失感情症、行動への負集中病がナルコレプシー、カタプレキシーと考へている」と記載されている。阿部先生はその他に『表情病』という本も出版しておられる。これは「表情の病気」という意味ではなく、「emotion-expression disease」という意味である。同書の序文には「私は感情そのものの本質は何か、とそれに伴う身体感覚を調べ、感情には必ず対応する身体感覚があり、感情と身体感覚の間には密接な関係のあることに気づいた。そして、この身体感覚に注意が集中し、異常に高まった時に病気という状態になりはしないかと、今日身体的には原因不明で、精神的には分析不能とされている、「難病」がこれに該当することを突きとめ、治療の目安もつけることが出来た」と記載されている。さらには「筋萎縮性側索硬化症、癌、脳腫瘍、白血病もこの面より解明することができた」とまで記されている。
私は研修医のころ、阿部先生が医局を訪れた場面に遭遇したことがある。そこに居合わせたオーベンの先生方は阿部先生を、荒唐無稽な理論を主張する人として敬遠していたことをよく覚えている。素直な研修医であった私はオーベンの先生方の姿勢に素直に納得し、阿部先生の独特の理論に素直に否定の気持ちを持っていたのであるが、振り返ってみれば、当時の精神医学の理論は(現代の理論も?)、たとえ優勢のものであってもどれも根拠薄弱であったという時代背景に鑑みれば、阿部先生の理論は傾聴すべき貴重なものであったと言えよう。後のDamasioのsomatic marker theoryとの繋がりを見出すこともできる。
Parkinson病に対するECT研究が1950年代から世界で細々と、しかし着実に進められていたことを、私は高宮彰紘特任助教の論文を読むまでは不覚にも全く知らなかった。この研究に着目した高宮特任助教を阿部先生と対比するのは失礼なことか、それとも称賛していることになるのか、あるいはその両方か、私には判断できないが、お二人のどちらの目にもECTと、ECTが有効な疾患についての画期的な未来を拓く可能性が見えていることは確かであろう。
高宮特任助教はECTとParkinson病についての研究論文を渉猟するにつれて「パンドラの箱をあけてしまったような妙な感覚になった」と記している。それがパンドラの箱か、玉手箱か、宝石箱か、私には判断できないが、箱を閉じたままでは何も得られないことは確かであろう。そして箱が開かれて出てきたものから目をそむけていては、希望に気づくことはできない。
(村松太郎、2021.6.28.)
重度の低栄養を伴う摂食障害のリフィーディング症候群による血清リン値の低下はBody Mass IndexとBUN/Cr比によって予測できる
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Funayama M, Mimura Y, Takata T, Koreki A, Ogino S, Kurose S: Body mass index and blood urea nitrogen to creatinine ratio predicts refeeding hypophosphatemia of anorexia nervosa. Journal of Eating Disorders (2021) 9:1 https://doi.org/10.1186/s40337-020-00356-7
【背景】
身体的に重度な摂食障害の急性期治療において、リフィーディング症候群に伴う低リン血症の重症度を予測することは臨床上重要である。過去の研究からは入院時のBody Mass Index (BMI)やBUN/Cr比がリフィーディングによる低リン血症の発症と関連することが明らかとなっている。しかし、これらの過去の研究は低リン血症発症の有無を調べた研究であり、実際の臨床で重要な血清リン値がどれだけ低下するかを予測する研究ではない。また、過去の研究の対象者の低栄養の程度はBMI12.7~16.2と、必ずしも重度ではない。さらに、過去の研究においてはリフィーディング時の実際の摂取量やリンの補充量を考慮していない。今回われわれは、重度の低栄養を伴う摂食障害のリフィーディングに起こる血清リン値の低下の程度に影響する要因について、後方視的研究ではあるものの、可能な限りの要因を取り込んだ上で調べた。
【方法】
対象は、1999年4月から2018年3月まで足利赤十字病院神経精神科病棟に入院したBMIが16未満の摂食障害68例のうち、治療や検査に協力できた63例(女性61例、年齢37.2 ± 10.4歳、BMI 11.5±1.6、治療開始後1週間の平均カロリー摂取量1233 ± 590 kcal/day)である。血清リン値の低下の程度には多変量線形回帰分析を用い、低リン血症の発症の有無 (P<2.5mg/dl) には判別分析を使った。説明因子には年齢、性別、入院時データ(血清リン値、BMI、BUN/Cr比、アルブミン値、拒食・過食タイプ)、治療に関するデータ(カロリー摂取量、リン投与量、体重増加率)を用いた。
【結果】
血清リン値は入院時3.9±1.4mg/dl、最低値2.6±0.8mg/dlであり、最低値は入院3.9±4.0日後に出現した。血清リン値の低下の程度および低リン血症の発症はいずれも、BMIとBUN/Cr比が関連した。すなわち、BMIが低いほど、また、BUN/Cr比が高いほど、リフィーディングによる血清リンの低下の程度は大きく、低リン血症の発症の危険性も高まることが明らかとなった。一方で、栄養投与量は過去の研究と同様に血清リン値の低下の程度にも低リン血症の発症にも影響しなかった。
【考察】
われわれの研究の対象は、今までの同種の研究の中では最も重度の低栄養を伴う摂食障害であった。リフィーディングによる血清リン値の低下の程度は、BMIとBUN/Cr比によって予測できることが明らかとなった。また、低リン血症の発症についても、過去の研究と同様に、BMIとBUN/Cr比と関連した。
リフィーディング時の栄養投与量については、以前は低リン血症を中心とする電解質の異常を懸念して、少量から徐々に増やすことが一般的な見解であったが、2010年代からはそれを覆す研究が相次いでいる。本研究から得られた知見も、その見解には矛盾しない結果であった。
極度の低栄養を伴う摂食障害に対しては、BMIとBUN/Cr比から血清リン値の低下を予測した上で適切なリンの補充を初日から行いながら、低栄養に伴うさらなる身体合併症を防ぐ上で、第1病日目からある程度の栄養投与を行うことが適切であるかもしれない。ただ、この点は今後のさらなる研究が必要である。
(船山道隆、2021.5.1.)
重症のAnorexia Nervosaでは脱水と動脈硬化に関連した脳梗塞が発症する可能性がある
三村悠 (慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)Yu Mimura, M.D., Yusuke Shimizu, M.D.1)2), Hiroki Oi, M.D., Shin Kurose, M.D., Shun Kudo, M.D., Taketo Takata, M.D., Masaru Mimura, M.D., Ph.D., and Michitaka Funayama, M.D., Ph.D. : “Case Series: Ischemic stroke associated with dehydration and arteriosclerosis in individuals with severe anorexia nervosa” Journal of Eating Disorders. (2021) 9:39. https://doi.org/10.1186/s40337-021-00393-w
現在足利赤十字病院から、摂食障害に関する病態、治療について精力的にデータ収集と論文執筆を進めている。船山部長が執筆された、「低リン血症の予測についてBMIとBUN/Cre比が有用である」という論文も同誌に出版されたばかりである。
私自身は、栄養療法中にどのようにインスリン動態が変化するか、をメインテーマにデータ収集、解析を進めている。
今回のケースシリーズはその過程で患者さんたちと触れ合っているうちにふと「脳梗塞が意外と隠れているのではないか?」という現場感覚から着想を得て執筆した。
【概要】
これまでAnorexia nervosa(AN)患者では心血管イベントや静脈血栓症のリスクが高いという報告はされてきた。しかし一方で脳梗塞についての報告は意外にも少ない。本ケースシリーズではAN患者と脳梗塞発症について検討した。
【ケース】
2018年4月から2020年12月まで当院に入院した全AN症例を対象とした。29入院例(19人)のうち、2名が入院中に脳梗塞の診断に至った。1例目は30代前半女性、第10病日に左肩の違和感と10分程度持続した左不全麻痺で発症し、臨床的には一過性脳虚血発作と考えられた症例だったが、画像上は多発脳梗塞が指摘された。2例目は50代前半女性、入院時より軽度の伝導失語、換語困難を認め、画像上は左縁上回を中心とした脳梗塞が指摘された。どちらの症例も若年の脳梗塞であるため徹底的に全身探索を行なったが、軽度の脱水と動脈硬化のみが指摘された。
【考察】
どちらの症例も採血で凝固能亢進を認めた。症例1/2ともにBUN/Cre比が高値であり脱水が示唆された。症例1では明らかな、症例2では軽度の動脈硬化も指摘された。
まずこのケースシリーズより、一般的な脳梗塞発症率から考えて重症ANでは脳梗塞発症率が高いことが示唆された。
病態はあくまで推測の域を出ないが、脱水は間違いなく関係すると考えた。さらに脱水に加えてAN患者は低血圧であり、低還流になることが増悪因子であると予測された。提示症例でも脳梗塞の予後予測因子で用いられるBUN/Cre比が高く、脱水の関与が示唆された。しかしCreが低いANでは過大評価する可能性があり、他の病態も考慮に入れる必要があった。また脱水が病態としても輸液についてはRefeeding症候群に伴う心不全のリスクを考えるとANにおいては1ml/kg程度の点滴が妥当であると考察した。
提示症例では採血から過凝固状態であることがわかった。その時点でラクナ梗塞は否定的と考えた。一方で全身探索から静脈血栓の塞栓源同定には至らなかった。ABI/CAVIの結果からは動脈硬化の関与が示唆されたことから粥状硬化には至らないレベルでの動脈硬化が脱水に加えて背景病態の一端を担うと考えられた。摂食障害では血小板数の低下、血小板機能の低下、血小板容積の増大などが起こることがしられており、それらが動脈硬化に関わっていると考察した。
脱水と動脈硬化自体も絡みあうものでありさらにその関係は複雑である。低栄養→脱水→低還流、低栄養→血小板機能低下→動脈硬化、というそれぞれの関係に加えて、脱水→血管内脱水→アルドステロン分泌亢進→動脈硬化、といった関係や、脱水→血管内皮機能低下→動脈硬化といった関係もあり非常に複雑である。
単一施設であること、全員にMRIをとっていないこと、経食道心エコーを行なっていなどの問題はあるが、本ケースシリーズではANと脳梗塞の関係についてはじめて言及できた貴重な報告と考えている。
【結論】
ANの急性期栄養管理において、脳梗塞発症の可能性に留意する必要がある。特に軽微な神経所見が診断の契機となりえる。病態としては動脈硬化と脱水に起因した過凝固状態が考えられる。どちらも栄養を整えることが再発予防に重要であるが、脱水に対してはRefeeding症候群による溢水に注意する必要がある。今後さらなる症例の蓄積が望まれる。
【論文で触れられなかった点】
論文内では議論が複雑になる関係や、字数の関係で触れられなかった点が2点ある。
まず、2症例ともに神経所見は微細なものであり、1症例目はMRIを撮らなかったらTIAとしていた可能性、2症例目は解離性障害の合併もあり診断に至らなかった可能性があった。ANの全身状態が悪いときには尚更神経巣症状を見落としやすいこともあり、非常に教育的な症例であったと考えている。
さらに、ここは自分の妄想に近いが、以前執筆した「摂食障害の神経心理所見」でも述べたように、AN患者ではセットシフト能力が弱くこだわりが強くなることがある。それは脳血管性認知症患者の性格変化(ないし先鋭化)に類似していると感じたことがあり、こういった虚血、低還流がAN患者の神経心理所見の偏りを説明できる可能性があると考えている。これについては字数の問題から議論を完全に見送ることとしたが今後検討していきたい。
また本題のインスリン動態についてもデータ収集を続けていき、ぜひ世界に発信し治療法に新たな示唆を与えたいと考えている。
(三村悠、2021.5.10.)
解説 摂食障害臨床の躍進へ
分化と融合の変転を繰り返すのは、おそらく人間社会の法則なのであろう。政治でも、科学でも、そして医療でも、高度な仕事の追究は専門分化を促進し、それはもちろんかなりの成果を上げるものの、分化が一定のレベルを超えると逆にタテ割りの弊害の方が大きくなって逆に融合の方向に転ずる。そしてまたどこかの時点で専門分化に向かう。この変転が長いスパンで繰り返されるのが人間社会の歴史である。
だが実臨床においては、この変転は迅速に繰り返されることが必要である。症状の一部だけを切り取っていくら精密に治療しても、それでは患者という人間の治療にはならないことはしばしばある。この問題が如実に現れるのは、精神症状と身体症状の両方が問題となる病態で、摂食障害はその代表的疾患である。今や摂食障害はcommon diseaseといえるほど患者数が多い疾患となっているにもかかわらず、精神科的治療と身体科的治療の適正な専門分化と融合に基づいた医療が標準になっているとは言い難いのが我が国の現状である。
そんな状況の中、身体的に重症な摂食障害であっても精神科医が中心となり高度な精神的・身体的治療を行っている数少ない病院の一つが足利赤十字病院神経精神科である。栄養状態の改善過程におけるリフィーディング症候群、そして適切な食行動を阻害する認知の歪みは、どちらも摂食障害治療における重要なテーマであるが、上に紹介した二つの論文はそれぞれについて同院神経精神科の船山道隆部長と三村悠医師(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室大学院博士課程)が、日常の臨床の実践を発展させた貴重な報告である。
船山論文には摂食障害の身体的治療に文字通り今日から役立つ知見が明快に示されており、三村論文にはそれに加え、摂食障害についてよく知られている行動特性に脳の器質損傷が関与しているという驚くべき可能性が示唆されている。三村院生は解説文の中で「自分の妄想に近い」と控えめに述べているが、根拠ある妄想こそが(それは妄想の定義と矛盾するが)、治療方法の劇的な変革に繋がることは医学の歴史の中に刻まれた事実であり、本論文のデータはまさにその「根拠」になりうる画期的なものである。
(村松太郎、2021.5.24.)
自閉症スペクトラム症者の介入に最適なロボット
国立精神・神経医療研究センター 児童・青年期精神保健研究室 室長 熊﨑博一Hirokazu Kumazaki, Taro Muramatsu, Yuichiro Yoshikawa, Yoshio Matsumoto, Hiroshi Ishiguro, Mitsuru Kikuchi, Tomiki Sumiyoshi, Masaru Mimura. Optimal robot for intervention for individuals with autism spectrum disorders. Psychiatry and Clinical Neuroscience. 74 , 581-586. doi: 10.1111/pcn.13132. 2020.
最近の急速な科学技術の進歩により、ヒト型ロボットは様々な分野において活躍している現状がある。最近のエビデンスは,ロボットが自閉症スペクトラム症(ASD)者への支援にも役立つ可能性を示唆している。ASD者において、人間の訓練士よりも、ロボットの方がタスクへの集中が高いことがよく見られる。ASD者に使用するロボットの種類や形態については、現在まで様々な方法で検討されてきた。外見がシンプルなロボットや動物型ロボットは、そのシンプルさと、愛着を促すこともあり、受け入れられている。アンドロイドロボットには、ロボットで訓練した成果を日常生活に汎化しやすい可能性があるという利点がある。ロボットとユーザーの親和性を考えることは、ロボット介入の潜在能力を最大限に引き出すために重要である。ロボット側の要因として、外見、運動、服装、髪型、配置は重要な要因である。また、年齢、性別、知能指数などの利用者側の因子は、ユーザーとロボットとの親和性に与える可能性がある。ASD者の支援者は、ASD介入におけるロボットの潜在的な役割を知らなかったり、気が付いていなかったりする。支援者がロボットの使用経験が豊富であれば、その経験に基づいてロボットの潜在的な役割の多くを特定することができる。これまでのところ、ASD者への支援を目的としたロボットの研究は少なく、そのための最適なロボットを実現するためには、今後さらなる研究が必要である。
(熊﨑博一、2021.4.1.)
解説 不気味の谷を越えて
ASD者がロボットに親和性を有することはよく知られており、膨大な研究論文がすでに存在する。しかしロボットとひとことで言っても多種多様であり、どのようなロボットがASD者介入に最適であるかについての研究はまだまだ少ない。ロボットによる介入は、人間との交流のための訓練に位置づけられるから、人間に似たアンドロイドロボットが最適であるというところまでは想像できるが、アンドロイドロボットといってもそれもまた多種多様である。人間に似ていれば似ているほどいいかというと、そう単純にはいかない。「不気味の谷」と呼ばれる、不気味な概念がある。不気味の谷とは、人がロボットに感じる親和性の程度についての経験則である。人間に全く似ていない、いかにも機械という外見のロボットよりも、人間に似ているロボットの方に人は親和性を持つ傾向があるが、あまり人間に似すぎているとかえって不気味に感じられて忌避される。そこを突き抜けて完全に人間そのものであれば親和性は最高度になる。つまり、横軸に人間との類似性、縦軸にそのロボットに感じられる親和性をとると、グラフは右上がりになるが、ある地点で急落し、それを超えると急上昇する。この急落した部分が不気味の谷である。ASD者ではこの不気味の谷が右にシフトし、そのまま再上昇しない。つまりアンドロイドロボットに対する親和性や不気味さの感覚が定型発達者とは一種異なっている。さらに興味深いことに、ASD者の親にも同様の傾向があり、これもまた熊﨑博一室長が論文に記している(Kumazaki et al: Impressions of humanness for android robot may represent an endophenotype for Autism Spectrum Disorders. J Autism Dev Disord 2017. DOI 10.1007/s10803-017-3365-0)。
このようにASDとロボットについて、広汎かつ深い研究を続けている熊﨑室長が、現在利用可能なロボットについて、ASD者への介入への適性という観点から具体的に論考を加えたのがPCNの本論文で、ロボット実物の写真もカタログ的に収載されており、いわゆる「今日から役立つロボット入門」とでも言うべき読みやすいものとなっている。ロボットについての豊富な臨床経験に支えられた基礎的・理論的仕事から、このように非常に実戦的な仕事まで幅広い論文をpublishしてきた熊﨑室長は現在、慶應義塾大学病院でのロボット外来の開設準備を着々と進めている。
(村松太郎、2021.4.28.)
統合失調症当事者の症状論 村松太郎 編著 2021年2月5日発行 中外医学社
本書は「統合失調症とは何か」という問いに答えようとする、いささか野心的な本である。
精神症状は当事者の語りの中にある。
これが本書序文の第一文である。
精神疾患は客観的な指標に乏しく、現代の精神医学における診断が当事者の語る内容を主たる根拠にしている以上、症状は当事者の語りの中から見出す以外にない。本書に収められた実例の大部分は、当事者の自発的なナマの語りである。
臨床における診察では、いくら当事者の自由な語りを重視する形で進めようとしても、診察が医師と当事者の対話によって進められるものである以上、そこには医師からの誘導という側面があることは否めない。この誘導があると、当事者の語りは現代の精神医学の枠に規定されたものにどうしても傾いていく。現代の精神医学が確固たる正確な体系であればそれでもよいが、まだまだ発展途上の精神医学の中で、統合失調症の症状論は特に未熟なのであるから、その枠内に規定してしまうことは致命的な問題である。
本書の実例では誘導は文字通り皆無である。このような語りの蒐集は、インターネットが発達した現代において初めて可能になった方法であることも特筆すべきであろう。本書の新しい点はそれだけかもしれないが、それだけでも症状論としての意義はきわめて大きいと著者としては考えている。
これはあとがきからの引用で、本のオビにも記された、本書の大きな特長である。
本のオビには、出版社が作成してくださったキャッチコピーとしての文章も記されている。次の通りである。
当事者から自発的に寄せられた膨大な発言を蒐集・分類し、精神症状論の再構築を図る唯一無二の書
停滞する統合失調症の診断学に楔を打ち込む意欲作
「唯一無二の書」かどうか、「楔を打ち込む」かどうか、それは読者が判定することであるが、少なくともそれを目指して著した書であるとまでは著者としてはっきりと言うことができる。
そしてこの大きなゴールに向けた本書の構成は、きわめてシンプルである。目次はたったこれだけである。
1章 幻聴論
2章 幻視論
3章 妄想論
4章 他律論
5章 診断論
そして1章の冒頭はこの語りから始まる。
歩いているとみんな私のことを見て「こいつは気持ち悪い」「死ね」とか言って笑うのです。電車の中でもみんなの目線がこっちを向いていてヒソヒソ話しています。
精神科臨床で当事者からよく聞かれる語りで、ごく平凡なものといってもいいであろう。しかし、では、この体験は幻聴なのか。それとも単なる自意識過剰なのか。それによってこのケースの評価は大きく異なる。DSM-5によれば幻聴は、「幻覚は鮮明で、正常な知覚と同等の強さで体験され」と定義されているから、この当事者からよく話を聞いた結果、声がはっきりと聞こえたわけではないと言われれば、この体験は幻聴ではないことになる。すると自意識過剰にすぎないのか。あるいは関係念慮という用語をあてるべきか。
というふうに、現代の精神医学用語にこだわることで、本質から逸脱した無用に錯綜した議論に陥り、統合失調症の症状が見えなくなっているという考えのもとに、別の視点からの症状論を提案したのが本書である。その具体的内容はぜひ本書を手に取ってお読みいただきたい。1章のキーワードは「幻聴系」という造語である。統合失調症では軽視されている幻視をあえて一つの章とした2章、さらには幻覚と妄想の共通の基盤を示さんとした3章を経て、統合失調症の全症状の統一的理解を目指した他律という概念の4章に移行していく。本書でいう他律とは、昭和の前半に島崎敏樹が提唱しそのまま凍結されていた用語を解凍し、神経心理学をはじめとする現代のニューロサイエンスとの接点を示した概念である。
そして診断論と題した最終論で展開するのは、当事者のためという視点からの診断論である。
医学の従来の診断論には、当事者への直接の情報提供という視点が欠如していた。医学は常に発展途上の学問であるから、診断論も当然に常に発展途上である。現代の診断基準、たとえばDSMは、遠い未来のより洗練された診断体系を視野に入れた、仮の体系にすぎない。だが現代の当事者にとっては、重要なのは遠い未来ではなく現在である。診断基準に限らず現代においては、研究途上・発展途上の医学的知見が、インターネットによってリアルタイムで当事者に伝えられる。したがって診断論は、当事者への直接の情報提供を前提としての診断論でなければならない。
本書タイトルに「当事者」という語を入れた意味は、ひとつには、精神症状とは当事者の語りの中にあることを強調するためであるが、もう一つは、当事者への情報として有効な症状論であることを意味している。
本書本文はこう結んだ。
当事者の症状論とは、過去の知見を尊重したうえでの、現在と未来の当事者のための診断論に基づく症状論を指す。
(村松太郎、2021.3.26.)
人への強制的な後追い:新しい環境依存性の行動
船山道隆 (足利赤十字病院神経精神科部長)Michitaka Funayama, Taketo Takata.
Forced person-following: a new type of stimulus-bound behavior.
Neurocase 25, 2019 doi.org/10.1080/13554794.2019.1638944
【今までに報告されてきた環境依存的な行動】
過去にさまざまな形の環境依存的な行為/行動、すなわち、本能性把握反応、道具の強迫的使用/利用行動、模倣行動、環境依存症候群、反響言語、強制的な呼称や音読などが報告されている。これらの行為/行動は前頭葉内側を中心とした損傷によって、外部環境からの刺激にためらいなくそのまま反応してしまう前頭葉性の解放現象として説明されている。今回われわれは今までの報告にない、強制的に人を後追いする症候を報告する。
【人へ強制的に後追いを続ける症例】
症例は38歳時に練炭を用いた自殺によって一酸化炭素中毒からの低酸素脳症を起こした患者である。脳の損傷部位は両側前頭葉、両側頭頂葉、両側側頭葉、およびそれらの皮質下、さらに両側の淡蒼球と両側の尾状核に及んだ。吸引反射などの原始反射が目立ったが、麻痺は上肢に軽度認めるのみであり下肢には麻痺は認めず、発症2ヶ月半後には歩行は自立できるようになった。しかし、それと同時に患者は視界に入った人に強制的に後追いをするようになった。視界から離れるまで強制的な後追いは続き、長いときは1時間にも及ぶことがあった。患者は同時に簡単な単語の理解も困難な重度の失語症、重度の視空間障害(ひとりで自室には戻れず、さらに椅子に身体を正しく合わせることが困難)、意味記憶障害(日常物品や家族さえも認識できない)を呈していた。発症9ヶ月後に原始反射の軽減と視空間障害の軽減(自室にひとりで戻れるようになった)と並行して、強制的な人への後追いは消失した。
【類似した症候と想定される機序】
この症候は、ガチョウの生まれたてのヒナが最初に見た生き物を後追いするすり込み現象や乳児の母親への後追いに類似する。本症例では前頭葉や基底核のみならず後部脳も大きく損傷され、後部脳の損傷を反映した重度の失語症、視空間障害、意味記憶障害も伴っていた。したがって、本症例の強制的な後追の機序は前頭葉損傷による解放現象ではあるものの、自分の居場所や周囲のものの意味が全く分からないという状況下であったことも影響しているものと考えられる。すなわち、すり込み現象や乳児の母親への後追いと同様に、周囲の状況が分からず、さらに前頭葉機能が低下しているために人の姿の刺激に対してためらいもなく追従する環境依存的な行動が惹起されたものではないかと考えられる。本症例に見られた人への強制的な後追いは、人間の本能的な行動の機序にヒントを与える可能性がある。
(船山道隆、2021.2.1.)
びまん性軸索損傷例に認められたaction slip
~ご飯をグラスによそり、携帯電話を冷蔵庫に入れる~Scooping rice into a glass and putting a cell phone in the refrigerator: Action slips in an individual with a diffuse axonal injury
Cognitive Behavioral Neurology 2020; 33: 259–265中島明日佳 船山道隆 中村智之
【背景】健常者においても、砂糖の代わりに塩をコーヒーに入れてしまったり、料理の後にガスを消し忘れたりするといった無意識に行っている行為に出現するミスを認めることがある。これらのミスは注意障害として捉えられることが多いが、行為の側面からはaction slipと捉える立場がある。外傷性脳損傷をはじめとする後天性脳損傷においてはaction slipが健常者よりも多発することが予想されるが、今までに報告はなされていない。むしろ、遂行機能障害や注意障害を行為/行動面から捉えるaction disorganization syndromeという概念によって後天性脳損傷の症状を説明する報告がなされてきた。しかし、action disorganization syndromeは環境依存的な行動、保続、注意障害などから出現する行為/行動の障害の総称であり、特定の症状を捉えた症候ではない。今回われわれは、びまん性軸索損傷後にaction slipのみが多発し、社会生活や日常生活に問題が生じている例を提示し、リハビリテーションの方法についても報告した。注意障害ではなくaction slipの概念を用いることで、びまん性軸索損傷後の症状がより明確になり、リハビリテーションにもつながる可能性について考察した。
【症例】39歳の男性、交通事故にてびまん性軸索損傷を罹患、保存的治療を行った。入院時のGlasgow Coma Scaleは10と中等度の意識障害を認めたが、運動機能や感覚系に障害は認めず、意識障害も数日以内に改善し、発症4週後に自宅に退院となった。復職をするものの、職場では書類を紛失したり、するべき仕事を忘れたり、機械の操作で重要なステップを省略してしまったりと、ミスが続発したために辞職を余儀なくされた。日常生活においてもご飯をよそっている際に息子にグラスを取ってと言われたときにご飯をグラスに入れてしまったり、冷蔵庫に買ってきたものを入れる際に携帯電話を冷蔵庫に入れてしまったりしていた(置換エラー)。また、コーヒーにミルクを入れる際にミルクのパケットを開けて実際にミルクを入れる前にパケットをゴミ箱に捨ててしまったり、パンにラップをしたままトースターに入れてしまったり、外出時に携帯電話や財布を忘れたり紛失したりしていた(省略エラー)。神経心理学的検査では、知能、行為、エピソード記憶、ワーキングメモリ、注意/遂行機能はすべて正常範囲であった。一方で、action slipを含む日常生活上の行為/行動の失敗を評価するスケールであるCognitive Failures Questionnaireでは、健常者と比較して大きな成績の低下(健常者平均から-4.9 標準偏差)を認めた。
【リハビリテーション】置換エラーに関しては、患者が行う行為や使用する物品を言語化したり指差し確認をしたりすることで無意識の行為を意識化してエラー数を減らすことを試みた。省略エラー数に対しては、外部補助としてウエストポーチを使用したりワイアレス・キー・ファインダーを導入したりして物の紛失を防いだり、AI (artificial intelligence) スピーカーによるリマインダー機能、さらには必要なものを思い付いたその場でAIスピーカーに話すことによって買い物リストを作成したりする方法を用いた。その結果、Cognitive Failures Questionnaireの成績は健常者平均から-3.1標準偏差まで改善した。
【考察】びまん性軸索損傷後にaction slipのみが残存する症例を報告した。他の神経心理所見はすべて正常範囲内であったため、本症例に出現している症状はaction slipとして捉えると理解しやすかった。本症例に生じたこれらのミスは一般的には注意障害として捉えられるが、リハビリの観点からは、トップダウン的に常に行う行為に注意を配るように患者に求めることは不可能である。むしろ、ボトムアップ的に捉えるaction slipの観点から検討すると分かりやすい。すなわち、一般的なaction slipの機序として、行為に関して無意識に動員されるスキーマ(一連の行為を構成するひとつひとつの動作に関する記憶)が十分に惹起できないためaction slipが生じるという考え方がある。無意識で行われている一連の行為は多数の動作の集合であるため、スキーマの活性が弱いと一部の動作に省略エラーが出現してしまったり、置換エラーで代表されるように容易に外部からの干渉刺激に動作が影響されてしまったりするのかもしれない。本症例で実施したように、活性が弱いスキーマを補充するために動作を意識化したり外部補助を利用したりするなどのリハビリへの応用につながる可能性がある。本症例は1例のみの検討であるので、今後はびまん性軸索損傷をはじめとする後天性脳損傷の多数例においてaction slipの頻度や日常生活上への影響、さらにはリハビリテーションの方法を検討していきたい。
(船山道隆、2021.2.10.)
解説 意図と行動。意図なき行動。意図を滑る行動。
----- 環境依存症候群とアクションスリップ -----
人は意図する。その意図に基づいて行動する。意図は目的から生まれるから、行動は目的の達成に向けて進められる。こうして人は日々の生活を送っている。
だが時としてそんな常識はあっさりと崩れる。人は意図なき行動を取ることがある。いや、行動したからには意図があったはずだと考えるのが普通だし、現に脳内に意図があったからこそ行動が発生したはずだが、本人には意図したという意識がないことがある。咄嗟の反射的行動は無意識的なものだし、毎日の習慣的行動も無意識的に行われていることが多々ある。
また、行動開始の時には確かに意図して始めたという意識があっても、それに続く一連の行動は無意識に進行することもしばしばある。むしろ逆に意識するとぎこちない行動になる場合の方が多いとも言える。これはすなわち、脳内にすでに行動のスキーマschemaが存在しており、行動するという意識的な意図は、そのスキーマ発動のスイッチにすぎないと解釈する方が妥当であろう。
スキーマが単なる解釈ではなく脳内の事実であると実感できるのは、脳が損傷され、意図からは分離された行動が現れた時である。ただしそれは一見何気無い症状の中に本質を見抜く鋭い臨床的観察眼があって初めて見えてくるものである。足利赤十字病院神経精神科船山部長の2つのケースレポートはまさにそれを具現した仕事である。
第一は、大脳の広汎な損傷後に人への強制的な後追いが現れたケースである。船山部長はこの症状を環境依存症候群の一つとして捉えた。環境依存症候群とは、1986年にLhermitteが記載したもので、文字通りの意味は「環境のcueへの過剰な反応」で、より具体的には、目の前に物を提示されると、あたかもそれを使用せよという命令に自動的に従うかのように行動するという症状を指す。実例として、額装された絵を見ると壁に釘を打って架けてしまう・ベッドを見ると服を脱いでそこに寝てしまう、などの非常に印象的な例がLhermitteの論文に写真とともに紹介されている。いずれも前頭葉損傷のケースで、前頭葉の障害によって後部脳に存在するスキーマが解放された現象であると考察されている。言い換えれば、本来は意図によって発動される行動が、環境のcueによって発動されたということで、意図なき行動=自律性personal autonomyの障害であると言える。
船山部長が報告した「人を見ると後追いせずにいられない」という症状も、環境のcueによって発動された意図なき行動という意味では環境依存症候群の一型に分類することができるが、この稀な症状(おそらく世界初に報告された症状)が見られたのは、船山部長の解説に記されているように、このケースでは前頭葉以外の脳部位も損傷されていたことが関係しているのであろう。そしてLhermitteの報告と根本的に異なる点は、動物の幼生体に見られる親を追うという本能的な行動が再現されているという点である。脳内の行動スキーマの中には、先天的なものと後天的なものが混在していると考えられるが、船山部長のケースで見られたのは先天的なスキーマで、これは前頭葉性の原始反射がより高次な形で現れたものと捉えることも可能である。
第二のケースは、びまん性軸索損傷後に見られたアクションスリップである。
ご飯をグラスによそってしまったり(置換エラー substitution errors)、携帯電話や財布を忘れたり(省略エラー omission errors)という症状は、非特異的な注意障害として見過ごされてしまいそうだが、このケースでは注意機能に関する神経心理学的検査成績が正常であること、そして何より精密な臨床観察により、単なる注意障害ではなくアクションスリップ、すなわち、脳内スキーマの発動障害であると船山部長は推測し、その推測に基づいて計画・実行した認知リハビリテーションの効果によって、推測が正しいことを裏づけた。このケースに見られた行動は、本人の意図にそっている部分があるものの、環境からのcueによって撹乱されてエラーに至っており、いわば意図から滑って逸れた形を取っているという意味で、アクションスリップという表現にまさに合致するものである。
アクションスリップは、元々はフロイトの無意識論(フロイト的失言: 思わず本音が出てくるslip)から発展した概念である。周知の通りフロイトはこれを精神分析的に説明しているが、船山部長のケースは白質損傷(びまん性軸索損傷)によって、行為に関するスキーマ、さらには意識化されないレベルのイメージが惹起されやすくなっていると考えられる。この症状は日常場面の行動の中にはっきりとした形で観察できるものなので、外傷性脳損傷のひとつの指標になりうると船山部長は考察している。
第一の強制後追い現象は非常に顕著な症状であったのに対し、第二のアクションスリップはつい平凡な症状(単なるうっかりミス)として見過ごしそうな症状であった。両方のケースに共通するのは、意図と行動を結ぶメカニズム、そして意図と環境の関係についてのメカニズムが、症状の中に立ち現れていることである。
それを見抜くためには並外れて鋭い臨床観察眼が必要であるが、論文化するにはそれに加えて不撓不屈の努力が必須である。症例報告が論文として受理されにくいのが近年の医学界の傾向であることはよく知られている。多くの臨床家は貴重なケースに出逢い論文化を志してもリジェクトを繰り返されて投稿を断念するか、あるいはそもそも論文化しようという意図を持とうとしない。環境依存症候群としての後追い行動とびまん性軸索損傷に見られたアクションスリップはどちらも、船山部長以外ではまず達成できない、それだけに計り知れない価値を持つ臨床報告である。
(村松太郎、2021.2.27.)
経頭蓋磁気刺激法を用いたアルツハイマー型認知症及び軽度認知障害の神経生理学的バイオマーカー:レビューとメタ解析
三村悠 (慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)Mimura Y, Nishida H, Nakajima S*, Tsugawa S, Morita S, Yoshida K, Tarumi R, Ogyu K, Wada M, Kurose S, Miyazaki T, Blumberger DM, Daskalakis ZJ, Chen R, Mimura M, Noda Y*. Neurophysiological biomarkers using transcranial magnetic stimulation in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 121: 47-59, 2021.
Transcranial magnetic stimulation (TMS)はコイルを利用した電気刺激によりヒトの脳皮質を刺激し、そこから得られる誘発電位より運動野の興奮性を評価することができる。Single pulse paradigm(単回刺激)では運動野のGABA/Glutamate機能を反映した興奮抑制バランスの指標である、Resting motor threshold(RMT、安静時運動閾値)を、Paired pulse paradigm(複数回刺激)では二回の刺激の組み合わせで得られる誘発電位を評価することでGABA-Aを反映した皮質の抑制機能 Short interval intracortical inhibition (SICI)、Glutamateを反映した興奮機能 intra cortical facilitation(ICF)、コリンを反映した抑制機能Short latency afferent inhibition(SAI)を計測できる。さらに頻回刺激に対する反応をみることで脳皮質の可塑性を評価することもできる。
今回、我々はAD患者およびMCI患者に対してTMSを用いた皮質興奮性の指標がどうなっているか、包括的なレビューとメタ解析を行った。
結果として最終的に37本の論文からデータ抽出を行った。
解析の結果、AD群ではRMT/SICI/SAIが有意に減じていることがわかった。さらにMCI群ではRMT/SAIが減じていることがわかった。AD群ではICFは減じている傾向が見られたが有意ではなかった。認知機能とこれら指標との相関は見られなかった。
以上をまとめると次のことがいえる。
AD群及びMCI群では運動野の興奮性が高いことがわかった。運動症状が目立たないADでもMCIの段階から運動野の興奮性変化が示されたことに意義がある。またAD群及びMCI群ではSAIが減じていることからコリン機能が減じていることが示唆された。これは実臨床ですでに確認されている通りである。重要であったのはAD群においてSICIが減じていることからGABA機能が減じていることが示された点である。これについてはGABA受容体作動薬が認知機能に与える影響について絡めながら考察した。一般的にはGABA受容体作動薬は認知症には好まれないが、GABA機能が減じていることからは一部研究で示唆されているGABA受容体作動薬の神経保護作用を支持する可能性があるかもしれない。神経可塑性については研究数が少なくメタ解析はできなかったがAD群全体として可塑性が落ちているという知見で一致していた。これは今後の介入研究が反復磁気刺激による可塑性の誘導を中心としている趨勢に一致する。
MCI患者についての結果もMCIがやがてADへと進展していく過程を見ていることに矛盾はしなかった。
認知機能と神経生理指標との相関については残念ながら有意な結果はなかったが、これは運動野の研究であることが主な原因と考えられた。今後は前頭前野に対するTMS刺激、そしてそのアウトプットとして脳波を解析するTMS-EEG法がADやMCIのさらなる皮質機能理解に必要である。
今回の結果をもって、現在進めているTMS_EEG-MCI研究に邁進する所存である。
(三村悠、2021.1.1.)
解説 統合するTMS
まずは分解する。それが科学の定法である。分解しなければ分析できないからだ。このとき、決して分解した個々の要素自体が重要だと考えているわけではないし、要素を組み合わせれば元の全体が得られると考えているわけでもない。しかし分解しなければ分析できない以上、第一歩としては分解する以外になく、それが正しいと誰もが考えるからこそ科学の定法になっているのである。全体を視野に入れるのは要素についての十分な知見が得られてからおもむろに、というわけだ。だが手段が往往にして目的となってしまうのが人の常だ。要素を科学的に正確に分析しようとすれば高度に専門的な技術を要するという事情もあって、真実追究の意志が強い研究者ほど視線が要素に固定される傾向が止まらない。かくして、精密かつ重要ではあるものの、いつどこで役に立つのかわからないようなデータが論文として次々に発表され、科学的に高い評価は得るものの、データ自体は店晒しになったまま時が過ぎてゆくという事態が起こりがちである。特に認知症のような、いまや全人類にとっての大きな課題については、あらゆる分野の専門家が研究に従事することから、そのような事態が起こりやすく、現に相互の関係性が見えにくい雑多な ----- と言ったら失礼だが雑多にしか見えないような ----- 知見が蓄積されている。
TMSはそんな知見を統合できる可能性を秘めている。キーワードは皮質興奮性である。ここに着目した三村悠大学院生が、様々な領域の研究データを統合しうる手法であるTMSによる研究論文を、さらに統合するメタ解析によって得たのは、MCIからADへの発展という、高齢社会における最重要とも言える問いへの回答に貢献するデータであった。
TMSには強力な統合力が潜在しているが、運動野のみに着目した本研究では、その統合力の一部が示されたにすぎない。今後、着目する要素を拡大することで、壮大な統合研究への道が開けている。そのすぐ先には治療もある。多くの医学論文の結びにはfuture directionとして治療法の開発への期待が記されているが、多くの場合にそれは形骸化した決まり文句にすぎない。TMSはこの点、大きく異なる。脳に直接介入するTMSは、具体的かつ速やかなレベルで、確かに治療法の開発に直結している。TMSに邁進すると宣言する三村院生の研究への期待は大きい。認知症がテーマである以上、それは全人類からの期待である。
(村松太郎、2021.1.25)
健常者を対象としたドーパミン神経伝達の恒常性維持に関するPET研究
山本保天 (慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程 / 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 量子医学・医療部門 放射線医学総合研究所 脳機能イメージング研究部 脳疾患トランスレーショナル研究チーム)Yamamoto Y, Takahata K, Kubota M, Takano H, Takeuchi H, Kimura Y, Sano Y, Kurose S, Ito H, Mimura M, Higuchi M.
Differential associations of dopamine synthesis capacity with the dopamine transporter and D2 receptor availability as assessed by PET in the living human brain.
Neuroimage. 2020; 226: 117543.
ドーパミン(DA)神経伝達は、運動制御、報酬探索行動、動機づけなどの脳機能に関与する。さらに、線条体におけるDA神経伝達の異常は、統合失調症や気分障害などの様々な精神疾患やパーキンソン病などの神経疾患の病態生理に関与していることが知られている。抗精神病薬は、D2受容体遮断作用を介して精神病症状に効果をもたらすことが知られており、DAトランスポーター阻害薬やDA作動薬などシナプス間隙のDA濃度を上昇させる薬剤は、幻覚や妄想などの精神症状を誘発することが報告されている。このように、DA神経伝達を適切なレベルに維持することは、極めて重要であると考えられる。実際に、薬理学的介入を伴う過去のPET研究では、DA神経伝達の構成要素が相互に関連して、DA神経伝達が恒常的に維持されている可能性が間接的に示唆されている。例えば、6-[18F]Fluoro-L-Dopaを用いた過去のPET研究では、健常者にDAトランスポーター阻害剤であるメチルフェニデートを単回投与すると、DA生成能が22%減少することが報告されており、DA生成能とDAトランスポーター密度との関連性が示されている。しかしながら、DA神経伝達の生成能、受容体、トランスポーターなどの構成要素が相互に関連して恒常的にDA神経伝達を維持されている機構はこれまで明らかにされていなかった。本研究では、健常者の線条体におけるDA生成能とDAトランスポーターおよびD2受容体密度との関連を調べることを目指した。
本研究では、量研機構にて過去に行われた研究で取得されたPETデータを網羅的に収集し、再解析を行った。まず、L-[β-11C]DOPA- PET検査と[18F]FE-PE2I- PET検査とを同日に受けた健常男性12名(24.5 ± 4.6歳)のデータを用いて、被殻と尾状核におけるDA生成能とDAトランスポーター密度との関連を調べた。その結果、被殻において DA 生成能と DA トランスポーター密度との間に有意な正の相関が認められた。次に、L-[β-11C]DOPA-PET検査と[11C]raclopride-PET検査とを同日に行った、健常男性29名(25.2 ± 3.8歳)のデータを用いて、DA 生成能と D2 受容体密度との関係を検討した。その結果、線条体において DA 生成能と D2 受容体密度との間に有意な相関は認められなかった。
本研究により得られた、健常者におけるDA 生成能と DA トランスポーター密度との正の相関は、DAトランスポーター密度に対するDA生成能の比率が一定のレベルで維持されていることを示し、DA生成能とDAトランスポーターとが関連し、シナプス間隙のDA濃度を恒常的に維持している可能性を示唆している。また、対照的に、DA 生成能と D2 受容体密度には有意な相関を認めなかったことからは、シナプス前自己受容体とシナプス後受容体とを含むD2受容体の総量は、この調節機構と直接的な関係を有さない可能性が示唆された。本研究の成果はDA生成能とDAトランスポーターの間の不均衡が、統合失調症や気分障害などの精神疾患の病態生理に関与している可能性を示唆するものであり、将来的に精神疾患の病態生理の解明に寄与することが期待される。
(山本保天、2020.12.10.)
解説 ヒト生体内でドーパミンを観る
ドーパミン関連の分野では、これまでに動物実験や機能画像研究が多数行われてきたが、ドーパミン神経伝達系を構成する諸機構の関係性をヒト生体内で直接検討した研究報告はほとんど存在しなかった。本研究はDA生成能を中心として、これとDAトランスポーターおよびD2受容体密度との関係を、同一の被験者で複数のPETリガンドを用いて検討したものであり、ドーパミン神経伝達の恒常性維持に関する非常に貴重なデータが得られた。この点が評価されて、Neuroimage誌に掲載されたものと考えられる。筆頭著者の山本保天院生は、本研究の成果を22q.11.2欠失症候群のドーパミン神経伝達機構に関する研究につなげてくるものと期待している。
(高畑圭輔、2020.12.14.)
うつ病における抗うつ薬治療開始後の4週間毎の脳機能変化
山縣 文 (慶應義塾大学医学部精神神経科 専任講師)Yamagata B, Yamanaka K, Takei Y, Hotta S, Hirano J, Tabuchi H, Mimura M. Brain functional alterations observed 4-weekly in major depressive disorder following antidepressant treatment. J Affect Disord. 2019 Jun 1;252:25-31.
過去の脳画像研究から、大うつ病性障害(major depression disorder; MDD)では、前頭葉内側、辺縁系、線条体、視床、および前脳基底部を含む広範な神経ネットワークの機能異常が関与していることが想定されている。しかしながら、現在まで診断や治療に直結する一貫した生物学的所見は見いだされていない。そこで、抗うつ薬治療による神経ネットワークの反応性を調査することで、不均一な病態であるMDDの生物学的所見の一側面を同定する試みがなされている。
近赤外分光法(near-infrared spectroscopy; NIRS)は、磁気共鳴画像法(magnetic resonance imaging; MRI)と比較し低侵襲性であるため、短い間隔で繰り返し測定することが可能であり、治療経過に伴う前頭前野の脳機能の変化を詳細に測定できる利点がある。そこで、われわれはMDDを対象に抗うつ薬の治療開始時から4週間毎にNIRSを測定し、従来のMRI研究と比べ短期間かつ高頻度に脳機能の変化を捉えることを目的とした。
52チャンネルNIRSを使用し、未治療のMDD 11名を対象に、語流暢性課題(verbal fluency task; VFT)を遂行中の酸素化ヘモグロビン(oxygenated hemoglobin; oxy-Hb)の賦活量を測定した。具体的には、セルトラリン治療開始前、開始後4週間目、8週間目、12週間目の計4回測定する全12週間の縦断研究を実施した。
うつ病の治療前後の脳血流の変化を検討した過去の脳画像研究の多くは、前頭前野における低活動性が抑うつ症状の改善に伴い正常化(normalization)することを報告している。しかしながら、我々の結果は従来の報告とは異なるものとなった。具体的には、12週間目の時点でMDD全員が寛解に至ったが、左下前頭回および上・中側頭回に位置する脳領域におけて、[oxy-Hb]値は治療開始前が最も高く、4週間目に一番下がり、その後、12週間目に向けて徐々に上昇するという非典型な変化を示した。一方で、他の脳領域では時間経過による[oxy-Hb]値に有意な変化はみとめなかった。我々の先行研究よりVFT遂行中の前頭葉の[oxy-Hb]値は抗うつ薬の服薬量と反比例することが示されており(Takamiya et al., 2017)、抑うつ症状が改善しているにも関わらず、[oxy-Hb]値が減少している理由として抗うつ薬の服用による影響が示唆された。
さらに、12週間を通して上記の脳領域における[oxy-Hb]値の級内相関係数が中程度であったことより[intra-class correlations (1,1) = 0.468; P < 0.001]、[oxy-Hb]値の非典型な経時的変化は個人差やアーチファクトの影響ではなく、全てのMDD患者が一貫して同様の変化をしていることが示され、MDD診断における生物的所見である可能性が示唆された。また、臨床症状との関係においては、4週間目の[oxy-Hb]値が4から8週間目まで(r = −0.727、P = 0.011)、および4から12週間まで(r = −0.63、P = 0.039)のハミルトンうつ病尺度の改善度と有意な相関関係をみとめた。
以上より、4週毎という短い間隔で繰り返しNIRSを測定することで、MDDにおける寛解に向けた前頭葉の血流変化パターンを同定し、さらにセルトラリン治療への反応性を予測する結果を得た。本研究は11例とサンプル数が少ないため学術的な信頼性が低いことは否定できない。しかしながら、NIRSの利点を活かすことで、従来のMRI研究では見いだせないMDDにおける生物学的所見を抽出できる可能性が示唆された。
(山縣 文、2020.11.1.)
解説 刻々を観る
人間の精神状態は刻々と変化する。すなわち脳の活動は刻々と変化する。その「刻々」とは具体的にどの程度のスケールなのか。秒か。分か。時間か。日か。年か。もっと長いスパンか。あるいは逆にミリセコンドか。マイクロセコンドか。ナノセコンドか。もっと短いスパンか。
どれも真実であろう。精神状態の「変化」をどのスケールで捉えるかによって、脳の活動の変化の適切な捉え方が決まるのだ。
では、疾患に対応する脳の活動を見ようとするときは、どのスケールで見るのが適切なのか。
それはわからないというのが真実であろう。疾患の本質がわからない段階では、症状のどのような変化が真に重要なのかはわからない。わからないから、とりあえず可能なスケールで見る以外にない。それが現実であり、これまでのどの研究もそうした現実の制約の下で行われている。たとえば治療の前後の脳活動の変化を見るというのは一つのよくあるパターンで、それはもちろん一定の意義を有するデータではあるが、「とりあえずできる検査を、とりあえずできる時期に行う」という側面があることは否めない。機能的MRIやPETを、週単位や日単位のスケールで行うわけにはいかないのである。
手法が比較的簡便で無侵襲な検査であるNIRSはこの点、大きなアドバンテージがある。それを最大限に生かしたのが山縣講師の本研究である。4週単位というスケールで脳活動の変化を見る。NIRS以外の検査手法では事実上不可能な研究デザインである。スケールが変われば、これまで無視されてきた問いに答えられる可能性が出てくる。その一つが、そして臨床的に重要な問いの一つが、薬に対する反応である。得られたデータは、従来の研究手法で同定された脳部位とは異なり、うつ病の脳内基盤を追究するうえで非常に示唆に富むものであった。11例という少数が対象であるからパイロットスタディ的な位置づけとなるが、多数例に適用しやすいこともまたNIRSの大きな特長である。次のステップに大いに期待したい。
(村松太郎、2020.11.30.)
<名著精選> 心の謎から心の科学へ 「感情: ジェームズ/キャノン/ダマシオ」
岩波書店 2020年
梅田 聡・小嶋祥三 (監修)
感情の研究には長い歴史があり,これまで数多くの理論が提案されてきた.そのなかでも特に重要な理論としてしばしば取り上げられるのは,「ジェームズ・ランゲ説」と「キャノン・バード説」である.前者は「感情の末梢起源説」,後者は「感情の中枢起源説」として知られ,感情の源が身体にあるか,脳にあるかという論点をめぐり,対比的なスタンスが取られている.近年の感情に関する論文においても,これらの論説は高頻度で引用される一方,十分に原著を読み込んだ上で論を展開しているとは思われず,内容的にニュアンスの異なる引用まで散見される.
この2つの論説が展開されてから数十年が経過し,神経科学に関する知見が積み重ねられた時代においても,これらの理論に立脚する形で論が展開されるケースが多い.その代表的な理論が,ダマシオによる「ソマティック・マーカー仮説」である.この仮説とともに有名なのが,「アイオワ・ギャンブリング課題(IGT)」である.ソマティック・マーカー仮説が,IGTを用いた研究結果に支えられていることは確かであるが,この課題が考案される以前に,いくつかの重要な自律神経活動に着目した生理心理研究が発表されている.しかしながら,IGTばかりが有名になってしまい,そちらの研究成果は埋もれてしまった感が否めない.IGTの特徴を理解する上で,その立案の元となった論文に触れることは,明らかに理解を深めることの助けとなるが,近年の論文ではもはやほとんど引用すらされなくなっている.
以上の理由から,今回,これら3つの理論の原著の骨子を日本語に訳し,あらためてそこから見えてくるものが何かについて考えてみることとした.本書は,4つのパートから構成される.最初のパートは「イントロダクション」であり,感情研究の歴史を振り返り,どのような背景でこれらの3つの理論が生み出され,それが発展していったかを繙いた.さらに,近年の神経科学をはじめとする研究の成果を踏まえると,それぞれの理論がどのように捉えられるのかについても概説した.今回の仕事のなかで最も難を極めた点は,訳語の統一である.感情の一側面を表す英単語には,emotion,affect,mood,feelingをはじめとする複数の概念が存在する.これらを訳出する際,日本語と一対一対応させることは困難である上,日本語の単語としてもそれぞれが独特の意味を持っており,それが原語の持つ意味とは異なる場合すらある.そもそも,用語概念の整理が,感情の概念に関する研究になってしまうレベルである.本書では,やや多めの文量をとってこれらの点に関する説明を試みた.
イントロダクションに続くパートが,3つの理論の原著論文の日本語訳である.各論文について,まずは抄録として背景と骨子をまとめた後で,原著の日本語訳を提示した.なお,本書では,プロの翻訳家に翻訳を依頼し,梅田がその監訳を行った.ジェームズの原著は,1890年に出版され“Principles of Psychology”の25章“The emotions”である.キャノンの原著は,1929年に出版された“Bodily changes in pain, hunger, fear, and rage”の第二版の抜粋である.この著者は,キャノンの提唱した有名な概念である「闘争・逃走反応」の発想の原点とも位置づけられる.第一版は1915年に出版され,15章構成であったが,新しい生理学研究の知見をもとに展開した第二版は,20章構成になっている.第二版で追加された計5章は,その多くが感情に関連する論考であり,特に第18章は,ジェームズの理論に対する批判的論述に当てられており,注目に値する.ダマシオの原著は,1991年に出版された“Frontal lobe function and dysfunction”という書籍の11章に収められた,“Somatic markers and the guidance of behaviour: Theory and preliminary testing”である.
いずれの論説も,感情を広い視野から俯瞰した視点に立っており,深い論考の上に成り立っている.歴史的な著作であるため,単に事実という意味では誤った記述が含まれる点は否めないが,それを超えた考察の深さがあることに疑いの余地はない.本書が,感情に関するさらなる理解の一助となれば幸いである.
(梅田聡、2020.10.18.)
解説 名著の名訳による名著
著者名は聞いたことがある。名著があることもよく知っている。いつか読まなければならないと思っている。だが結局は読んでいない。読んでいないのに引用する。古典的な名著をめぐるこうした事態はしばしば発生している。自分の研究に特に関係する部分だけでもしっかり読んで引用するならまだいいが、まったく読まずに引用されることさえある。すると当然に原著の記載は歪められた形で引用される。それをまた誰かが引用する。もはや下手な伝言ゲーム状態となって、名著の内容は痕跡を残すのみとなり、名著は「名」が知られているだけの抜け殻と化す。かくして名著に刻まれた人類の貴重な叡智は人々から忘れ去られ、すでに完結していたはずの議論を一から蒸し返すような研究が始められるという不毛な営みさえ発生することになる。
この事態を打開するために考えられる方法は二つある。原著を原文で読むこと、または、原著を翻訳で読むことである。もちろん原文で読む方が望ましい。しかし現実にはそれは難しい。古典的な名著はしばしば長文である。超長文のこともある。自分の専門分野の最新の最重要文献ならともかく、いくら名著とは言え何十年も昔の大論文を原文で読む時間などなかなか取れるものではない。
すると古典を読む機会は翻訳しかない。だがそれは別の意味で難しい。なぜなら医学論文の翻訳の大部分はあまりに低品質だからである。そんな訳文を読む時間など、取れるものではない。
こんな憂うべく状況を粉砕したのが、岩波書店の「名著精選」シリーズの中の一冊、梅田聡教授(慶應義塾大学文学部心理学専攻)編集の『感情』である。
本書は傑出した名訳である。名訳に仕上がっていることには理由がある。
ひとつは、翻訳者がプロの翻訳家であること。この種の訳本は多くの場合、テーマに関連する研究室のメンバーが分担して翻訳するのが定法である。しかしそれでは訳文が拙劣になることが避けられない。論文を読めることと訳せることは全く別のスキルなのである。翻訳は翻訳のプロに任せなければならない。だがそれだけではまだまだ不十分である。翻訳のプロは医学の専門家ではないから、医学的内容はしばしば誤解されて訳されている。もちろん優れた翻訳家は、専門的な内容は専門家の意見を聞いて正確を期する努力をするものであるが、それでも限界があることは否めない。
では本書はなぜ名訳に仕上がったか。梅田教授がすべての訳文を精密にチェックしたからである。本の表紙に記されている「監修」は、名ばかりのことが多いが本書はそうではなく、名実ともに梅田教授の深く広い知見が浸透している。
それは訳文だけにとどまらない。本書は、冒頭に感情研究の流れについての30ページに及ぶ秀逸なイントロダクションがあり、加えて、各論文に数ページの密度の濃い解説が付けられている。梅田教授によれば、これらの内容も裏をとる必要がある部分が多く、一行の文章を書くのに数冊の古典にあたるという作業をされたとのことである。このイントロダクションと各論文解説の傑出した質の高さにはこうした背景があり、独立した論文としても十分以上に価値のあるものである。これらだけを読めば感情研究についてすべてがわかった気になってしまうほどであるが、本文を通読することでさらに深い本書の真価が初めて体感できることは言うまでもない。名著である原著が、名訳によって日本語に生まれ変わり、最終的には翻訳書というジャンルを超越した名著となったのが本書である。
最後に本書の目次を記す。
イントロダクション
梅田聡
情動
William James (1890) 南條郁子訳
痛み、空腹、恐れ、怒りに伴う身体変化 --- 情動の興奮の機能をめぐる最近の研究報告
Walter B. Cannon (1929) 藤原多伽夫訳
ソマティック・マーカーと行動指針 --- 理論と予備的検証
Antonio R. Damasio, Daniel Tranel, and Hanna C. Damasio (1991) 北川玲訳
(村松太郎、2020.10.30.)
自覚的認知機能低下を訴える健常高齢被験者へのアルツハイマー病発症前診断の結果開示が与える長期的な心理的影響
和氣大成(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 研究員)Wake T, Tabuchi H, Funaki K, Ito D, Yamagata B, Yoshizaki T, Nakahara T, Jinzaki M, Yoshimasu H, Tanahashi I, Shimazaki H, Mimura M. : Disclosure of Amyloid Status for Risk of Alzheimer Disease to Cognitively Normal Research Participants With Subjective Cognitive Decline: A Longitudinal Study.
Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2020;35:1533317520904551. doi: 10.1177/1533317520904551
アミロイドPETによるアルツハイマー病の発症前診断が世界中の臨床研究で行われているが、「自覚的認知機能低下(Subjective Cognitive Decline: SCD)」を訴え不安の強い人へのPET結果開示の心理的影響についてはほとんど明らかにされていなかった。自覚的認知機能低下は、従来の検査では客観的に神経心理学的な異常を認めないものの、本人は持続的に認知機能の低下を自覚することと定義され、アルツハイマー病を発症するおよそ15―20年前の前臨床期で注目されている。
アミロイドβの異常蓄積という病変がすでに始まっている前臨床期で不安症状が高まると、内因性糖質コルチコイドの上昇を通じて、より著明な認知機能の低下を誘発するとの指摘もある。このため、前臨床期で自覚的認知機能低下のある人へのアルツハイマー病発症リスクの情報開示が不安を増悪させないか検証することは喫緊の課題であった。
予備的研究では、自覚的認知機能低下のある健常高齢者42名に対してアミロイドPETを実施し(陽性10名)、PETの結果開示前後の不安および抑うつレベルを比較するとともに結果開示後6週のトラウマ症状を測定した(本HP 2017.12.の解説参照)。
本研究ではこれらの全被験者に対して、さらに結果開示後24週と52週まで長期的に追跡した。PET陽性・陰性のどちらの群においても、不安、抑うつ、トラウマ症状の継時的変化は認められず、臨床的に重要となる値以下で推移した。不安と抑うつに関しては各時点で両群に差はなかったが、トラウマ症状に関しては、52週時点で陰性群のほうが陽性群よりも有意に高いレベルとなった。さらに詳細な統計学的解析を行ったところ、陰性群においては、ベースラインの不安と52週時点のトラウマレベルが同群の平均より高いサブグループの存在が明らかとなった。
自覚的認知機能低下のある健常高齢者に対して、アミロイドPETによるアルツハイマー病発症前診断の結果を開示しても、長期的に明らかな心理的危害があるとは言えないことが示された。しかし、アミロイドPET陰性群には、客観的に評価された認知機能と自覚する認知機能およびそれに伴う不安との乖離の程度に関してスペクトラムが存在する可能性が示唆され、陰性であってもアミロイドPETの結果開示は慎重に行う必要があることが明らかになった。
健常高齢者に対するアルツハイマー病の発症前診断を臨床の場で実施することはガイドラインが不適切と定めている。結果開示の不利益の一つと想定されたのは「心理的な危害」である。しかし少なくとも現在に至るまで、本研究も含めて明らかな危害は報告されていない。アルツハイマー病の発症リスクを知りたいと望む声は多く、自らの人生にとって極めて重要な意味を持つ健康情報を知る/知らないでいる権利をどう保障するか、さらなる倫理学的検証が求められる。このため今後は本研究を発展させ、理論と実証の神経倫理学的アプローチを統合し、より洗練された倫理規範の提示を目指す。
(和氣大成、2020.9.18.)
解説 ガイドラインの彼方にある倫理
ガイドラインに従っていれば間違いない。批判されない。専門家らしく見える。安全だ。だが、人間でなくてもできる。AIを持ち出すまでもない。入力された命令を実行するだけの第一世代のコンピューターでもガイドラインに従うことは十分にできる。人間ならガイドラインの裏にある事実を読まなければならない。我が国のアミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン(2017.11.17.)には、この検査の不適切な使用として「自覚的な物忘れ等を訴えるが客観的には認知機能障害を認めない場合」「無症候者に対するアルツハイマー病の発症前診断」などが挙げられている。同様の記載は国際的なガイドライン(Appropriate Use Criteria for Amyloid PET, 2013)にもある。但しそこには「現時点では、アミロイドPETによる発症前診断にはベネフィットは小さく、害の可能性がベネフィットを上回っている。発症予防の治療が開発されれば状況は間違いなく変わるであろう(At present, the potential harms outweigh the current minimal benefits. The availability of proven preventive therapies undoubtedly would alter this.)」と付記されている。害とはすなわち心理的な害である。PETでアミロイド陽性であれば、自分はまもなくアルツハイマー病を発症するのではないかと不安になるであろう。不安に圧し潰され抑うつ的になるかもしれない。かといって現時点では発症を予防する有効な手段はない。そうであればPET検査などしないほうがいい。ガイドラインはそう教えている。明快な論理だ。納得できる理由である。だが、人間でなくてもわかる単純な論理だ。人間ならガイドラインの記載を書き換える努力をしなければならない。それは現状打開への努力である。そのためには検証への第一歩を踏み出さなければならない。アミロイドPETの結果を知ることは当事者に本当に心理的な害をもたらすのか? それが和氣研究員による本研究のテーマであった。そして、自覚的認知機能低下のある健常高齢者に対して、アミロイドPETによるアルツハイマー病発症前診断の結果を開示しても、長期的に明らかな心理的危害があるとは言えないことを示した。
ガイドラインは便利な一方で、欺瞞も含んでいる。特に倫理的な事項についての記載は、その絶対的ともいえる強制力と裏腹に、根拠は単なる推定にすぎないことも多く、しばしば空疎である。しかし倫理を前面に出されると、違反して非倫理的だと指弾されることを避けたいと思うあまり、無条件的に従うということになりがちである。「検査結果を告知することは当事者にとって害となる」ことを理由にアミロイドPETの施行を禁ずるのも、倫理の領域にある記載であり、そして空疎な根拠しかない記載である。人間ならガイドラインの彼方にある倫理を見抜かなければならない。今後、精度も検査希望者数も急峻に高まることが必至のアミロイドPETを、当事者に最大の利益をもたらす形で発展させていくためには、倫理的事項についても実証データを出していくことが、技術的な研究に匹敵するか時にはそれ以上に重要な課題であるが、そうした研究は驚くほど少ない。倫理ガイドラインは、ひとたびそれらしいものが作成されると、批判されることなく維持されるのが常なのである。
どの時代にも、どの領域にも、人には特に疑いを持たないままに持ち続けている信念beliefというものがある。そうした信念を問い直し続けたソクラテスの系譜を継ぐ応用倫理研究所がオックスフォード大学哲学科に設置され、従来の倫理学の枠を超えた実証的アプローチを展開している (https://www.practicalethics.ox.ac.uk/home)。和氣研究員の本論文は、その研究所からも注目され、国際共同研究がまもなく開始されようとしている。
(村松太郎、2020.9.25.)
タウタンパク質をターゲットとしたPETリガンド11C-PBB3を用いた精神病症状を伴う老年期うつ病患者における生体内可視化研究
森口翔 (慶應義塾大学医学部精神神経科 助教)Moriguchi S, Takahata K, Shimada H, Kubota M, Kitamura S, Kimura Y, Tagai K, Tarumi R, Tabuchi H, Meyer JH, Mimura M, Kawamura K, Zhang MR, Murayama S, Suhara T, Higuchi M.
Excess tau PET ligand retention in elderly patients with major depressive disorder.
Molecular Psychiatry 2020 Jul 1. DOI https://doi.org/10.1038/s41380-020-0766-9
うつ病は、アルツハイマー型認知症をはじめとした認知症の危険因子であることが知られている。また、認知症の約3割はその発症前に何らかの精神疾患であると診断されているが、その多くはうつ病である。このようにうつ病と認知症には何かしらの共通点があるのではないかと考えられてはいるものの、うつ病と認知症の間にある共通した病態メカニズムについてははっきりとはわかっていない。その中のひとつの仮説として、タウやアミロイドβの蓄積はこれら2つの疾患に共通している可能性が言われており、それらの存在が示唆されてきた。これまで、タウとアミロイドβ両方に結合するイメージング剤18F-FDDNPで行われた老年期うつ病のPET研究では、うつ病の脳内で18F-FDDNPの結合が高く認められたものの、それがタウ蓄積によるものなのかアミロイドβ蓄積によるものかは不明のままであった。本研究では、老年期うつ病を対象にタウならびにアミロイドβ特異的に結合する2つのイメージング剤を用いてそれらの蓄積量ならびに分布と、臨床的特徴との関連を明らかにすることを目指した。
本研究では、50歳以上の老年期うつ病と同年代の健常者を対象に、タウに対してはイメージング剤11C-PBB3を用いて、アミロイドβに対してはイメージング剤11C-PiBを用いてPET検査を行い、タウおよびアミロイドβの脳内の各領域における蓄積量を調べた。その結果、老年期うつ病患者では脳内の大脳皮質全体にタウ蓄積が認められ、その中でも前帯状皮質と呼ばれる脳部位で高い傾向がみられた。また、患者内において精神病症状の有無で分けて比較したところ、精神病症状を有する老年期うつ病患者群の大脳皮質全体においてタウ蓄積がより多く認められ、特に前頭前皮質、前帯状皮質、側頭葉などの脳部位で高い傾向がみられた。なお、アミロイドβの蓄積量は、老年期うつ病患者群と健常者群で差はなかった。次に本研究結果を検証するため、東京都健康長寿医療センターで行われた高齢者ブレインバンクプロジェクトの死後脳データを用いて、顕著なアミロイドβの蓄積がないもののタウの蓄積が認められるケースが抑うつ症状の認められた症例でみられることが明らかになった。これにより、PET検査による結果と同様にうつ病患者の一部にタウ蓄積が関連している可能性が死後脳でも示唆された。
本研究の成果は、一部の老年期うつ病、特に精神病症状を呈する患者にタウの蓄積が関与している可能性を示唆した。これまでの精神疾患の操作的診断基準では、若年者のうつ病も老年期うつ病も、同一のうつ病として診断され、治療方法も分かれてはいなかった。しかし、臨床上はこれら2つのうつ病が明らかに異質な症状を呈している場合が少なくなかった。その中でも、妄想や幻覚などを呈する精神病症状は老年期うつ病に比較的多く認められ、若年者にはほとんど認められないことが知られている。こうした老年期うつ病に比較的特有な精神病症状としては、うつ病の一群としても考えられるコタール症候群などがある。このような臨床的観察により、以前から老年期うつ病の中には若年者とは別のメカニズムが関与しているのではないかと言われていた。
本研究の結果はそのような精神病症状を呈する老年期うつ病にタウ蓄積が関与していることを示唆するものであった。一方で、本研究において精神病症状を呈する老年期うつ病であってもタウ蓄積が認められない症例も認められたため、今後、精神病症状が認められたとしてもどのような場合にタウ蓄積が関連しているかを明らかにするための研究が必要となる。また、本研究の成果は診断のみではなく、老年期うつ病の今後の治療指針についても有用である可能性がある。アルツハイマー病などの認知症では、タウ蓄積を標的とした根本的な治療薬の開発と複数の臨床試験が実施されており、タウが関与している一部の老年期うつ病を早期に診断することが可能となれば、こうした新しい治療法を適用できるようになると期待される。
(森口翔、2020.8.17.)
解説 カオスの中の真実を見抜く
何もわからなければとりあえず外見で分類するしかない。そんな開き直りから生まれたのが現代の精神疾患の分類体系である。だから外見が同じなら同じカテゴリーに分類される。トマトもサクランボもアセロラもイクラも、赤くて丸いという外見だから同じカテゴリーに分類される。そんな乱暴な分類があるかと批判するのはトマトやイクラとは何であるかを知っているから言えることであって、外見しか見えなければとりあえず外見で分類するのは決して乱暴ではなく、わからないことについては過剰な推定をしないという謙虚で科学的な姿勢である。
「抑うつ気分」「興味の喪失」「睡眠障害」「罪責感」・・・こうした項目が一定数そろえばうつ病と診断するのも、謙虚で科学的な姿勢である。うつ病の脳内がどうなっているのかよくわからない。予後もよくわからない。どの治療が効くのかもよくわからない。わからないことについて雄弁に語るのは軽薄である。わかることについてのみ静かに語るのが賢者である。今とりあえず確実にわかるのは、外見としての症状しかない。症状だけに基づいて分類する診断体系は、現代の精神医学を集大成した到達点なのである。
但しそれは「とりあえず」であり、「開き直り」であることを意識していなければならない。
トマトもサクランボもアセロラもイクラもひとまとめにしたとき、いかに精密に研究しても、「どれも赤くて丸い」という以外の結果は得られない。それではあんまりなので、手持ちの分析技術や統計手法を駆使すれば、赤という外見を発現させる色素についての知見が得られ、それらしい論文はできあがるかもしれないが、それはトマトについての本来の研究目的からはかけ離れている。うつ病に関する現代の論文の大多数、とは言わないまでも、相当の数がこの問題を内在している。内在というより蔓延といった方がいいかもしれない。現代のうつ病概念が、とりあえずの開き直りから生まれた暫定的なものであることを常に意識しなければ、トマトとイクラを同一視するという不条理から必然的に醸成されるカオス空間を彷徨う論文ばかりが生産され続ける。
このカオスの中から真実を抽出するためには新しいテクノロジーが必要である。そこで森口翔助教は11C-PBB3と11C-PiBを活用した。どちらもPETのイメージング剤で、前者はタウ、後者はアミロイドβに特異的に結合する。タウ、アミロイドβといえば連想されるのはアルツハイマー病で、うつ病の文脈に登場することには違和感を持たれるかもしれないが、臨床疫学的にはうつ病と認知症の関連性は従来から指摘されているところであり、また、老年期のうつ病はしばしば精神病症状を伴うなど、若年のうつ病とは異なる精神病理があることもまたよく知られていた。「赤くて丸い」という点は共通していても、細かく観察すればいくつもの重要な相違点が見えてくる。それは外見観察の段階では漠然とした印象にすぎないが、テクノロジーの駆使によって、背後にある真実が姿を現わす。本研究で森口助教が示したのは、うつ病の診断を洗練するのみならず、治療方法の最適化にも繋がる貴重な知見である。
(村松太郎、2020.8.26.)
【1】ハンチントン舞踏病に対するブレクスピプラゾールの可能性
【2】Pisa症候群を合併したPosterior Cortical Atrophyの一例
三村悠 (慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)【1】Mimura Y, Funayama M, Oi H, Takata T, Takeuchi H, Mimura M: Effectiveness of Brexpiprazole in the Treatment in a Patient with Huntington's Disease. Psychiatry Clin Neurosci. 2020 Jan 13.
【2】Mimura Y, Kurose S, Takata T, Tabuchi H, Mimura M, Funayama M: Pisa syndrome induced by switching of a choline-esterase inhibitor treatment from donepezil to galantamine: a case report. BMC Neurology (2020) 20:183.
【1】足利赤十字病院の病棟で経験したハンチントン舞踏病の症例からヒントを得て症例報告をした。
【症例】40代男性。X-7年からふらつき、突然食器を落としてしまうなどの症状が出現した。X-6年からてんかんとして加療された。X-1年、自傷行為が激しくなり当院へ紹介受診され2ヶ月の入院加療を行った。その際はバルプロ酸を主剤として対応し衝動性は改善した。退院後、遺伝子検査の結果ハンチントン病と確定診断された。X年、再度自傷行為が激しくなり再入院とした。ブレクスピプラゾールを主剤として加療したところ、運動症状と精神症状共に劇的な改善をみせ、開始後8週間で自宅退院となった。
【考察】ハンチントン舞踏病は舞踏様運動、認知機能低下に加えて衝動性などの精神症状もあることで著しくQOLを減じる疾患である。精神科医として診るときには正確な診断はもちろん、舞踏運動を抑えつついかに精神症状もコントロールするかが重要である。経験した症例は舞踏運動が目立ち、さらに衝動的な自傷行為が激しく家族看護が困難な一例であった。
当時薬について調べたところモノアミン小胞トランスポーター阻害薬であるテトラベナジンかオランザピンが選択肢とのことであったが一方、エキスパートオピニオンレベルでアリピプラゾールが推奨されているとのことであった。テトラベナジンは自傷行為のある症例には使用しにくく、またオランザピンも入院後に誤嚥性肺炎もあり過鎮静のリスクから避けたいと考えた。
たまたまブレクスピプラゾールが日本で使用できるようになってすぐであったこともあり、アリピプラゾールが推奨されているのであれば、アリピプラゾールより過鎮静や錐体外路症状のリスクが低いブレクスピプラゾールが治療に適切なのでは、と考え家族に説明の上処方とした。
結果として、運動症状は改善し、自傷行為も目立たなくなり、身体抑制することなく病棟生活を送ることができ一旦は自宅退院につなげることができた。合併症もなかった。
ブレクスピプラゾールはアリピプラゾールに比べてD2 受容体に対する活性が2/3程度であること、5HT1Aや5HT2A受容体に対する活性も強いことが副作用(過鎮静、錐体外路症状、アカシジア、ジストニアなど)を避けつつ、舞踏運動と精神症状双方に効果を示した可能性があると考察した。
ハンチントン舞踏病の対症療法の選択肢として今後さらなる使用経験を積みたい。
【2】も足利赤十字病院からの症例報告である。
【症例】55歳で発症したPosterior cortical atrophy:PCAに対してガランタミンにて加療したところPisa症候群をきたした一例を経験した。症例は典型的なPCAの経過を辿り、ドネペジル塩酸塩で加療し、10mgまで増量した。発症から5年後、幻覚妄想が目立つようになり、当院へ医療保護入院となった。各種検査の結果、PCAの進行による症状増悪と診断した。ドネペジル塩酸塩への忍容性低下からガランタミンとメマンチンによる併用療法へ変更したところ2週間でPisa症候群を発症し歩行障害が出現した。ガランタミンを中止したところ2週間で改善した。ガランタミンによるPisa症候群の報告は少なく、ドネペジル塩酸塩から変更後の発症例の報告はない。これまで提唱されてきたコリン/ドパミン機能バランス説以外に線条体内のドパミンバランスの破綻やムスカリン/ニコチンのバランスも発症に影響する可能性が示唆された。
【考察】Pisa症候群は1972年に初めて抗精神病薬による副作用として報告された特徴的な体位、すなわち体幹が左右どちらかへ偏位し、体軸の回転を伴う体位を呈するジストニアである。コリンエステラーゼ阻害薬で発生することは知られていたが、5年間ドネペジルで起こらなかったジストニアがガランタミン への変更で発生したことを興味深いと考え報告した。
本症例報告には二つのポイントを考えた。
一つはガランタミン で発症したことである。これまでガランタミン での発症はそれなりに多く、むしろ発症率はガランタミンで一番多いとされているが、他のコリンエステラーゼ阻害薬からのスイッチ後に発症した例はなかった。ガランタミンはニコチン受容体に対するアロステリック活性化作用があることから、ニコチン受容体を介して線条体のドパミン放出を促進することが知られている。一見するとPisa症候群とは相容れないようだが、片側Parkinsonism mouse modelの実験から、片側にのみドパミン活性が上がり線条体内でのドパミン活性バランスが崩れることが発症に寄与したのではないかと考察した。さらにニコチン-ムスカリン間のバランスにおいてはムスカリンに対する活性が相対的に弱いことが錐体外路症状を引き起こしている可能性があると考えた。
さらにもう一つは本症例が視空間認知機能低下を主徴としたPCA症例であったことである。視空間認知機能やさらには身体的定位機能の低下が、体幹ジストニアを引き起こした可能性もあると考察した。
(三村悠、2020.7.20.)
解説 Case studyが拓く未来
「ジェナイン家の四つ子(the Genain Quadruplets)と呼ばれる有名なCase studyがある。報告者であるNIMHの頭文字から、ノーラ(N)、アイリス(I)、マイラ(M)、へスター(H)と仮名をつけられた一卵性の四人の女児は、全員が統合失調症を発症した。彼女らの発症年齢は16歳から24歳までの幅があり、その後の病像や経過も四人で少しずつ違っていることが、1950年代からほぼ10年ごとに症例報告として発表されている。Case studyとしての最後の論文は「39年間のフォローアップ」と題された66歳に達したこの4人についての報告で(Mirsky AF et al: Schizophrenia Bulletin 26; 699-708,2000)、2019年には全経過・全論文のミニレビューが発刊されている(Mirsky AF : Monte S. Buchsbaum and the Genain Quadruplets. Psychiatry Research 277; 70-71, 2019)。そこには、画像所見と臨床症状や薬物反応性の関係(「相関なし」が結論)、神経心理学的検査に示される認知機能の経時的変化(「進行性の悪化なし」が結論)など、貴重な知見が溢れている。これらの知見はどれも統合失調症における最重要といえる臨床的テーマにかかわるものであるが、多数例を対象とした研究では到達し得ない精緻な領域に及ぶ所見が示されていることが、Genain Quadruplets Studiesの真価である。統合失調症に限らず、精神疾患は人間としての全体がかかわる病態であり、かつ、スタートの時点で全体から部分を切り出して扱わざるをえない多数例研究では決して見えてこないものがまだまだ膨大に残されているはずであり、それらは単一症例の精密な観察に基づくCase studyによってのみ追究できる性質のものである。
そしてCase studyは、鋭い観察に病態についての深い知識が加われば、斬新な治療法の開発の道を拓く。三村悠院生の二つの論文、「Effectiveness of Brexpiprazole in the Treatment in a Patient with Huntington's Disease」と「Pisa syndrome induced by switching of a choline-esterase inhibitor treatment from donepezil to galantamine: a case report」は、まさにそれが実現された仕事である。精神神経症状の脳内メカニズムに基づく治療薬の決定は、精神科に薬物療法が導入されてから試行錯誤が繰り返されてきているが、なかなか理論通りの効果は得られないという現実が長く続いていたところ、近年ようやく理論と臨床が一致するケースが見られるようになった感がある。ただしそのためには、臨床観察によって症状の本質を見抜く慧眼と、臨床と基礎の両面にわたる精密な知識が必要である。この両方を兼ね備えた三村院生は、次々と貴重な一例報告を発表している。それらは合理的な治療法開発への貴重な礎石になると同時に、報告されたご本人に対して、他ではまずできなかった最良の治療を提供しているという点でも非常に大きな意義を持つものである。
(村松太郎、2020.7.31.)
ITによるアプローチがCOVID-19パンデミックの期間の総合病院精神科における精神科治療を促進させる可能性
船山道隆 (足利赤十字病院神経精神科部長)New information technology (IT)-related approaches could facilitate psychiatric treatments in general hospital psychiatry during the COVID-19 pandemic.
Michitaka Funayama, Shin Kurose, Shun Kudo, Yusuke Shimizu, Taketo Takata
Asian Journal of Psychiatry 54 (2020) 102239
【背景】COVID-19のパンデミックは、身体面のみならず精神面にも多大な影響を及ぼすことが明らかになっている。COVID-19の感染者に出現する精神症状やCOVID-19の治療者に生じる精神的なストレスといった感染による直接的な影響のみならず、社会の変化による間接的な影響も大きい。外出自粛、学校の長期休業、ロックダウンなどといった社会的隔離、マスメディアからの不安を煽る報道、不況や産業構造の変化など、さまざまな社会の変化が多くの人々の精神面に影響を及ぼしている。足利赤十字病院で分かる範囲であるのだが、COVID-19に感染したという妄想から1例は自殺既遂、もう1例は極端な低栄養に至って亡くなるなど、合計2人がCOVID-19のパンデミックによる間接的な影響によって亡くなっている。COVID-19による精神症状に関するレビューからも、不安やうつ病に伴う症状が多く出現することが明らかになっている。これらの症状に対しては総合病院精神科が精神科クリニックと並んで治療する場所であるはずなのだが、われわれの外来では緊急事態宣言後には初診の人数がそれ以前と比べて約半分に減少した。同様に、イタリアではCOVID-19のパンデミックに伴って総合病院精神科に入院する患者の数が減少していることが明らかになっている。この原因は総合病院の中で感染してしまうという患者の恐怖心や、クリニックからの紹介の敷居が高くなっていることが原因であるとイタリアでは言われている。
【足利赤十字病院神経精神科での取り組み】これらの状況を考慮して、足利赤十字病院神経精神科ではITによる新たなアプローチを開始して、患者の感染の恐怖心を最小限にすることを試みた。外来では、すでに慶應義塾大学精神神経科で以前から取り入れられている遠隔医療を早急に導入した。緊急事態宣言後には病院の通院を控えるために日本全国で電話による再診が急増したが、電話診療と異なりオンラインによる診療では情報量が圧倒的に多い。特に、精神科の面接や診断において最も重要である患者の雰囲気、表情、仕草が明確に判断できる。患者にとっては感染の危険性の心配をせずに安心して受診ができ、逆に発熱があるために病院内に入りにくい患者にもオンラインによる診療はスムーズに行える。高齢者などITに縁が深くない患者の場合には、ITに詳しい外来看護師がオンライン診察の導入に必要なアプリのインストールや使い方を説明している。
病棟に関しては、感染予防のために精神科病棟のみならず全国の病院の病棟や施設で面会禁止措置が施行された。しかし、面会禁止措置によって入院患者の精神状態が悪化する例が散見されるようになった。そこで当院神経精神科病棟では、家族が患者の荷物や日用品を持ってきた際に「タブレット面会」を始めた。実際に、この形式の面会によって大きな安心につながる場合がある。各病室でのfree Wi-Fiの導入によっては、タブレットやパソコン上での面会が自宅と病室で直接的にできるようになる可能性がある。
この遠隔医療やタブレット面会の形式を応用して、当院神経精神科病棟にCOVID-19の感染患者が実際に入院した場合にはタブレット診察を試みようと考えている。すなわち、ある程度ITを使えるレベルの精神状態の患者であれば、感染予防の観点から患者と医師あるいは患者と看護師との接触回数を減らすために、タブレットによる診察や状態確認を推進していこうと考えている。
論文には記載しなかったが、治療の必要のある患者に総合病院精神科への受診を促すため、地元の保健所および医師会、県の健康増進課や精神保健福祉センター、いのちの電話に状況を報告し、地域の市民が当院神経精神科にて安全に精神科治療が受けられることを周知して頂くように促した。さらに、保健所を通じて各家庭に配布される広報誌にも、上記の一部の内容を掲載して情報を広めた。
これらのITを含めた取り組みによって、今後も断続的に起こるであろうCOVID-19の流行時にも、多くの人々に適切な精神科医療を提供できる体制を整えていくつもりである。
(船山道隆、2020.6.28.)
COVID-19と自閉症研究:世界各地からの視点
熊﨑博一 (国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所児童・予防精神医学研究部 児童・青年期精神保健研究室)Kumazaki H, Muramatsu T, Yoshikawa Y, Ishiguro H, Mimura M: COVID-19 and Autism Research: Perspectives from Around the Globe. Autism Research. 13: 844–869. 2020.
COVID-19及び、ロックダウンは自閉スペクトラム症者にも大きな影響を与えている。そして自閉症研究にも影響を与えることが予想される。本論評は世界各地の自閉症研究者が各地域及びそれぞれの研究領域の視点から自閉症研究への影響について述べたものである。我々(熊﨑、村松、吉川、石黒、三村)は「コロナ下における自閉症者へのロボット研究の必要性」というタイトルで、まずコロナ状況下におけるロボットを用いる有用性、潜在性について述べた。一方で、ロボットの使用により、ひきこもりの悪化やロボット依存が起きる危険性についても記した。自閉スペクトラム症の支援には長期的視点が不可欠であり、ロボットを用いることで発生する問題に留意しながら、研究を進めていくことが重要と考えている。
(熊崎博一、2020.6.29.)
解説 COVID-19の精神科への影響と対応: 速報
COVID-19 (新型コロナウィルス)の感染拡大は精神医療にも当然に巨大な影響を与えた。特に急速にクローズアップされたものとして遠隔医療とロボットの活用がある。どちらも我々のグループが従来から開発に向けて力を注いできたテーマであり、しかし法的規制等のため技術が現場に届きにくい状態が続いていたが、この機会に壁が取り払われ一気に躍進した感がある。そして論文の形による世界への発信も敏速であった。
船山部長の論文は、精神医療場面でのIT導入の実体験を通しての精神科治療の促進の可能性を論じたもので、短報だが内容はかなり豊富である。というふうに要約してしまうと真価に気づかず何気なく通過してしまいそうだが、我が国でCOVID-19緊急事態宣言が出されたのが2020年4月で、この論文発刊が2020年6月、そしてその内容が実際の臨床場面での数々の試みの報告であることを見れば、コロナ禍に対して船山部長がいかに迅速かつ精力的に対応したかを実感することができる。その背景には日々積み重ねてきた研究の蓄積、そしてもちろん常に患者にとって最善の医療を提供しようという船山部長の臨床家としての熱意がある。
熊崎室長の論文は、彼自身がEditorを務めるAutism Researchからの依頼原稿で、COVID-19パンデミックの自閉スペクトラム症研究への影響についての、世界中のこの分野の第一線の研究者たちの報告の特集の一環として書かれたものである。こちらも短報であるが、論点の記載が必要十分になされた価値の高いessayである。ソーシャルディスタンスが推奨される社会は、ロボットにとってはいまだかつてなかった追い風である。だがそれに奢ることなく、このような追い風の中にあってこそ、ロボット導入によるマイナス面を意識しなければならないという、真に良心的な実践家の姿勢が淡々と、しかし雄弁に綴られている。
(村松太郎、2020.6.30.)
自閉症スペクトラム症者の非言語性コミュニケーション改善を目指したアンドロイドロボットを用いた就職面接訓練
熊﨑博一 (国立精神神経医療研究センター精神保健研究所 児童・予防精神医学研究部 児童・青年期精神保健研究室 室長)Kumazaki H, Muramatsu T, Yoshikawa Y, Corbett BA, Matsumoto Y, Higashida H, Yuhi T, Ishiguro H, Mimura M, Kikuchi M. Job interview training targeting nonverbal communication using an android robot for individuals with autism spectrum disorder. Autism. 23(6):1586-1595. doi: 10.1177/1362361319827134. 2019.
背景:高機能自閉症スペクトラム症(HFA)者にとって、就職面接は適切な非言語性コミュニケーションを取ることが難しいこともあり大きな障壁となっている。多くの支援者は、非言語性コミュニケーションのスキルを教えることが難しいと感じている現状がある。ロボットはその振る舞いに規則性を認めること、細かい動きの調整が可能なこと、ASD者が最先端の科学技術への興味が著しいこと、及びASD者の具体的・視覚的な強さを背景にHFA者にとって魅力的なインタラクションの対象となることが期待される。アンドロイドロボットは外見がヒトに酷似したロボットであるが、本研究では、アンドロイドロボットを用いた模擬面接訓練プログラム(MUA)を開発しその効果を検証した。
方法: MUAは以下の3つのステージから構成されている。1)アンドロイドロボットを遠隔操作し、アンドロイドロボットを介して面接者と会話する(面接官の役割の模擬体験)、2)アンドロイドロボットを用いて対面で模擬就職面接を行う(面接受験者の模擬体験)、3)アンドロイドロボットを用いた面接の振り返りと非言語性コミュニケーションの練習。参加者は、「教員による面接指導(IGT)とMUAの併用介入」(n=13)と「IGT単独介入」(n=16)の2群に無作為に割り付けられた。介入の前後に、両群の参加者は人間の面接官による模擬面接を受け、非言語性コミュニケーション、面接への自信、唾液性コルチゾールによる評価を行った。
結果:MUAの後、対照群の参加者と比較して、IGTとMUAの併用介入を受けた参加者は、非言語的なコミュニケーションスキル及び面接への自信の改善を示した。また唾液コルチゾールの有意な減少を示した。
結語:本研究では、アンドロイドロボットを用いた模擬面接プログラムの有用性が示された。
(熊崎博一、2020.6.1.)
自閉スペクトラム症者向けに開発した簡素なヴァーチャルオーディエンスを用いたスピーチ練習法の有用性
熊﨑博一 (国立精神神経医療研究センター精神保健研究所 児童・予防精神医学研究部 児童・青年期精神保健研究室 室長)Kumazaki H, Muramatsu T, Kobayashi K, Watanabe T, Terada K, Higashida H, Yuhi T, Mimura M, Kikuchi M. Feasibility of autism-focused public speech training using a simple virtual audience for autism spectrum disorder. Psychiatry and Clinical Neuroscience.74(2):124-131.
背景: 大勢の前で話すことは自閉スペクトラム症(ASD)者にとってもっとも不安を引き起こす状況の一つである。現在までエビデンスのある介入方法はほとんど存在せず、そもそもスピーチ練習を行う機会は限られていた。我々は、一般的なヴァーチャルオーディエンスとは異なり、シンプルな顔表情及び目を強調した点で特徴的な、簡素なヴァーチャルオーディエンスを用いた大衆の前でのスピーチ練習法(APSV)を開発した。本研究ではASD者の教育方法としてのAPSVにおける実行可能性の評価を目的とした。
方法: 15名のASD男性がランダムに2群に割り付けられた。一つのグループ(8名)はAPSVによる学習(APSV群), もう一つのグループ(7名)は自習学習群とした。2日目から6日目までAPSV群、自習学習群ともに、実際に大衆の前でのスピーチにおいてよく聞かれる質問に対し、声を出して回答するように促された。APSV群ではAPSVシステムの前で練習を行った。自習学習群では空き室で練習を行った。訓練の前後で両群の参加者はスピーチ模擬練習を約10分間、10人の聴衆の前で行い、大衆へのスピーチに関する自信についての質問紙、唾液コルチゾールによる評価を行った。
結果: 訓練の前後で、APSV群では自習学習群と比べて大衆へのスピーチについての自信が改善し、唾液コルチゾールのレベルは著しく低下した。ASD者において、APSVは自信を改善させ、スピーチにおけるストレスを低下させた。
結論: APSVはASD者にとってスピーチについての自信の改善、ストレスの軽減に有用なことが予備的に示された。今後はより大規模で多様なサンプルを用いた、縦断的なデザインを用いた研究をさらに進めていくことが重要と考えている。
(熊崎博一、2020.6.2.)
解説 2種類の将来に目を向けて
ASD者は、人は苦手で機械は得意である。これはあまりに単純化しすぎたまとめ方ではあるが、全体的な傾向としては事実である。したがってこの二つの論文で熊崎室長が扱っているロボットやヴァーチャルオーディエンスはASD者にとって最適とも言える対象であることがわかる。得意な対象だから、まず導入がスムースである。複雑・曖昧な情報処理が苦手で、変化にも弱いというASD者の特性に対し、ロボットやヴァーチャルオーディエンスは外観も動きもシンプルである。また、ロボットは声の細かい調整が可能であることから、聴覚過敏への対応もしやすい。そして研究として行うとき、実験の状況をコントロールしやすいという大きな特長も見逃せない。ASD者と生身の人間との交流では、いわゆる相性によって様々な差が発生するから、いかに実験条件をそろえても、他の人間との交流で同じ結果が出るとは限らず、データの再現性に大きな問題がある。ロボットを使用した実験ではこの問題は回避できるから、より科学的に信頼できるデータを得ることができる。
こうしたメリットを駆使した研究によって出された熊崎室長のデータから、ASD者の社会適応に向けての大きな希望が生まれている。優れた能力を持ちながら社会性の問題のために適応困難となり能力を発揮しにくいASD者において、ロボットなどのテクノロジーを活用した訓練の効果を証明するデータは、将来への明るい期待を繋いでいる。
ここでいう「将来」とは、ASD者全体にとっての意味が大きいが、同等かそれ以上に重要で、かつ慎重を要するのは、ASD者個人にとっての将来についてである。たとえば、ASD者にとって、ロボットはツールかパートナーかという問題がある。就職面接のクリアというような短期的ゴール達成を目指す訓練においては、ロボットがツールであるという位置付けは明確で、ロボットの使用は限定された期間にとどまっている。一方、より長期的で大きなゴール、たとえばコミュニケーション能力の向上を目指すときは、より長い期間にわたってロボット使用が必要になるであろう。ロボットは、ASD者にとって対人困難の原因となる要素が排除された擬似人間という特長を持っているが、それはすなわちロボットはツールでなくパートナーになってしまうという危険性を潜在しているということである。ネット依存という前例がある。ASD者がネット依存になりやすいというのは、多くの研究が共通して出している結論で、その背景には、ASD者が機械を好む、対人交流が苦手、などの理由がある。社会という苦痛な状況からネットに逃避し、そこに安住してしまった結果が、ネット依存という病理になり、ひきこもりをますます助長するのである。ロボットやヴァーチャルを治療に用いるのは人との交流というゴールのためのステップであったはずが、そこに逃避し安住し、ロボットやヴァーチャルをパートナーとすることで満足し、かえって人との交流がなくなっていく状況にもしなれば、それは依存というべきであろう。今後ソーシャルロボットややヴァーチャルリアリティがもっと進化し機能が向上すれば、依存のおそれはさらに増大する。
論文にはそうしたことまでは書かれていないが、常に臨床で多くのASD者に接している熊崎室長の研究は、目先のポジティブデータにとらわれず、本人の成長を視野に入れて行われている。ASD者において、ロボットやヴァーチャルはあくまで訓練のツールであって、人間との交流へのステップであるというのがこの種の研究の最も重要な原点である。
(村松太郎、2020.6.28.)
中枢性自律神経ネットワークを含めた脳全体で脳血流の亢進を認めた悪性緊張病の1例
黒瀬心 (足利赤十字病院 神経精神科 医員)Kurose S, Koreki A, Funayama M, Takahashi E, Kaji M, Ogyu K, Takasu S, Koizumi T, Suzuki H, Onaya M, Mimura M. Resting-state hyperperfusion in the whole brain: A case of malignant catatonia that improved with electric convulsion therapy. Schizophr Res, 2019. 210. 287-288
緊張病症状に自律神経障害をともなう場合、悪性緊張病とよばれる。かつては致死性カタトニアと記載されてきたが、悪性症候群との症状の類似点から薬剤性のもの非薬剤性のもの含めて、Philbrick and Rummans(1994)が悪性緊張病と名付けた。頻脈・発汗・発熱などの著しい交感神経系の過活動と筋強剛が病態の中核であり、脱水、急性腎不全、横紋筋融解症、尿閉・尿路感染症、誤嚥性肺炎、敗血症、深部静脈血栓症・肺塞栓症、不整脈、呼吸不全といった様々な身体合併症を呈し、しばしば治療に難渋する。
緊張病の過去の脳画像研究では、補足運動野を含む皮質基底核路や眼窩前頭皮質を含む前頭頭頂ネットワークの異常が指摘されてきたが、自律神経障害を伴わない軽症例の横断研究にとどまっていた。我々は尿閉、尿路感染症、深部静脈血栓症、巨大膀胱、巨大結腸などの様々な身体合併症をともない修正型電気けいれん療法で軽快した悪性緊張病の1例で治療前後にMRIのarterial spin labelling (ASL) により脳血流評価を行った。過去に報告されていた補足運動野だけでなく、前帯状皮質、島、扁桃体、視床下部、基底核で血流が亢進しており、電気けいれん療法により正常化した。特に、前帯状皮質、島、扁桃体、視床下部は自律神経系を調節する中枢であるthe central autonomic network (CAN)で中心的な役割を果たし、この領域の活動性が亢進すると交感神経系が過剰に賦活化されうる。今回の我々の結果から、the central autonomic network (CAN)の異常が悪性緊張病の病態に関与している可能性が示唆された。
悪性緊張病の疫学的な報告はなく、症例報告レベルにとどまり稀であるとされている。近年のレビュー (Walther et al. 2019) でも自律神経症状については他の緊張病症候群の症状とは別に考えるべきとされているが、研究の対象となってきたのが軽症例であり、実際の臨床場面では緊張病症候群を呈する急性期の精神病エピソードに自律神経症状をともなうことは稀ではない。現在我々は同様の症例を蓄積している。今後、軽症例だけでなく重症例でも研究が進み自律神経障害を含む緊張病の病態の解明が進むことが期待される。
(黒瀬心、2020.5.3.)
解説 重症者のいる風景
精神医学の臨床研究において、対象選択バイアスは深刻な問題である。本人が研究への参加に同意することが研究対象とされるための第一歩であるが、そのような同意ができるのは精神科患者全体からみれば軽症例に限られ、病態解明や治療法の開発の必要が特に高い重症例は研究対象から外されることになる。そして、軽症例から得られた知見が重症例にも適用できるという根拠は欠如しているにもかかわらず、その問題には目をつぶって、あたかもその知見が全体に通用するかのようにして、エビデンスなるものが構築されていく。かくして、論文数は増加し、エビデンスは増加し、精神医学の外見的な科学性は増加し、取り残された重症の患者が増加するという事態が日常の風景になっている。
精神科医になって2年と少しの気鋭の黒瀬医師による本研究は、そんなけだるい風景に新鮮な風を吹き入れる仕事である。生命にもかかわる悪性緊張病が精神科臨床の重要な課題であることは論をまたない。しかし精神症状と身体症状がともに重篤な対象者から科学的に信頼できるデータを得ることは困難であるし、そもそも研究の対象とすることがさらに困難である。このため悪性緊張病の従来の研究対象は軽症例に限られていたが、そのデータが重症例に適用できるかは疑問であるし、そもそも軽症の悪性緊張病というもの自体が臨床的にはイメージしにくい。きれいな研究データを作って論文化するために、軽症患者を無理に悪性緊張病と診断したのではないかという疑問も生まれよう。
そんな風景に安住していたら真に意味のあるデータは得られない。本研究は、黒瀬医師が、精神科救急の現場で一刻を争う診療に従事しつつ、同時に真実を追究するという研究への強い意欲があって初めて可能になったものである。一般的な画像研究では、事前に同意をとりMRIなどの検査枠を抑えるという手続きが必要だが、緊張病は病像が速やかに移り変わるため、このような方法を取る限り、昏迷などの状態像を脳の所見として捉えることは不可能で、通常の手続きを超えた方法を取らなければならない。すると倫理委員会の承認も容易でないと推測されるが、家族に同意を得たうえで、改善後に再度患者本人から同意をとるという形で、許可がおりたのだという。
黒瀬医師による解説の最後の一文、「今後、軽症例だけでなく重症例でも研究が進み自律神経障害を含む緊張病の病態の解明が進むことが期待される」は淡々とした記述で、一見すると論文の結びによくある常套句として通過しがちだが、直前にあるさらに淡々とした「現在我々は同様の症例を蓄積している」という一文と合わせれば、悪性緊張病の臨床研究に宿命的に伴う様々な困難を認識したとき、ずっしりとした重みを持って迫ってくる。精神医学の臨床研究の風景を書き換える黒瀬医師の今後の研究に期待したい。
(村松太郎、2020.5.27.)
統合失調症の入院患者の死には緊張病、寝たきり、窒息、水中毒、自殺が関連する
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)、是木明宏、高田武人、黒瀬心Michitaka Funayama, Akihiro Koreki, Taketo Takata, Shin Kurose
Catatonia, bedridden status, choking, water intoxication, and suicide are involved in deaths of schizophrenia inpatients
Asian Journal of Psychiatry 51, 2020, 102054
【背景】統合失調症の患者は、健常者と比較して11年から25年間短命であるという研究結果がさまざまな研究グループから発表されている。短命に影響する死因として、自殺と比較して心疾患、呼吸器疾患、悪性腫瘍などの身体疾患による死が圧倒的に多いことも明らかになっている。さらにその背景として、健康への関心が少ないこと、医療機関へのアクセスが悪いことなどが挙げられている。ところが、われわれ精神科医が普段診療している統合失調症の入院患者の死亡原因を調べた研究は極めて少ない。今回われわれはこの点を明らかにするために、自施設での後向き研究を行った。
【方法】1999年から2017年に足利赤十字病院神経精神科病棟に入院した統合失調症1823例の中で、入院中に死亡した41例を対象とした。最初に直接死因を明らかにし、その後、その死因に精神症状が明らかに影響した例を挙げた。
【結果】直接死因として割合が多かった疾患は、順番に呼吸器疾患16例(肺炎が12例、肺血栓塞栓症2例など)、悪性腫瘍9例、心疾患6例(心不全3例、頻脈性不整脈2例、心筋梗塞1例)であった。精神症状が死に明らかに影響したと考えられる例は、41例中約半数の20例にも上った。具体的には緊張病が12例、極度のアパシーによる寝たきり(65歳未満で骨折も麻痺もなく寝たきりになった例)3例、窒息と自殺がそれぞれ2例、水中毒が1例であった。緊張病からは4例の誤嚥性肺炎、2例の頻脈性不整脈、1例の肺血栓塞栓症による死につながった。寝たきりからは2例の誤嚥性肺炎、1例の肺血栓塞栓症の死につながった。
【考察】これらの精神症状は他科の医師には分かりにくく、精神科医こそが病態を把握する必要がある。これらの精神症状を改善することで、入院中の統合失調症患者の多くの死を防げる可能性がある。
【関連文献】本報告をベースとして、われわれのグループからは入院中の統合失調症に関わる身体疾患に関して、以下の論文も報告している。病棟担当の精神科医にとって有益な情報であると思われ、興味のある方は参考にしていただくと筆者としては非常に幸いである。
1. 緊張病の身体合併症:Psychosomatic Medicine 80: 370-376, 2018
2. 統合失調症に出現する窒息:General Hospital Psychiatry 59: 73-75, 2019
3. 寝たきりと関係する身体拘束による身体合併症: General Hospital Psychiatry 62:1-5, 2020
4. 水中毒の経過中で発生した橋中心髄鞘崩壊:Schizophrenia Research 125: 300-301, 201
(船山道隆、2020.4.1.)
身体拘束は精神疾患入院患者の誤嚥性肺炎と深部静脈血栓症の危険性を高める
足利赤十字病院神経精神科 船山道隆Funayama MichitakaTakata Taketo: Psychiatric inpatients subjected to physical restraint have a higher risk of deep vein thrombosis and aspiration pneumonia. General hospital psychiatry 62, 2019.
DOI: 10.1016/j.genhosppsych.2019.11.003
【はじめに】近代精神医学の創始者のひとりであるピネルが精神疾患の患者を鎖から解放して人道的治療の先陣を切ったように、われわれ精神科医は身体拘束を外すことが人道的にも治療的にも必要であることは重々承知している。ところが、わが国の精神科病棟内での身体拘束の期間はヨーロッパやアメリカと比べて10倍以上の長い時間にわたり、近年は身体拘束を行う患者の割合がさらに増加している。背景には、入院中に転倒して骨折した場合に病院側に責任を求められる可能性を、われわれ医療者側が過大に恐れている側面がある。転倒のリスクや点滴の管などを抜去する可能性が高いという理由で身体拘束を行う合理性はあるのか。むしろ、身体拘束によって肺血栓塞栓症や身体拘束の物理的な影響で死に至る例も報告される。この臨床的な問いに対するひとつの方法は、身体拘束を行った際の合併症を明確なデータとして示すことである。しかし、この点を明らかにした包括的な大規模の研究は今までなされていなかった。本研究の目的は、身体拘束中に発生した身体合併症を包括的にかつ大規模な例をもとに調べることである。
【方法】後方視的に2012年3月から2016年3月までに足利赤十字病院神経精神科病棟に入院した全1308例を対象とした。入院して一度でも身体拘束を受けた身体拘束群(n=110, 8.4%)と身体拘束を一度も受けなかった非身体拘束群(n=1198, 91.6%)の2群に分けた。身体拘束群に1%以上生じた各身体合併症について、両群の発生率をFisher直接比較法で比較した。厳密に身体拘束中に関連した身体合併症を検討するため、身体拘束群に関しては身体拘束に至る前に生じた身体合併症は除外して、身体拘束を受けた期間のみに生じた身体合併症に限定した。潜在的な交絡因子による影響をコントロールするために多変量解析を行った。
【結果】身体拘束群は深部静脈血栓症(OR=6.0)と誤嚥性肺炎(OR=4.1)の合併が多かった(P<0.01)。潜在的な交絡因子(年齢、性別、入院期間、入院時の身体合併症、寝たきりの状態、GAF、緊張病性昏迷の有無、抗精神病薬の使用の有無)をコントロール後も、身体拘束群では深部静脈血栓症と誤嚥性肺炎が多かった(それぞれP<0.01, P=0.01)。
【考察】身体拘束によって危険な身体疾患を生じる可能性が高く、最小限にする必要性が示唆された。筆者の意見としては、これらの危険性を考慮した場合、転倒のリスクなどを理由に身体拘束をする必要はないと考えている。
(船山道隆、2020.4.10.)
解説 死に至るpublication bias
二つの重大なメッセージがある。
第一は、「死に至る精神症状がある」ということである。死亡診断書に記される死因は大部分の場合に身体疾患だけかもしれない。だがその身体疾患を引き起こしたのが精神症状であれば、あるいは精神症状によって生じた身体の状態がその身体疾患を引き起こしたのであれば、死に至る因果関係の連鎖の元々の原因は精神疾患である。船山道隆部長の論文はそのことを明確に示している。この連鎖を認識して早期に対処することは精神科医でなければできないし、それは精神科医の義務であるとも言える。
第二のメッセージは、第一と同じように重大で、かつ、深刻さは第一をゆうに超えている。
それは、「死に至らしめる医療的処置がある」ということである。その代表が身体拘束だ。
身体拘束が血栓などの原因になることは以前から知られており、身体拘束を減らすことの必要性は繰り返し各方面から指摘されているが、我が国の身体拘束は諸外国より多いこともまた繰り返し各方面から指摘されている。それでも減らないことには複雑な理由があるが、ひとつには、良心的な医療者であるほど患者の安全のために身体拘束をするという逆説的な事情がある。徘徊による転倒を防ぐためである。あるいは自殺を防ぐためである。
入院患者の身体拘束が不十分だったために自殺という結果を招いたとして訴訟になり、病院が敗訴したという判例もある(東京地裁平成4年(ワ)14712号 損害賠償請求事件)。しかしこのような判決を「安全のためにはしっかり拘束せよ」というメッセージであると受け取るのは誤りである。判決文をよく読めば、病院側に確かに大きな落ち度があったとわかる。医療訴訟で病院が敗訴した事件の多くはそうした事情があり、表面的な判決結果だけを見て防衛的になるのはほとんどの場合に失当なのである。しかも、身体拘束は患者の安全のためになるどころか、逆に死亡の危険性を増していることを船山部長の本論文が示していることからみても、事故のリスクを恐れて身体拘束をするのは決して良心的な医療者のとるべき手段ではない。「これらの危険性を考慮した場合、転倒のリスクなどを理由に身体拘束をする必要はない」と船山部長が解説文を結んでいる通りである。
そしてもう一つ、論文からは読み取れない、別次元の深刻なメッセージがある。
それは、この論文(死に至る精神症状があることを示した論文)が、実に13のJournalからrejectされたという事実に由来する。臨床的に最大級と言えるほどに重要な研究論文であることは誰が見ても明らかなのだが、臨床的であるがゆえに逆にアクセプトされにくいという事態が発生しているのだ。多くのJournalにおいて、「科学的」「実証的」に見える体裁が整っていることが最優先にされ、一体なんの意味があるかわからないようなデータが膨大にpublishされている一方で、患者の生命にかかわる臨床的に価値の高い論文を世に出すことは非常に難しくなっている。これは患者を死に至らしめるpublication biasである。本論文は船山部長がそのあまりに強い逆風をはね返し、七転び八起きならぬ 十三転び十四起きでpublishした貴重なデータである。
(村松太郎、2020.4.30.)
PETリガンド[11C]SL2511.88を用いたうつ病患者における脳内MAO-B密度の生体内可視化研究
森口翔 (Research Imaging Centre, Centre for Addiction and Mental Health, Canada)(Neurochemical Imaging Program in Mood Disorders, Research Imaging Centre, Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada)
Moriguchi S, Wilson AA, Miler L, Rusjan P, Vasdev N, Kish S, Rajkowska G, Wang J, Bagby M, Mizrahi R, Varughese B, Houle S, Meyer JH. Greater Monoamine Oxidase B Distribution Volume in the Prefrontal Cortex of Major Depressive Disorder: An [11C]SL2511.88 Positron Emission Tomography Study. JAMA Psychiatry 2019; 76: 634-641.
うつ病の治療は未だ十分なものではなく約50%が治療抵抗性であり、80%は再発・再燃すると言われている(Rush and Jaint et al. 2019)。その中で、モノアミン酸化酵素(MAO)阻害薬は治療抵抗性うつ病や再発・再燃予防(Geddes et al. 2003)、また、その他の抗うつ薬への反応の乏しい非定型うつ病に有用な薬であることが知られている(Chockalingam et al. 2019)。現在MAO阻害薬は日本では使用されていないが、その主な理由としてMAO阻害薬はチラミンを含んだ食事の制限が必要であり生活に制限が加わることがある。元来MAO阻害薬の主要な効果は脳内のセロトニン・ノルエピネフリン・ドパミンといったモノアミンの代謝を阻害することで脳内のモノアミンを増加させると想定されていた。そのため、モノアミンを増やすという同様の効果があり食事制限等の必要がなく使用しやすい三環系抗うつ薬やSSRIで代用可能と考えられたこともあり、MAO阻害薬は徐々に使用されなくなっていった。しかし、近年うつ病の病態メカニズムにモノアミン仮説以外にも神経炎症仮説(Miller et al. 2009)が提唱されている。MAOの中でもMAO-Bが脳内のアストロサイトに広く分布しており、モノアミンを代謝する際に過酸化水素を産生し、オキシダーゼストレス、神経炎症を引き起こし、そのことがうつ病のメカニズムに関わっているのではないかと考えられるようになった。このようにMAO-Bはうつ病の病態生理に重要な役割があると考えられているものの脳内で直接MAO-B密度を測定することは最近まで困難であった。そのような中、近年トロント大学でMAO-Bに特異的に結合する高性能な放射性リガンド[11C]SL2511.88が開発された(Rusjan et al. 2014)。[11C]SL2511.88はMAO-Bに特異的に結合し可逆性であることや代謝物が脳内に入らないといった点などから臨床応用が十分可能である。今回、PETを用いて20名の未服薬うつ病患者と20名の健常者を11の脳領域で比較し、さらに患者内において症状との関連との相関を検証した。その結果、腹外側前頭前野においてうつ病患者群でMAO-B密度の上昇が認められた。また患者内ではうつ病の症状評価尺度や認知機能検査、心理尺度との相関は認められなかったが、罹病期間とMAO-B密度とは腹外側前頭前野、前頭前野眼窩部、視床において有意な正の相関が認められた。本結果は、うつ病患者において罹病期間が長いほどMAO-B密度が増加することを意味している。このことはMAO阻害薬に効果がある非定型うつ病では罹病期間が長いこと(Stewart, et al. 2007)や時間経過とともにメランコリー親和型うつ病が非定型うつ病へ変化する場合があること(Angust, et al. 2007)、非定型うつ病において炎症性マーカーと罹病期間が相関が認められること(Dunjic-Kostic et al. 2013)やMAO阻害薬が再発・再燃予防に効果があることとも大きく矛盾はしないと考えられる。MAO阻害薬の治療のターゲットがセロトニン・ノルエピネフリン・ドパミンのみであれば非定型うつ病や再発・再燃予防に有効であるといった他の抗うつ薬と異なる性質の効果があることの説明が困難である。そのため、MAO阻害薬はMAOの働きを阻害することで神経炎症を防ぐなどその他の抗うつ薬とは異なったターゲットに作用し抗うつ効果を得ていることが想定される。
現在、本研究の続きとして我々のチームはMAO阻害薬を用いた縦断研究が行っている。この研究において、多くの患者にMAO阻害薬が使用されているが、私も複数の抗うつ薬に反応しない罹病期間の長いうつ病患者に有効であり驚いた経験がある。これらの経験からうつ病治療の選択肢のひとつにMAO阻害薬が有効であるのではないかと考えるようになった。また、現在一部ではMAO阻害薬を再考する流れもある(Entzeroth, et al. 2017)。もちろん、うつ病はサブタイプも多く、MAO阻害薬のみではうつ病の治療は完結しないだろう。しかし、治療の選択肢のひとつとして現在使用されている抗うつ薬に加え、MAO阻害薬を使うことは患者にとって有益ではないだろうか。
(森口翔、2020.3.16.)
解説 うつ病を究める
本HP 2017年2月で紹介した、「うつ病におけるノルエピネフリントランスポーター密度の機能の検討」(Moriguchi S et al: Norepinephrine Transporter in Major Depressive Disorder: A PET Study. Am J Psychiatry. 2017 Jan 1;174:36-41) の著者の森口翔院生(当時)は、その半年後にはPET Quantification of the Norepinephrine Transporter in Human Brain with (S,S)-18F-FMeNER-D2. J Nucl Med. 2017 Jul 58: 1140-1145 (日本精神医学会の精神医学奨励賞の受賞論文。本HP2018年3月「(S,S)-18F-FMeNER-D2を用いた大脳皮質におけるノルエピネフリントランスポーターの定量評価」)を発表し、そして博士の学位を取得して大学院を卒業後、うつ病におけるさらに高度で有意義なPETイメージング研究のためトロントの Research Imaging Centre, Centre for Addiction and Mental Health, Canada に留学した。JAMA Psychiatryの本論文は、その留学先での仕事である。こうして森口博士は、「うつ病のPET研究を究める」ための道を着々と歩んでいる。いや、この途切れることない高品質の研究成果に「着々と歩んでいる」という言葉はむしろ不適切で、「猛スピードで疾走している」と言うべきであろう。そして本論文の自著解説の最後の一文、「治療の選択肢のひとつとして現在使用されている抗うつ薬に加え、MAO阻害薬を使うことは患者にとって有益ではないだろうか。」に象徴されるように、森口博士の目は常に臨床に向いている。
MAO阻害薬がかつてはうつ病の治療薬として日本でも使われていたことは、今となっては知らない精神科医も多いが、特に非定型うつ病(昨今のいい加減な概念ではなく、古典的な非定型うつ病)に対する効果は定評があり、したがってMAOはうつ病の生物学的研究の有力なターゲットの一つであった。筆者もMAOの遺伝多型に注目し、気分障害との関係を研究したことがある。(Muramatsu T et al: Monoamine oxidase genes polymorphisms and mood disorder. Am J Med Genet 1997 Sep 19; 74: 494-6.) 1990年前後には、このような遺伝子からのアプローチが世界中で盛んになされていたが、この方法では精神疾患の解明には到達できないということが徐々に明らかになり、MAOも表舞台から去った感さえあった。だが今回森口博士が記しているように、うつ病の病態生理における重要性が否定されていたわけでは決してない。MAOは、いわばバックステージで出番を待っていた主役級の物質であったと言えよう。
そんな名優に光を当てたのは、トロントで開発された高性能な放射性リガンド[11C]SL2511.88と、うつ病に対する森口博士の熱意で、本研究はそれが見事に結晶化した成果である。本HP2017.2.、大学院時代の森口博士の論文の解説のタイトルは「うつ病のPET研究を究める」であったが、学位を取得して海を渡り3年間のトロント留学から帰国した森口博士は、これまで専門としてきたPET研究に限定せず、「うつ病を究める」ため、2020年4月からは慶應でさらにグレードアップした研究と臨床を実行する。
(村松太郎、2020.3.28.)
自閉スペクトラム症のエンドフェノタイプと臨床診断に関与する皮質表面構造
山縣 文(慶應義塾大学医学部精神神経科 専任講師)Yamagata B, Itahashi T, Fujino J, Ohta H, Takashio O, Nakamura M, Kato N, Mimura M, Hashimoto RI, Aoki YY. Cortical surface architecture endophenotype and correlates of clinical diagnosis of autism spectrum disorder. Psychiatry Clin Neurosci. 2019 Jul;73(7):409-415
自閉スペクトラム症(ASD)はその発症に遺伝要因が大きく関与しており、その同胞における発症リスクは一般人口より高く、非罹患同胞においても臨床水準以下の臨床的特徴を有している。過去の脳画像研究ではASDとその非罹患同胞が共有する異常所見をASDの遺伝要因に関与する生物学的所見(エンドフェノタイプ)としている。しかしながら、エンドフェノタイプを有する群(ASDとその非罹患同胞)において、一方はASDと診断され、片方は健常であることを考慮すると、ASD診断に関与する生物学的所見についてはほとんど検討されていない。
ASDエンドフェノタイプ群(ASDとその生物学的な非罹患同胞15ペア)30名と定型発達(TD)群(健康な生物学的な兄弟15ペア)30名を対象とした。頭部MRIを撮像し、脳皮質体積、皮質厚、皮質構造の複雑さ、皮質溝の深さ(SD)を皮質構造パラメータとした。まず、これら4つのパラメータのうちASDエンドフェノタイプを反映する多変量パターンを同定した。さらに、TD同胞間の差を考慮したうえで、ASDとその非罹患同胞の差をブートストラップ法を用いて検討し、ASD診断に関与する脳領域を同定した。
スパースロジスティック回帰分析と交差検証の結果、SDが他のパラメータと比較し高い精度(73.3%)でASDエンドフェノタイプを判別した。さらにブートストラップ法にて6つの脳領域のSDがASD診断に関与していることが示された。これらの多くは”社会脳”であったが、ASDエンドフェノタイプとASD診断に関与する領域はほとんど重複がなかった。
SDがASDエンドフェノタイプを最も鋭敏に反映する皮質構造パラメータであり、SDを用いてASD診断の神経基盤も同定できることが明らかとなった。従来の2群比較の研究デザインでは検出できなかったが、ASDのエンドフェノタイプと診断に関与する脳領域がそれぞれ異なっている可能性が示唆され、今後の脳画像研究手法の一助となることが期待される。
本研究の独自性は、ASDとその非罹患同胞ペアだけでなく、TD群においても同胞ペアを対象とした研究デザインを採用したところにある。疾患と健常との間には、疾患発症に関与する効果と疾患発症の遺伝的脆弱性に関する効果(エンドフェノタイプという。ただし、この効果だけで発症しない)が存在することが想定される。つまり、従来の疾患有り無しの2分法の研究デザインでは、この両者を合わせた効果を検出しており、個々の効果についての検討が困難であった。そこで、我々は疾患群と健常群それぞれにおいて同胞ペアを対象とすることで両者を分類できるのではないかという着想に至った。実際、本研究において右側のpSTSの皮質溝の深さが浅くなることがASD発症に関与する神経基盤であることが見いだされた。各群15例という比較的少ないサンプル数ながら、過去の研究と矛盾しない結果と新たな知見が同時に得られたことは、この研究デザインの妥当性・検定力の十分さを支持するものと考える。今後の展望としては、多施設大規模研究を実施することで、本研究デザインの妥当性を検証する必要がある。さらに、統合失調症や双極性障害といった内因性精神疾患においても家族内集積の高さがASD同様に報告されており、これらの疾患においても本研究デザインを用いることで、疾患発症に関与する神経基盤を抽出することができ、他疾患の脳画像研究への応用も期待される。本研究はPCNのEditor’s Choiceにも選ばれた。
さらに、我々は本研究と同様の研究デザインを用いて、安静時機能的結合や白質構造においても解析を行い、以下の2つの論文も報告している。
機械学習を用いた自閉スペクトラム症のエンドフェノタイプの機能的結合パターンの同定
山縣 文(慶應義塾大学医学部精神神経科 専任講師)
Yamagata B, Itahashi T, Fujino J, Ohta H, Nakamura M, Kato N, Mimura M, Hashimoto RI, Aoki Y. Machine learning approach to identify a resting-state functional connectivity pattern serving as an endophenotype of autism spectrum disorder. Brain Imaging Behav. 2019 Dec;13(6):1689-1698.
自閉スペクトラム症のエンドフェノタイプと臨床診断に関与する白質構造
山縣 文(慶應義塾大学医学部精神神経科 専任講師)
Yamagata B, Itahashi T, Nakamura M, Mimura M, Hashimoto RI, Kato N, Aoki Y.
White matter endophenotypes and correlates for the clinical diagnosis of autism
spectrum disorder. Soc Cogn Affect Neurosci. 2018 Sep 4;13(7):765-773.
(山縣文、2020.2.1.)
解説 ASDは「罹患」するのか
同胞(きょうだい)は似ている。だが違うところももちろんある。ではそれは個性の違いなのか、それとも病気か病気でないかの違いなのか。これが第一の問いである。
同胞(きょうだい)は似ている。それはすなわち、その二人は他の人々とは違うことを含意している。ではそれは、その二人が共通して持つ個性なのか、それともその二人は他の人々とは違って病気またはその因子を持っているのか。これが第二の問いである。
病気と健常の線引きが明確な場合、上の二つの問いが生まれることはない。だが精神疾患では往往にしてその線引きが曖昧なことから、上の二つは時に重大な問いとしてわれわれに迫ってくる。
自閉スペクトラム症ASDに遺伝性が強いことは動かせない事実である。兄がASDのとき、弟にASDの傾向が認められることはよくある。このとき弟は「閾値下のASD」と呼ばれたりする。つまり二人ともASDに関連する何かを持っている。その何かとは、遺伝子あるいは脳の中に見出されるはずである。この観点からの同胞研究は多数あり、脳についての陽性所見がいくつも発表されている。この陽性所見は上の第二の問いに関連している。それは「ASDという病気」に対応する陽性所見ではないが、「ASDの傾向」に対応する陽性所見であり、したがってこの所見を基礎として、さらに何かの因子が加重することで「ASDという病気」が成立するのである。兄はその「何かの因子」を有しており、弟は有していない。
かくして最も重要な、冒頭の第一の問いに答える準備が整う。ASDの兄と、ASDではないがその傾向のある弟の脳の違いこそが、「ASDという病気」を決定する所見である。論理的には一点の瑕疵もない推論である。
しかしながら現実はそう単純ではない。第一の問いをよく見てみる。その前提にあたる「同胞(きょうだい)は似ている。だが違うところももちろんある。」という文章は、ASDの同胞ペアだけにあてはまるものではなく、同胞ペア一般にあてはまるものである。したがって、ASDの兄と、ASDではないがその傾向のある弟の脳の違いは、単に同胞間に常に存在する兄と弟の個性の違いにすぎないかもしれない。そのような個性の違いの部分を除外しなければ、「ASDという病気」を決定する所見であると言うことはできない。
そこで山縣文講師は、ASD同胞ペアに加えて、TD同胞ペアについても検討を行った。それによって、ASD同胞ペアのみに見られる、兄と弟の違いを抽出した。精密な思考に基づき精密にデザインし、精密な分析によって得られた貴重なデータである。
そしてその先にはもっと大きな問題が控えている。兄がASDで弟が「閾値以下のASD」というとき、その閾値はいかにして決定されたのか。閾値によって、兄は「ASDに罹患」、弟は「ASDに非罹患」と分類されるから、それは治療の必要性にかかわってくる。「罹患」していれば治療の適応ということになるから、閾値の設定は医学的に最重要であるが、そこには社会的・文化的・歴史的要因も入ってくるから、純粋に医学的な観点のみから閾値を設定することはできない。
さらには、ASDに「罹患」しているからといって、必ずしも治療の対象になるとは限らない。
ASDの存在は人類全体にとっての恩恵の一つであるとする、
Temple Grandin: The world needs all kinds of minds
https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds
という立場は決して特異なものではなく、治療する・しないについては、当事者の意見や希望を考慮することも必須である。
これはASDの周辺にあるあらゆる種類の発達障害、そして、うつ病や高次脳機能障害、さらには精神疾患と呼ばれるものすべてにかかわる精神医学の根本にかかわる大問題でもある。そのような途方もなく巨大な問題に対して山縣講師は、細部の精密な分析の集積によって挑み続け、次々に成果を発表している。
(村松太郎、2020.2.23.)
精神症状を神経心理学から捉える
前田貴記、是木明宏、黒瀬心、三村悠、船山道隆 (企画者 船山道隆)
特集「精神症状を神経心理学から捉える」 神経心理学 Vol.35 No.4 176-224 (2019)
【本企画の目的】
本企画は精神科医が日常臨床で診ている精神症状を、神経心理学や行動心理学、あるいは脳画像研究の観点から検討する企画である。統合失調症に認められる自我障害、緊張病症候群、摂食障害、常同行為やこだわり、さらにはさまざまな精神疾患のベースである内受容感覚の異常といったテーマである。これらの症状が上記の観点で取り上げられたことは少なく、チャレンジングな話題が多いので、明確な答えがない場合も少なくなく、誤っていることもあるかもしれない。しかし逆に言えば、今後発展する可能性を十分に秘めているトピックである。今回の特集から、精神症状を理解する上での議論のとっかかりになることを期待する。
【前田貴記: Sense of Agency: 自己意識の神経心理学 178-186】
最初に統合失調症に認められる自我障害をsense of agencyの観点からこの分野の第一人者である前田貴記先生に説明していただいた。連合弛緩、妄想知覚と並んで、統合失調症に特異的な症状である自我障害は理解するのは困難である。この論文では「自分が震災を起こした」「天の声に操られる」などという不思議な主観的体験の神経心理学的なとらえ方を示すだけではなく、その神経基盤とリハビリの方向性も含む広範かつ詳細な解説がなされている。
【是木明宏: 精神症状と内受容感覚 187-196】
内受容感覚は心拍や呼吸といった主に身体内部の生理的な情報の感覚であり、身体全体のホメオスタシスに関連することが言われてきた。近年、内受容感覚が感情や意思決定など脳機能に影響をおよぼしていることが明らかになってきている。さらに最近は、不安障害やパニック障害などの精神疾患の背景としての内受容感覚の異常が研究されてきている。この概要を是木明宏先生に解説していただいた。
【黒瀬心: 緊張病症候群 197-206】
黒瀬心先生にお願いした緊張病症候群は、さまざまな精神疾患、ときには身体疾患にも出現する、臨床上極めて重要な病態である。精神症状でありながら、カタレプシー、昏迷などの特徴的な症状からさまざまな身体合併症も発展する病態である。この病態は、ようやくここ20~30年前から脳画像研究が進んできている。黒瀬先生自身の貴重な臨床研究結果とともに解説していただいた。
【三村悠: 摂食障害と神経心理学的所見 207-214】
摂食障害を神経心理学から捉える試みは少なく、心理学から捉える立場が一般的である。しかし実際の臨床では、極度の低栄養の状態の中で認知機能が低下しているとしか思えないケースに頻繁に出くわす。実際に栄養状態が改善すると摂食障害者の認知機能が改善することが少なくない。さらに、摂食障害に特有の認知パターンがあり、これが摂食障害の治療を妨げている可能性が高い。かなり冒険的な試みであるが、三村悠先生に自験例を含めて解説していただいた。従来の心理学からの知見からはかなり異質ではあるが、必ずしも矛盾することはなく、むしろ相補的に摂食障害の病態の把握へのつながるのではないかと考えられる。
【船山道隆: 常同行為/行動とこだわり 215-224】
最後に船山が、後天性脳損傷や変性疾患に出現する繰り返しの行為/行動とこだわりについて概説した。強迫性障害の強迫症状とこれらの繰り返しの行為/行動を区別せずに用語を用いていることもあるが、今回はこの違いを強調することを試みた。その理由は、その背景を区別することによって神経基盤やアプローチが変わる可能性があるためである。こだわりについては、周囲への影響が強く、外傷性脳損傷などの後天性脳損傷にて周囲が最も困る症状であるにもかかわらず、今ひとつ研究がなされていないために取り上げた。筆者自身はこだわりが一次的にあるのではなく、背景にある認知機能の低下に注目すべきであると考えている。
(船山道隆、2020.1.7.)
インターネット中毒と臨床デモグラフィックおよび行動要素の関連
ムハンマド・エルサルヒ (慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 共同研究員)
ElSalhy, Muhammad, Takahiro Miyazaki, Yoshihiro Noda, Shinichiro Nakajima, Hideki Nakayama, Satoko Mihara, Takashi Kitayuguchi, Susumu Higuchi, Taro Muramatsu, and Masaru Mimura. Relationships between internet addiction and clinicodemographic and behavioral factors. Neuropsychiatric disease and treatment 15 (2019): 739.
インターネットは私たちの現代生活に不可欠な構成要素になったが、その負の影響、つまりインターネット中毒(IA)についても、国民と学術の注目が集まっている。臨床デモグラフィックおよび行動因子は、IAのメカニズムに仮説的に関係しているが、そのような因子がIAの重症度にどのように関連しているかはまだほとんど不明のままである。したがって、この研究は、IAの重症度と、さまざまな教育段階においての日本人学生のIAに潜在的に関連する要因との間の関係を調査しようとした。本研究の方法としてはアンケートベースの調査である。4119人からの協力をいただき、最終的に研究に含まれたのが3224人の回答でした。調査のアンケートには、オンライン活動のタイプと臨床デモグラフィック情報に関する質問、IA重症度のIAテスト、および心理的苦痛のK6スケールが含まれている。対象にしたのは小学生から大学生までの幅広い年齢層に調査した。データを集めてから重回帰分析を実施し、臨床デモグラフィックおよび行動因子によるIA重症度を予測した。
この研究で主に得た結果は、IAの重症度は、オンラインメッセージ、フェースブックなどのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、オンラインゲーム、休日のインターネット使用、心理的苦痛を表すK6スコアに有意に正の関連があるとみられた。しかし、教育目的でのインターネットの使用や、初めてのインターネットを使った年齢、および睡眠時間、この3つの要素が上がれば上がるほど、IAの重症度が下がるとみられた。 本研究での年齢の直接影響がみられなかった。しかし、年齢によって、インターネットの使用活動が異なり、この活動によってIAの重症度が変わる。
結論:IAはさまざまなオンライン活動と心理的苦痛の程度にリンクされている。これは、IAをさらに理解するために、オンライン行動と心理的要因の包括的な評価の重要性を示している。
(ムハンマド・エルサルヒ、2019.12.1.)
解説 第一歩、そして限りない躍進
気がついたら深刻な問題になっていた、という事態は避けたいものだが、避けがたいものでもある。そして避けがたかったとしても、気づいたら一刻も早く対策を立てることが必要である。そのための第一歩は、現状を把握することである。
インターネット中毒 (IA: Internet Addiction。このaddictionを中毒と訳すか、依存と訳すか、嗜癖と訳すかは悩ましい問題だが、ここはムハンマド・エルサルヒ博士の訳語「中毒」を採用することにする。ちなみに上の解説文は、彼自身がすべて日本語で書いたものである)もその一つで、エジプトからの留学生・ムハンマド院生による、我が国の生徒・学生のIAをめぐる状況を詳しく調査した本研究データは、これからますます拡大すると思われるIAについての実効ある対策を立てる基礎データとなる貴重なものである。この論文で学位を取得し医学博士となったムハンマド院生は、現在はオマーンに在住し、日本の医師国家試験合格を目指して勉強に励んでいる。つまり将来はまた日本に戻る予定のようであるが、その後の活動内容や活動空間についての彼の計画は我々の想像を超えた限りない躍進を秘めている。
「国際化」という言葉はよく耳にするが、日本人のいう「国際化」の多くは「欧米化」であって、真の国際化からは程遠いのが実情であるが、アラビア語・日本語・ドイツ語・英語を駆使し、軽快なフットワークで地球上を移動するムハンマド博士こそは真の国際人という呼び名にふさわしい。彼の関心はIAにとどまらず、行動嗜癖、そして人間の行動全体に広がっている。日本人にはない視点からの活躍が大いに期待される。
(村松太郎、2019.12.21.)
頭部外傷の遅発性脳障害を引き起こす異常タンパク質を生体内で可視化することに成功
高畑圭輔 (国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 脳機能イメージング研究部 脳疾患トランスレーショナル研究チーム)
Takahata K, Kimura Y, Sahara N, Koga S, Shimada H, Ichise M, Saito F, Moriguchi S, Kitamura S, Kubota M, Umeda S, Niwa F, Mizushima J, Morimoto Y, Funayama M, Tabuchi H, Bieniek KF, Kawamura K, Ming-Rong Zhang, Dickson DW, Mimura M, Kato M, Suhara T and Higuchi M. PET-detectable tau pathology correlates with long-term neuropsychiatric outcomes in patients with traumatic brain injury. Brain 2019; 142: 3265–3279.
研究の背景:コンタクトスポーツで引き起こされる頭部への反復性の脳震盪や、交通事故などによって引き起こされる重度頭部外傷は、数年〜数十年後に進行性の神経変性疾患を引き起こすことがあり、遅発性脳障害と呼ばれている。死後脳を用いた神経病理学的検査により、頭部外傷による遅発性脳障害の多くは脳内にタウが過剰に蓄積するタウオパチーの一種であることが判明している。その代表的な病態が、現在米国を中心に大きな問題となっている慢性外傷性脳症(chronic traumatic encephalopathy: CTE)である。CTEなどの遅発性脳障害の問題は、タウの蓄積を生体内で検出する技術が存在しないために存命中に診断することが不可能であるという点にあった。そのため、遅発性脳障害に対する早期介入が困難となり、タウを標的とする治療法の開発に向けた取り組みにおいても大きな障壁となっていた。こうした問題は、コンタクトスポーツや頭部外傷のリスクを伴う職業に従事する人々に大きな懸念をもたらしている。このような経緯から、著者は頭部外傷によって引き起こされる遅発性脳障害の原因となる脳内タウの蓄積を生体内で捉える診断技術の開発が必要と考えていた。
研究を開始した経緯: 著者が所属する量研機構は、2013年に第一世代タウトレーサーの一つである11C-PBB3を世界に先駆けて開発した。当初は、アルツハイマー病や進行性核上性麻痺などの神経変性疾患を中心とする研究に関わる予定であったが、同じ時期に米国からコンタクトスポーツと脳内タウ蓄積の関連を示唆する不穏な報告が相次いでなされたことが転機となった。アメリカンフットボールやアイスホッケーなどのコンタクトスポーツで活躍した選手が引退後に自殺や殺人を犯すなどの悲惨な出来事が続いていること、亡くなった選手の脳を病理解剖によって調べたところ、いずれも脳内に多量のタウタンパク質が蓄積していたことなどが、センセーショナルに報道されたのである。頭部外傷や神経変性疾患によって引き起こされる器質性精神障害に強い関心をもっていた著者は、米国から発せられた頭部外傷の遅発性脳障害に関する一連の報告に注目していた。そうした時期に量研機構で11C-PBB3が開発されたことから、生体内でタウを可視化するポジトロン断層撮影(PET)技術が慢性外傷性脳症の早期診断や将来の治療薬開発にとって有用な技術になると考え、頭部外傷による遅発性脳障害を標的としたタウPET研究を開始した。
研究の成果:本研究では、量研機構と慶應義塾大学病院との共同研究として行われた。量研機構では、生体脳でタウを可視化する技術を用いて頭部外傷により遅発性脳障害を発症した可能性のある被験者の脳内タウ蓄積量を非侵襲的に測定し、慶應義塾大学病院では患者リクルートおよび神経心理検査を行った。その結果、様々なタイプの頭部外傷でタウの蓄積を生体内で捉えることに初めて成功した。さらに、脳の灰白質との境界部に近接する白質の表層部のタウ蓄積が遅発性脳障害の症状に関連していること、白質全体のタウ蓄積量が多ければ多いほど精神病症状が重症化するという関係性があることを明らかにした。これらの成果は、遅発性脳障害が精神症状を引き起こす機序の一端を明らかにしただけでなく、PET技術により捉えた生体脳におけるタウ蓄積が遅発性脳障害の早期診断のための評価指標になり得ることを示すものであり、将来的に、遅発性脳障害におけるタウ蓄積を標的とする治療法の開発に寄与することが期待される。本研究で得られた成果を踏まえ、現在はタウ検出能が向上した第二世代タウトレーサーを用いた研究を進めている。
最後になるが、本研究を開始するにあたって大きな助言を頂いた故加藤元一郎先生に対して心から感謝の意を捧げたい。
(高畑圭輔、2019.11.2.)
プレスリリース (2019年9月2日)
https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2019/9/2/28-60411/
解説 3億人のアスリートのために。そして。
頭を打つと、脳に永続的かつ進行性の損傷を発生させ得る。これが本論文で高畑圭輔博士が示した鮮烈なメッセージである。このメッセージは、コンタクトスポーツ(すべての格闘技とラグビー、アメリカンフットボール、サッカーなどの球技を含む)のあり方を変えるにとどまらず、脳の外傷学の教科書を書き換え、さらには精神疾患の成因についての常識までも刷新する、革命的な知見である。
背景がある。高畑博士は解説にこう記している。
死後脳を用いた神経病理学的検査により、頭部外傷による遅発性脳障害の多くは脳内にタウが過剰に蓄積するタウオパチーの一種であることが判明している。その代表的な病態が、現在米国を中心に大きな問題となっている慢性外傷性脳症(CTE)である。
ボクシングなどで頭部に激しい打撃を受けると脳に後遺症が発生することは、パンチドランカーやボクサー脳症の名で昔からよく知られていた。ではその「激しい打撃」とはどの程度なのか。ノックアウト(=脳震盪)に至らなければ問題ないのか。ヘルメットで防護されていれば問題ないのか。サッカーのヘディング程度なら問題ないのか。それらはすべて不明であった。不明であったが、この長年くすぶっていた問題が、米国のアメリカンフットボールリーグ(NFL)で20世紀末に急速にクローズアップされたのである。
始まりはマイク・ウェブスターの死だった。
“Iron Mike”と呼ばれた彼は、 NFL、ピッツバーグ・スティーラーズの名センターであった。米国では知らぬ者がいないほどのスターであったマイクの人生は、しかし、引退後に暗転する。精神が不安定になり、生活が大きく乱れる。浪費。怠惰。薬物乱用。認知機能低下。抑うつや幻聴も現れる。現役時代に獲得した豪邸も家族も失いホームレスとなり、寝泊まりしていた廃車内で心筋梗塞を起こしその一生をとじた。50歳であった。
ここまでであれば、よくあるスターの没落物語で終わったかもしれない。だが彼の検死を担当したオマル医師(Dr. Bennet I. Omalu)が、マイクの名誉を回復した。マイクの死後脳の切片を免疫染色し、脳の広汎な部位にタウタンパクを見出したのである。ボクサー脳症、すなわち、頭部に激しい打撃を繰り返し受けた場合に生ずる脳症にもタウタンパクが認められることが従来から知られていたが、それがフットボールという、相対的に弱い脳への打撃でも生ずることをオマル医師は発見したのである。(Omalu BI, Kekosky ST, Minster RL et al: Chronic traumatic encephalopathy in a National Football League Player. Neurosurgery 57; 128-134, 2005.)
この論文を発表したオマル医師は、無邪気にも自分はNFLから感謝されると信じていた。フットボール選手を脳症から守る方法の開発に貢献する第一歩になると考えたからである。
それは科学的事実に基づいた真摯な考えであったが、社会的状況に基づけばあまりに甘い考えであった。オマル医師の発見が正しいと認められれば、フットボール選手の脳にはプレイによる深刻な後遺症があることになり、NFLへの責任追及が必至だからである。圧倒的な財力を持つNFLに雇われた(に違いない)権威ある医師達からのオマル論文への攻撃はどぎついまでに強烈なもので、その経緯はFainaru-Wada M and Fainaru S: League of Denial. The NFL, Concussions, and the Battle for Truth. Three Reivers Press, NY, 2013.に詳述されている。もっと手軽な資料としては、2015年に封切られた映画Concussion(邦題: コンカッション)で、NFLからの有形無形の圧力に苦悩するオマル医師をウィル・スミスが見事に演じている。(Concussion. Columbia Pictures Industries, 2015.)
医学と社会と金が錯綜したこの争いは、最終的にはオマル医師の発見が正しいことが証明されることで決着し、引退したプレーヤー約4500人からの集団訴訟に対しNFLは総額8億ドルの和解金を支払うことになる。オマル医師とNFLの選手達は勝利したのである。
だが、3億人が残された。世界のコンタクトスポーツの競技人口3億人にとって、オマル医師の発見は重い警告にはなっても、恩恵にはなっていない。オマル医師の発見は画期的であったものの、それは死後脳の切片を顕微鏡で見て初めて診断できるものであって、すなわち死ななければ診断できない。それでは実臨床の役には立たない。今まさに診断と治療(そして時には補償)を必要とする当事者の恩恵にはならない。彼らのためには、脳画像検査でタウタンパクの蓄積が目に見えなければならない。
それを可能にしたのが本研究である。高畑博士の本解説のタイトル「頭部外傷の遅発性脳障害を引き起こす異常タンパク質を生体内で可視化することに成功」は、その巨大な意義を静かに、しかし高らかに告知している。
時代が始まる。
慢性外傷性脳症(CTE)の早期発見が可能になる。頭部打撃の危険性が正確に示されれば、予防が可能になる。さらには、タウタンパクの増殖を抑制する治療法の開発にもつながる。CTEの症状は多彩である。伝統的な精神医学で内因性と呼ばれてきた精神病症状も出現する。他方、外傷に起因しない精神病症状も、高齢者においてはしばしばタウタンパクの蓄積が関与していることが明らかにされつつある。脳画像としてのタウタンパクの可視化がさらに洗練されれば、CTEを超え、あらゆる精神疾患の診断と治療の発展にその貢献範囲が拡大されることは疑いない。慶應の大学院生も含む量研機構(放医研)・高畑チームの臨床の慧眼と最先端のトレーサー技術、そして科学的真実を追究するエネルギーが、それを現実のものにしている。精神医学の黎明期から予言されていた、内因と外因を結ぶ謎の実相が、今、姿を現わしつつある。
(村松太郎、2019.11.27.)
大うつ病性障害における悲観的未来性思考に関与する前頭極の活動
片山 奈理子 (慶應義塾大学医学部精神・神経教室 大学院博士課程)
Frontopolar cortex activation associated with pessimistic future-thinking in adults with major depressive disorder.
Katayama N, Nakagawa A, Umeda S, Terasawa Y, Kurata C, Tabuchi H, Kikuchi T, Mimura M.
NeuroImage: Clinical 2019 ; 23 : 101877
大うつ病性障害(Major Depressive Disorder :MDD)は世界で約3億人が罹患している有病率の高い精神疾患である(World Health Organization, 2018)。MDD患者は未来に対して悲観的でありそれは絶望感とも関連する(MacLeod et al, 1998)。Aron T. Beckの認知理論では、MDDは具体的に考えられず、将来を想像する能力の減少を指摘している(Beck A.T, 1963)。ICD-10やDSM-5でも将来に対する悲観はMDDの主要な症状の1つとしている。健常者における脳画像研究では、未来を考える時(未来性思考)には主に前頭極(Brodmann area [BA] 10)の関与が報告されている(Benoit et.al, 2011)。これまでのMDDの画像研究では自己参照プロセスに関連する行動異常や反芻(ルミネーション)、自責感などの症状にBA10の機能の関連性が指摘されている(Johnson et.al, 2009; Jones et.al, 2017)。しかし、MDDにおける未来性思考中の脳神経活動は未解明であり、我々はMDDにおける未来性思考の神経基盤の解明を目的とする研究を行った。
対象者はMDD患者23人と健常者23人。未来性思考の評価尺度であるFuture Thinking Implicit Relations Assessment Procedure(Kosnes et.al, 2013)を改変した未来性思考課題を用いて脳機能画像(functional MRI)を試行した。未来性思考課題は、遠い未来/近い未来を想像する条件と遠い過去/近い過去を想起する条件の4条件あり、未来を想像するもしくは過去を想起する間の脳神経活動をMDDと健常者と比較し、さらにBA10の活動と悲観の強さおよびうつ病の重症度との相関を検討した。また、安静時functional MRIを用いてBA10を基点とした安静時脳機能的結合性も検討した。
健常者と比較して、MDD患者は、将来について悲観的であり、特に遠い未来おいてポジティブに反応することに困難さを認めた。そしてMDD患者は遠い未来を想像する時、内側の前頭極(BA10)の活動が増加し(family-wise error correction p <0.05)、そのBA10の活動は遠い未来対するネガティブ度およびうつ病の重症度と正の相関を認めた。さらに、安静時fMRIではMDDは健常者と比較して右BA10領域と後帯状皮質(PCC)と機能的結合性の増強していた。
遠い未来に対して悲観的であるMDD患者は、遠い未来を考えている時に前頭極(BA10)の活動がより高く、安静時においてもPCCとの結合性が高まっていた。これらからMDD患者の悲観や絶望に、BA10の機能不全が重要な役割を果たしていることが示唆された。本研究はうつ病における遠未来性思考時の内側BA10における脳活動と未来に対するネガティブな認知の偏りの関係を評価した最初の研究であり、遠未来思考時の内側BA10の機能障害はうつ病における未来に対する否定的な認知を反映し、認知行動療法(CBT)などの認知機能を改善させる治療効果を評価するニューロマーカーとなる可能性が示唆される。
(片山奈理子 2019.10.1.)
解説 将来、夢が・・・
「将来、夢が」という文字が提示される。数秒後に「叶う」(または「叶わない」)という文字が提示され、自分に当てはまるかどうかを「はい」「いいえ」のボタンを押して答える。これが片山奈理子大学院生が用いた未来性思考課題の一例である。他の例として、「将来、努力が評価」「される」/「されない」、「近いうちに、目標を達成」「できる」/「できない」、「昔、自分に自信が」「あった」/「なかった」、「この前、物事に集中」「できた」/「できなかった」などがある。これらのうち、「将来」で始まる文が遠い未来、「近いうちに」が近い未来、「昔」が遠い過去、「この前」が近い過去である。本研究、うつ病(MDD)患者の反応は、古典的精神病理学が教える通り、未来について悲観的であり、そしてfunctional MRIの主要な結果は、うつ病患者では遠い未来について想像するときにBA10の活動が強いというものであった。BA10はうつ病の中核症状である自責感との関係が示されている部位でもある。
うつ病の診断は、現代の操作的診断基準に基づいた場合でも、古典的な従来診断に基づいた場合でも、結局は症状項目の確認によってなされる。ただ前者ではそこであえて思考を停止するのに対し、後者ではその先まで見通そうとする点が大きく異なる。見通そうとする懸命な努力を重ねても、症状の観察から到達できることには、よく言って限りがある、悪く言えば何もないという現実が見えてきたことで、操作的診断基準が誕生したわけだが、それはかえって精神疾患研究を歪めてしまったという反省や批判も根強いものがある。
そんな状況の打開策として大いに期待されているのは、脳という視点の導入である。悲観的思考と自責感が、BA10という共通する脳部位に収斂することを示した片山院生の本研究は、精神病理学と脳科学を融合することで、うつ病の解明に向けて大きな一歩を踏み出したものである。本論文で学位を取得した片山院生はそこで立ち止まることなく、うつ病患者に認知行動療法を行うと未来性思考中のBA10の活動がどう変化するかという研究を精力的に進めている。それは精神病理学と脳科学の融合をさらに有効な治療に発展させようという試みで、近い将来に実を結び、遠い将来に渡って高く評価されるであろう。
という未来についての予測=未来性思考は、明るく健全なものである。それに対してうつ病患者は将来について悲観的なのであるが、その「悲観的」とは、あくまでも健常者と比較しての相対的な意味で悲観的ということであって、将来、夢が・・・「叶う」と感じることが現実的か否かはまた別の話である。実はうつ病患者の思考の方が健常者より現実的であるとする depressive realism という言葉もある。(“Yesterday, all my troubles seemed so far away” と回想し、”Now it looks as though they’re here to stay”と認識できるのが冷静なrealismというものであろう)
だが研究のゴールとは、個人の夢ではない。一つ一つの論文は、確かに一つの貴重な成果物ではあるが、たとえばうつ病の本質の解明や画期的な治療法の開発といったゴールは、数多くの質の高い論文が集積されて初めて到達できるものである。叶うかどうかは、個人としてではなく、人類としてどうかという視点から考えなければならない。夢とは、叶うか叶わないかを問うものではなく、追い続けるものなのであろう。
(村松太郎、2019.10.28.)
脳血管障害による失語症に対する十分な言語リハビリテーションを行った後の予後予測因子
船山道隆 (足利赤十字病院神経精神科部長)
Yoshitaka Nakagawa, Yoko Sano, Michitaka Funayama, Masahiro Kato.
Prognostic factors for long-term improvement from stroke-related aphasia with adequate linguistic rehabilitation. Neurol Sci. 2019 Jun 10. doi: 10.1007/s10072-019-03956-7. [Epub ahead of print]
【過去の失語症の予後研究】
失語症は脳血管障害後の後遺症の中でも最も頻繁に出現する症状のうちのひとつであり、患者の人生に大きな影響を与える。脳血管障害による失語症の予後予測因子についてはすでにいくつかの研究がなされていて、ベースラインの失語症の重症度、音韻機能、病巣の大きさ、ウェルニッケ野の損傷などが予測因子として挙げられている。しかし、これらの研究はいずれも発症後1年以内の予後研究である。実際の臨床ではその後も長期にわたって失語症が改善することが知られている。さらに、今までの失語症に関する予後研究の対象例は、失語症のリハビリテーションを受けた例と受けていない例が混在していた。これら問題を克服するため、今回われわれは左半球のみに損傷があり言語リハビリテーションを2年間以上行った脳血管障害後の失語症121例から、失語症の予後予測因子を求めた。
【長期のリハビリテーションを受けた失語症の予後予測因子】
失語症の予後予測因子を求めるため、ステップワイズ法を用いた重回帰分析を行った。説明変数には発症年齢、性別、教育歴、脳卒中のタイプ(脳梗塞/脳出血)、左半球内の6病巣(ブローカ領域+中心前回、縁上回+中心後回、角回、ウェルニッケ野を含む上側頭回、中側頭回、基底核)、病巣の大きさ、ベースラインの失語症の重症度(標準失語症検査 10点満点評価)、ベースラインの各言語機能(意味機能として漢字の理解と文章の理解、音韻機能として語および文の復唱と仮名一文字の音読、さらに呼称能力)を用いた。目的変数として、発症2年後の失語症の重症度(標準失語症検査 10点満点評価)を用いた。
結果は、失語症の予後は発症年齢(若年発症であれば予後が良好)、ウェルニッケ野を含む左側頭回の病巣、ベースラインの失語症の重症度およびベースラインの漢字の理解で表される意味機能と仮名一文字で表される音韻機能によって予測できることが分かった。これらの結果は、過去の発症後短期間の予後予測研究と矛盾することはなく、長期のリハビリテーションを受けた失語症の予後は、年齢、病巣、ベースラインの言語機能によって予測できる可能性を示唆している。また、今回の研究から若年発症例は言語機能が大きく回復することが判明したため、言語リハビリテーションをする上ではこの点を考慮に入れる必要がある。
(船山道隆、2019.9.1.)
解説 失語症当事者の真の利益を追求する
努力を重ねても結果が出るとは限らない。良い結果が出ても努力と因果関係があるとは限らない。努力と因果関係があったとしても、その結果が一般化できるとは限らない。治療行為には常にこうした問題がつきまとう。
脳損傷に対するリハビリテーションでは特に顕著である。自然経過によってある程度は回復するという性質上、結果のうちどこまでがリハビリテーションの効果であるかの判定は容易でない。良い結果は努力の成果だと考えるのは願望にすぎないのであって、願望を信ずることは心の安寧には繋がっても、現実から乖離した信仰から得られる安寧と変わるものではない。
リハビリテーションにはもちろん理論的裏付けがある。だが医学の歴史を振り返ってみれば、効果が先で理論が後追いの治療法と、理論が先で効果が後追いの治療法の2種類がある。前者の代表は電気けいれん療法で、効果ははるか昔に証明され、しかもその効果は他に抜きん出て強力であるが、メカニズムの解明がいまだ道の途上であることは、医学的治療における効果の理論的解明の困難さを象徴している。その困難さは同時に、逆に理論から治療法を開発しようとすることの困難さもまた物語っている。
だがそんな理屈を言い合うのはほどほどにして、行動しなければならない。前に踏み出さなければならない。実社会には30万人〜50万人の失語症の人々が回復を切望する毎日を送っているのだ。医療者に求められるのは学問的理論ではなく、真に実効ある医療行為を洗練していくための研究である。しかるに失語症についての臨床研究がまだまだ不十分であったことは、予後研究といっても1年以内の調査にとどまり、何よりリハビリテーションを受けた例と受けていない例が混在しているデータしかないことからみても、あまりに明らかである。
船山部長の本研究は、そんな状況を大きく変えようとする試みである。「言語リハビリテーションを2年間以上行った脳血管障害後の失語症の予後研究」というデザインは一見すると特に主張のない地味なもののように見えるが、失語症をめぐる状況を広く深く見れば、医学的にも社会的にも画期的なものであることに気づく。もちろんこの研究だけで、リハビリテーションの効果を証明しているとは言えないが、リハビリテーションを行なった例の予後予測因子を明らかにしたデータは、当事者の真の利益を追求するうえでの貴重な基礎資料になるものである。
(村松太郎、2019.9.28.)
【1】電気けいれん療法の海馬歯状回に対する急性期・長期の影響と臨床効果の関連
【2】電気けいれん療法の電流源密度と位相同期に与える影響と臨床効果の関連
高宮 彰紘(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)
【1】Acute and long-term effects of electroconvulsive therapy on human dentate gyrus
Akihiro Takamiya, Eric Plitman, Jun Ku Chung, Mallar Chakravarty, Ariel Graff-Guerrero, Masaru Mimura and Taishiro Kishimoto
Neuropsychopharmacology, 2019 https://doi.org/10.1038/s41386-019-0312-0
【2】Electroconvulsive Therapy Modulates Resting-State EEG Oscillatory Pattern and Phase Synchronization in Nodes of the Default Mode Network in Patients With Depressive Disorder.
Akihiro Takamiya, Jinichi Hirano, Bun Yamagata, Shigeki Takei, Taishiro Kishimoto and Masaru Mimura
Front. Hum. Neurosci. doi: 10.3389/fnhum.2019.00001
電気けいれん療法 (electroconvulsive therapy: ECT) は重症なうつ病に対して最も有効な治療であるが、一過性の認知機能障害のリスクを有する。ECTの作用機序には不明な点も多い。ECTの抗うつ効果、認知機能障害に関する神経基盤の解明は、高い治療効果を維持し副作用を減弱した新しい脳刺激法あるいは革新的な抗うつ治療につながる可能性があり重要な課題である。これまでの研究は、ECT前後の脳画像あるいは神経生理指標変化に関する報告が多かった。しかし単なるECT前後の変化には、臨床的な変化と関係のある変化(抗うつ効果に関する変化や認知機能障害に関する変化)、臨床的な変化と関係のない変化(電気刺激そのものや発作による影響)が混在していると考えられる。我々は臨床効果と関連する脳構造、脳機能変化の解明のため、以下の2つの研究を行った。
【1】動物実験では、ECTは海馬歯状回におけるニューロンやグリアの可塑的な変化を誘導することが1970年代より報告されていた。我々はメタ解析の手法でECTがMRIで測定される海馬体積を増大させることを報告した (Takamiya et al., 2018)。しかし、ECTの海馬体積への影響に関して、臨床症状改善の変化との関連、長期的な変化については未解決だった。そのため、ECTと海馬の関連に関して詳細な検討を行うため、MRIを用いた縦断研究によりECTの海馬歯状回の体積に対する急性期と3ヶ月後の影響を調べた。
メランコリー型の特徴を伴う抑うつエピソードに対して臨床的にECTを受けた25名の患者をリクルートし、ECT前後と3ヶ月後に臨床症状の評価とMRIの評価を行なった。その結果、ECTによる海馬体積の増大は歯状回の体積増大の寄与が最も大きく、その増大率は年齢と負の相関を認めた。また、急性期に寛解状態に至った参加者の歯状回の体積変化は寛解に至らなかった参加者の変化よりも大きかった。しかし、寛解状態を維持していた参加者の歯状回体積も、3ヶ月後には治療前のもとの体積レベルまで戻っていた。
本研究では、ECTの海馬への影響は主に歯状回による影響であり、動物実験の結果と矛盾しない結果だった。さらにECTの急性期の抗うつ効果の背景に海馬歯状回の可塑的な変化があることが示唆された。しかし、長期の寛解維持もしくは再発の神経基盤は海馬以外の脳部位も含めた今後の研究が必要である。また、ECTでも改善しない最重症のうつ病患者は脳の可塑性が著しく低下、あるいは神経変性過程が始まっている可能性が示唆され、認知症との関連を含めた、PETなど多様なモダリティでの評価が必要と考えられた。
【2】ECTが急性期に脳波の徐波化を引き起こすことは1930年代より知られていたが電気生理学的な変化の臨床的意義は不明だった。本研究では、13名のECTを受けたうつ病患者をリクルートし*、ECTの電流源密度 (CSD) と位相同期への影響、臨床症状の変化の関連を調べた。
ECTは前部帯状回、前頭極/内側前頭前皮質、右下前頭葉といったデフォルトモードネットワーク (DMN) の主要な結節点のCSDを変化させたが、これらの変化と抑うつ症状や全般的認知機能の変化に関連を認めなかった。位相同期に関しては、ECTはtheta帯域の右後部帯状回と前頭前皮質の位相同期を上昇させ、beta帯域の左後部帯状回と左側頭部・左島皮質、右上頭頂葉と右島皮質の位相同期を低下させた。左半球のbeta帯域における位相同期の変化は全般的認知機能の変化と関連を認めた。
ECTはDMNの主要な結節点の活動性を低下させた。この変化はPET研究のメタ解析におけるECTのDMN結節点の血流・代謝低下という結果とも一致した。DMNの変化とうつ症状の変化との関連(本研究ではMADRS総得点との関連)は認めなかった。DMNの変化は臨床的意義がない可能性もあるが、そう結論づける前にDMNに関する反芻など特定の症状、あるいは自伝的記憶などの認知機能との関連を調べる必要があると考えられた。左半球の位相同期の低下は全般的認知機能の低下と関連を認めたが、この結果は右片側刺激の認知機能低下の少なさを支持するかもしれない。
なお、ECTとDMNの関連のこれまでの知見については日本語の拙著(高宮彰紘他. 電気けいれん療法とdefault mode network. CLINICAL NEUROSCIENCE 2019; 37(2): 220– 222 http://www.chugaiigaku.jp/item/detail.php?id=2800)を参考にされたい。
*本研究は【1】の研究とは別のコホートである。
(高宮彰紘、2019.8.1.)
解説 加速するECT研究
ECTはなぜ効くのか。
この問いに答えることを目指した研究が、近年、急激に増大している。ECTによる脳への影響を明らかにするというのが、その最有力なデザインである。だが発表された論文を読むと、そこに示された脳の変化と臨床効果の関連が不明確なものが非常に多いという現状があった。それに対して高宮院生の今回の2つの論文は、【1】が抗うつ効果と関連する脳の変化、【2】が認知機能変化と関連しない脳の変化、を明確に示したものである。このように洗練された研究の蓄積の先に、ECT効果のメカニズムの解明と、そのメカニズムに特化した治療法、すなわち副作用が最小化された治療法の開発がある。
ECTはなぜ効くのか。
この問いが堂々と前面に出されるようになったのは最近のことである。ECTがきわめてよく効く治療法であることは、20世紀半ばからわかっていた。にもかかわらず、研究が遅々として進まなかった大きな理由は偏見である。精神疾患への偏見が、精神医療への偏見や治療法への偏見に姿を変えて、広く深く蔓延してきた。精神疾患に苦しむ人々を救う方法の進歩が、この偏見によってブレーキをかけられていた。現在もブレーキは解除されていない。そんな偏見を浴びていた治療法の代表であるECTについて、今、「なぜ効くのか」という問いを正面から研究できる時代になった。先人の努力の甲斐あって、ECTはようやく健全な評価と進歩のルートに乗りつつあるのだ。ECT研究の歩みは、偏見にさらされているものを健全な形に軌道修正して進歩させる実践のモデルになるであろう。
ECTはなぜ効くのか。
この問いの解明に向けた国際協力も進行している。【2】の論文をスイスで行われた国際学会(22nd Organization for Human Brain mapping) で発表した高宮院生は、各国のECT研究者とdiscussionを重ね、その結果、ECT国際共同研究グループGEMRIC (The Global ECT-MRI Research Collaboration) https://mmiv.no/gemric/ のメンバーとなり、ECTの益々の発展に向けての前進を続けている。
(村松太郎、2019.8.21.)
統合失調症におけるAgencyネットワークのDysconnectivity
是木明宏 (下総精神医療センター / St George’s University of London)
Koreki A, Maeda T, Okimura T, Terasawa Y, Kikuchi T, Umeda S, Nishikata S, Yagihashi T, Kasahara M, Nagai C, Moriyama Y, Den R, Watanabe T, Kikumoto H, Kato M, Mimura M. Dysconnectivity of the Agency Network in Schizophrenia: A Functional Magnetic Resonance Imaging Study. Front Psychiatry. 2019 Apr 3;10:171.
統合失調症の自我障害の説明として、Sense of Agency (SoA)の異常が指摘されている。Sense of Agencyとは、何かイベントが起きたときに、それが自分の行為によって引き起こされたものであるとする感覚であり、自分の体が自分のものであるという感覚であるSense of Ownershipと双璧をなす自我の基本構成要素と考えられている。SoAの核となる神経基盤は島皮質および頭頂葉下部であるといわれている。しかし近年、Agencyの学習という観点から線条体、特に尾状核の関与も指摘されている。一方、統合失調症のPET研究からも尾状核の異常が指摘されている。これらのことから島皮質や頭頂葉下部に尾状核も含めた脳内ネットワークをAgency Networkとして捉え、統合失調症ではこのネットワークに異常があるのではという仮説を立て、慶應版Agency課題を用いたfMRI実験を行なった。
統合失調症患者15名および健常者15名が被験者となった。課題では、画面の下から四角が現われ上行し、音が鳴ったところで被験者はボタンを押すように指示される。すると数百ミリ秒のタイムラグの後に四角は上にジャンプし、その後ボタンを押す前と同様に上行して画面から消える。被験者はこのジャンプが自分が起こした感じがするかどうかを答えるように指示された。なおタイムラグは被験者の回答によって調整され、その被験者にとって最も判断に迷う状態を維持した。
課題中の脳の機能的連関を解析したところ、健常者では頭頂葉下部の特に縁状回と尾状核の機能的連関を認めたが、統合失調症患者ではその連関の有意な低下を認めた。またこの異常は患者の陽性症状との相関を有意な傾向で認めた。
この結果は、統合失調症におけるAgency Networkの異常を示唆するもので、統合失調症の中核となる病態生理に迫る所見と考えられる。尾状核は目標指向行動において、行為の結果が予測できているときに活動する部位であり、人が新たな環境で適応的なSoAを学習していく上で重要な役割を担っているものと考えられている。そのため統合失調症における線条体、特に尾状核の異常は、不適切なSoAの学習を通して自我障害を引き起こすと考えられる。
(是木明宏、2019.7.1.)
解説 空中分解を阻止するネットワーク
自我障害は統合失調症の本質に迫る唯一とも言うべきキーワードであるが、具体的な症状との関係で説明しようとするとなかなか難しい。よく挙げられる例はさせられ体験で、確かにそれはわかりやすい例ではあるものの、では統合失調症の臨床で典型的なさせられ体験がどれだけ認められるかというと、決してありふれた症状ではないから、自我障害こそが本質だという説明は迫力に欠ける。実際には自我障害は、急性期から慢性期に至る統合失調症のあらゆる諸相に多彩な様相を呈して現れる・・・などと正論を展開しても、具体的に目に見える形でそれが示されなければ、机上の正論とみなされ虚しく響くばかりである。そこで自我障害のより具体的な表現として、シュナイダーは自己所属性 Meinhaftigkeitと言い、島崎敏樹は自律性 Autonomie の意識の障害と言った。さらに安永浩のファントム理論は異常体験を脳機能に近いことばで記述しようとする革命的な試みであった。だがこれらの碧学による記述は、現代の精神医学における認知度という面から見ると、古文書の奥深くに埋もれている感さえある。いくら優れた理論でも、科学的な検証手段がなければ、そこから先には進まない。それどころか逆に統合失調症は、DSM-5に代表されるように、個々のわかりやすい症状を寄せ集めただけの像に解消されつつある。寄せ集めとはすなわち、拡散と雲散霧消にほかならない。
そんな悲観的な状況を本来の形に修正する力を秘めているのが、Sense of Agency (SoA)と、それを実証的に示さんとして前田講師が開発した方法論、SoA task (Keio Method)である。本サイトこのページの一番下、2014年3月に前田講師が紹介しているこのタスクを武器とするSoA研究は進化を続け、ついに統合失調症の脳に手がかかったのが本論文である。
大学院を卒業後ロンドンに留学した是木博士が中心となって行ったこの仕事は、脳内のAgency networkと統合失調症におけるこのネットワークの異常を示したもので、疾患の脳科学的研究としてはスタートラインについたにすぎないとも言えるが、空中分解の兆しさえあった統合失調症を脳内ネットワークという形あるものを示すことで自我障害というテーマに引き戻し、今後あるべき方向性を示した貴重な研究である。
(村松太郎、2019.7.30.)
自覚的認知機能低下患者における、客観的認知機能検査、脳血流シンチグラフィを用いたアミロイドβ蛋白蓄積の予測
船木桂 (慶應義塾大学医学部精神神経科 大学院博士課程)
Can we predict amyloid deposition by objective cognition and regional cerebral blood flow in patients with subjective cognitive decline?
Funaki K, Nakajima S, Noda Y, Wake T, Ito D, Yamagata B, Yoshizaki T, Kameyama M, Nakahara T, Murakami K, Jinzaki M, Mimura M, Tabuchi H.
Psychogeriatrics. 2019 Jan 27. doi:10.1111/psyg.12397. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30688000.
アルツハイマー病(Alzheimer’s disease:AD)は認知症の半数以上を占めるが根本的治療法は未だない。現在は、ほとんど認知機能低下のないADハイリスク者を対象とした、早期介入による発症予防を標的とする治験が行われている。
軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment:MCI)はADハイリスク群として広く知られているが、さらに前段階である自覚的認知機能低下(Subjective Cognitive Decline:SCD)もハイリスク群として注目されている。SCD、アミロイドβ蛋白(Beta-amyloid:Aβ)と認知機能の関連性を縦断的に調べた先行研究では、SCDかつAβ陽性者が最も認知機能低下が顕著であった。すなわち、SCDにおけるAβ陽性者を同定することは臨床的に重要である。Aβ蓄積はアミロイドPET(Positron Emission Tomography)で判定できるが、費用や設備、侵襲などから研究使用に限定されるため、日常臨床で行われている検査所見からSCD患者におけるAβ蓄積が予測できれば有用である。
本研究では、SCD患者におけるAβ蓄積の有無と神経心理検査、精神症状評価、SPECT(Single photon emission computed tomography)脳血流所見との関連を調査することを目的として横断研究を行った。
認知機能低下を自ら訴え当院メモリークリニック、精神・神経科外来を受診し、Mini Mental State Examination(MMSE)、ウエクスラー記憶検査の論理記憶(Logical Memory)、Clinical Dementia Rating(CDR)が正常範囲であったSCD患者42名(女性22名、平均年齢 74.5±4.7歳)を対象とした。18F florbetabenをトレーサーに用いてアミロイドPETを施行し、対象をAβ陽性群(10名)、陰性群(32名)の2群に分けた。またADの遺伝リスク因子であるアポリポタンパク質E(Apolipoprotein E:APOE)4の有無を採血にて調べた。評価項目は、聴覚記憶、視覚記憶、注意機能、遂行機能、語想起能力などを測る神経心理検査、自覚的認知機能低下の強さを表すMemory Complaint Questionnaire (MAC-Q)、不安・抑うつ、アパシーなどを測る精神症状評価、SPECT脳血流所見とした。統計学的手法としては、予備解析としてt検定を用いて各評価項目の群間比較を行った。主解析として、Aβ蓄積の有無を従属変数、人口統計学的特徴とt検定で有意な群間差(P<0.05)を認めた項目を独立変数として二項ロジスティック回帰分析を行った。
両群の人口統計学的特徴では教育歴、APOE4を含め有意差を認めなかった。t検定では論理記憶の直後再生-遅延再生/直後再生では、Aβ陽性群で有意な成績低下を認めた(P=0.04)。しかし、二項ロジスティック回帰分析ではAβ蓄積と有意に相関する因子を認めなかった。
本研究では認知機能低下を訴え自発的に診療機関を受診したSCD患者を対象に、詳細な神経心理検査、精神症状尺度、SPECT脳血流所見を解析したがAβ蓄積の有無を臨床所見から予測することが出来なかった。臨床場面ではSCD患者を対象に脳画像検査を始め種々の検査がなされているが、臨床検査所見よりSCDにおけるADハイリスク群を絞り込むことは困難である可能性が示唆された。今後、対象数を増やし、縦断的評価を行うなど更なる検証が必要と考える。
(船木桂、2019.6.1.)
解説 未曾有のスケール
早期発見早期介入を掲げれば、100%の支持を得られるのが常だ。
病気が早期発見でき、そして早期介入できれば、病の苦しみは激減し、医療費も激減する。特に超高齢化社会である我が国において認知症の早期発見早期介入ができれば、個人にも社会にも限りなく大きな恩恵になる。
だが現実はそう単純には行かない。。
早期発見早期介入が100%の支持を得られるのは、早期発見「できれば」、早期介入「できれば」という条件つきである。前半の早期発見の段階からすでに難題が山積している。精密な手法や検査を用いても、100%正確な診断は不可能で、必ず何%かの偽陽性と偽陰性が生ずるというのがその難題の一つである。それらが1%程度なら優れた方法であると一般的には言えるが、未曾有の高齢者人口を抱える我が国では認知症予備群もまた未曾有のスケールであるから、たとえ1%の偽陽性・偽陰性であってもその実数は膨大で、はたしてそれでも有益な早期発見手法と言えるかどうかと迫られると答えにつまることになる。
しかしそうやって立ち尽くしているうちにも高齢化はどんどん進行していき、その先には手のほどこしようがなくなる局面が見えている。そこで船木桂院生が着目したのはSCDであった。SCD (Subjective Cognitive Decline:自覚的認知機能低下)は、たとえば慶應病院のメモリークリニックのように認知症を扱う医療機関の受診動機として最も多い訴えの一つである。アミロイドPETにみるAβ蓄積をアルツハイマー病の診断マーカーと位置づけ、SCDの人々を対象とする神経心理学的検査、精神症状尺度、SPECTによってAβ蓄積が予測できるかというのが本研究で船木院生が立てた問いである。
結果は、「予測できない」であった。
このデータは、ある方向から見れば、認知機能低下の自覚症状はアルツハイマー病早期発見の役には立たないとネガティブに捉えることができる。別の方向から見れば、認知機能の自覚症状があるからといってアルツハイマー病を心配する必要はないとポジティブにとらえることができる。
どちらも一面的な見方であり、過剰な解釈は禁物である。もとより原著論文とは、未知の事実を究明するための大きな絵の一部なのであり、特に認知症という未曾有のスケールの対象を扱う場合はその意味合いが強い。一つの研究結果から言えることは限られている。それは決してデータの価値を低く評価するということではなく、大きな絵の一部を構成するという限度において重要な知見であると評価すべきものだ。
本研究は船木院生の学位論文である。彼は大学院を卒業後も慶應病院のメモリークリニックでの外来を継続しつつ、訪問診療を軸にした高齢者医療に力を入れている。研究を臨床に生かすという船木院生の実践は、後輩の大学院生が範とすべき一つのモデルと言えるであろう。
(村松太郎、2019.6.28.)
拡散テンソルトラクトグラフィを用いた双極性障害の解析
仁井田りち (慶應義塾大学医学部精神神経科 特任助教)
Aberrant Anterior Thalamic Radiation Structure in Bipolar Disorder: A Diffusion Tensor Tractography Study.
Niida R, Yamagata B, Niida A, Uechi A, Matsuda H, Mimura M.
Front Psychiatry. 2018 Oct 24;9:522. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00522.
MRIの進歩に伴い拡散テンソルトラクトグラフィー画像(diffusion tensor tractography:DTT)を用いた神経線維の画像化が可能となった。DTTとは水素分子の拡散の方向、程度を捉える拡散テンソル画像(diffusion tensor image:DTI)から神経線維の走行を追跡することにより、大脳白質の微細構造の異常、神経線維の整合性を評価することができる。MRI画像撮影時にDTI撮像法を4-5分加えることで日々の臨床応用可能である。
双極性障害において白質(WM)統合性の障害が指摘されている。 我々は前視床放線(anterior thalamic radiation :ATR)の構造的な WM 異常がDTTによって視覚的に評価されることができるかどうかを調べた。研究対象は、57人のBD患者 と57人の健常者(HCs)による114人。ただ1本のATR 繊維束も灰白質と白質の境界に達することができなかったものを描出不良なATRと定義した。 ATR 描出不良はHCsよりBDの左ATRで有意に高かった。(p=0.042)。 さらに、我々はFA値を調整し、ATR の描出が末梢側まで届かない値を最適な FA 閾値と定義した。最適な FA 閾値0.28を用いることにより右のATRでaccuracy 71.1%(sensitivity=89.5%とspecificity=52.6%)BD とHCsを区別できた (AUC=0.76)。今回の結果は最適な FA 閾値がBD とHCsを区別する生物学的指標となることを示唆する 。DTTによるATR の視覚的評価が臨床の場でBD のための有用な補助的診断ツールとなるかもしれない。
DTT解析は、錐体路、感覚路、視放線などの神経線維の走行と病変との位置関係が観察可能であるため脳外科領域で治療計画や術前シミュレーションでの応用に用いられたことが始まりである。今後のDTTの応用は臨床科の垣根を超え多岐にわたっている。我々は慶應大学病院で667例(2019年4月末現在)のDTT解析を行ってきており、多くの精神疾患についての知見が蓄積しつつある。
(仁井田りち、2019.5.2.)
解説 手が届く(かもしれない)聖杯
精神医学には根強い聖杯伝説がある。
「近代精神医学の歴史の中で、たまたま、まだ発見されていない病因の存在を前提とした疾患単位モデルが成功を収めたこと」(『精神医学の実在と虚構』 村井俊哉著 日本評論社)。
京都大学の村井教授はこれが聖杯伝説の第一の要因だと述べている。ここでいう「疾患単位モデルの成功」とはもちろん神経梅毒のことを指している。症状-経過-病理所見-病因の証明による神経梅毒という疾患単位の確立、そして治療法の開発は、ひと昔前の精神医学の教科書には必ず記されていた史実である。
「聖杯」とはゴールの象徴、「伝説」とは非現実の象徴。あわせて「聖杯伝説」とは、入手不可能な宝を目指す、希望のない夢物語であることを示唆している。過去には成功の輝かしい実績があるのになぜ夢物語なのか。それは成功が「たまたま」だったからである。神経梅毒は「たまたま」単一の原因によって起こる単一疾患だった。そしてその原因は「たまたま」当時に活用可能な技術、すなわち剖検脳の病理学的検索によって発見できる性質のものだった。神経梅毒は、この二つの「たまたま」がかけあわさって僥倖を得たという偶然の成功例だったのである。
精神科病院に神経梅毒患者があふれていた情景を実体験していない我々には実感しにくいが、この成功によって当時の精神科が大変な興奮と活気に包まれたことは想像に難くない。成功体験の記憶は人に希望を持たせ、前進への原動力になる。だが他方、時には成功モデルと方法への強いこだわりに人を導く。そしてついには、成功の記憶が消退しても、硬直した方法論だけが慣性の法則に支配されているかのように延々と続く。すなわち、決して手の届かない「聖杯」の探究である。かくして、遺伝子解析、画像解析などの新しい技術が開発されるたびに、とても単一疾患とは考えられない「疾患」の例数を集めてとにかく解析してみるという不毛な営みが精神医学研究として繰り返されている。そんな現状を要約する言葉として「聖杯伝説」はまさに箴言である。過去の栄光にすがるのは惨めな姿であるが、それと気づかずに過去の栄光に縛られているのは道化でしかない。
そんな状態を打開し、聖杯を視野内に捉えたのが本研究である。本研究の成功は決して「たまたま」ではなく必然と言えるものであった。その理由は第一に、精神疾患のうち、均質性が高いことが期待できる双極性障害を選択したことである。双極性障害は、気分がスイッチするという、他の精神疾患にはない顕著な特徴を持っている。躁うつ病(クレペリン)、循環病(シュナイダー)、そして双極性障害と名前は変わっても、常にこの特徴がその名前に映し出されていることは、時代を超えて疾患の本質が認識され続けていることを示していると言えよう。第二は、膨大な画像診断法の中から、拡散テンソルトラクトグラフィ(DTT)を選択したことである。
「たまたま」に頼ることなく、合理的な研究の実施を可能にしたのは、放射線医学と精神医学の両方の専門家である仁井田りち特任助教の見識と慧眼である。双極性障害の前視床放線をDTTで解析するという発想は、放射線科医にも精神科医にもまず生まれ得ないもので、両方の分野の専門知識があって初めて想到できる研究計画である。
本論文のabstractには The present results suggest that the optimal FA threshold can serve as a biological marker that distinguishes individuals with BD from HCsと記されている。Biological marker はそれ自体聖杯ではないが、聖杯の一部が見えたとまでは言うことかできる。「見える」から「手が届く」までにはまだまだ距離があるが、「見える」ことで双極性障害の聖杯に俄然近づいたことは間違いない。
沖縄と東京を定期的に往復する仁井田助教が慶應義塾大学病院でDTT解析を施行した667例は、認知症、高次脳機能障害、発達障害と多岐に及んでいる。いずれも、精神医学の聖杯伝説を果敢に切り崩そうとする仕事である。
(村松太郎、2019.5.27.)
知覚変容が顕著であった抗NMDA受容体脳炎の2例
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)
Michitaka Funayama, Jin Mizushima, Taketo Takata, Akihiro Koreki, Masaru Mimura.
Altered perception might be a symptom of anti-N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) encephalitis.
Neurocase. 2019 https://doi.org/10.1080/13554794.2019.1573260
コタール症候群を呈した抗NMDA受容体脳炎の1例
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科)
Michitaka Funayama, Taketo Takata, Masaru Mimura
Cotard’s syndrome in anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis
Psychiatry Clin Neurosci. 2018 Jun;72(6):455-456. doi: 10.1111/pcn.12658
【背景】
抗NMDA受容体脳炎は、病初期に多くの例で精神症状を呈して精神科に受診する。早期に治療を開始すれば全く後遺症がない例が多いが、一方で鑑別できずに中枢性呼吸障害などによって死に至ることもあるため、精神科医の鑑別診断が極めて重要である。しかし、その指標となる精神症状は幻覚妄想などと一括されているのが現状である。この2つのケースレポートでは、詳細な精神症候学を用いて精神科医による抗NMDA受容体脳炎の診断率を高める可能性をポイントとしている。
【症例報告】
レポートの3例はいずれも足利赤十字病院神経精神科で治療した抗NMDA受容体脳炎である。特徴的であることは、初診、治療、退院後のリハビリテーションもすべて精神科医が行い、詳細な精神症状の記載につながった点である。
はじめの2例のケースレポート(Neurocase)では、時間感覚や知覚の変容が目立つ一方で、統合失調症にみられやすい連合弛緩や自我障害がないという点を報告した。2例は、「みんなの動きがスローモーションに見える」「時間が逆さまになっている」「右から聞こえる話は現在、左から聞こえる話は過去に思える」「歌や時間が逆から流れているように聞こえる。反対向きな感じ」「テレビの音が正面ではなく、下とか後ろの方から聞こえてくる」「シラスの目が怖い」「壁の小さな穴に吸い込まれそう」などと話していたが、これらを語っていた期間は統合失調症より言動や行動にまとまりがあった。
次のケースレポート (Psychiatry and Clinical Neuroscience) は、離人症や身体の知覚変容からコタール症候群に至った症例であるが、この例も抑うつ気分や連合弛緩や自我障害は認めなかった。「体から自分が抜けたみたい。私に体がないみたい。」「ずっとぐるぐる回っていて、常に逆さになっている」「磁石のように体が壁に引っ張られて、壁に吸い込まれそう」「世界が終わったみたい」「私は死んだ。心臓がない。血が全部抜かれた。体がこなごなに切られた」などと、比較的整然と話していた。
【考察】
上記のように、抗NMDA受容体脳炎の中には視覚、身体、時間感覚が変容するという、同じくNMDA受容体を抑制するケタミン中毒と類似した症状が比較的純粋に出現する例が存在するのではないか。もちろん全例にこれらの症状が出現するのではないが、これらの症状によって統合失調症との鑑別につながり、素早い治療によって死亡率や予後を改善することができる可能性がある。他にも、情動の著しい変動、エピソード記憶障害、口部ジスキネジア、髄液所見や卵巣奇形腫の有無も鑑別に非常に有効であるが、初診に来た全例に髄液検査を行うことは不可能である。むしろ、精神科医が日常臨床の道具である精神症候学を用いて、抗NMDA受容体脳炎と統合失調症を中心とする精神疾患の鑑別をできるのではないか。今後も抗NMDA受容体脳炎の精神症状を詳細に取り、より確かな精神症状を明らかにしていきたい。
(船山道隆、2019.4.1.)
解説 花の色は幻覚
たとえば花を分類する。
色で分類すればわかりやすい。しかしそれではあまりに恣意的だと誰もが思うであろう。
では花びらの数で分類するのはどうか。それもわかりやすいが、色でなく数に着目したというだけで、やはりただ外見で分類したというにすぎない。数量化すればそれでいいというものではない。客観性は確かにあるが、それだけである。
そこで対称性で分類してみる。点対称の形をしている花(たとえば梅)を放射相称花、線対称の形をしている花(たとえば藤)を左右相称花とする。これは外見による分類という点では同じでも、単なる形の先にある花の機能の進化という要素が入っているので、より本質に接近した分類であると言える。花の属性として最も目立つ花の色や花びらの数だけにとらわれていたら、決してこの発想は生まれない。万人受けする枠組みから解放されたときに初めて進歩があるのだ。
精神病症状についてはどうか。
「わけのわからないことを言っている」「意味不明のことを言っている」などが精神病を疑う第一歩であるが、それだけではどこにもたどり着かない。そこで、そんな混沌の中から健常者でも追体験可能な要素を抽出する。代表は幻覚と妄想である。確かに幻覚と妄想は目立つ。だがそういうわかりやすい指標に着目して分類してしまうのは、花を色で分類して満足しているのと同様で、本質への接近を阻害する態度にほかならない。幻覚や妄想が患者に認められるとき、「統合失調症様の症状」と名付けられがちで、その幻覚や妄想が統合失調症に特徴的な性質を持っているか否かはほとんど論じられず、ましてや幻覚妄想以外の精神病症状は「意味不明」と一括されてその先には進まず思考停止してしまっていることがあまりに多い。
今回船山道隆部長がまとめた複数の症例報告は、「その先」に踏み込んだ貴重な論文である。しばしば「統合失調症様」と表現されるNMDA受容体脳炎の精神症状を精密に分析し、その主症状は知覚変容であって、連合弛緩や自我障害は認めないことを示したことは、精神病の脳内メカニズムが全く不明の時代の先人たちが開発・発展させた精神症候学に大きな価値があることを再認識させものである。
それだけでは単なる懐古趣味だが、この研究にはさらにその先がある。ひとつには、早期に統合失調症から鑑別して脳炎の治療を開始するきっかけになるという形で、すぐにでも臨床に役立てることができる。また、船山部長の解説文に記されているように、ここで抽出された症状は、NMDA受容体を抑制するケタミン中毒と類似性を有していることが注目される。それが偶然であるはずはなく、ここに精神病症状をドーパミン関連のものとNMDA関連のものに峻別できる可能性が見えている。精密な精神症候学とニューロサイエンスの融合から生まれる未来への期待は大きい。
(村松太郎、2019.4.23.)
同意・非同意患者、家族を対象とした電気けいれん療法の満足度調査
高宮 彰紘(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)
Attitudes Toward Electroconvulsive Therapy Among Involuntary and Voluntary Patients
Akihiro Takamiya, Kyosuke Sawada, Masaru Mimura and Taishiro Kishimoto
Journal of ECT 2019. DOI: 10.1097/YCT.0000000000000571
電気けいれん療法 (electroconvulsive therapy: ECT) は有効性も安全性も確立されていながら誤解や偏見の多い治療である。1つの要因としてメディアがECTの正しい情報を伝えていないという報告もある (Sienaert. Brain Stimul 2016)。ECTは緊張病性昏迷や精神症状のために拒食拒薬となっている、あるいは別の理由により身体的に危険な状態にあるなど、緊急性の高い場合に患者の命を救うために必要な治療である。精神症状が激しいあるいは昏迷状態の時には本人から治療の同意をとれないことが少なくない。諸外国では、本人同意のないECTは廃止すべきであるという意見や、ECT自体を廃止すべきという意見を表明する団体や個人もいる。しかし、精神科救急医療現場においては、緊急性が高くECTが必要となるケースは少なくなく、また、薬物療法や精神療法で改善しない場合もECTで劇的に改善するケースも少なくない。
ECTの誤解や偏見を解く第一歩として、ECTを受けた患者本人とその家族の体験をまとめることが必要であると考え、我々はECTを受けた患者53名とその家族44名に対してアンケート調査を行なった。質問項目はECTを受けた経験、ECTの有効性と有害事象、再度ECTを受けることへの意見、ECTのイメージに関する合計19の質問で構成されており、-3点から3点までの7段階のリッカート尺度を用いた。結果の表示に関して、マイナスの評点は否定的、プラスの評点は肯定的としてカテゴリーによる分類も行った。評価は効果に対する肯定的なバイアス、認知機能への否定的なバイアスが生じやすいECT直後の時期を避けるため、最終ECTから平均30日の間隔を空けて施行した。また、否定的な意見を表明しやすいように対面のインタビュー形式ではなく自記式のアンケートを行なった。
80%以上の患者と家族はECTの有効性に肯定的だった。約60%の患者は再発時に再度ECTを受けたいと答え、ECTは安全で、ECTは記憶に悪影響がなく、歯科治療を受けるよりも怖くなかったと回答していた。家族は患者本人よりも治療効果に対する満足度が有意に高かった。23名は家族の同意のみのECTの施行だったが、本人同意の参加者の回答と比較してうつ症状の改善度も、アンケートのほぼ全ての回答も有意な差は認めなかった。
本研究では本人同意の有無に関わらずECTの満足度は高かった。ECTに関して、特に非同意患者へのECTの是非を論じる際には、実際に治療を受けた患者本人やその家族の意見を参考にすることは重要と考えられる。
(高宮彰紘、2019.3.18.)
解説 当事者の真の利益とは
専制君主を打倒しようなどとは決して考えないのが大人のたしなみというものである。それは自分の身の安全のためだけではない。専制というといかにも横暴で不条理100%のようだが、そもそもは多くの人から支持されたからこそ君主になったのであって、のみならず、その地位が維持されているのは多くの人の支持があるからだという事実も認めなければならない。浅薄な正義感から打倒を考えるのは危険な独善である。行動を起こす前に、人々の幸福とは何かという根本に立ち返って、広く深く慎重に考慮しなければならない。
現代の日本には専制君主は存在しないが、専制君主的な単語はいくつかある。たとえば「個人情報」。保護の必要性が認められて高い地位を獲得するまではむしろ望ましい経過だったが、「個人情報は正義。反論する者は賊軍」となって、誰もが沈黙するという奇妙な状況が立ち現れた。いったん個人情報だと宣言されたら、それが本当に個人情報にあたるかどうかを検証しようとするだけで専制君主の逆鱗に触れる。「人権」や「いじめ被害者」もそんな例だ。それが本当に人権にあたるのか、いじめは本当にあったのか、検証しようとすれば身の危険を覚悟しなければならない。個人情報も人権もいじめ被害者も、尊重され大切に扱われるのが当然だが、意見することさえ許さない専制君主となれば話は別になってくる。
医療現場でそれに近い単語の一つに「同意」がある。本人の同意は尊重するのが当然だ。尊重しなければ本人の大きな不利益を生む。しかしでは、本人に同意能力がない場合はどうするか。病識がない場合はどうするか。専制君主には従うのが大人のたしなみであるから、同意がなければ治療はしないのが身の安全のためには得策である。有効な治療法があっても同意がなければしない。安全な治療法があっても同意がなければしない。専制君主には逆らわない。だがこれでは当事者の大きな不幸を招く。
電気けいれん療法は有効で安全な治療法である。ただ有効というだけでなく、少なくとも一部のうつ病にとっては最も有効で、効果はまさに劇的である。決して難治例のための最後の手段ではない。むしろ最初の手段として行うことで、本人の苦しみを速やかに取り除けるだけでなく、医療経済的にもメリットがあることが、多くの論文にすでに記されている。それなのになぜ十分に普及しないのか。一つには「同意」という専制君主によるブロックがある。電気けいれん療法が必要な当事者ほど、同意能力や病識が不十分だというのは臨床的な事実である。そこで直ちに、当事者を幸福にするために専制君主を打倒しようと考えたとすれば、それはあまりに浅薄な正義感に基づく発想である。専制君主も同意も、その存在が人々の利益になり支持されているからこそ高い地位を維持しているのであって、尊重する姿勢は堅持したうえでの現実の改善策を考えなければならない。
高宮大学院生が本論文で示したのは、本人の利益最優先を大前提にしたうえでの画期的なアプローチである。同意そのものを打倒しようなどという浅薄なことはしない。「満足度」という、現代の日本で専制君主の地位を獲得しつつある別の単語を、「同意」という先輩専制君主の領地に送り込み、冷静な評価を促したのである。
同意はそもそも、その先にある当事者の満足という大きな目的に向けての中継点にすぎない。同意を専制君主の地位におくのは、中継点を目的化するものにほかならない。本来は当事者の利益のためであったはずの「同意」が、それ自体が目的となった瞬間に形骸化し、逆に当事者の不利益を促進するものに変身し、専制君主の地位におさまっているとすれば、人々にとってこんな不幸はない。
有効で安全な治療法を、それを必要とするすべての人が受けられるようにする。そんな当たり前のことを実現するまでに、様々な障壁があるのが精神科臨床である。電気けいれん療法の生物学的解明を目指すと同時に、現場での実行を阻む障壁の氷解に向けて努力を続ける高宮院生は、臨床研究者のあるべき姿を具現している。
(村松太郎、2019.3.25.)
日本語版Rapid Dementia Screening Test修正版に関する検討(2)
Yasushi Moriyama, Aihide Yoshino, Taro Muramatsu, and Masaru Mimura:
Detailed analysis of the Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test using Arabic-hiragana conversion.
Psychogeriatrics 18(6): 446-450, 2018
日本語版 Rapid Dementia Screening Test(Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test: RDST-J)は,スーパーマーケット課題と数字変換課題の2題からなる. スーパーマーケット課題は,1分の間に「スーパーマーケットやコンビニエンスストアで買えるもの」を答えてもらう言語流暢性課題である. また数字変換課題は,アラビア数字を漢数字に変換する2題(209→二百九,4054→四千五十四)と,漢数字をアラビア数字に変換する2題(六百八十一→681,二千二十七→2027)からなる. 本検査は3~5分で施行可能でMini Mental State Examination (MMSE)程の時間を要さず,多忙な臨床における認知症のスクリーニング検査として有用である.
われわれは以前,RDST-Jが健常群と CDR0.5 の鑑別補助に有用であることを示した (Moriyama Y et al: Psychogeriatrics. 2016; 本サイト 2015.10. 軽症アルツハイマー病の診断補助には,時計描画課題よりも日本語版Rapid Dementia Screening Testが有用である ).さらにRDST-J修正版における検討で,数字変換課題の漢数字の質問・回答形式を横書きから縦書きに変更した修正版は,原版と比べてCDR 0.5のスクリーニング検査として低い感度と高い特異度を有することを報告している(Moriyama Y et al, Psychogeriatrics.2017.; 本サイト 2017.7. 日本語版Rapid Dementia Screening Test修正版に関する検討).
今回修正第2版として,数字変換課題をアラビア数字/漢数字からアラビア数字/ひらがなに変更することの影響を調べた.すなわちRDST-J原版(アラビア数字/漢数字)と修正版(アラビア数字/ひらがな)との認知症スクリーニングをおこなう上の感度・特異度を比較した.
対象はclinical dementia rating scale (CDR)0.5群45例と健常群52例で,原版と修正版との間に,干渉課題としてMMSEと時計描画課題をおこなった.
結果はCDR 0.5群を健常群と鑑別する上で, カットオフ値を8/9に設定した場合, RDST-J原版では感度73.1%,特異度75.5% であったのに対し,修正版では感度71.8%, 特異度73.0%であった.
以上ひらがな版RDST-Jの感度・特異度は原版とほぼ同等であった.
(森山泰、2019.3.1.)
解説 パズル、もしくは山
高みを目指して山を登るというたとえのほうが格調高いのだが、まずはもっと気軽にできるジグソーパズルのたとえから始めよう。ピースを正しい位置に置いていくことによって、まだ見えぬ絵を見えるものにしていくのがジグソーパズルである。ただここでたとえとして出すジグソーパズルは、第一に、絵とは無関係のピースもたくさんあるという点が普通とは異なる。つまり膨大なピースの中から、絵を構成するピースだけを選ばなければならないので、格段に難しいパズルになる。だからひとりではなく多くの人々が協力して仕上げるという点が普通のパズルと異なる第二の点である。
このパズルを解くためには、無関係なピースを除外していくという作業を重ねることが必要になる。その作業があって初めて、正しいピースを正しく置いていくことが可能になる。あるピースについて、それが絵を構成するピースでないと確認したら、そのことを広く知らせることが大切だ。それをしなければ、また別の人が同じピースと格闘するという無駄な努力をすることになり、パズルの完成は大きく遅延する。
現代の医学研究はそんなジグソーパズルに似ている。絵を構成しないピースにあたるのはネガティブデータである。ポジティブデータすなわち絵を構成するピースを発見した研究者が脚光を浴びがちだが、その影では誰かが無関係なピースを取り除き続けている。ポジティプデータとネガティブデータは、したがって、真実を目指す営みである研究という世界では同じ価値を持っている。
山を登るたとえでも同じことが表現できる。頂上に至る正しい道はどれか。それを知るためには、誤った道がどれであるかを明確に示すことによって、人が迷い道に入り込むことを防ぐことが大切である。誤った道すなわちネガティブデータも、したがって、正しい道すなわちポジティブデータと同じ価値を持っている。
森山博士の本論文は日本語版Rapid Dementia Screening Test(RDST-J)の改良過程におけるネガティブデータを示した。文字通り日に日に大きな問題になっている認知症対策の一端を担うことが期待されるこの検査を完成に向けるための、重要な仕事の一つである。
山のたとえは高みを目指すというイメージがあるから格調高い。しかし山を登るのは相当な苦労がいる仕事である。そして頂上を征服したとしても、現実として得られるのは達成感だけである。他方、ジグソーパズルは気軽に楽しむことができ、完成すれば実質的な成果物も得られる。RDST-Jについての研究はどちらにたとえるのが適切だろうか。それに答える資格を持っているのは、この検査の開発に心血を注いでいる実践者である森山博士以外にはいないであろう。
(村松太郎、2019.3.15.)
沖村宰 (慶應義塾大学医学部精神神経科特任助教、長谷川病院)
計算論的精神医学: 情報処理過程から読み解く精神障害 勁草書房 2019年1月20日発行
国里 愛彦, 片平 健太郎, 沖村 宰, 山下 祐一(共著)
本書が扱う「計算論的精神医学」とは,精神障害の理解において,情報処理システムである脳の計算原理を数理的に表したモデルを用いる研究手法のことであり,精神医学の新しい研究分野である。精神医学の歴史においては,現在隆盛を極める生物学的な研究方法に限らず,神経心理学や精神病理学などといった,いわば「心身二元論」の立場で精神障害を記述し,その病態理解を試みるというアプローチもとられてきている。これらは精神障害の研究だけでなく精神科医療の臨床の基盤をなす分野である。一方で,現在の精神障害の疾病分類が,生物学的基盤や病因論に基づいていないこと,近年の生物学的知見の蓄積によっても,その疾病分類の生物学的妥当性が否定されつつあることなど,現代精神医学が抱える重要な問題が浮き彫りになってきている。米国国立精神衛生研究所(NIMH)の現所長Joshua A. Gordon 氏は,各所で度々計算論的精神医学に言及し,NIMH において“Computational Psychiatry Program”を開始するなど,計算論的アプローチが上記したような現代精神医学が抱える問題に貢献できる可能性を強調している。また,海外ではすでに,神経科学・精神医学の一流誌へ計算論的精神医学に関するレビューが次々と掲載され,書籍も複数出版されるなど,この分野の必要性・重要性が認識されてきている。
こういった世界的現況の中で,本書の著者らはいずれも,国内では他に先駆けて計算論的精神医学研究に取り組んできた研究者で,2015 年からは「計算論的精神医学コロキウム」と題する研究会を開催し,この分野に興味を持つ研究者のネットワーク構築を行ってきた。本書はそこでの議論の成果から生まれた,国内最初の計算論的精神医学の解説書である。そして計算論的精神医学の概要から最先端の具体的な研究事例,実際的な理論的知識まで幅広くカバーされるように本書を構成した。
本書は大きく3 部構成になっている。第1 部では,計算理論とはどのようなことを指すのか,計算論的精神医学では,どのような研究デザインが組まれるのかなどについて解説する。脳の情報処理過程を数理モデル化するという意味での計算理論と,高度な数理的テクニックを用いてデータを解析するデータサイエンス・機械学習との関係についても概説する。第2 部では,計算論的精神医学において用いられる代表的な方法論である生物物理学的モデル,ニューラルネットワークモデル,強化学習モデル,ベイズ推論モデルの概要を紹介する。さらに,精神障害の疾病分類学における問題の克服に向けた取り組みであるNIMH により提案された研究領域基準(Research Domain Criteria: RDoC)と従来の疾病分類学とを計算論的アプローチによって統合する試みについても紹介する。第3 部では,最先端の具体的な計算論的精神医学研究事例を紹介し,同時に,第2 部で紹介した方法論がどのように用いられているのかも解説する。
本書では,数理モデルの解説については,理論の重要な概念を理解するために欠かせない部分以外は,極力数式による表現を避けて,初学者が理論の概要を理解しやすいように心がけた。また,脳のモデルとしてはどれも最先端のものであるので,精神医学を研究対象としていない読者にとっても,脳の数理モデル・計算理論のわかりやすい入門書として十分役立てていただけるものであると考える。
(沖村宰、2019.2.6.)
解説 未来へのインプット
客観的な症状に基づけば生物学からかけ離れる。生物学に基づけば臨床症状と一致しない。主観的な訴えに基づけば前世紀と大同小異。如何にしても全方位からの批判が飛んでくるのが精神疾患の分類である。
背景には対応の神話がある。精神疾患の原因には、遺伝子があるはず。脳障害があるはず。ストレスがあるはず。そのはずまでは正しいはずだが、どれも疾患と一対一には対応しない。そこでgeneはpolygeneに、局在はネットワークに、ストレスは全生活史に、というように疾患に対応する要因は拡張されていく。そして疾患そのものも境界線を越えて拡張されさらには融合されていく。DSMもICDも、疾患単位という概念をいったん放棄して、新たな疾患分類の出発点にせんとするポリシーから生まれた野心的な試みであったが、どうやらかえって逆に研究の方向性を歪めているのではないかという見解が優勢になってきた。2008年にデビューしたRDoC (Research Domain Criteria)は、”is not meant to serve as a diagnostic guide, nor is it intended to replace current diagnostic systems (NIMHのサイトより)”とされてはいるものの、実のところはアンチDSMの鮮烈な具現と捉えることができよう。
従来の疾患単位を完全に解体し、現代の生物学的知見に基づいた症状分析・整理を目指したRDoCは、理論的には隙がなく、現代の知を結集したシステムであるとさえ思える。だがしかし、その具体的内容を見れば、あまりに複雑でこれで使い物になるのかという感も否めない。扱われている変数が多すぎて、とても普通の人間には全貌を把握しきれないのである。それは決してRDoCの罪ではなく、人間の精神の複雑さを反映させようとすれば、このような姿になるのが厳然たる事実ということなのであろう。
そんな状況の救世主になることが期待できるのが、計算論的精神医学Computational Psychiatryである。沖村宰博士らによって上梓された、精神医学の領域で最も先駆的な出版物といえる本書には、RDoCを「観察可能な行動指標とそれに対応する神経回路機能の基本的な構成要素に基づき、健常から異常にいたるスペクトラム(連続体)として精神障害をとらえるという研究方略である」と紹介したうえで、ここに計算論的精神医学がどのように応用・貢献できるかが記されている。もはや世の中の多くの事象が、人間の認知機能では処理しきれない領域で扱われる時代となっているが、精神疾患の分類もそれに倣うことで初めて真のブレークスルーが得られると思われ、そのためには計算論的精神医学の手法が必須であると言えるかもしれない。
如何にテクノロジーそのものが秀逸であっても、インプットするデータが曖昧では威力は発揮できない。これは見過ごされがちで深刻な問題で、精神医学の臨床研究においても、とても厳密とはいえない評価尺度や質問紙から得られたスコアを、厳密な統計学的解析にかけてそれらしい結論を導いた論文が多数存在するが、膨大な無駄であることはそう遠くない将来に明らかになるであろう。計算論的精神医学という斬新で強力な武器を用いた研究により真に有意義な結果を出すためには、インプットするデータすなわち上述の「観察可能な行動指標」が精密であることが絶対ともいえる必要条件である。それは厳格な症状論のみから得られるものであって、逆にたとえば、統合失調症の幻聴と、解離性障害の幻聴と、脳器質疾患の幻聴を、同じ「幻聴」としてインプットするようなことがあれば、脳機能との対応はとても期待できまい。最新のテクノロジーの開発は、精神病理学の精密な症状論と、症状の量だけでなく質を精密に分析する神経心理学の価値を再発見する絶好の機会にもなっている。
(村松太郎、2019.2.22.)
人の良し悪しの判断に影響を及ぼすのは何か?
江口洋子 (慶應義塾大学医学部精神神経科研究員・心理士)
Komeda H, Eguchi Y, Kusumi T, Kato Y, Narumoto J, Mimura M.
Decision-Making Based on Social Conventional Rules by Elderly People.
Front Psychol. 2018 Aug 13;9:1412. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01412. eCollection 2018.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01412/full
架空の人物に関する状況説明文を読み、その人物に対して良い・悪いのどちらに判断するか、高齢者と若年者を比較して世代により差異があるかどうか、判断にはどのような特性が関連するのかについて、インターネットによる調査と実験を行い、検討した。
対象者は、若年群は平均年齢25.7歳で男女各50名、高齢群は平均年齢63.6歳で男女各50名で、すべての参加者は大学卒である。これらの対象者に実験1、2と信頼に関する質問紙(Yamagishi & Yamagishi, 1994)を実施した。
【実験1】 コンピュータの画面に、(文1・特性)人物の特性、(文2・行為)人物の行為、(文3・結果)状況の結果、を文ごとに経時的に呈示し、文3を読んだ後に、架空の人物が良い人か悪い人かの判断をさせた。群×特性×行為×結果の4要因の分散分析をおこなった結果、高齢群は若年群よりも架空の人物を「良い人」と判断するという結果を得た。
【実験2】架空の人物A、Bについて、(文1・特性)、(文2・行為)、(文3・結果)の3文を、ひとつの画面に同時に呈示する。文1と文2は人物A、Bで異なった内容(たとえば、良い特性・悪い行為vs.悪い特性・良い行為)とし、文章の結果となる文3は人物A、Bのどちらも同じである。画面呈示後、人物A、Bのどちらが良い人(あるいは悪い人)かを選択させた。文2から得る情報を優先してする判断をBehavioral-Based Judgments(たとえば、良い人を選択させる試行では、文2で良い行為(一般的に良い印象を与えるふるまい)をした人物を選んだ場合)とし、Behavioral-Based Judgmentsの割合を目的変数とした重回帰分析をおこなった結果、世代、性別、信頼に関する質問紙における一般的信頼傾向と用心深さが「行為で人物を判断」することに影響を与えることが示唆された。
実験の結果をまとめると、高齢者は若年者よりも人物を良い人であると判断する傾向があり(実験1)、高齢、女性、一般的信頼傾向が高い、用心深さが低いほど、人物判断の際には行為の情報をより使用すること(実験2)が示唆された。
(江口洋子、2019.1.22.)
解説 個人と社会の錯綜した関係
高齢化している日本社会と、それに伴い高齢者を狙った詐欺の増加が、この論文(原文)のイントロの冒頭で指摘されている。「人の良し悪しの判断に影響を及ぼすのは何か」を追究する本研究は、詐欺被害の対策を視野に入れた、社会的文脈での大きな意義を持つ仕事である。「高齢者は若年者よりも人物を良い人であると判断する傾向あり」という結果を受けて、これは詐欺防止プログラム開発に有用なデータになり得るとする本論文(原文)のまとめには説得力がある。だがこの結果は別のいくつもの角度から光を当てることで、さらに興味深い風景が見えてくる。
たとえば、ひとつは詐欺に関してである。
高齢者が詐欺被害に遭いやすい理由は認知症やMCIの影響と考えるのがごく自然であるが、本論文のデータは、認知機能が低下していなくても高齢者は人を信用しやすい=詐欺被害に遭いやすい傾向があることを示している。これはもちろん詐欺の防止計画策定という観点から重要なポイントであるが、逆に犯罪者の観点から見れば、「高齢者は、認知症でなくても詐欺のカモにしやすい」という貴重なデータであり、詐欺の実行計画策定においても重要なポイントになるであろう。
たとえば、もうひとつは信用に関してである。
高齢者は人を信用しやすいから詐欺に遭いやすい。そう示されると、人を信用しないことが大切なんだと素直に納得しそうだが、人を信用するのは、人間として本来は好ましい特徴ではなかったのか。逆に人を信用しない=猜疑心が強いのは、なるほど詐欺被害には遭いにくいかもしれないが、人間として好ましい特徴とは言えないであろう。猜疑心が強いことが好ましいとされるとすれば、それは詐欺に溢れた荒んだ社会である。だがそもそも社会に詐欺が溢れるのは、人が人を安易に信用しすぎるからであって、溢れさせないためには猜疑心が必要 ----- と思いをめぐらせば、そこには個人と社会の錯綜した関係が立ち現れる。
本研究で得られたデータは、詐欺への言及で始められ、詐欺への言及で結ぶ論文としてまとめられることで、魅力的なものとなっている。論文をpublishするためには、読者へのインパクトが必須であり、すると高齢者の詐欺被害が多い今という時代にあわせたストーリーとして見せることはpublishという目的にかなっているが、他方でこのデータは、見方によって多彩な光を放つ意味深長なデータでもある。本HPに寄せられた江口研究員の解説文には、詐欺についての記述が一切ないことに注目すべきであろう。結果だけを淡々と綴った江口研究員の解説は、データに対する著者らの誠実な姿勢を静かにしかし雄弁に示している。
(村松太郎、2019.1.28.)
大うつ病障害と双極性障害における局所脳体積の減少
―VBMによる解析-
仁井田りち(慶應義塾大学医学部精神神経科 特任助教)
Richi Niida, Bun Yamagata, Hiroshi Matsuda, Akira Niida, Akihiko Uechi, Shinsuke Kito, Masaru Mimura: Regional brain volume reductions in major depressive disorder and bipolar disorder: An analysis by voxel-based morphometry.
International Journal of Geriatric Psychiatry 2018 Oct 17 https://doi.org/10.1002/gps.5009
帯状回皮質は大脳辺縁系の主な組織であるが、脳梁膝部より吻側を膝下部前帯状回(Subgenual anterior cingulate cortex:sgACC)といいBrodmann領野(BA)では 24、33野の一部の領域に相当する。膝下部前帯状回の吻側に隣接する部位は梁下野(Subcallosal area:SCA)BA25野にあたる。Bora らによるMRIのVBMを用いて脳の体積減少をみた論文のメタ解析によれば、MDD(大うつ病性障害)において最も一貫して限局性に体積減少がみられる領域はsgACCであると報告されている。SCAはMaybergらが難治性うつ病患者に対して同部をターゲット部位とした脳深部刺激療法(Deep Brain Stimulation: DBS)にて劇的な精神症状改善を報告して以来注目されている部位である。これまでsgACCとSCAを分けて評価をすることはなされなかったが、我々はMRIのボクセルベースの形態計測(VBM)を用いて全脳検索を行って分離されたsgACCとSCAの関心領域 (Volume of Interest: VOI)を設定することに成功し、MDDの体積減少部位に関して縦断的、横断的なリサーチを試みた。まず、横断研究では治療中のMDD患者群ではsgACCの体積減少が認められ、縦断的経過との関連を分析したところ年齢、性別、疾患の重症度、治療期間、罹病期間、使用薬剤に関係なくsgACCの体積減少が認められた。更にこの領域の体積減少はMDD緩解後も持続した。その後丹念に画像と実際の臨床の患者症状とを照らし合わせていく作業の中、SCAだけの体積減少の患者は、BD(双極性障害)の患者が多く処方のコントロールが困難であるという結果も併せて得られた。
目的:今回我々は早期アルツハイマー型認知症診断支援システム (Voxel-Based Specific Regional Analysis System for Alzheimer’s Disease: VSRAD)を用いて大うつ病障害(MDD)と双極性障害(BD)のVBMを用いた脳領域の体積減少を解析した。
方法/デザイン:この研究では、MDD患者92人、BD患者32人、および43人の健常対照(HC)を対象としてsgACC、SCAと海馬の脳領域における体積減少の程度をzスコアとして計算し、これらの領域におけるzスコアの差異をMDD、BD、HC群で解析した。
結果:海馬のzスコアでは有意差は認められなかったが、sgACCのzスコアはMDD群でBDおよびHC群よりも有意に高く、SCAの zスコアはMDD群およびBD群ではHC群よりも高かった。
結論:sgACCの体積減少はMDDの可能性が高く、SCAのみに体積減少があると、BDの可能性があると考えられた。sgACC、SCAの体積減少は、MDDとBDを鑑別するための客観的な補助ツールとして有用かもしれない。
この研究の限界は54歳~80歳を対象としたことである。しかし、18歳から53歳のMDD、BDについても我々はすでに10代ごとのデータベースを作成しており、海馬傍回、sgACC、SCAのVOIと臨床所見の関係を研究している。例えば若年で重要な病態の一つである産後うつはBDの可能性が高いが、もし、産後うつで、sgACCに体積減少がなくSCAに体積減少が有ることを病初期にMRIで確認することができたら、将来はBDになる経過予測ができるかもしれない。
なぜsgACCの体積減少とMDD群が関連しているのか?根底にあるメカニズムはまだ明らかにされていないが、sgACCは皮質中の中でセロトニントランスポーターの密度が最も高い部位である。この部位の体積減少は神経細胞そのもの及びグリア細胞の密度の低下を反映しているとの報告がある。またMDDと体内炎症に関する報告もあり、sgACCでミクログリア活性が報告されており、神経炎症が高齢発症MDDの重要なメカニズムではないかと推測されている。MDDを有する患者は、炎症促進性サイトカインの上昇を示す。ストレスで活性化されたミクログリアは脳内で炎症性サイトカインを遊離し,サイトカインは sgACCを過剰に活性化し続け、その結果sgACCのグリア細胞が障害される機序が推測されている。sgACCの体積減少はtrait markerである可能性があり、炎症やストレス、その他の因子が加わり高齢にMDDの発症が増えることが推測される。
(仁井田りち、2018.12.5.)
解説 過剰と謙抑の収束点を目指して
うつ病は初発の時点で確定診断することは不可能である。診断を確定するためには経過を観察しなければならない。経過の中に躁状態が現れれば双極性障害と診断する。現れなければ単極性うつ病と診断する。
なんと頼りない診断方法なのか。と傍観者は言うであろう。だがこれが精神科診断の現実である。精神症状こそが最終的な診断根拠である以上、そして精神症状とは時々刻々と変化するものである以上、「経過をみなければ確定診断できない」というのは優れて真実を反映した解決方法なのだ。
欠陥がある方法を正当化するためにこのように理屈を持って来るのは、しかし、一種の開き直りである。それは進歩を停止させる。そこで開き直りに安住せず一歩踏み出し、過去から未来にわたる長い経過を精密に観察してみる。すると、従来単極性うつ病とされてきたもの、特に難治性とされてきたものの中には双極性障害が相当数含まれていることが指摘されるようになってきた。過去の経過をよく見れば、そこには躁状態の色彩がある症状が見逃されていることがわかる。たとえ操作的診断基準上は双極性障害とは言えなくても、生物学的には双極性障害の要素がある。そうなれば治療方法も単極性うつ病とは違ってくる。長い開き直りの時代への反動もあって、このbipolarityの概念が精神医学界で脚光を浴びるようになった。これまで単極性と誤診されていた双極性障害の人々を救う道が開けたというわけである。
だが脚光という光は大きな陰も生み出した。双極性障害の過剰診断である。ごく一時的な不眠や、ごく一時的な易怒、ごく一時的な活動性。その中には確かにbipolarityの証とみなさせるものもあるが、正常な心理変動の範囲内のものももちろんある。見分けるためには慎重さと慧眼が必要である。しかし「見た通り正常範囲である」と言うより、「一見正常に見えるものの中にも、見る人が見れば病理性が隠れていることがわかる」と言うほうが、いかにも深い洞察を感じさせる。かくして双極性障害の過剰診断が止まらない。
ひとたび新たな概念や診断手法が提唱されると、それまでの過小診断から逆の過剰診断へと大きく振れる。精神医学では繰り返し見られてきた風景で、双極性障害に限った出来事ではない。そして過剰診断への加速が、新薬の販売促進の時期と一致しているのも偶然ではない。うつ病のSSRI。統合失調症の認知機能を改善すると称する薬。そして既存の薬の双極性障害への適応拡大。今後も同じようなことが繰り返されるであろう。ただし薬は過剰診断を促進する一要因にすぎず、症状を最終的な診断根拠とする限り、過小診断と過剰診断の大きな振幅と混乱は精神医学の宿命である。
この混乱を根本的に解消する手段があるとすれば、それは診断根拠としての生物学的・客観的指標の同定である。単極性うつ病と膝下部前帯状回の体積減少、双極性障害と梁下野に限定された体積減少の関係を示した本論文がまさにその1つで、気分障害の診断手法を革命的に変えるポテンシャルを持っている。
本研究を可能にしたのは、放射線学会診断専門医であり、かつ精神神経学会専門医でもある仁井田りち特任助教の広く深い学識と実行力である。彼女の臨床診断の正確さと、脳画像の読影の精密さがこの画期的なデータを支えていることは疑う余地がない。
開き直りへの反動が過剰診断なら、症状を根拠とする診断への反動がNeuroreductionismである。脳の所見を示すことによって精神疾患が説明できるとするNeuroreductionismは、問診 → 検査 → 確定診断 という身体医学の診断方法に一致することもあって、精神疾患の「科学的」診断方法として高い評価を受けやすい。客観的に示すことが可能な所見への過剰な依存は、人間の精神活動の複雑さを忘れた、逆に非科学的な営みなのであるが。
だが本研究がNeuroreducionismへと発展することを危惧するのは杞憂である。上記著者解説文の「なぜ」以下の最終段落について、仁井田特任助教は掲載を躊躇していた。本研究で有意義な結果が得られたことは事実であるが、その結果についての解釈は謙抑的に行うというのが彼女の基本的な姿勢なのである。放射線診断の専門家というと、画像を何より信じ、臨床症状というファジーなものは無視しないまでも価値を低くみるのではないかというイメージを持たれがちであるが、仁井田特任助教はそういうステレオタイプとはかけ離れている。精神神経学会専門医と放射線学会診断専門医に加えて、心身医学会内科専門医、東洋医学会認定医の資格も有するという広い学識。そして1ヶ月のうち3週間は東京で、1週間は沖縄で臨床と研究に従事するという広い行動範囲が仁井田特任助教のここ数年の日常である。客観的所見と主観的所見の適切な融合がこれらの精神医学には必須であるが、仁井田特任助教はまさにそれを実践しており、その実践の中から生まれたのが本論文である。
(村松太郎、2018.12.25.)
左前頭葉眼窩部損傷後に出現した物品、人物、場所の誤認
船山道隆 (足利赤十字病院精神・神経科部長)
Delusional misidentification of inanimate objects, persons, and places after a left orbitofrontal cortex injury
Miki Tanabe, Michitaka Funayama, Yota Narizuka, Asuka Nakajima, Isamu Matsukawa, Tomoyuki Nakamura
Cortex 2018 Sep 18. pii: S0010-9452(18)30273-9. doi: 10.1016/j.cortex.2018.08.021. [Epub ahead of print]
【背景】脳損傷後に人物や場所に関する誤認が生じることがしばしば報告されている。過去の報告からは右側を中心とする前頭葉の損傷による例が多く、機序については形態と情動の認知の統合ができないといった説や親近感が失われるといった説がある。今回われわれは左前頭葉眼窩部損傷後に人物や場所に限らず、物品に対して誤認が頻繁に生じた例を報告し、前頭葉眼窩部で誤認が生じる背景を検討した。
【症例】61歳男性、前交通動脈瘤破裂によるクモ膜下出血(Hunt and Kosnik Ⅲ)にて入院治療となり、動脈瘤に対してはクリッピング術を、水頭症に対してVPシャント術を行った。頭部CTでは左前頭葉眼窩部と左前頭極に損傷を認めた。麻痺や感覚障害はなく、発症2か月後には病棟内のADLはおおむね自立したが、エピソード記憶の障害や作話や誤認が目立った。病室のドアを開けて自分の仕事場に行くなどの作話、親しくしていた姪や妹に病棟スタッフを誤認する人物誤認、自分が仕事場にいるなどの地理的定位錯誤をしばしば認めた。
行為については標準動作性検査にて異常は認めず、検査場面では失行はないと考えられた。一方で、物品の誤認が頻繁に認められた。爪切りをはさみとして使い、実際に襟足を爪切りで切っていた。歯磨きを付けた歯ブラシでひげをそろうとしていた。部屋の中では流しをクローゼットと誤認し、壁に冷蔵庫が設置されていると誤認してスナックを入れようとしていた。電気ポットを使い捨てペーパータオルのボックスだと誤認し、使い捨てペーパータオルを取ろうとしていた。これらの誤認は頻繁に個室では頻繁に出現したが、2人部屋に移ると大幅に減少した。
【考察】物品の誤認に関する過去の報告例では、同じ種類の物品が劣化した品質に置き換わったという内容であったが、本例の特徴は、爪切りをはさみに誤認するなど異なった物品への誤認が生じたことである。右前頭葉ではなく左前頭葉損傷であった点は、物品の使用が左半球の機能と関連することを反映しているのかもしれない。
ところで、前頭葉眼窩部は外界と内界を区別する機能を有することが過去の神経心理研究から明らかになっている。解剖学的にも前頭葉眼窩部はすべての種類の感覚に関連する皮質からの連絡を持つ唯一の皮質であり、さらに辺縁系との連絡も強い。感覚に関連する皮質が外界の情報を、辺縁系が内界の情報を連絡すると考えると、前頭葉眼窩部で外界と内界の情報を整理している可能性が十分にある。
本症例に当てはめると、患者が親しかった姪と会いたいと考えると、病棟スタッフを姪に誤認するのかもしれない。仕事に行きたいときは、部屋のドアを仕事場に通じるドアであると誤認するかもしれない。ひげをそりたいと考えるとシェーバーがなくとも歯磨きのついた歯ブラシでひげをそろうとしたり、襟足を切りたいときは爪切りをはさみとして使用したりするのかもしれない。このように、前頭葉眼窩部の外界と内界を区別する機能が障害されると、物品、人物、場所に対する誤認や作話が生じる可能性が考えられる。
(船山道隆、2018.11.6.)
解説 見えるからわかるまではまだ見えない
見ればわかる。それが常識だ。ところが脳が損傷されると見てもわからなくなることがある。この症状は日常生活への影響が大きく、メカニズムの仮説も立てやすく、その仮説の検証もしやすい。網膜への入力から「わかる」までの経路を順にチェックしていけばよい。見えているのか。見えたものが像として脳内に結ばれているのか。その像が名前と連結しているのか。意味と連結しているのか。記憶と連結しているのか。神経心理学的検査を精密に行うことによりこれらの問いの一つ一つに答えて障害レベルを同定することができ、呼称障害、視覚失認、意味記憶障害等々の名称が障害ごとにつけられてきた。かくして「見てもわからない」という症状については、すでに全貌が見えており、教科書の記載はもはや確固たる不動の知見のように思える。
だが本論文のケースは、これまでに知られているどんな症状とも異なる。
彼は確かに見えている。そして見えた物が何であるか、わかることの方が多い。ところが状況によってはわからないことがある。状況による認知機能の変動は、その基礎に意識の変動があると考えるのが医学の常識だが、彼の意識は通常の意味では常に清明である。するとこの症状は古典的ないわゆる非失語性呼称障害(non-aphasic misnaming; Weinstein, 1952) に似ているが、誤認した物品を使い続けるという行為は、それとは異なる。また、「病室のドアを開けて自分の仕事場に行く」というエピソードは作話ともとれる一方、重複性記憶錯誤の要素もありそうだが、いずれにせよ彼の認知機能障害はそれだけではとても説明できない。するとこれは、未知の新しい種類の脳機能障害なのである。
損傷部位が前頭葉眼窩面であることと、観察された症状から、外界と内界を区別する機能の障害を述べる船山部長の仮説は魅力的である。そして「姪と会いたいと考えると、病棟スタッフを姪に誤認する」のように、症状出現には本人の願望が関与していると思われることも見逃せない重要な特徴である。すなわち、網膜への入力から「わかる」までの脳内の経路だけをいかに精密に検査しても、このケースのメカニズムを解明することはできない。感情が認知を大きく修飾するのだ。船山部長が立てた仮説を今後いかにして検証していくかが、本論文が投げかけている刺激的な課題である。そこには狭義の認知機能検査とは別の次元の検証方法が必要であり、脳と心についての深遠な世界が広がっている。
(村松太郎、2018.11.30.)
ドナルド・トランプの危険な兆候 精神科医たちは敢えて告発する
バンディ・リー編 村松太郎訳 岩波書店 2018年10月発売
The Dangerous case of Donald Trump. Bandy Lee St. Marin’s Press New York
マスコミに出てくる精神科医のコメントの大部分はでたらめである。でたらめでない場合も全く的外れである。これは事件の容疑者の真の姿とコメントを対比する機会がある度にありありと実体験できることであるが、そんな機会などなくてもでたらめだということは容易に推定できる。本人を一度も診察することなく、報道されたごくわずかな情報に基づいて述べるコメントが正しいはずがない。それなのに何か事件がある度に出されるコメントは、精神医学の信頼性の下降に貢献することだけがその存在意義となっている。
以上は日本の話。
アメリカでは全く事情が異なる。精神科医に発言を禁じるゴールドウォータールールと呼ばれる倫理規定を、米国精神医学会が定めているからである。
そうした規定がある中、ドナルド・トランプ氏について、20名以上の精神科医がその病理を指摘した本書は「タブーを乗り越えた禁断の発言集」(翻訳書の帯の記述)である。
強力な国家元首が精神障害者であることは、決して珍しいことではない。ウィストン・チャーチルはうつ病だった。エイブラハム・リンカーンもうつ病だった。ジョン・F・ケネディはステロイド精神病だった。クレッチマーは次のように述べている(The Psychology of Men of Genius. Ernst Kretchmer. Translated by R. B. Cattell.
Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. London. 1931. p.4. )。
天才と呼ばれる人の多くは、狂気(madness and insanity)を傑出した人の最高の特質として称えている。ところが伝記作家は天才の前に立ちはだかり、両手を挙げて彼らを守り、精神科医が天才を冒瀆しないように見張っているのである。
アメリカでベストセラーになった本書で精神科医の著者たちがトランプ氏の診断名として示唆しているのは、自己愛性パーソナリティ障害、サイコパス、認知症など、多岐にわたっている。ゴールドウォータールールを破って発言することについては、倫理的な面からも、また、診断根拠の面からも、説得力ある理由が述べられている。この中で認知症は神経心理学に密接にかかわるもので、高齢の指導者には認知機能を受けることを義務づけるべきだという主張は、デリケートな問題を含んでいるものの、これからの社会では避けられない議論であると言えよう。
それはそうと、トランプ氏の精神状態について論ずる本書の著者たちが一貫して述べているのは、彼が精神疾患であるということではなく、彼が危険であるということである。歴史上の君主は万の単位で人を殺したかもしれないが、現代のアメリカ大統領は、地球を何個も消滅させる威力のある武器を手にしているのである。著者たちのいう「警告する義務」は首肯できる。彼らは熱意を持って、しかし冷静に、正確に警告している。いま、「警告された者の義務」とは何かを考える時なのであろう。
(村松太郎、2018.10.30.)
成人ADHDにおける前頭葉機能異常
山縣 文 (慶應義塾大学医学部精神神経科 専任講師)
Yamagata B, Takei Y, Itahashi T, Pu S, Hirano J, Mimura M, Iwanami A
Aberrant spatial and temporal prefrontal activation patterns in medication-naïve adults with ADHD.
Front Psychiatry. 2017 Dec 5;8:274.
過去の近赤外線スペクトロスコピー(NIRS)研究より、成人の注意欠如多動性障害(ADHD)は、健常群(HC)と比較して語流暢性課題(VFT)遂行中の前頭前野において、酸素化ヘモグロビン(oxy-Hb)の賦活量が有意に低下していることが報告されている。ADHDの診断において、特に成人の場合、幼少期の詳細な発達史が聴取できず、本人の主観的な訴えにのみ基づいて診断せざるを得ないケースが多いため、過剰診断の危険性が指摘されている。そのため、診断補助のための客観的な生物学的マーカーを確立することが重要と考えられる。
しかしながら、現在のNIRS研究には以下のような問題点がある。
1. 多くの研究が、賦活課題遂行中のoxy-Hbの全ての変化量を時間で平均した値を群間比較のパラメーターとして使用しており、時間情報を全く利用していない。つまり、NIRSの持つ0.1秒という高い時間分解能を活用できていない。
2. NIRS(ETG-4000装置)は両側の前頭側頭部をカバーする52チャンネルで構成されており、さらに測定時間は1251のタイムポイントを有する(課題全体の長さは125.1秒:0.1秒の時間分解能)。そのため被験者毎に数万単位のデータポイントを有することになる。この場合、多重検定について考慮する必要があるが、通常のfamily-wise error補正はNIRSデータには過度に厳密であるため、他の統計解析手法が必要となる。
上記の問題を解決するために、我々はcluster-based nonparametric randomization testを用いて、ADHDに特異的な前頭前野の賦活パターンを抽出することを目的とした。
本研究は、63名の中枢神経刺激薬を未使用の成人ADHDと38名のHCをリクルートした。ADHDは、両側の前頭前野(より左側)および側頭葉領域(より左側)に位置するチャンネルにおいて、HCと比較してVFT遂行中の[oxy-Hb]の賦活量が有意に低下していた。さらに、ADHDにおける[oxy-Hb]の賦活量の低下の程度が、課題遂行中の時間帯や脳領域によって異なるという特徴的な賦活パターンが見出された。
今回、初めてcluster-based nonparametric randomization testを用いることで、従来のNIRS研究では見い出せなかったADHDにおけるより詳細な前頭および側頭葉の賦活パターンを抽出することに成功した。他の脳画像検査と比べ、NIRSはその非侵襲性やコストの安さ、可搬性といった利点があり、本研究の結果はNIRSの臨床応用の可能性を示唆するものであった。
(山縣文、2018.9.23.)
解説 精密診断を目指して
障害個性論という言葉がある。かつて障害者白書に掲載されたこの文章がその代表である。
我々の中には気の強い人もいれば弱い人もいる。記憶力のいい人もいれば忘れっぽい人もいる、歌の上手な人もいれば下手な人もいる。これはそれぞれの人の個性、持ち味であって、それで世の中の人を二つに分けたりはしない。同じように障害も各人が持っている個性の一つと捉えると、障害のある人とない人といった一つの尺度で世の中の人を二分する必要はなくなる。そうなればことさらに社会への統合などと言わなくても、一緒に楽しんだり、喧嘩をしたり、困っているときには、お互いに助けあい、支えあう普通の人間関係を築ける社会になるであろうというものである。
ここに描かれているのは一つの理想社会である。白書なので硬い文章になっているが、もしこれをポスターにでもするのであれば、「障害なんて、ほんとはこの世にないんだ」といようなキャッチコピーがつきそうである。障害を障害と呼ぶことがそもそも間違いの始まりだった。ちょっと変わった人にすぎない。これまで障害と呼ばれていたものは、個性と呼ぶべきだ。それが障害個性論である。誰も「障害の受容」などに悩まなくていい。理想の社会がそこには立ち現れる・・・。
というように、悪意の誘惑者は、慈愛の笑顔で近づいてくる。
障害者というものの存在自体を否定する障害個性論。それを国が掲げる時、そのプラカードの裏には、「障害者施策不要」と書かれている。
障害は個性。障害者は障害者としてでなく、他の誰とも同じ、一人の人間として扱うべき。であれば、障害者施策はいらないというのはごく当然である。したがって、障害者のための予算もいらないという結論に到達することになる。
「障害」というネガティブな言葉を、「個性」というポジティブな言葉に置き換える。これは、国が障害者を排除するためのレトリックなのである。
というのが、障害個性論反対者の主張である。
しかしまさか白書を書いた官僚が慈愛の笑顔で仮面した悪意の誘惑者であるなどということはないであろう。予算削減などという陰の意図ではなく、真摯に障害者のことを考えて、これが理想だというものを打ち出したのであろう。しかしだとしても理想は現実ではない。そもそも今の社会、人と人がどれだけ支えあっているといえるのか。支えあっていない局面もたくさんある。そんな現実を横目で見ながら、障害個性論を掲げ、誰もがわけへだてなく、支えあう社会を、というスローガンには、虚しい響きが漂う。
障害個性論の是非はともかく、精神疾患の中の、少なくとも一部は、個性との境界が曖昧である。ADHDはその代表で、治療薬の市場拡大のため診断が乱発されているという批判まである。他方でまったく逆に、診断されないために医療の恩恵を受けることができず苦悩している人々も多数存在する。この問題は、診断を裏付ける客観的所見に乏しいという精神疾患の特性に起因するところが大きい。という指摘はよくなされ、確かにそれは重要な一因ではあるが、はるかに大きく重要な問題は、ではどのような客観所見があれば、精神疾患と確定診断する根拠にできるかという問いである。身体疾患であれば、臓器に所見があれば病気であり、確定診断の根拠になるであろう。では精神疾患は、脳に所見があれば病気といえるかといえば、そう単純にはいかない。あらゆる精神現象は脳の活動の現れである以上、それが症状であれ、個性であれ、それに対応する脳の活動があるのは当然であり、「脳に所見が見出された」とは、「テクノロジーの進歩により、対応する脳の活動を見出すことが可能になった」ということにすぎず、決して「病気」や「異常」を意味するものではない。
さらには、所見とはそもそも何かという問題もある。
脳機能画像においては、ナマのデータから最終的な画像が描出されるまでのプロセスに、様々な仮定や、一部は恣意的な操作が加わるものであるが、テクノロジーが進歩し、そして細分化している現代においては、大部分の検査が大部分の人々(そこには医学の専門家も含む)にとってブラックボックスと化している。
こうした様々な問題をすべて把握したうえで、ADHDの診断に貴重な1ページを加えたのが、山縣講師の本研究である。ADHDの診断は精密でなければならない。それは、生物学的に精密なだけでなく、社会的にも精密であることが求められる。最新のテクノロジーから臨床まで、全方位を視野にいれて初めて、真の「精密な」診断が可能になる。そしてそこから初めて当事者にとって最適な介入・治療を行うことができる。
山縣講師はまさにそれを実践している。そして彼が最近慶應病院で開設した発達障害専門外来は、すでに予約が溢れた状態になっている。
(村松太郎、2018.9.28.)
日常場面における記憶:近年の研究成果とその再考
梅田聡 (慶應義塾大学文学部教授)
Tsukiura, T., & Umeda, S. (Eds.) Memory in social context: Brain, mind, and society. Springer. 2018.
科学的な記憶研究の原点は,ヘルマン・エビングハウス (1850-1909)とされており,実験室という統制された環境で,人がどの程度の記憶機能を発揮できるのか,さまざまな角度から検証された.同時期,あるいはそれより以前にも,精神疾患や神経疾患における記憶の障害については,症例をベースとした報告が数多くなされており,記憶を科学的に探求するための「素材」が揃っていたことは事実である.しかし,それをどのような理論的枠組みで捉えるかについては,一定した見解に乏しく,結果として,研究者が独自に記憶分類を提案するという時代が長く続いた.その結果として,短期記憶,長期記憶,近時記憶,遠隔記憶,エピソード記憶,意味記憶,宣言的記憶,手続き記憶,潜在記憶,顕在記憶,展望記憶,回想記憶,自伝的記憶など,「〜記憶」と呼ばれる概念が山ほど提案された.近年,MRIや脳波計などを用いたニューロイメージング法が台頭し,記憶機能の背後にある構造的・機能的メカニズムが徐々に明らかにされつつある.健忘症や認知症における記憶の機能低下の謎も少しずつ解かれてきている.そのような流れの中で,上記の「〜記憶」という概念も大幅に見直され,現代の記憶研究で用いられる概念はかなり整理されてきたといえる.
では,このような研究が発展した結果として,記憶の姿は本当に見えてきたといえるのだろうか.この問いは,言い方を変えると,「実験室で測定する記憶機能は,日常生活における記憶のパフォーマンスを正確に反映しているといえるだろうか」という問いに置き換えることができるかもしれない.臨床場面での検査の成績は決して悪くないのに,日常生活では物忘れが目立つということは十分にありえるし,またその逆もありえる.かつて,フレデリック・バートレット (1886-1969)は,エビングハウスによる「無意味つづり」のような人工的な材料を用いた記憶実験を批判し,日常生活における「生きた記憶」を対象とすることの重要性を主張した.そして,実験室と日常生活における記憶のパフォーマンスに乖離があることを実証した.この流れは,アーリック・ナイサー (1928-2012)に受け継がれ,「観察された記憶 (Memory observed: Remembering in natural contexts) (1982)」という書物の出版に至り,記憶研究者に大きな影響を与えた.
それから35年の歳月を経た2017年,我々は "Memory in social context: Brain, mind, and society" という書物を刊行した.本書は,4つのパートからなる計18章で構成されている.本書で取り上げている内容は,1) 記憶研究へのアプローチ,2) 社会的・日常的文脈における記憶研究の諸側面,3) 発達的側面からみた記憶の変化,4) 記憶研究の応用的側面という4つの観点でまとめられている.各章では,それぞれの観点について,記憶の行動的特徴と神経基盤などを掘り下げており,近年の記憶研究の進歩について,網羅的に知ることができる.各章の概要を取り上げることはここでは避けるが,全体的な印象としては,社会的文脈を考慮した記憶,すなわち「生きた記憶」の行動・神経メカニズムに関する理解は,かなり進んだと感じる.一方,細分化が進んでいることも否めない事実であり,さらに不明な点がどこかが見えてきたという面もある.記憶研究に限ったことではないが,研究を大局的な視点から位置づけることが重要であることにあらためて気づかされたのは確かである.異分野間連携が当たり前になりつつある現在,一般化可能な理論構築を実現するためには,他の分野の進歩に目を配っておくことは極めて重要である.本書を通して,読者の皆さんにそのことに気づいていただけたならば,一編者として幸いである.
(梅田聡、2018.8.20.)
Impairment in judgement of the moral emotion guilt following orbitofrontal cortex damage
Michitaka Funayama, Akihiro Koreki, Taro Muramatsu, Masaru Mimura, Motoichiro Kato and Takayuki Abe
Journal of Neuropsychology 2018 Apr 19. doi: 10.1111/jnp.12158.
前頭葉眼窩部損傷は罪悪感を感じる状況に対する判断の低下につながる
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)、是木明宏、村松太郎、三村將、加藤元一郎、阿部貴行
【背景】モラルと脳との関係は、現在の神経科学のトピックのうちのひとつである。その中でもモラルと前頭葉眼窩部との深い関連は脳イメージ研究によって明らかになっている。しかし、実際の人間の損傷例での研究はほとんど行われていなかった。今回われわれは、脳血管障害例を対象としてこの問題に取り組んだ。
【方法】72例の脳血管障害例に対して、4つの課題を行った。1つはコントロール課題として長さの違いを求める知覚課題、次に具体的なものである野菜の選好課題、最後にモラルに関する判断課題2つ(怒り課題と罪悪感課題)を行った。知覚課題以外は、8つのものやモラルに関する状況を2つずつの組にして、どちらのものや状況を好きか/怒りを覚えるか/罪悪感を感じるかについて判断させ、それぞれの課題に関する判断の一貫性のなさ(判断のゆらぎ、すなわち、判断の低下)を求めた。判断のゆらぎに対して、病巣(前頭葉眼窩部、前頭葉背側部、頭頂葉、側頭葉、後頭葉、大脳基底核、視床)、病巣の大きさ、神経心理所見(知能、記憶、遂行機能)、年齢、性別、教育歴、脳血管障害の種類(脳梗塞か脳出血)を説明変数とした重回帰分析を行った。
【結果】罪悪感課題の判断のゆらぎは前頭葉眼窩部の損傷とのみ関連していた。他の説明変数は罪悪感課題のみならず、いずれの判断のゆらぎにも関連していなかった。
【考察】われわれの人間の脳損傷例での結果は、前頭葉眼窩部がモラルに関する感情の中でも中心的な感情である罪悪感と関連することを示している。前頭葉眼窩部を損傷されたサルでは、実際にはその場になく想像を要する課題であればあるほど価値判断が低下することが知られている。罪悪感は野菜の好き嫌いや怒りの感情とは異なり、実際の出来事とは違う別の選択肢があったら結果はどうであったか想像する反事実的思考(counterfactual thinking)を要すると言われている。解剖学的にも前頭葉眼窩部は状況を想像する前頭葉背外側部と感情とかかわる辺縁系と強い連絡を持つ。罪悪感など状況を想像する必要がある場面では、前頭葉眼窩部を損傷されるとその状況に伴う感情が惹起されにくいのかもしれない。
(船山道隆、2018.7.1.)
解説: モラル研究が開く扉
脳に損傷があり、機能に障害があるとき、神経心理学の本領が発揮されるのが常である。モラルは人間にとって特に重要で興味深い機能であり、前頭葉眼窩面損傷によってモラルが障害されることは昔からよく知られている。ところが人間の脳損傷例でのモラルをテーマとする研究はこれまでほとんど行われてこなかった。二つの大きな障壁があるからである。
一つは、前頭葉眼窩部の機能が複雑であること。抑制、選好判断、注意のシフト、報酬処理、感情処理など、多数の説があり、どれにもそれなりの根拠となるデータがあるが、どれもいまだ定説に至っていない。
もう一つは、モラルという機能が複雑であること。「モラル」という単一の機能があるとは到底考えられないうえに、測定することも困難であるから、方法論が定めにくい。
モラルという機能の重要性は誰もが認識しつつも、誰もが腰が引けていた背景にはこうした事情がある。そこに果敢に挑戦したのが船山部長の本研究である。
複雑性を突破するために主として二つの技が用いられた。ひとつは罪悪感についての判断の「ゆらぎ」を測定したという点である。罪悪感は、有り・無しの二分法で答えを求めるのはいかにも乱暴であるし、数値化することにも限界がある。そこで、判断のゆらぎが大きければ、当該判断力には障害があると判定するという手法を用いたのが、臨床神経心理学に精通した船山部長の繊細な技である。もうひとつは重回帰分析の適用で、モラルという複雑な機能については単なるケース-コントロールスタディでは雑音の混入が多すぎて何を判定しているのかわからないという問題を解消している。この統計手法の適用に必要な症例数(前頭葉眼窩面損傷例32名、コントロールとしての他部位損傷例が40名)を集めるという力が、技の実現を支えているという事実も見逃せない。
このように力と技を駆使して得られた結果は、「罪悪感の低下」であった。すなわち、罪悪感かはかなり特異的に前頭葉眼窩面に関連しているということで、モラルの脳研究における大きな一歩が本研究によって踏み出されたと言える。
次のステップは、では罪悪感とは何か、ということになろう。動物実験を含めた多くの研究から、罪悪感とは、仮想的な事態を想像し、その事態についての価値判断(反事実的思考: counterfactual thinking)の一型であるとされている。
このことは、モラルが関与する究極の状況、すなわち刑事事件における被告人の非難が、当該犯行を思いとどまるという反対動機を形成できたか否かを重視して決められるということの関連において非常に興味深い。「反対動機形成」という法の言葉が、「反事実的思考」という脳科学の言葉と急接近し、法的判断に脳科学の適用が欠かせない時代が目の前に来ていることを実感せずにはいられない。
脳に損傷があり、機能に障害があるとき、神経心理学の貢献は、脳のメカニズムを理解するというニューロサイエンスの領域と、症状を評価し症候学を確立し治療やリハビリの開発に結びつけるという臨床の領域の二つであるとするのが通例だが、モラルという機能に関しては、さらに非難/称賛という第三の領域が立ち現れる。この領域が最も明確化されるのが犯罪非難の場面であるが、反対動機を形成できないことが脳機能障害の一症状であるとすれば、なぜそれが非難できるのかという深刻な問いに答える必要が発生しよう。失語、失行、失認といった症状を非難することは全く不条理である以上、モラルの低下という「症状」を非難することに合理性を見出すのは容易でない。
そして非難の対極にある称賛についての問いはさらに深刻である。モラルの感覚が高い人(そしてその感覚に基づいた行動を取る人)は、「人格者」として尊敬されるのが社会の常であるが、モラルも高次脳機能の一つである以上、モラルという機能のみに「人格」という特権的な地位を与えることに合理性を見出すことも容易でない。すると人が人を尊敬するとは一体何なのか。モラル研究は従来の高次脳機能研究が触れなかった新しい領域の扉を開き、人は不条理で出口の見えない迷路に迷い込む。
(村松太郎、2018.7.26.)
主体性の精神病理学-“自我障害”から症状論・病態論・治療回復論について考えるー
前田貴記 (慶應義塾大学医学部精神神経科学教室 専任講師)
精神科治療学, 33(1);5-12, 2018.
“自我障害”を統合失調症の中核症状として見据え、“自我障害”を切り口として、統合失調症の症状論・病態論・治療回復論について考えてきた(病因論についてまでは難しい)。しかし、「自我」という概念は多義的で曖昧な概念であり、また、実体としてとらえられるものではなく、さらに、個の個別性・固有性・歴史性・一回性についても含意しているため、医学においては扱いにくい。「自我」を「主体」へと、概念を置き換えることで、“自我障害”を医学的に扱うことができるのではないかと考えている。
「主体とは、或る意志をもって、或る認識のもとに、或る行為をし、環境に作用するもののこと。」と定義される。主体は、環境の中で、環境および他の主体と相互作用する生命的個体としてとらえることができ、観測可能という意味で、自然科学の方法を用いることができる。主体には認識主体としての側面と、行為主体としての側面があるが、特に行為主体の側面に着目した場合、agent/agencyという用語が用いられる。
主体と自我の関係について言えば、“自我(私)”という意識が生まれる以前から、個体は生物として既に環境の中で適応すべく主体的に生きており、このとき必ずしも主体が自身について意識的である必要はない。主体は、“自我(私)”という意識に先立っており、その上で、自と他という体験が分化してくるのである。このような前提に立てば、統合失調症では、自と他という体験を分化、成立させている機構に障害をきたしているという病態仮説が導かれようか?
「主体性」の精神病理学は、精神病理学と、自然科学としての生物学さらには脳科学との連繋を目指す試みであるが、これは統合失調症のみならず精神医学全体の課題であり、その一つのモデルとなればと考えている。
(前田貴記、2018.6.28.)
解説 主観の失地回復は急務
精神医学の臨床は、主観至上主義である。
精神科では、診断は患者の訴えの分析によって決定される。患者の訴えとは患者の主観的体験にほかならない。そして治療効果も、患者の主観的体験の変化に基づいて判定される。診断も治療も主観が頼り。つまりは主観至上主義である。
もっとも、現在では脳の画像診断がある。神経心理学的検査によって、脳の機能の表出を客観的に測定することも可能である。「主観至上主義」は過去の精神医学の臨床であって、「主観至上主義だった」という過去形が正しく、現在は違うというのもまた合理的な主張であろう。だがこれらの検査はまだまだ補助手段にすぎない。現在でもなお、精神医学の臨床では主観的体験が最も重要であることに変わりはない。「主観至上主義である」は言い過ぎだというのであれば、「主観至上主義にかなり近い」と言い直そう。
「主観至上主義だった」時代、患者の主観的体験は精密に研究された。その結果、統合失調症の症状論は頂点といえるレベルにまで発展した。そして今は退化している。前田講師が本論文に「症状学は浅薄化し・・・」と記載している通りである。
症状学はなぜ浅薄化したのか。精神医学を性急に「客観至上主義」にしようとする風潮が主因である。もちろん客観化〜科学化は必要であり、歓迎すべき進化である。だが、客観化(それは医学ではほぼ数量化と同義に用いられている)できない部分を等閑視した精神医学研究は、実体を無視して影だけを扱っているに等しい。特に統合失調症という精神医学の最重要課題については、主観的体験を中心にすえない方法論の限界はあまりに明らかである。
本論文『主体性の精神病理学』は、こうした状況を十分に意識した前田貴記講師が、古来から統合失調症の基本障害とされてきた「自我障害」を生物学的な研究の対象とすることを目指した試みである。その要点は上記前田講師自身の紹介文の通りであるが、原文を手に取ってみると、本文全7頁のうち、「はじめに」が2頁という異例の大部を占めていることが目をひく。そこには統合失調症に関しての中途半端な自然科学的な知見をもとに単純化された症状論とそこから派生する問題、そして世に跋扈している方法論的誤謬についての、前田講師の熱い批判が綴られている。
だがあえて言えば、統合失調症研究で現在主流となっている客観至上主義の方法論には根本的な問題があることは、前田講師に指摘されるまでもなく明らかであるというのが事実であろう。統合失調症とは、主観が客観化され客観が主観化されるという障害であり(そう単純には言えないことも本論文で指摘されているが、それはともかくとして)、「客観至上主義」の自然科学的手法の射程から逸脱した領域に着目することなしには到達できない障害なのである。統合失調症が主観と客観の「境界」の障害であるとすれば、客観的所見に偏重した現在の統合失調症研究は主観と客観の「不均衡」に致命的な問題があると言えよう。
精神医学が主観至上主義であることは、その臨床だけにとどまらない。少なくとも、客観至上主義よりははるかに主観至上主義に近い。だからといって主観的体験の記述のみを繰り返していても進歩はない。主観という領域に切り込む新たな方法論が必要である。前田講師の「主体性の精神病理学は、・・・、統合失調症のみならず精神医学全体の課題であり、そのモデル」は、まさに箴言である。
(村松太郎、2018.6.30.)
認知症の医学と法学
村松太郎 著 中外医学社 2018年6月発刊
解説 Neuro-: -psychology; -law; -ethics; -criminology
神経心理学 Neuropsychologyは、NeurologyとPsychologyの合成語である。かつて、心の学問と脳の学問は全く別々に発展し、二つの間に接点を見出すことはできなかった。長い時代を経てNeurologyとPsychologyが成熟し、心理学が脳と関連づけて語れるようになったとき、Neuropsychologyという分野が成立したのである。
現代においては、Neurolaw, Neuroethics, Neurocriminologyといった分野が誕生している。かつては自然科学との接点など全くなかった法律、倫理学、犯罪学が、脳で語れる時代になってきたのである。そして法とは、学問であると同時に、常に実践でもある。社会から争いが絶えることはなく、社会は常に争いの解決に多大なエネルギーを注いでおり、そこには必ず法がある。では法を、倫理を、犯罪を、脳で語れるようになりつつある今、どのような議論が行われているのか。今後どのような方向に進むのか。現実の裁判を素材としてこれを語ることを目指したのが本書『認知症の医学と法学』である。
民事篇には、たとえば遺言能力がある。遺言をするのは多くの場合高齢者で、その中には認知機能が低下していたり、さらには認知症に罹患していたりするケースがある。そうした場合、遺言は有効なのか無効なのか。そして遺言は、本人が書き替えることがある。普通に考えれば、書き替えられた後の遺言が彼/彼女の最終的な真意と解されよう。だが第一の遺言から第二の遺言に至る間に、認知機能が低下していたり、認知症を発症していた場合はどう考えたらいいのか。あるいは、純粋に本人を守ろうという意図を持った家族によって施設入所させられたことを恨んで、遺言が書き替えられた場合はどう考えたらいいのか。あるいは、親身になって介護している家族をBPSDの妄想によって恨み、遺言が書き替えられた場合はどう考えたらいいのか。どの遺言を正当と認めるのが正義なのか。認知症本人の真意はどれか。そもそも人の真意とは何か。
刑事篇には、たとえば前頭側頭型認知症 FTDがある。FTDと犯罪に関連性があることは古来から知られており、現代のFTDの犯罪では当然に責任能力が問題となる。責任能力とは弁識能力(是非善悪の判断能力)と制御能力(弁識能力に従って自分の行動を制御する能力)から成ると法は定めている。だが行動を決定するまでの脳内メカニズムが弁識能力と制御能力という2段階から成っているという保証はない。というより、そんな可能性はほとんどないと言ったほうがいいであろう。法律が定めたメカニズムは、人を制約する力はあっても脳を制約する力などあるはずがない。しかも法が責任能力を弁識能力と制御能力に分けたのは1931年で、当時はLawとNeuroscienceの接点は皆無であった。だが改正されない限り法は固く遵守されなければならないのであって、FTDの責任能力は弁識能力と制御能力で語られなければならず、結果としては法廷では制御能力が、ある種きわめて奇怪な論理の適用によって論じられ、判決が下されている。
本書で取り上げた25例の1例1例にこのような法と医の相克がある。この相克が、今後の脳科学の発展にしたがってどう変化していくかは大変興味深いものだが、「興味深い」と余裕を持って眺めていられる状況ではない。高齢化社会となった日本で、すでに患者数が400万人以上に達している認知症は、遺言や財産管理や自動車運転、そして犯罪に至るまで、医師が責任を持ってかかわらなければならず、時には訴訟当事者になるリスクが隣合わせである。また、ひとたび法的争いになったとき、正確な診断と認知機能の評価があってはじめて正義が行使されるという意味では、医の役割は非常に重い。
認知症とその裁判は、医と法の接点であるとともに、自然科学と社会科学が出会う実践の場でもある。
認知症の医学と法学 目次
民事篇
第1章 財産被害
Case 1 意思能力 妻・長男vs長男の妻
Case 2 公序良俗 保佐人vs不動産会社
Case 3 錯誤 養子vs不動産会社
第2章 養子縁組
Case 4 一審、縁組は有効。
Case 5 二審、逆転。縁組は無効。
第3章 遺言能力
Case 6 長男vs次男、遺言有効
Case 7 甥vs他人、遺言無効
Case 8 母vs次女、遺言有効
第4章 徘徊事故
Case 9 屋外での凍死
Case 10 他害としての鉄道事故
第5章 自動車運転
Case 11 症状としての自動車運転事故
第6章 脳損傷
Case 12 交通事故後のアルツハイマー病発症
Case 13 交通事故後せん妄、そして認知症
Case 14 高次脳機能障害
Case 15 画像所見なき脳損傷
Case 16 アメリカンフットボール選手集団訴訟
刑事篇
第7章 刑事責任能力
Case 17 老老介護殺人 心神耗弱
Case 18 前頭葉障害と窃盗 心神耗弱
第8章 前頭側頭型認知症
Case 19 夫殺し 完全責任能力
Case 20 漬物泥棒 心神喪失
Case 21 リンゴ泥棒 完全責任能力
Case 22 大型ディスカウントショップ連続放火事件 完全責任能力
第9章 訴訟能力
Case 23 アルツハイマー病。公判停止。
Case 24 コルサコフ症候群。公判停止。
Case 25 公判停止19年、裁判打ち切り
終章 法と医を結ぶ認知機能
(村松太郎、2018.5.26.)
電気けいれん療法の海馬と扁桃体体積に対する影響:システマティックレビューとメタ解析
高宮 彰紘(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)
Effect of electroconvulsive therapy on hippocampal and amygdala volumes: systematic review and meta-analysis
Akihiro Takamiya, Jun Ku Chung, Kuo-ching Liang, Ariel Graff-Guerrero, Masaru Mimura and Taishiro Kishimoto
Br J Psychiatry. 2018 Jan 212: 19–26
電気けいれん療法 (electroconvulsive therapy: ECT) は重症なうつ病に対して最も有効かつ即効性のある治療である。その作用機序はよくわかっていない点も多いが、1930年代の登場以来多くの仮説が提唱されてきた。近年は、抗うつ効果に関する神経可塑的な変化が注目されている。マウスやサルの研究からECTは主に海馬における脳の可塑的な変化(神経新生、血管新生など)を誘導することが指摘されてきた。ヒトを対象とした研究では、2010年にECTが頭部magnetic resonance imaging (MRI) を用いて測定された脳の海馬の体積を増大することが報告された (Nordanskog et al., 2010)。それ以降、ECTによる脳の体積変化の報告がされてきた。
そのような背景のもと、我々はECTが海馬と扁桃体の体積に与える影響に関してシステマティックレビュー・メタ解析を行い、さらにECTによる体積変化と関連する臨床特性があるかどうかメタ回帰分析を行なった。
メタ解析では8つの研究 (193人) のデータを用いて、標準化平均差 (standardized mean difference: SMD) を計算した。その結果、ECTは(片側・両側刺激に関わらず)両側の海馬・扁桃体の体積を増大させ、メタ回帰分析では海馬の体積増大は年齢と負の相関を示した 。すなわち、海馬の体積変化は高齢者ほど小さい可能性があるということである。これはマウスで得られた年齢と可塑的変化の知見、すなわち高齢マウスほどECTによる海馬の可塑的変化が小さいという知見と矛盾しない。
しかし、MRIで測定される「体積の増大」は何を意味するのだろうか。ヒトの脳における「体積の増大」をもたらすミクロな変化までは現時点の技術ではわからないため今後の技術発展を待つほかはない。少なくともECTによる海馬の変化は、拡散テンソル画像などの研究から単なる水分の移動、すなわち浮腫の影響でないことは示されている。その他、マウスとサルの研究からわかっているニューロン、グリア、血管などミクロな変化についての変化は論文のDiscussionを参照されたい。
また、体積変化の臨床的な意義は何だろうか。残念ながら今回のメタ解析ではECTによる海馬の体積増大と臨床症状の改善度合いに正の関連があるという単純な結論は見いだせなかった。否定的な見方をすれば、ECTによる海馬の体積変化は電気刺激もしくは発作による単なる副産物で臨床的意義はないのかもしれない。別の可能性としては、海馬の体積変化は臨床症状の改善ではなくECTによる認知機能の変化を反映しているのかもしれない。しかしECTによる海馬の体積変化と認知機能の変化を調べた唯一の研究では、その関連性は否定的だった。現時点ではECTと海馬の体積変化についてメタ解析の結果から早急に結論づけるのではなく、臨床症状の詳細な評価をした個別のデータを用いた多変量解析、多施設共同研究による大規模なデータ解析により検討する必要があると考えられた。
(高宮彰紘、2018.4.23.)
解説 派手な治療の着実な研究
うつ病の治療に真剣に取り組んでいる臨床医であれば誰でも、電気けいれん療法(ECT)の劇的な効果を実感している。特に、最重度のうつ病患者の苦悩を直視すれば、ECTなしでは精神科の臨床はとてもやれないといっても過言ではない。
しかし、1930年代から行われている治療であるにもかかわらず、ECTの発展は渋滞していた。
その原因の一つは偏見、もう一つは機序が不明なことである。
偏見の方は長い時間をかけて解消してきているが、機序の方は時間だけでは明らかになるはずもなく、研究が必要であることは自明だ。それなのに研究は遅々として進んでいない。ECTが施行されるのは重症なうつ病に限られるのが通例なので、統計的データを出すに足るサンプルサイズがなかなか得られないことがその主因の一つであった。
そこで高宮大学院生はメタ解析を行った。解析の対象となった論文数は8本で、決して大規模な研究とは言えないが、British Journal of Psychiatryという一流誌が高く評価し採用した背景には、ECTという重要な治療法をめぐる上記の事情が大きいとみるのが妥当であろう。
結果はある意味、地味なものであった。ECTを施行すると海馬の体積が増大するが、その度合いは年齢と負の相関を示したというものである。
ではその体積変化は何を意味するのか。当然興味はそこに移るが、高宮院生は派手な考察をすることは避け、淡々と事実のみを綴っている。
論文のDiscussionには Clinical relevance of hippocampal changesというsectionがあり、つい他を飛ばしてここを読みたくなる。しかし高宮院生によれば、このsectionは当初のドラフトにはなく、Br J Psychiatryのeditorからの指示で後から追記したとのことだった。
そう思って読むせいか、この部分の文章は他とは違う。本当は言いたくないことを言わされているような雰囲気が感じられる。このような推定的な考察を記すのは著者として不本意だったのかもしれない。(高宮院生本人には未確認であるが)
論文のConclusionとして記されているのはこれだけである:
ECT increased brain volume in the limbic structures. The clinical relevance of volume increase needs further investigation.
確固たる結果は得られた。結果からの過剰な推定はしない。ただこれからの研究の土台としてのデータを提供するのみ。これは科学研究論文の本来あるべき姿であり、高宮院生の一貫した研究姿勢でもある。ECTの作用機序は、最先端で注目される分野であるだけに一層、派手な結論に飛躍しない冷静な高宮院生の着実な前進に期待したい。
(村松太郎、2018.4.25.)
(S,S)-18F-FMeNER-D2を用いた大脳皮質におけるノルエピネフリントランスポーターの定量評価
森口翔 (Research Imaging Centre, Centre for Addiction and Mental Health, Canada)PET Quantification of the Norepinephrine Transporter in Human Brain with (S,S)-18F-FMeNER-D2.
Moriguchi S, Kimura Y, Ichise M, Arakawa R, Takano H, Seki C, Ikoma Y, Takahata K, Nagashima T, Yamada M, Mimura M, Suhara T.
J Nucl Med. 2017 Jul 58(7): 1140-1145
【本研究について】
ノルエピネフリンは認知機能やうつ病をはじめとする精神疾患などにおいて重要な役割を果たしていることが知られている。これまで、抗うつ薬の作用メカニズムに関する研究やうつ病患者の死後脳研究、うつ病のモデル動物の研究により、うつ病の病態生理の1つとして脳内の神経伝達物質であるノルエピネフリンの関与が示唆されてきた。その中でも抗うつ薬のターゲットにもなっているノルエピネフリントランスポーターは注目されていたが、それを生体内で直接観察することはこれまで困難であった。しかし、近年、生体内のノルエピネフリントランスポーターの密度をPETで定量化することが可能となった。現在、使用されているノルエピネフリントランスポーターを対象とした2つの主なリガンド((S,S)-11C-MRB 、(S,S)-18F-FMeNER-D2)は視床や脳幹で定量可能ではあったが、その他の大脳皮質での測定は困難であった。その理由として(S,S)-11C-MRBはリガンドの動態が安定せず、ノルエピネフリントランスポーター密度の低い皮質での測定が困難であった。一方で(S,S)-18F-FMeNER-D2ではリガンドの動態は安定しているもののリガンドの脱フッ素化により18Fイオンが骨に蓄積してしまい、放射能が皮質へ影響を与えてしまいこれまでの定量方法では大脳皮質での測定は困難となっていた。そこで本研究において、大脳皮質での密度の測定が可能かどうかを検討した。まず、240分間撮像した(S,S)-18F-FMeNER-D2のPET画像から18Fイオンが骨に蓄積しない時間帯を抽出した。その結果、0分から90分の時間帯で定量することによってこれまで困難であった皮質におけるノルエピネフリントランスポーター密度の測定が可能となることがわかった。
【留学について】
私は現在トロント大に付属するCAMH(Centre for Addiction and Mental Health)という研究施設にて気分障害を対象としたPET研究を行っております。こちらの施設では日本で行っていたPET研究と手技では似ている部分も多いのですが、日本との研究のやり方の違いがあり色々と勉強になります。例えば、被験者のリクルートをするためにカフェに募集のチラシが貼ってあるなど日本ではあまり見かけない光景です。またPET研究ではトレーサーによっては動脈血採血を頻繁に行わなければならないトレーサーがあり、私が参加しているプロジェクトでは動脈血採血が必要とします。日本で動脈血採血を行う場合は採血から運搬、代謝物の測定まで医師が行う範囲が広いため丸一日がかりの大仕事です。一方でトロントでは分業が進んでおり動脈ラインを取る専門の人がいたり、採血を運搬する人がいたりと、ひとりひとりの役割が明確に分かれています。人件費はかかるのですが、それぞれ専門の人が行うためかなりスムーズです。留学開始当初、文化や言葉の壁もあり戸惑うことが多かったのですが、半年ほどたつとこちらの研究環境には徐々に慣れてきました。とは言ってもまだわからないことも多く、スムーズに研究をすすめることはまだまだ難しいのでラボの戦力になれるよう今後一層努力したいと思っています。
(森口翔、2018.3.1.)
解説 精神医学奨励賞受賞
本サイト2017年2月「うつ病におけるノルエエビネフリントランスポーター密度と機能の検討」(論文出版は2017年1月)の執筆者の森口翔博士が2017年7月に出版した論文である。これらの論文をはじめとする一連の仕事が精神神経学会から「ノルエピネフリン・トランスポーターのPET研究に取り組み、世界初の所見などの先進的な成果を複数の優れた論文として発表している」と認められ、森口博士は2017年の精神医学奨励賞を受賞した。
https://www.jspn.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=45
この賞は、精神医学の発展のため顕著な業績を上げた若手(40歳未満)の研究者を表彰する制度であり、精神医学の学問的なレベルの向上を図る目的で設置されたもので、慶大大学院時代に着手したPET研究を現在留学中のCAMH(Centre for Addiction and Mental Health, Canada)で発展させている森口博士の研究スタイル・業績にまさにふさわしいものであると言えよう。「うつ病のPET研究を究める」(本サイト2017.2の解説のタイトル)そのものの道を、彼は歩みつつある。
(村松太郎、2018.3.24.)
高機能自閉スペクトラム症児が好む外見の好みについての予備的研究:治療目的の使用への示唆
熊崎博一 (金沢大学子どものこころの発達研究センター 特任准教授)Kumazaki H, Warren Z, Muramatsu T, Yoshikawa Y, Matsumoto Y, Miyao M, Nakano M, Mizushima S, Wakita Y, Ishiguro H, Mimura M, Minabe Y, Kikuchi M. A Pilot Study for Robot Appearance Preferences Among High-Functioning Individuals with Autism Spectrum Disorder: Implications for Therapeutic Use. PLOS ONE.
doi.org/10.1371/journal.pone.0186581
【本研究の目的】最近のロボット技術の進歩は著しく、医療用ロボットの活躍も目覚しいものがある。ロボットはその振る舞いに規則性を認めること、細かい動きの調整が可能なこと、自閉症スペクトラム(Autism Spectrum Disorder: ASD)児が熱中してロボットに関わること、及びASD児の具体的・視覚的な強さを考慮すれば、ロボットのテクノロジーがASD児に対しインタラクションを促す道具として有用であると期待される。実際、ASD児のコミュニケーション能力や社会性の改善を目指したロボットを用いたセラピーのエビデンスも蓄積されてきている。ところでロボットセラピーにおいてロボットの外見や行動が子どもたちに与える影響は大きく、課題も多いのが現状である。ASD児への介入に用いるロボットには、ヒトに外見の近いヒューマノイドロボットから外見が人には程遠い、ノンヒューマノイドまで多様である。好みの幅が狭いASD児への介入において、個々の児の特徴、介入に合わせて適切なロボットを選択することが重要になる。
【研究の概要】本研究では10歳から17歳の高機能ASD児16名を対象とした。 (1)成人女性型ロボット、(2)小型の人間型ロボット、(3)ぬいぐるみ型ロボットの3体を別々の診察室に配置した。児は医師の指示のもと、診察室に入室し各ロボットとそれぞれ5分程度の関わりを持った。各ロボットにはPCを用いて遠隔操作で会話が行える状況を作った。医師は児とロボットとの関わりを観察し記録した。また事後に児、母親よりアンケート調査を行った。年齢、自閉症スペクトラム指数(Autism-Spectrum Quotient:AQ)、WISC-Ⅳプロフィールとの相関について検討した。ASD児がシンプルなものを好む特性から、小型の人間型ロボットやぬいぐるみ型ロボットを好む児が多いことが予想された中で、AQ(自閉症の重症度)の高い群ではむしろ成人女性型ロボットを好むとの結果が出た。背景に、AQの高い群では最先端の技術を好む傾向が高いこと、大人っぽい顔を好む傾向があることが影響している可能性が示唆された。ASD児にとってシンプルな外見を持つという要素は重要であるが、成人女性型ロボットも生身の人間よりは表情がシンプルであるということも重要と考えられた。ASD児のセラピーにおいて、ロボットの外見がどこまでシンプルである必要があるかについては今後の課題となった。
(熊崎博一、2018.2.15.)
アルツハイマー病における数字変換課題と計算課題の成績の関係について
森山泰(駒木野病院精神科診療部長)森山泰,吉野相英,秋山知子,村松太郎,三村將: アルツハイマー病における数字変換課題と計算課題の成績の関係について. 精神科治療学 (32) 1355-1360, 2017.
数字変換課題と計算課題は必要とされる認知機能などにおいては異なる部分が多いものの,数を操作する失算関連の検査という点では共通している.今回われわれはアルツハイマー病における計算課題と数字変換課題の成績の関係について検討した.対象はMini Mental State Examination (MMSE) 12~26点(18.2±4.3)のvery mild~severe AD219例(男性101例,女性118例)で, Clinical Dementia Ratingは0.5~3である. 心理検査としてMMSE, 時計描画テスト, RDST-J(the Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test), 計算課題をおこなった. 数字変換課題はRDST-Jに含まれるものでアラビア数字を漢数字に変換する2題(209→二百九,4054→四千五十四)と,漢数字をアラビア数字に変換する2題(六百八十一→681,二千二十七→2027)からなり,それぞれ正解で1点ずつが与えられる(最高4点).
計算課題 (Serial 7 Subtraction test: 7 series)はJapanese version of MoCA に含まれるものと同様に100-7,93-7,86-7,79-7,72-7のそれぞれ5課題をおこなった.一方配点は各課題の正答数を評価することもありMoCA-Jの方法とは異なりそれぞれ正解を1得点とした(最高5点).
結果は計算課題と数字変換課題は中等度の相関を示したのみならず,それぞれがMMSE,時計描画テストと中等度の相関を示していた.
数字変換課題と計算課題は必要とされる認知機能などにおいて異なる部分も多い一方で,両課題は数そのものを操作するという点では共通している.しかし今回の結果は,数の操作といった比較的高次の認知機能ではなく,相対的に低次の認知機能である注意障害が関係していると考えるのが妥当であろう.
(森山泰、2018.2.1.)
日本における認知症介護者の心理的苦痛に関する予測因子:横断的研究
色本涼(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)Predictive factors associated with psychological distress of caregivers of people with dementia in Japan: a cross-sectional study.
Shikimoto R, Sado M, Ninomiya A, Yoshimura K, Ikeda B, Baba T, Mimura M
Int Psychogeriatr. 2017 Nov 10:1-10. doi: 10.1017/S1041610217002289. [Epub ahead of print]
人口の高齢化に伴い認知症者数は全世界で急増しているが、わが国においては世界に類をみない速さで増加すると予測されている。認知症者の多くは自宅にて家族による介護を受けているが、認知症介護者は心理的苦痛をみとめやすく、時にうつ病のような精神疾患にいたる。したがってこれら介護者の心理的苦痛のリスクを検討していくことが重要であるが、わが国において十分なデータによってこれらを検討した報告は行われていない。本研究の目的は、日本における認知症介護者の心理的苦痛に 関連する予測因子を検討することである。デザインは横断研究で、日本における認知症の経済的評価の研究の一部として実施された、インフォーマルケア時間調査に参加した、1,437名の認知症者とその介護者を対象とした。 評価項目は、認知症者およびその介護者の基本的背景、1週間のインフォーマルケア時間、Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)として幻覚、妄想、昼夜逆転、暴言、暴力、介護抵抗、徘徊、火の不始末、異食、性的逸脱行為の有無等とした。分析は、介護者の心理的苦痛をKessler’s Psychological Distress Scale (K6)で測定し、その予測因子を重回帰分析およびロジスティック回帰分析を用い検討した。その結果、認知症介護者の69%はK6点数が5以上で、18%はK6点数が13点以上であった。重回帰分析の結果、K6点数は認知症者のBPSD、身体合併症、インフォーマルケア時間、介護度、介護者の性別、介護者の人数と関連した。ロジスティック回帰分析の結果、K6のカットオフを4/5とした場合、K6点数は認知症者のBPSD、身体合併症、インフォーマルケア時間、認知症者と介護者との同居、介護者の人数、介護度と関連した。K6のカットオフ12/13とした場合、K6点数は認知症者のBPSD、身体合併症、介護者の性別、インフォーマルケア時間と関連した。これらすべての解析方法において、インフォーマルケア時間、暴言、介護抵抗、徘徊はK6点数と関連した。またBPSDの中では特に、暴言 (OR 2.03; 95%CI 1.48–2.77)、介護抵抗 (OR 2.35; 95%CI 1.72–3.22)、徘徊 (OR 1.72; 95%CI 1.21–2.44) のオッズ比が高いことが示された。本研究において、認知症介護者の心理的苦痛の点数は非常に高く、認知症者のBPSDが認知症介護者に関連していることを示した。これらの結果は先行研究に一致している。今後は、認知症者の精神症状を改善したり、介護者の負担を軽減するような介入の開発が求められる 。
(色本涼、2018.1.15.)
解説 人を支えるために
需要が増えるという予測があれば増産する。スマホが増えるのなら電子機器を増産する。人口が増えるのなら食料を増産する。インフルエンザが増えるのならワクチンを増産する。推定される需要増に応じた数を確保することが将来の安定への鍵である。
ただし需要が「人」の場合、そう単純にはいかない。
医師不足が予測されるから、医学部の定員を増員する。だが医師の数だけがいくら増えても、地域偏在を解消しなければ、問題の解決にはならない。人は意思を持っている。人は心を持っている。必要な数だけいくら正確に計算しても、行動までは計算できない。
これからの日本で確実に需要が増えるのは、高齢化に伴う認知症の増加に伴う介護者である。認知症患者の多くは家族から介護を受けており、その限りにおいて介護者の数は充足されているように見える。だがそれは需要が「人」であるという重要な事項を無視した抽象論である。認知症の介護にはストレスがつきものであり、ストレスのために介護者がダウンすれば、認知症を支える土台が崩れ、土台が崩れればすべてが崩れる。
認知症が急速に増加することがわかっていながら看過されてきたこの介護者の心理的苦痛の問題が、色本涼大学院生の学位論文のテーマである。認知症に伴う多彩な症状から本研究によって抽出された項目は、そのまま優先的な治療ターゲットになる。リアルタイムで増え続ける認知症を前にして、しかし認知症の根治療法がまだまだ見出せない現在、いま何をすべきか、何に力を注ぐべきかの決定が、医療者にも社会にも求められている。本研究は、認知症を支える土台である介護者を支えるための貴重なデータを示している。
(村松太郎、2018.1.30.)
アミロイドPETの結果告知が日本人高齢者に与える心理的影響 ー症状のない自覚的認知機能低下者に関する予備的調査ー
和氣大成(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 研究員)Wake T, Tabuchi H, Funaki K, Ito D, Yamagata B, Yoshizaki T, Kameyama M, Nakahara T, Murakami K, Jinzaki M, Mimura M. The psychological impact of disclosing amyloid status to Japanese elderly: a preliminary study on asymptomatic patients with subjective cognitive decline. Int Psychogeriatr. 2017 Nov 2:1-5. doi: 10.1017/S1041610217002204. [Epub ahead of print]
告知は心理的に「害をなす」のか?
──あなたは、10年後にアルツハイマー病を発症する危険性が高いです
こうした発症前診断が技術的に可能になりつつある。アルツハイマー病(AD)の症状がまだ現れていないものの、その原因とされるアミロイドたんぱく質が異常に蓄積している段階は、プレクリニカル ADと呼ばれる。ADの根治には、このプレクリニカル ADにおける超早期の介入が必要との意見が強まっており、診断方法としては、アミロイドPETによる脳画像検査が有力とされる。
ここで重要となるのが、次の問いである。すなわち、根治薬がない現在、その結果を告知することは倫理的に正しい行為なのか、あるいは間違ったことなのか?これに答えるべくさまざまな観点から議論が続けられているが、中核的な論点のひとつは、告知による心理的な悪影響である。
ところが興味深いことに、アミロイドPETによる発症前診断の告知が与える心理的な影響についてはほとんどわかっていない。とりわけ、神経心理学的検査などの客観的な評価では認知機能が正常であるが、自覚的な認知機能の低下(Subjective Cognitive Decline: SCD)のある群は注意を要する。なぜならSCD群はADの前駆症状と考えられることに加え、SCDのない健常者と比較して不安や抑うつが強いと指摘されており、告知に危険性をともなうからである。
本研究では、客観的には認知機能が正常であるが、自覚的な認知機能の低下のある群(SCD群)42名に対してアミロイドPETを実施し、AD発症の「高リスク群(n = 10)」と「低リスク群(n = 32)」の2群にわけた。告知前と告知後6週間後に、状態不安および抑うつを測定し、告知6週後にトラウマのレベルを測定した。その結果、状態不安と抑うつのレベルは、両群とも告知前後においてカットオフ値以下で推移し、各時点で両群の得点に差はなかった。トラウマ得点も、告知6週後で両群に差がなかった。
以上から、日本人SCD群に対してアミロイドPETの結果を告知しても、短期的には心理状態が悪化しないことが示唆された。
わが国では、AD発症後はおろか、発症前の告知が与える心理的な影響について実証的な研究がまったく行われてこなかった。それにもかかわらず、アミロイドPETを研究や診断のために使用し、結果を告知している施設もあるとみられる。さらに、プレクリニカルADを対象にアミロイドPETを用いる大規模臨床研究が近く始まろうとしている。
このような状況のもと本研究は、AD発症前診断の結果告知の是非に関して、倫理的基盤を実証的に提供したものと考えられる。
(和氣大成、2017.12.1.)
解説 それぞれの川
川から「助けて!」という声が聞こえる。見れば人が溺れている。川に飛び込み、助ける。やれやれと思ったのも束の間、また「助けて!」の声が聞こえる。飛び込み助ける。するとまた「助けて!」の声・・・いくら助けてもきりがない。ではどうしたらいいのか。川の上流に行き、人が川に落ちる原因を見出し解決するというのが答になる。
これは、公衆衛生の重要性を述べるとき必ずと言っていいほどイントロに使われる挿話である。言うまでもなく、川に落ちた人を助けるのが通常の医療の治療で、上流で対策を講ずるのが予防医療にあたる
アルツハイマー病を上流で解決する道がいま、開けようとしている。アミロイドPETによる早期診断である。プレクリニカルADを発見し、川に落ちる前に何とかするのが、人口の高齢化が急速に進行している我が国の公衆衛生の喫緊の課題である。
だが見逃せないのは、この川のたとえは二段階から成っていることである。第一段階は、上流にある原因の同定。第二段階はその原因の解決。川に落ちる原因がわかったら、そこに柵を作ればよい。だが現実はそう簡単にはいかない。アミロイドPETの導入によって、アルツハイマー病の川は第一段階に達した。第二段階はまだ先である。原因だけ同定されて、対策はまだない。川全体を管理する立場からは原因の同定は朗報だが、当事者本人にとってはそうとは限らない。あなたはアルツハイマー病になります。止めることはできません。以上、情報提供でした。そんな情報を人はほしがるだろうか。かえって残りの人生を暗くするだけなのではないか。新しい診断技術の華やかさに浮かれることなく、当事者のことを真摯に考えれば当然気にかけなければならないこの問題がこれまでほとんど無視されてきていたという現状への突破口を開いたのが、和氣研究員による本研究である。
結果は上記の通りで、告知は心理的に害をなすことはないというものであった。論文タイトルが示す通り、もちろんこれはまだ予備的研究の段階であるが、実証データを示したことの意義は大きい。
予防や早期介入の重要性を説くうえで川のたとえは秀逸だが、現実社会は、たくさんの人が同じひとつの川を流れているわけではない。ひとりひとりが、それぞれの川の流れを生きているのだ。上流から下流にリアルタイムで流れる川の中に人はいるのであって、遡ることはできない。自分で変えられることがあるとしても、それは下流部分だけである。
和氣研究員は、慶應義塾大学法学部政治学科を卒業した後、自由民主党本部で8年間勤務した後に渡米し、ハーバード大学国際問題研究所でフェローを1年間務め、その後ボストン・カレッジでカウンセリング心理学を学び修士号を取得、ボストンのカウンセリングセンターでメンタルヘルス・カウンセラーとして1年間勤務し帰国したという異色の経歴を持っている。永田町から心理職に転向したのはなぜか? 誰もが聞きたくなるこの問いに和氣研究員は、転向ではないと答える。彼の関心は「よく生きるとはどういうことか」という一貫したものであり、政治学も心理学も、彼にとっては死生学に通じる手段なのである。
予防医療は重要だが、上流ばかりを見ていると、今をどう生きるかという最も重要なことが忘れられがちである。川の最下流にある死を意識することがなければ、人にとって真に価値ある公衆衛生は成立しないであろう。アルツハイマー病が国民全体の課題になりつつある今、生と死を見つめる和氣研究員の今後の研究発展が期待される。
(村松太郎、2017.12.27.)
高用量の抗うつ薬とNIRS波形
高宮 彰紘(慶應義塾大学医学部大学院博士課程)High-dose antidepressants affect near-infrared spectroscopy signals: A retrospective study.
Takamiya A, Hirano J, Ebuchi Y, Ogino S, Shimegi K, Emura H, Yonemori K, Shimazawa A, Miura G, Hyodo A, Hyodo S, Nagai T, Funaki M, Sugihara M, Kita M, Yamagata B, Mimura M.
Neuroimage Clin. 2017 Feb 13;14:648-655.
近赤外線スペクトロスコピィ (near-infrared spectroscopy: NIRS) は、大脳皮質機能を非侵襲的に簡便に高い時間分解能で測定可能な検査です。言語流暢性課題 (Verbal Fluency Task: VFT) 施行中の脳賦活の特徴がうつ病、双極性障害、統合失調症で異なるため、抑うつ状態の鑑別診断補助としてその有用性が示されており、わが国では2014年より「抑うつ状態の鑑別診断補助」としてNIRSが保険収載されるようになっています。しかし、向精神薬がNIRS波形に与える影響を体系的に調べた研究は存在しませんでした。そこで我々は、向精神薬の内服量とNIRS波形の関連を調べる事を目的にカルテ調査を行いました。
本研究の対象は、2012年から2015年の間に慶應義塾大学病院精神・神経科を抑うつ状態で受診し、52チャネルのNIRS検査を受けた、20歳から65歳の方です。NIRS波形の主な指標はVFT施行中の酸素化ヘモグロビンの平均値を用いました。向精神薬の内服量は抗うつ薬、抗精神病薬、ベンゾジアゼピンについてWHOの定めるDefined Daily Dose (DDD)という1日あたりの平均的服薬量の基準を用いて計算しました。
本研究では40例のデータを解析に用い、両側前頭側頭部の広範な領域で抗うつ薬内服量とNIRS波形で負の相関を認めました (FDR補正p <0.05)。特に右側頭部のチャネル (ch22)のNIRS波形 は年齢、性別、抑うつの重症度の影響を考慮しても有意な相関があり (p = 0.002) 、さらに抗うつ薬が通常用量よりも多く使用されている高用量群では通常用量群よりも有意にNIRS波形の値は小さくなっていました。さらに、わが国において鑑別診断補助として使用されている前頭部重心値を用いた診断補助への向精神薬の内服薬量の影響を調べたところ、抗うつ薬の高用量群ほど双極性障害や統合失調症のNIRSパターンと診断されやすい傾向にありました。抗精神病薬、ベンゾジアゼピン系薬剤では有意な相関は認められませんでした。本研究の結果は、抗うつ薬の内服量はNIRS検査の結果に影響を与える可能性があり、特に高用量の抗うつ薬を内服している場合はその解釈に注意を要することを示唆しています。
(高宮彰紘、2017.11.1.)
解説 NIRSという芽
精神疾患を対象としたNIRS研究論文(英文)の2/3が日本発であること一つを取って見ても、NIRSは他に例を見ない特異な地位を占めている手法であることがわかる。慶應では2012年の導入以来、多数の臨床例が蓄積されてきている。本研究は高宮大学院生が中心となり、精神神経科の専攻医の共同作業によって完成したもので、共著者の多くは入局2年目前後の若い医師である。
向精神薬がNIRS波形に影響するという本研究結果は、精神症状の改善に最も効果がある治療法が向精神薬による薬物療法であるという現実に照らせば、NIRSの波形は精神疾患の生物学的原因に直結する意義を有しているという推定を導くことも可能だが、高宮院生はそのような派手な結論に飛躍することなく、「抗うつ薬の内服量はNIRS検査の結果に影響を与える可能性があり、特に高用量の抗うつ薬を内服している場合はその解釈に注意を要する The results emphasize the need for caution when analyzing NIRS signals in patients receiving high dose of antidepressants. 」という、抑制の利いた表現にとどめている。
先駆的で新しいテクノロジーは、過大評価されやすいものである。そこには人々の期待がある。NIRSに期待が膨らむのは当然である。精神科の診断は現代においてもなお主観至上主義である。そんな精神科の長い歴史を、NIRSは書き替える可能性を秘めている。ただしそれはまだ可能性にすぎない。可能性を期待に昇華することは推奨されよう。だがその期待を過大評価にまで水増しすれば、病者に不幸をもたらす。それを防ぐのは医師の役割のはずだが、残念ながらNIRSは我が国の臨床の場ですでに濫用され、誇大広告され、誤った解釈や評価が跳梁跋扈している。もし研究の場でも同じ事が起きれば、NIRSに未来はない。NIRSの論文の2/3が日本発という現状は、日本が世界をリードしていると見ることもできる一方、国際社会はNIRSという手法に期待は有しておらず、日本の研究に冷ややかな目を向けていると見ることもできる。NIRSという芽が伸びずに枯れるか、それとも大きく成長するかは、限界を見定めての臨床での活用と、着実にデータを積み重ねる研究の継続にかかっている。臨床経験を重ね、得られたデータから確実に導けることだけを提示した高宮院生の本研究は、それを実践したものである。
(村松太郎、2017.11.28.)
自閉スペクトラム症者に対してアンドロイドを遠隔操作することが、表情理解を促し、表情表出を増加させる
熊崎博一 (金沢大学子どものこころの発達研究センター 特任准教授)Kumazaki H, Muramatsu T, Yoshikawa Y, Matsumoto Y, Miyao M, Ishiguro H, Mimura M, Minabe Y, Kikuchi M. Tele-Operating an Android Robot to Promote the Understanding of Facial Expressions and to Increase Facial Expressivity in Individuals With Autism Spectrum Disorder. American Journal of Psychiatry. 174(9) 904–905. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.17030257
【報告の目的】顔の表情表出は意思疎通に重要であるが、自閉スペクトラム症者では表情表出は少ないことが知られている。一方で表情表出を増やすための効果的な治療についての報告は現在までほとんど行われていない。
【症例の概要】本例(Aとする)は18歳の高機能自閉スペクトラム症者である。コミュニケーション能力改善のために現在まで、行動療法をはじめとした多くの介入が行われたが、どれも改善にはつながらなかった。
アンドロイドはヒトに外見が酷似したロボットで、眉寄せ、頬引き、呼吸といった自律動作の他に微笑み、おじぎ、うなずくといった遠隔操作によるノンバーバルなコミュニケーション及び対話が可能となっている。姿勢の変化、頭や目の動き、胸で呼吸する様子といった人間らしい動きの模倣のほか、対面に居る人の簡単な動作(手を振る、顔を動かす、お辞儀など)を視覚のシステムで反射点を追い、関節の動きを計算し、追従させることが可能で、動作を記憶し再現することもできる。我々は被験者がアンドロイドを操作し、アンドロイドを通して対話者と会話するというシステムを用いて、Aに対話者とコミュニケーションしていただいた。Aはアンドロイドを操作することで表情が持つ意味とその重要性について理解できるようになった。アンドロイドを操作して以来、日々の生活でも表情を出すようになり、またコミュニケーションにも自信がついた。
【本例からの示唆】表情を表出することは、他者の表情理解につながることが知られている。本症例ではアンドロイドを操作し、自身の代わりにアンドロイドの表情を表出したことも、他者の表情理解につながったと考えられる。普段はコミュニケーションに興味を持ちにくい自閉スペクトラム症者の多くが、最先端の技術には興味を持つ傾向があり、アンドロイドの技術への興味がアンドロイドを操作することによるコミュニケーションへのモチベーションを持たせた可能性も考えられる。
(熊崎博一、2017.10.1.)
解説 人間そっくり
American Journal of Psychiatryに掲載された熊崎准教授のこの論文ページを開くと、誠実そうな若者の写真がまず目をひく。それは著者の近影・・・ではなくて、この研究で使われたアンドロイド、ACTROID-Fである。もしこれが動画で表情の動きが見られれば、人間そのものであることがさらに実感できたであろう。但し姿勢を大きく変えられるようには作られていないから、夜間も座位のまま部屋に保管されている。深夜にそれを見た警備員が、人が潜んでいると思い腰を抜かしたという実話もある。ACTROID-Fはそのくらい人間そっくりなロボットなのである。
自閉スペクトラム症のコミュニケーション能力改善を目的としてロボットを利用する手法は、近年急速に研究が進められている。その多くは、自閉スペクトラム症者が、苦手とする「人」ではなく「ロボット」を相手にコミュニケーションを訓練するという形である。自閉スペクトラム症者の機械を好むという一般的特徴と相まって、この手法には大いに期待が寄せられているが、対・ロボットで学んだことを社会での対・人間の場面に汎化する段階が大きなネックになっている。
本研究で熊崎准教授が採ったのは、従来の手法とは正反対と言えるもので、自閉スペクトラム症者が対ロボットで訓練するのではなく、自らがロボットを操作して対人コミュニケーションを行うという画期的なものであった。人間そっくりのアンドロイドACTROID-Fの精巧さがそれを可能にした。この研究に参加した被験者A君は、それまでは自らのコミュニケーション障害のため将来の夢をあきらめかけていたのであるが、アンドロイド操作で適切な表情の表出等を学んでからは自信をつけ、志望していた大学にも合格し、大いに自尊心を高める結果となっている。
現代社会へのロボットの浸透は著しい。医療においても、外科手術の分野などではすでに実用化がかなり進んでいるが、アンドロイドの登場によって、精神医療への応用可能性も一気に高まっている。そして本研究で熊崎准教授が示したアンドロイドの見事な活用は、発想を転換させた手法によって、すぐにでも精神科患者の利益に資することが可能な段階に来ていることを実感させてくれるものである。
(村松太郎、2017.10.22.)
視床損傷による意味性ジャルゴンは注意障害と関係する
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Attentional dysfunction and word-finding difficulties are related to semantic jargon after a thalamic lesion: a case report
Asuka Nakajima and Michitaka Funayama
Aphasiology 2017 (published online 20 July 2017)
【本研究について】失語症のジャルゴンは非実在語が頻発する新造語ジャルゴンについては多く報告されその機序も音韻の障害などさまざまな説明がなされてきているが、実在語のみによるジャルゴンである意味性ジャルゴンについての報告は極めて少ない。今回われわれは、視床損傷後に意味性ジャルゴンを呈した症例を8年にわたり経過を追い、本症例の意味性ジャルゴンの機序を検討した
方法として、発症2年後、4年後、8年後と経時的に言語、知能、注意機能の変化を調べた。言語面の評価は失語症語彙検査の呼称課題によって喚語能力や分類別の錯語(特に意味性ジャルゴンの主要因なる無関連錯語の割合)を調べた。知能はレーブン色彩マトリックス検査にて、注意機能は標準注意評価法の選択性注意課題を用いた。
結果は以下の2点である。無関連錯語の減少が選択的注意課題のfalse positive反応の減少と並行したが、喚語能力の変化とは並行しなかった。しかし、無関連錯語がほぼ消滅した8年後においても喚語困難は残存した。
【意味性ジャルゴンと視床の言語機能に対する役割】本例の経過からは、視床損傷後の意味性ジャルゴンは注意障害と喚語困難が関連することが示唆された。特に選択的注意のfalse positive反応と無関連錯語は、注意機能と言語機能という違いこそあれ、無関連な反応が生じてしまうという点で類似する。
元来視床の役割は情報のフィルター機能が重要視されていたが、近年は必要な情報を活性化して不必要な情報を不活性化する注意機能が強調されている。本症に照らし合わせると、視床損傷にて目的となる語やイメージを十分に活性化できず、同時に無関連の語やイメージを十分に不活性化できないというメカニズムが推察される。
視床失語は、復唱は保たれ理解障害が軽度であるにも関わらず、無関連錯語や意味性ジャルゴンが生じる。元来言語機能と注意機能の狭間とされ、一般的な失語との違いが強調されてきた。本症例の経過からは、視床機能の障害そのものが無関連錯語や意味性ジャルゴンにつながる可能性が示唆された。この機序が視床失語の本質かもしれない。
(船山道隆、2017.9.1.)
解説 脳の言葉を聴く
この論文には次のような対話が紹介されている
患者 「床辰巳に糸がなかった?」
----- どんな糸のことですか?
患者 「細胞の一致」
----- それ、何に使うんですか?
患者 「口の中100度になったり10度になったりしてあまり高い音にはならないけれど、100度とか120度になるから」
患者は流暢に話す。アクセントはごく自然である。知的機能は損なわれていない。だが言葉はこのようにわけのわからないものになっている。形式上は日本語として成立しているが、文脈と関連のない単語に溢れている。意味性錯語と呼ばれる単語である。意味性錯語が多発する発語が意味性ジャルゴンである。
この患者は、視床出血後に意味性ジャルゴンを呈するようになった。視床損傷による言語症状は古来から視床失語と呼ばれているが、そのメカニズムはいまだに謎のままである。船山部長はこの患者を8年間にわたって精密にフォローアップし、症状の変化と検査所見の関連を追究した。そして上記の通り、無関連錯語の減少が選択的注意課題のfalse positive反応の減少との鮮やかな相関を見出した。
パイプを「ひよこ」、馬を「ピアニカ」、線路を「お餅」などと答える。これらが検査場面でこの患者に認められた無関連錯語である。他方、選択的注意課題とは、紙に書かれている記号から三角形をターゲットとして選んで斜線をつけるもので、このとき、円や十字など、ターゲット以外の記号に斜線をつけてしまうのがfalse positive反応である。両者が相関するということはすなわち、無関連錯語とは、脳内に浮かんだ多数の単語の中で、その時点で選択すべき単語にフォーカスを絞ることができないために、他の無関連な単語が発話されてしまうというメカニズムによって発生することを強く示唆している。
脳の深部に座する視床。その機能は、不必要な情報を不活性化し、必要な情報を活性化する、すなわち注意のフォーカスであるとする説が有力である。まさにこの機能をみる検査である選択的注意課題のfalse positive反応と無関連錯語に明確な相関があることを8年間かけて示した本論文は、視床損傷によって生ずる意味性ジャルゴンが、注意の選択という視床機能の障害から直接説明できることを雄弁に示している。
脳の中は目に見えない。ニューロイメージングが如何に進化しても見えるのは脳のハード部分に限られる。精神機能がどのようにプログラムされ、どのように動いているかを知るためには、症状の精密な分析が不可欠である。中でも言語症状は、脳が自らの状態を訴えかける、脳の言葉とも言うべき貴重な表出である。本論文で船山部長が行った、 言葉を精密に分析する手法は、あらゆる精神疾患の解明に繋がるものであり、その先には真に合理的で有効な治療やリハビリの姿が見えている。
(村松太郎、2017.9.20.)
自発的な記憶想起の背後にみられる自律神経活動<展望記憶と内受容感覚の関係性>
梅田聡(慶應義塾大学文学部教授)Umeda S, Tochizawa S, Shibata M, Terasawa Y (2016)
Prospective memory mediated by interoceptive accuracy: A psychophysiological approach. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371.
展望記憶 (prospective memory) とは,自らの予定や他人との約束のような,未来に実行することを意図した行為の記憶を意味する.記憶というと,単語の再生・再認テストに代表されるような,過去に体験したエピソードの記憶を意味することが多い.しかしながら,日常生活においては,このような「過去の記憶」ばかりでなく,「未来の記憶」が必要とされる場面が多い.未来の記憶である展望記憶の最大の特徴は,想起にタイミングが必要とされるという点である.多くの臨床場面における記憶テストでは,刺激を覚えてもらった後に「はい,思い出してください」と教示し,被験者に記憶の再生や再認を促す.しかし,我々の日常生活では,帰りにパンを買って帰る,駅で封筒を投函する,3時になったら〇〇さんに電話をかけるなど,誰に促されることもなく,自発的に予定を想起しなければならない場面が多い.展望記憶には,タイミングよく,自発的に想起するスキルが必要とされるのである.
では,「ふと思い出した」と感じるような場面で,いったい何が想起を促すトリガーとして働いているのだろうか.心の中では「ふと思い出した」と感じていても,神経系では何らかのインプットがあると考えるのが妥当である.我々の考えた仮説は,「自発的想起のトリガーとなっているのは,身体状態の変化である」というものであり,本研究ではこの仮説の妥当性について検証した.
本実験では,参加者の心拍を計測しながら,ワーキングメモリの2-back課題を実行してもらった.用いた刺激はアルファベット文字である.2つ前に提示された文字と同じならば "1" のキーを,違っていれば "2" のキーを押すように教示した.さらに,展望記憶課題の教示として,もし母音の文字 (A,E,I,O,U) のいずれかが提示されたら,そのときは "3" のキーを押すように教示した.そして,展望記憶課題の成績として,母音の文字が出たときには,2-back課題よりも展望記憶課題を優先し,正しく "3" が押せた比率(正答率)を求めた.
その結果,この正答率が高い被験者ほど,展望記憶のターゲット刺激である母音の文字が出たときに,心拍が速まっていたことがわかった.さらに,自身の心拍の動きをどの程度正解に把握できるかを表す指標である心拍検出課題を用いて,参加者の内受容感覚の正確さ (interoceptive accuracy) を調べたところ,内受容感覚が正確な被験者ほど,展望記憶課題の正答率が高いことが示された.これらの結果は,展望記憶の自発的な想起に,心拍の変化が潜在的なトリガーになっている可能性を示唆している.
「ふと思い出した」と感じる直前に,いったい何が起きているのか.この疑問に取り組んだこれまでの研究は,心や脳の機能ばかりに着目していた.その結果,どこか表面的で,現象的なエビデンスが蓄積されるにとどまっていた.この疑問に取り組むためには,心や脳だけではなく,身体を含めた多角的な側面からのアプローチが必要であることが,本研究によって示されたのである.今後は,求心性・遠心性の双方向の信号伝達を想定しながら,身体における自律神経活動と脳活動のインタラクションをより詳細に検討し,自発的想起の謎の解明を進めていく必要がある.そして,軽度認知障害 (MCI) や初期の認知症において,展望記憶の機能低下が顕著に現れる原因を多面的に探っていきたい.
(梅田聡、2017.8.8.)
解説 「ふと」の因果律
「ふと思い出した」ときの「ふと」とは何か? 梅田教授が立てた仮説は「身体状態の変化」であった。そして2つのタスクを駆使してこの仮説に挑んだ。一つは一見単純な心拍検出課題 Heart Beat Detection Taskである。もう一つはワーキングメモリと展望記憶を組み合わせたいかにも複雑な dual task である。これらのタスクについて梅田教授にさらにお聞きした。まずは一見単純な方の、「自分の心臓がいま鼓動したと自覚できるか」という、誰にでもすぐに追体験できるタスクについてである。
村松: 先日の神経心理研究会では大変興味深いプレゼンテーションをありがとうございました。一連のお仕事の中のRoyal Societyの論文に出ていた心拍検出課題をあのあと私も実際にやってみたところ、自分の心拍を感じ取ろうとしても(検出しようとしても)、全く検出できている感じがしないのですが、これは私の内受容感覚が鈍いということでしょうか? たとえそうだしても、他の多くの人が私の感覚より著しく鋭いとはちょっと考えにくいので、多くの人々はかなり微妙な「感覚」に依拠して、「自分は心拍を検出した」と報告しているのではないかと予想しています。
私自身も、無理をして「心拍を感じている」と自覚しようとすればできないこともないのですが、それは自分の心拍数がおおむね60だと知っていることに基づいて推定しているという要素が強いように思います。
この疑問、つまり「心拍を検出したといってもそれは真に検出しているのではなく、ただ推定しているだけではないか」というのは、心拍検出課題においてはおそらく誰もが持つ疑問だと思います。論文中には時間推定課題time estimation taskの成績と相関がないという実験データを示すことによって推定でないことを担保したと述べられていますが、あれでは担保できていないのではないでしょうか? つまり、仮にある人物の心拍検出課題の成績が良いことが、彼の時間推定能力を反映していると仮定した場合、それを「心拍検出課題成績と時間推定課題の相関の程度」によって証明するためには、最初の心拍(第一拍)を起点としての時間推定を測定する必要があり、(つまり、起点がずれていたら、いくら時間推定が正確でも心拍検出は正確にはなり得ない)、単なる時間推定課題の結果だけでは、人物の心拍検出課題との関連を言うことはできないのではないでしょうか。
梅田: 確かに心拍検出課題だけでは限界がありますし,時間推定をコントロールとしても限界があるというのはその通りです.内受容感覚の研究領域では,この指摘はずいぶん前からあり,さまざまな工夫がなされています.我々も心拍に応じたタッピングをやらせてみて,ちゃんとタイミングが同期しているかということも調べたことがあります.そうすると,やはり心拍検出課題の成績がよい人ほど,同期の精密度で高いことがわかりました(これは未公刊ですが).
また,呼吸の内受容感覚(吸気負荷)や胃の内受容感覚(膨満感)などとの相関を調べた研究もあり,これもそれなりに高い相関が示されています.
所詮,主観報告ですので,無論,限界はあるのですが,以上のような周辺的エビデンスの蓄積により,「心拍検出課題はそれほど悪くない指標である」ということが認められており,今回もこの課題を踏襲して使っています.
ちなみに,別実験として,今もこの課題の妥当性については検証を続けており,それも論文化中です. その妥当性の検証方法というのは,つまりは,安静時ではない状態で心拍検出課題を実行するというものです.これですと,知識からのトップダウンの影響は限定的ですので,妥当性が増すものと考えています.
村松: 本論文のメインとなる、展望記憶とワーキングメモリのdual taskの巧妙さには感銘を受けました。この2つのタスクの結果が乖離するためには、それぞれのタスクの難易度が影響すると考えられますので、難易度の決定は相当に精妙になされる必要があったと予想されますが、これは如何にして行ったのでしょうか。相当な予備実験を行った? にしても気が遠くなるような気がしますが・・・?
梅田:これは展望記憶の行動実験として,これまでに膨大な数の論文があり,背景課題と前景課題のそれぞれの難易度によって,どのように変化するかが検討されています. それらを細かくレビューし,今回の課題がベストオブベストであろうで推察し,さらに予備実験を行った上で最終決定しました.かなり時間のかかるプロセスであったことは事実です. 実践的な意味でいうと,展望記憶課題のエラーをある程度の試行数,確保しないと,統計的な分析に載せられませんので,その辺りの調整が重要です.
村松: 背景課題としてワーキングメモリ課題は最適なのでしょうか? 展望記憶課題の成績にはまさにtargetが出た時点のinner stateが大きく影響すると直感的に考えられますが、ワーキングメモリ課題(2-back task)はより長いtime spanにおけるinner stateが影響すると考えられるのではないでしょうか。だとすれば、比較対象としては2-backではなくより適切なタスクがあるのでは?
梅田: 仰る通り,この実験では,展望記憶課題に対するcardiovascular responseと,ワーキングメモリ負荷に対するcardiovascular responseの両方が質的に異なる形で,自律神経に影響を及ぼしていると考えています.
ただし,先生がご指摘のように,これを質的に類似したtime-spanに対する影響を及ぼすことを前提に背景課題を選定してしまうと,今度は心拍の影響がどちらの課題によるものかを捉えにくくする可能性があるように思います.この課題で結果がうまく出たのは,異質的な自律神経系への影響があったからではないかと考えています.
論文にはタスクそのものについての説明はあるが、タスク決定に至る経緯についての記載はない。実際には上記の通り、精緻な考察と膨大な予備実験に支えられて初めて決定されたタスクなのである。それはstrong paperの常であり、決して「ふと」思いついて実行できるものではない。我々のまわりには多くの「ふと」がある。「ふと」に見えるものがある。「ふと」の帰結は時に驚くほど正確なものだが、その正確性の背後には、細心の注意に満たされた精妙な過程が隠されているのである。
(村松太郎、2017.8.14.)
日本語版Rapid Dementia Screening Test修正版に関する検討
森山泰(駒木野病院精神科診療部長)Yasushi Moriyama, Aihide Yoshino, Taro Muramatsu, and Masaru Mimura
Detailed analysis of Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test, revised version
Psychogeriatrics. DOI:10.1111/psyg.12248 [Epub ahead of print]
日本語版 Rapid Dementia Screening Test(Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test: RDST-J)は,スーパーマーケット課題と数字変換課題の2題からなる. スーパーマーケット課題は,1分の間に「スーパーマーケットやコンビニエンスストアで買えるもの」を答えてもらう言語流暢性課題である. また数字変換課題は,アラビア数字を漢数字に変換する2題(209→二百九,4054→四千五十四)と,漢数字をアラビア数字に変換する2題(六百八十一→681,二千二十七→2027)からなる(酒井ら,2006). 本検査は3~5分で施行可能でMini Mental State Examination (MMSE)程の時間を要さず,多忙な臨床における認知症のスクリーニング検査として有用である.
われわれは以前,RDST-Jは時計描画課題と比較し,健常群と CDR0.5 の鑑別補助に有用であることを示した (Moriyama et al,2016).
RDST-Jの数字変換課題における漢数字の質問・回答形式は横書きとなっている.しかし漢数字は本来,縦書きで書かれるものである.そこで今回,本課題で漢数字を縦とする影響を調べた.すなわちRDST-J原版(漢数字が横)と修正版(漢数字が縦)との認知症スクリーニングをおこなう上の感度・特異度を比較した.
対象はアルツハイマー病(Alzheimer’s disease: AD) 211例と健常群42例で,AD群のMMSEは12-26点,clinical dementia rating scale (CDR)は3-0.5である.修正版と原版の間に,干渉課題としてMMSEと時計描画課題をおこなった.
その結果,数字変換課題の4課題はいずれも縦バージョンは横のものに比べて成績が有意に高得点であった.次に CDR 0.5群(38例)を健常群(42例)と鑑別する上で, カットオフ値を7/8に設定した場合, RDST-J原版では感度63.8%,特異度76.6% であったのに対し,修正版では感度60.1%, 特異度85.8%であった.
以上RDST-J修正版は,原版と比べてCDR 0.5のスクリーニング検査として低い感度と高い特異度を有していた.
(森山泰、2017.7.1.)
解説 タテをヨコにするのではなく
もちろん国際化は必要だが、国際化は手段であって目的ではない。
論文を英語で書くことのみを目指すと、歪んだ研究が生まれる。最近しばしば目にされるのは、外国で作成された質問紙の翻訳をツールとして用いた研究に内在する問題である。Publishされた英語論文だけをいくら読んでもこの問題は見えてこないが、いかにも不自然な日本語が連ねられた質問紙が堂々と使われているというのが真実であることがよくある。このとき、back translationが形式的信頼性の免罪符でしかないことは、いったん論文化されるとその質問紙はもはやほとんど使われることがないことからも明らかである。診断や検査のツールを作るためには、単なる翻訳では全く不十分なのであって、WAIS-ⅢやWMS-Rも、日本の文化にあわせて原文に綿密な修正を加えて初めて汎用される検査として成立している。
Rapid Dementia Screening Testについての森山博士の一連の仕事も、真の検査を目指す妥協のない歩みである。本論文はその中の一歩として、従来はヨコに記して行っていた漢数字課題をタテに記すことによって特異度が増したことを示したものである。もし中等度以上の認知症を対象にするのであれば、ここまでの精度は必要ないかもしれない。だがCDR 0.5 という微妙な認知機能障害を捉えるためには、どこまでも精密さが要求されるのであって、そこには記述のタテヨコのような文化的要素も取り入れた検査が必要であることを本研究は雄弁に語っている。
もちろん国際化は必要である。但し医学研究における国際化は、真実の探究という目的を達成するための手段となって初めて意味を有する。お題目としての国際化と形式的物証としての英語論文の量産のために、単にタテのものをヨコにしたかのような論文が増殖している現代に対する警鐘を、本論文の中に読み取ることも可能であろう。
(村松太郎、2017.7.23.)
後天性脳損傷例における異食症は意味記憶障害と関連する
船山道隆(足利赤十字病院神経精神科 部長)Semantic memory deficits are associated with pica in individuals with acquired brain injury.
Michitaka Funayama, Taro Muramatsu, Akihiro Koreki, Motoichiro Kato, Masaru Mimura, Yoshitaka Nakagawa
Behavioural Brain Research 2017: 329: 172-179
異食症は介護上で最も大きな厄介な症状のうちのひとつである。急性の中毒、窒息、腸管の穿孔など緊急治療を要することも少なくない。自宅での介護をあきらめ施設入所が必要となることも少なくない。ところで、異食症は変性疾患、後天性脳損傷、統合失調症、自閉症スペクトラム障害、妊婦、乳幼児などに出現するが、機序は明らかになっていなかった。われわれはこれまで行われていなかった異食症の機序を解明する研究を行った。
対象は、変性疾患を除いた後天性脳損傷例にて異食症が出現した異食症群11例と対照群として異食には至らないが強い口唇傾向を示す口唇群の8例である。研究方法として、これら2群に対して神経心理学的所見と脳画像の比較を行った。神経心理的所見としては、前頭葉の解放現象(把握反射、吸引反射、利用行動)、意味記憶(日常物品の使用能力、意味記憶障害に関する介護者への質問紙、日常物品および食事動作の際の意味的誤使用についての介護者への構造的面接)、食行動の異常について調べた。結果は、異食症群は口唇群と比較して前頭葉の解放現象は弱く、一方で意味記憶障害は重篤であった。脳画像での比較では、異食症群の病巣は口唇群の病巣と比べて左優位の中側頭葉回後方が中心であった。
本研究の神経心理学的所見と脳画像所見は矛盾せず、異食症は左優位の中側頭回後方を中心とする損傷による意味記憶障害が関係する可能性が考えられた。後天性脳損傷に限らず、変性疾患、自閉症スペクトラム障害、乳幼児においても、意味記憶の障害ないしは形成が不十分であるために異食症が出現する可能性がある。また、意味記憶の神経基盤は側頭葉であることが定説であるが、本研究の所見は矛盾しない結果であった。さらに道具/人工物に関する意味記憶は左中側頭回後方を中心とする左半球が神経基盤であるとする研究が少なくないが、本研究での異食の対象の多くは歯磨き粉、洗剤、スポンジなどの道具/人工物であることから、これも矛盾しない結果となった。
われわれは異食という厄介な症状に対して、意味記憶による視点を切り口として症状の理解を深め、環境調節等による予防を行うことができるかもしれない。
(船山道隆、2017.6.1.)
解説 とりあえず食べる
食べ物ではない物を口に入れ食べる。それが異食症Pica である。異食症は認知症などの脳障害の症状として昔からよく知られている。だがメカニズムは不明であった。
直ちに連想するのは乳幼児の行動であろう。子が何でも口に入れるのは、世の親に共通する頭の痛い問題である。
異食症はそんな乳幼児の行動に似ている。だから原始反射が関係しているのだろう。退行現象だろう。局在的には前頭葉が主に関連しているのだろう。それが原因についての素直で自然な考え方だ。
しかしそうではなかった。関連する部位は側頭葉。関連する症状は意味記憶障害。船山部長が本研究で明らかにしたこの結果は、人々の直感に反するものであった。
物の意味がわからなくなるのが意味記憶障害である。つまり目の前の物が何であるかがわからなくなる。意味記憶障害は人に何をもたらすか。素直で自然な考え方は、物品の誤用である。だが誤用の中で、「食べる」だけが突出して現れるとは考えない。たとえば洗剤が何かわからない場合。たとえばスポンジが何かわからない場合。いずれも誤用のオプションは多岐にわたり、その中で特に「食べる」という誤用が突出して現れるとすればそれは奇異で、異食を意味記憶障害の二次的な症状のみで説明することは困難である。
すると「食べる」は人間の根源にある行動なのか。本論文のDiscussionには次のように記されている。
We human beings might be inclined to eat unrecognizable substances when we are unable to understand their meanings through any sensory modalities.
目の前の物が何だかわからなければとりあえず食べてみる。それが人間の脳にプログラムされた行動だという推定は、生命維持するための「食べる」ことの重要性に照らせば、素直で自然な考え方のようにも思える。が、これもまた何らかの方法による検証が必要であろう。
優れた臨床研究は臨床に還元できる。異食症は臨床上深刻な問題で、危険物が胃に入れば急性中毒や消化管穿孔のおそれがあり、いずれも生命の危険に直結する。本論文で示された異食症のメカニズムは、その予防や治療に貴重な示唆を与えるものである。
加えて本研究は、人に「食べる」ことの意味を考えさせる。人間の数々の行動における「食べる」ことの特権的な地位を考えさせる。脳についての優れた臨床研究データに内在するこの広がりこそが神経心理学の真髄である。船山部長の一連の臨床研究には常にそれを見出すことができる。
(村松太郎、2017.6.28.)
うつ病の医学と法学 中外医学社 2017年6月出版
著 村松太郎 (慶應義塾大学医学部精神神経科准教授)
解説 鵺の如し
判決文は法という異界から見たうつ病論である。
たとえば過労自殺。労働者側は会社の責任を追及する。過重な労働をさせた。だから自殺に追い込まれた。このとき、「過重な労働」と「自殺」を結ぶのが「うつ病」である。法の世界では自殺は自己責任であるが、「うつ病」という病気が介在されることによって、責任が会社に向けられることになる。
たとえば拡大自殺。母子心中で子が亡くなり母が命をとりとめたとき、母は殺人罪の被告人となる。このとき弁護人は母がうつ病に罹患していたと主張する。殺人は言うまでもなく重罪であるが、「うつ病」という病気が介在されることによって、被告人の刑事責任は大きく変わり得る。
目的がある。法廷にうつ病が持ち出されるとき、そこには目的がある。会社の責任追及。被告人の責任評価。そのほか如何なる事例であっても、それぞれに目的がある。それぞれの目的に合わせた形でうつ病が持ち出される。そして現代精神医学におけるうつ病とは不定形の概念であるから、法はそれぞれの事例の目的に合う部分だけを抽出する。それは不定形の特定部分が不自然に強調された、奇妙な「うつ病」となっている。
そして法廷とは閉鎖空間ではない。判例は社会に示された行動指針という性質を持ち、したがって法のうつ病論を、医は無視することはできない。法廷という異界でそれぞれの目的に合わせて改造され、判決文として社会に戻されたうつ病は、鵺の如き奇態なものと化しているが、それもまたうつ病であると、精神医学は認めなければならない。
一方、精神医学にも目的がある。治療? 確かにそれが一義的であるが、そこから派生した手段はしばしば目的と化する。薬の販売のための病気概念の拡大。新たな治療法適用のための病気概念の改変。研究の客観性担保のための病気概念の単純化。病気は医学の縄張りだと医学者は無邪気に信じているが、医学界で日常的に行われている営みは、別の世界から見れば異界の所業であって、現代のうつ病概念は異様な外観を呈しているばかりではなく、異臭さえ放っているのかもしれない。
法という異界からの逆光は、そんな医の現状を映し出す。異界のうつ病論たる判例から、刑事・民事あわせて22件を厳選し医の立場から論じた本書は、法と医の両方の実務に資することを目指して著したものであるが、同時に混乱の渦中にある現代精神医学のうつ病論を見直し、修正への道標を示さんとしたものでもある。
(村松太郎、2017.5.30.)
金銭報酬によるintentional bindingの事後的修飾作用に関する研究
高畑圭輔 (国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 脳機能イメージング研究部 研究員)It’s Not My Fault: Postdictive Modulation of Intentional Binding by Monetary Gains and Losses
Takahata K, Takahashi H, Maeda T, Umeda S Suhara T, Mimura M, Kato M.
PLos One 2012: 7(12): E53421
随意運動の「随意」が何を意味するのかは、なかなか難しい問題である。例えば、「腕を上に動かした」という行為の事実と、「腕が上に移動した」という物理的事実とは決してイコールではない。ある哲学者は、“What is left over if I subtract the fact that my arm goes up from the fact that I raise my arm?” という問いを立てた (Wittgenstein, 1953) 。この問いに対して、現代認知科学は、「腕を持ち上げようとする意図」(intention)と、「自らが腕が上に上がったことの起因主体であるという体験」 (sense of agency) という2つの体験要素であるという一応の解答を与えている (Haggard et al., 2005)。随意運動の主観性を構成するとされる、これら2つの体験要素は精神医学においても非常に重要な概念である。例えば、「他人の手徴候」と呼ばれる症候をintentionの障害と捉える立場や、統合失調症における自我障害の中核的要素がsense of agency の障害であるとする仮説もある。こうした背景から、運動意図(Will)及びsense of agencyに対する心理実験が数多くなされてきた。
まず、随意運動におけるintentionに関する古典的知見としては、Benjamin Libetが行なった有名な実験がある(Libet et al., 1983)。Libetは、2560ミリ秒で回転する時計を見せながら、被験者に運動意図が意識に上った瞬間にボタンを押すという随意運動を行わせると同時に脳波を記録した。さらに、運動意図が意識に上ったタイミング(W)とボタンを押したタイミング(M)を、時計の針の位置によって答えさせた。実験の結果、運動意図が生じる以前に、既に脳内では無意識的な神経活動(readiness potential)が開始していることが示された。この結果をどのように解釈するかについては、大きな議論がなされたが、Libetの結果自体は複数の実験で再現されており(Haggard et al.,1999;Susan Pocket et al.,2007)、概ね正しいものとみなされている。そして、現在では運動意図は脳が作り出した錯覚に過ぎないとするラディカルな仮説まで提唱されている(Wagner DM, 2003)
一方、Sense of agencyについては、1965年に通称alien hand実験と呼ばれる随意運動に関する古典的な研究 (Nielsen et al, 1965)がなされたのが端緒であり、以後この手法が様々な形に修正されてsense of agencyの検討に用いられてきた。Nielsenのalien hand実験及びその変法は非常に巧妙な手法である。しかし、sense of agencyという体験について明示的に(explicit)に質問を行うという点で被験者のバイアスがかかりやすく、より定量的かつimplicitな指標が求められていた。そこで、2002年にロンドン大学のPatrick Haggardは、上述のLibetの手法を改変することにより、sense of agencyをimplicitに定量評価する手法を確立した(Haggard et al., 2002)。この実験では、Libetと同様に被験者に2560ミリ秒で回転する時計を見せる。そして、被験者に運動意図(will)が意識に上った瞬間にボタンを押すという随意運動(action)を行わせる。すると、ボタンが押された250ミリ秒後に短いbeep音(effect)が鳴る。最後に、時計の針の位置で「ボタンを押したタイミング(action)」と「beep音が鳴ったタイミング(effect)」を答えさせるという手順である。実験の結果、随意運動条件でのみ、actionとeffectの主観的な時間間隔が圧縮されるという現象を発見した。これは、intentional binding(またはaction-effect binding)と呼ばれる現象で、sense of agencyのimplicitな指標であるとみなされている(Moore et al. 2012)。
我々は、Haggardの実験結果を詳細に検証する過程で、intentional bindingの強度が随意運動(action)によってもたらされる結果(effect)によって事後的に変化するのではないかという仮説を立てた。この仮説を検証するため、Haggardの課題を改変し健常者を対象に実験を行なった。随意運動(action)の部分はHaggardの条件と同一であるが、行為の結果(effect)に対して+500円(positive条件)、+0円(neural条件)、-500円(negative条件)と情動価を割り振り、オペラント条件付けを行なった。実験の結果、negative条件ではintentional bindingが弱まることを発見し、仮説が正しいことを確認した。Intentional bindingをsense of agencyの指標とみなせば、我々が得た結果は、行為の結果によってsense of agencyが事後的に修飾され得ることを示している。また我々の結果は、健常者がネガティブな出来事の原因帰属を他者に向ける傾向(自己奉仕バイアス)とも一致しており、その背景にsense of agencyの情動による事後的修飾が関与しているのではないかと考え、これらの結果および考察を本論文として報告した。なお、著者としては、今回の結果をもってagencyが錯覚であるという主張を行う気は全くなく、むしろ事後的に柔軟に変化するagencyの弾力性こそが、心の健康に関わっていると考えている。
なお、うつ病患者では、自己奉仕バイアスとは逆に、本来自らと関係のないネガティブな事象を自己に過剰に帰属させる傾向を持つ。これは、self-blaming bias あるいはdepressive realismと呼ばれる。うつ病患者のこうした心理学的傾向も我々の課題によって定量評価ができるのではないかと考え、うつ病患者を対象にした研究も行なっており、近々その結果を発表する予定である。
最後になるが、本研究は故加藤元一郎教授と前田貴記先生の全面的指導によってなされた。惜しむらくも2015年3月に亡くなられた加藤元一郎先生に対して、本解説でもって深い感謝の意を捧げたい。
(高畑圭輔、2017.4.21.)
遠隔操作ロボットの研究開発におけるSense of Agencyの重要性
前田貴記 (慶應義塾大学医学部精神神経科講師)Strength of Intentional Effort Enhances the Sense of Agency
Minohara R, Wen W, Hamasaki S, Maeda T, Kato M, Yamakawa H, Yamashita A, Asama H.
Frontiers in Psychology August 2016 Vol. 7 Article 1165
本論文は、東京大学工学部精密工学科の淺間一教授のグループとの共同研究で、筆頭著者の簑原凜君は修士課程の大学院生である。淺間教授はロボット工学の専門家で、特に人の生活を豊かにするためのサービス・ロボティクスがご専門である(介護支援ロボット、遠隔操作ロボットを用いての災害レスキュー、原発廃炉処理ロボットの研究開発など)。ロボットの遠隔操作において、その“操作性”を高める上で、Sense of Agency(以下SoA)は極めて重要な感覚であるが、特に巨大重機の操縦や繊細な作業を必要とするようなロボットの遠隔操作においては、タイムラグが500msec以上あったり、さらにそのタイムラグに揺らぎがあると、SoAが減弱し操作性は急激に低下してしまう。タイムラグやその揺らぎが全くないロボットを製作することは技術的に困難であるため、そのような制約条件のもとでも、SoAを強めることにより、遠隔操作における操作性を向上させるための基礎研究を進めている。
本論文では、Sense of Agency Task (Keio method)において、ボタン操作の際に必要な力の異なる3条件を用意することで(0.10N, 0.65N, 2.70Nの3種類)、タスクに臨む被験者の“エフォート”を変化させるという実験設定となっている。SoA判断に迷うようなあいまい条件では、よりエフォートを要する条件の方がSoAが強まることを示した。簡単に言えば、ロボットの遠隔操作において、操作者のエフォートを要する機器の方がSoAが強まり、操作性が高まるということである。これは、ロボット遠隔操作という極めて繊細な世界においては、極めて重要な知見である。今後、我々の生活において益々ロボットが導入されてくると思われるが、淺間教授らと伴に、SoAという観点から、遠隔操作ロボットの技術開発を進め、人の安全・安心な生活、そして豊かな生活に貢献できればと考えている。
なお、本論文の精神医学における意義について述べると、自我障害としてのSoA異常を来たしている統合失調症において、SoAに影響しうる諸条件が明らかになることは、SoA異常に対する治療・リハビリテーションにおいて、重要な示唆を得ることになろうかと思う。例えば、統合失調症においては、或る一群や或る条件下においてSoAが過剰に体験されていることが示されているが(Maeda et al., 2012; 2013, Koreki et al., 2015)、患者さんにエフォートを敢えて控えさせることでSoA異常を調律するという治療・リハビリテーション戦略も成り立つのではないかと考えている。
我々の、もう一つの射程として、今後、遠隔診療において遠隔操作ロボットも導入されてくるであろうが、ロボットを介しての遠隔精神療法についての基礎研究とすることも目指している。
(前田貴記、2017.3.28.)
解説 一体感への希求
手に持つ単純な武器でもいい。工具でもいい。楽器でもいい。あるいは自転車や自動車でもいい。人間は道具とともに歩んで来た。道具を作り、使うことで、人間は社会を作り、歴史を作って来た。そして優れた道具の条件は、人間と一体感が感じられることである。手になじむ。血が通う。体の一部になる。道具についてのこうした言語表現は、Sense of Agency (自己が行為の作用主体agentであるという意識)やSense of Ownership (身体・行為などが自分のものであるという意識)が、スムースな道具使用に不可欠であることを反映している。多くの人にとって最も身近な「道具」がPCになった現代もそれは同様である。近未来での汎用が予感されるロボットにおいては、SoAやSoOの重要性はさらに大きくなるであろう。
前田講師が東大工学部と共同で行った本研究は、そんな近未来を見つめた仕事である。一定の条件下においては、よりエフォート(努力)を要する条件の方がSoAが強まるという結果は、日常感覚的にも納得できるとともに、操作性とは楽なら楽なほどいいというわけではないことを再認識させられるという点で、きわめて示唆的である。努力というものを全く必要としない世界では、人間はSoAを失い、同時に生き甲斐も失うのであろう。さらには、どの程度の努力がSoA的には至適なのか、そしてその至適な努力量は、時代や文化によって変化するのかというのも興味あるところである。
そうした哲学的思索以前に、本論文の現実的な意義は大きく広い。研究を主導された東大工学部グループが専門とする災害ロボット、介護ロボット等の操作性向上は現代社会の喫緊の課題であるし、医学の領域でもすぐ目の前に来ている遠隔診療ロボット開発においても必須の基礎データになるであろう。
一体感という言葉は、その源である自分が一つのまとまりある存在であることが大前提であることは言うまでもない。この大前提が崩れるのが統合失調症であり、Sense of Agency Task(Keio method)はこの病の研究のために開発されたものである(本サイト 2014年3月 「統合失調症の自我障害についての実証的研究」参照)。ロボット研究に貢献するという展開は、このツールが開発者のSoAから離脱し自律性を獲得したかの如く感があるが、その自律性は工学の世界で新たな知見を充填され、統合失調症のリハビリテーションに応用が期待される姿となって医学の世界に帰還している。人間にとってSoAは重要だが、画期的な発展や真の創造性はSoAの彼方にあるのかもしれない。
(村松太郎、2017.3.31.)
うつ病におけるノルエピネフリントランスポーター密度と機能の検討
森口翔 (慶應義塾大学医学部大学院博士課程)Norepinephrine Transporter in Major Depressive Disorder: A PET Study.
Moriguchi S, Yamada M, Takano H, Nagashima T, Takahata K, Yokokawa K, Ito T, Ishii T, Kimura Y, Zhang MR, Mimura M, Suhara T.
Am J Psychiatry. 2017 Jan 1;174(1):36-41
これまで、うつ病の病態生理に、脳内神経伝達物質の1つであるノルエピネフリンの関与がセロトニンと並んで指摘されてきた。うつ病患者の死後脳では、脳の青斑核においてノルエピネフリンを再取り込みする機能のあるノルエピネフリントランスポーター(NET)密度が変化していることや、ノルエピネフリン放出を調節していると考えられているα2A-アドレナリン受容体密度が変化していることが報告されている。これらの研究やNETを標的としたデュロキセチンやミルナシプランといった抗うつ薬が精神科の臨床で広く使われていることから、うつ病の病態生理にノルエピネフリンが重要な役割を果たしていることが示唆されている。
しかし、これまでうつ病の生体においてNET密度やその機能を検討した研究はなく、多様なうつ病の病態においてノルエピネフリンがどのように関わっているかは不明であった。そこで本研究では、うつ病患者の脳におけるノルエピネフリン神経伝達機能を調べるため、生体の脳におけるNET密度を評価し、またノルエピネフリンが注意・覚醒などの機能に作用することに着目し、うつ病患者の認知機能の変化との関連を明らかにすることを目的とし研究を行った。
うつ病患者19名、健常者19名を対象に 脳内のNETに結合する(S,S)-[18F]FMeNER-D2という薬剤を用いてPET検査を行った。患者と健常者でこれらの定量値を比較したところ、患者の視床のNET密度が健常者よりも29%高いことが判明した。さらに、視床内部を機能的に異なる7つの領域に分割して、それぞれの領域のNETの密度を評価した。その結果、前頭葉と線維連絡を持つ領域において、患者のNET密度が28.2%高いことが明らかとなった。次に、患者のNET密度と注意機能との関連を検討するために注意機能検査を実施し、患者のNET密度と注意機能との相関解析を行った。その結果、視覚性注意を調べる検査(Trail Making Test A)において、患者の 視床のNET密度が高いほど、反応時間が速く、視覚的探索機能が高いことが明らかになった。これは、うつ病患者においては注意・覚醒機能はむしろ高まっており、その変化とノルエピネフリンシステムが関連していることを示唆している。
うつ病患者においてNET密度の異常増加 が示唆されたことは、うつ病治療ではノルエピネフリン神経伝達機能の調整が有効であることを示しており、今後、多様な症状が現れるうつ病の治療において、脳内の異常を想定した効果的な抗うつ薬の選択と治療戦略につながることが期待される。
(森口 翔、2017.2.20.)
解説 うつ病のPET研究を究める
うつ病という今や人類にとっての大問題となった疾患とPETという日進月歩のテクノロジー。この二つを組合せようというのは誰もが持つ発想で、現にうつ病のPET研究論文は増え続けている。だがそれは、「うつ病」という疾患に「PET」という検査を施行して、得られた「画像」を見れば何かわかるといった単純なものではない。そうした単純な発想で進められた研究は、うつ病について発生している混乱をさらに攪拌し破壊に向かわせるばかりである。
第一に、うつ病とは何かという問題がある。現代においてうつ病と呼ばれているものは、生物学的には雑多な疾患の集合体であり、それは診断基準をいくら厳密に用いても解決しない。しかも時として無節操になされている投薬が混乱に拍車をかけている。こうした問題をクリアして初めて、うつ病についての有意義なデータを得ることができる。
森口大学院生の本研究は、うつ病研究において最重要な、対象者の厳選という出発点に細心の注意が払われている。まず大前提としてのDSM診断をするのは当然として、19名中16名は抗うつ薬服用歴なし、3名は少なくとも2年間は服用なしのうつ病患者である。脳内の神経伝達物質研究においては抗うつ薬の影響のない患者を対象とすることがデータの純粋性のためには必須とはいえ、こうした患者をリクルートするのは非常に困難なことである。さらには大部分にあたる17名はMINIでメランコリー型の基準を満たすことで、現実的に可能な範囲でうつ病としての均質性を高めている。
結果は森口院生の解説文の通りで、視床のノルエピネフリントランスポーター密度について、そして注意機能との関連について、うつ病解明のための将来の研究に繋がる貴重なデータが得られている。
PETについては、結果として得られた画像の解釈が重大な問題を内在している。美しい一枚の写真を呈示され解説されると説得力は抜群で、その写真さえ見れば重要な知見が読み取れるかのように錯覚しがちであるが、PETを初めとする脳機能画像は統計的処理を駆使したいわばヴァーチャルな絵にすぎず、正しく解釈するためには絵の作成過程についての深い理解が必須である。
すなわちうつ病のPET研究は、
対象である「うつ病」とは、いったい何を見ているのか。
方法である「PET」とは、いったい何を見ているのか。
という、きわめて重要な二つの問題がある。
だが逆に言えば、この二つの問題をクリアすれば、うつ病のPET研究によって無限の新世界が開けることが大いに期待できる。
森口院生は本論文完成の後まもなくトロントの Research Imaging Centre, Centre for Addiction and Mental Health, Canada に留学し、うつ病におけるさらに高度で有意義なPETイメージング研究を追究している。
(村松太郎、2017.2.28.)
うつ病の気質、性格と治療効果: 6か月間前向き予備研究
工藤由佳 (慶應義塾大学医学部大学院博士課程、群馬病院)Kudo Y, Nakagawa A, Wake T, Ichikawa N, Kurata C, Nakahara M, Nojima T, Mimura M.
Temperament, personality, and treatment outcome in major depression: a 6-month preliminary prospective study.
Neuropsychiatric Disease and Treatment 2016; 13: 17-24.
うつ病は、発症契機、症状、経過、転帰に渡り、実に様々である。薬物療法が治療の中心であり、それだけで回復する人もいるが、再発も多く、寛解に至らない人もいる。長期的な回復を目指すには、自分の特徴を理解し、同じパターンに陥らないようにする精神・心理療法を行うことが重要になるが、そのためには、患者がどのようなタイプかを見極めなければいけない。しかし、これまでに提唱されてきたうつ病の分類には、治療選択を意識したものがほとんどなかった。
そこでGordon Parkerらは、非メランコリー性のうつ病に多く見られる気質と性格傾向に注目し、それぞれの気質と性格傾向に応じた精神・心理療法的アプローチを提案した。彼らは、The Temperament and Personality Questionnaire (T&P)を作成し、うつ病に多く見られる気質と性格傾向として、不安が強い、人に内面を見せない、完璧主義、易刺激性、社交回避、拒絶に敏感、自己批判的、自己中心的の8つを見出した。
我々は、日本語版T&Pを作成し、信頼性、妥当性を評価する研究を行い、臨床使用可能な尺度であるとして報告した(Kudo et al, 2016)。今回は、日本語版T&Pを使って、それぞれの気質と性格傾向を有した患者がどのような転帰をたどるかを観察する前向き研究を行った。
対象は慶應義塾大学病院と群馬病院のうつ病外来で治療を受けた20~75歳の非メランコリー性のうつ病患者51名。ベースラインでT&Pを行い、ベースラインと6ヶ月後にうつ病重症度の尺度であるハミルトンうつ病評価尺度を行った。
寛解するかしないかにT&Pの各傾向の点数がどの程度寄与するかを調べるため、6ヶ月後に寛解した患者(ハミルトンうつ病評価尺度≦7, n=23)と寛解に至っていない患者(n=28)を分け、T&Pの点数を比較した。結果は、寛解に至っていない患者の方が、人に内面を見せない、拒絶に敏感、自己批判的傾向で高い点数であった。ベースラインのハミルトンうつ病評価尺度を調整したロジスティック回帰分析では、寛解/非寛解に影響を与えたのは、人に内面を見せない傾向のみという結果であった。
今回の研究では、治療転帰不良を予測するのは、人に内面を見せない傾向であった。人に内面を見せない傾向を持つ患者は、自分の内面を人に語ることが苦手であるため、精神・心理療法でもセラピストに対し、自分の内面を語ることが難しい場合が多く、そのことが治療転帰不良と関係している可能性がある。今後は、人に内面を見せない傾向を持った患者に対して、Gordon Parkerらが提案している、対人関係スキル教育や不安へのアプローチなどを診療の中に取り入れ、彼らの回復を援助できればと考えている。
(工藤由佳、2017.1.26.)
解説 精神科医に治療意欲を問う
「メランコリー性うつ病には生物学的治療(薬物療法、電気けいれん療法)が有効」は、精神医学においてかなり確立している命題である。
これに対比するのは「非メランコリー性うつ病には非生物学的治療が有効」であるはずだが、こちらの方は確立されているとは到底言い難い。確立どころか、検証の対象として述べられること自体が少ない。現代の精神科臨床ではむしろ非メランコリー性うつ病の受診者の方が数としては多いにもかかわらず、これはどうしたことか。一つ大きな理由は、非メランコリー性うつ病と呼ばれているものの中に多種多様なものが含まれていて、一つのカテゴリーとみなすことに大きな無理があるからである。
そこでオーストラリアのGordon Parkerらが提唱しているのが、気質と性格に基づくディメンジョナルな表現である。彼らのいう気質temperamentとは遺伝で規定されたもの、性格personalityとはそこに環境等の因子が加わって形成されたものを指している。彼らによるT&Pの日本語版を作成し、信頼性と妥当性を検証するという丁寧な作業を経て 工藤大学院生が着手した前向き研究の最初の成果が本論文である。
精神医学の50年を振り返ると、DSM、ICDが改訂を繰り返されることによって、精神障害の分類は発展を続けている。しかし治療法が分類と乖離しているのが現状である。治療という観点を無視した表面的なカテゴリー分類がなされているというもっともな批判もある。精神科医には分類意欲はあっても治療意欲がないのか。
工藤院生は、まず非メランコリー性うつ病という一群をカテゴリーとして抽出し、気質と性格というディメンジョナルな観点から転帰を調査した。うつ病についての臨床知見の実情にあわせてカテゴリーとディメンジョンをハイブリッドしたこの秀逸な研究デザインによって、治療計画に直結する貴重なデータを得ることに成功している。この優れて臨床的な研究を学位論文とした工藤院生が、これからの研究において、うつ病の治療についてのさらに新たな知見を重ねていくことが期待される。
(村松太郎、2017.1.31.)
眼窩部皮質と脳梁膝直下帯状回の損傷にて治療抵抗性うつ病が消失した例
船山道隆 (足利赤十字病院神経精神科 部長)Funayama M, Kato M, Mimura M.
Disappearance of treatment-resistant depression after damage to the orbitofrontal cortex and subgenual cingulated area: a case study.
BMC Neurology (2016) 16: 198
【報告の目的】脳卒中後うつ病post stroke depressionはよく知られた概念であるが、病前のうつ病がどのように変化するかという報告は極めて少ない。脳損傷後のうつ病の変化を調べることで、うつ病のメカニズムが明らかにできる可能性がある。
【症例の概要】本例は55歳発症の治療抵抗性うつ病のケースである。義父の介護が不十分であったと自責的に後悔したことをきっかけにうつ病が発症、3環系抗うつ薬やSNRIを長期に使用したものの発症後14年間うつ病が改善しなかった。うつ病の中でもTellenbachのいうメランコリー型であり、他者のために自分を犠牲にしがちであり、過剰な責任感や計画性を持ち合わせ、過去の出来事を過度に後悔していた。
69歳時に前交通動脈瘤破裂によるくも膜下出血を罹患した。重症度はHunt and Hess分類の3度であり、クリッピング術を行った。脳実質の損傷部位は眼窩部皮質と脳梁膝直下帯状回であった。患者は発症2ヶ月後には退院し、6ヶ月後には自立した生活を送れるまで改善した。各種神経心理検査では知能、記憶、遂行機能ともに明らかな低下は認めず、アパシーも認めなかった。一方でくも膜下出血直前にも自殺念慮を伴う重度のうつ状態であったが、くも膜下出血直後からうつ病が消失した。過剰な責任感や計画性はなくなり、適度となった。過去の出来事を後悔することもなくなった。その後81歳で亡くなるまで12年間うつ病は再発しなかった。
【本例からの示唆】損傷部位である眼窩部皮質と脳梁膝直下帯状回は、うつ病の消失に影響を与えたものと考えられる。Camille et al 2004は眼窩部皮質が「後悔」の感情と関連が深いと述べているが、本例は眼窩部皮質の損傷後に後悔することがなくなっている。脳梁膝直下帯状回は、治療抵抗性うつ病に対してMaybergらが行っている深部電気刺激のターゲット部位である。彼女らはこの部位が治療抵抗性うつ病では代謝が亢進しているため、深部電気刺激によって代謝を抑制することが深部電気刺激治療の根拠であると述べている。このように、本例のうつ病が消失した経過は神経心理学的にも脳生理学的にも矛盾しない。本報告はあくまでもケースレポートであるが、うつ病のメカニズムにひとつの示唆を与える可能性がある。
(船山道隆、2016.12.1.)
解説 逆にたどる真実
損傷が先で症状が後だ。
次に観察が来る。症状の綿密な観察。損傷部位の正確な同定。そして似た損傷部位、似た症状の多数例の観察。さらには他部位損傷例の観察による二重解離の証明を経て、脳の特定部位と特定症状の関連性が確立する。この営みが数限りない回数繰り返され、脳機能の局在が明らかにされていく。これがBroca以来の神経心理学の歴史である。そして20世紀末に脳機能画像というテクノロジーが導入されてから、脳機能のマッピングは精緻化が急速に進行している。機能局在という意味では、脳の全貌の解明はすぐ手の届くところにあるとさえ感じられる時代になった。
だがこの方法論ではどうしても到達できそうにない疾患がある。
内因性の精神障害である。
もちろん脳の局在損傷によって、内因性の精神障害に似た症状が現れることは多数報告されている。しかしそれは似てはいても非なる症状である。たとえば統合失調症様(Schizophrenia-like) と統合失調症(Schizophrenia)は、症状を「幻覚」「妄想」という単語に矮小化してしまえば差異は見えなくなるが、疾患の本質にかかわるレベルにおいては両者は全く異質のものである。
一方、うつ病では事情が異なるようにも思える。たとえばpoststroke depressionは、”depression” であって “depression-like” ではない。脳損傷によって、確かにdepressionは現れる。
だがこれはdepressionという用語の多義性に起因するトリックである。
英語の ”depression” と日本語の「うつ病」の意味の違いはこの際措くとしても、うつ病depressionという語はあまりに多種多様の状態を包含しており、もはや「うつ病」とひとまとめにして研究の対象にした瞬間から結果の無意味さが見えるといった状況になっている。
だが内因性うつ病は別だ。Tellenbachをはじめとする慧眼によって見出された内因性うつ病は、うつ病depressionの理念型Idealtypusとしての地位を現在もなお維持し続けている。
そしてこの内因性うつ病は、脳損傷による巣症状として現れることは皆無と言ってよい。それは内因性精神障害の病理の深さ・複雑さの証であるといえばその通りであるが、脳機能との関連を具体的に見出せないことが、内因性精神障害の病態解明の、そして治療開発の進歩を阻んでいるのもまた事実である。
船山部長の本研究は、この状況を大きく打開する端緒になる画期的な論文である。14年間治療抵抗性の内因性うつ病であった患者が、前交通動脈瘤破裂によるくも膜下出血を機に突然完全寛解した。この論文に報告されている事実はこれのみであり、症状が先で損傷が後という点を除けば、シンプルな一例報告にすぎない。だがそこにあるメッセージは歴史的な重みを持っている。すなわちこの論文は、古来から内因とされていた「何か」が脳内にあることの証明になっているのである。
歴史的課題の証明は、直ちに近未来の扉を開く。それは内因性精神障害の根治療法の開発である。
うつ病に限らず、難治性の精神疾患においては、脳に直接介入する手法が画期的な治療法として期待されている。その実現にあたっては技術的にも倫理的にも解決しなければならない様々な障壁があるが、「内因」が脳内にあること、そしてある程度までは局在することの証明がなければ、脳への介入はその出発点において根拠が失われる。本研究の症例の損傷部位である脳梁膝直下帯状回は、Maybergらの治療抵抗性うつ病の治療としての脳深部刺激Deep Brain Stimulationターゲット部位に一致しており、本論文は彼女らの治療の正当性を側面から支持するものであると言える。
損傷が先で症状が後に来るのが臨床の常識であるが、それを逆にたどった船山部長の研究は、今まで姿を隠していた内因性うつ病の真実に接近している。そしてその先には治療という光が見えている。
(村松太郎、2016.12.31.)
精神医学におけるスペクトラムの思想 学樹書院 2016年11月出版
責任編集 村井俊哉+村松太郎
解説 精神科診断学の哲学論稿集
今どき希有で貴重な硬派の出版社である学樹書院の重厚なMOOK、<<精神医学の基盤>>の第3巻として出版されたのが本書である。このシリーズ、”Power MOOK” という名にふさわしい力のこもった本がすでに2冊出版されているが(「薬物療法を精神病理学的視点から考える」と「うつ病診療の論理と倫理」)、本書もこれらに並ぶpowerfulなもので、京都大学の村井教授のまえがきに記されている通り「精神科診断学の哲学論稿集」と冠されるにふさわしい仕上がりになっている。
診断とは精神科に限らずカテゴリー的に定義されるのが通例であるが、いまだ本態不明の精神疾患をクリアにカテゴリー分類することには深刻な矛盾が内在していることは否定し難い。そこで近年では「自閉症スペクトラム」「統合失調症スペクトラム」のように、連続的に捉えようという「思想」が優勢になって来ている。タイトルの「精神医学におけるスペクトラムの思想」はそんな現代の状況を指している。
精神の病というものを真摯に見つめれば、マニュアルや評価スケールはそのごくごく限られた一面との接点しか有しておらず、病の表面にある薄皮をなぞっているにすぎない。病の真実に接近するためにはいわば哲学的ともいえる論考が必須である。それを深く理解している執筆陣の熱意が本書に結晶している。
当教室関係者は以下の項に登場している。
■対談 精神医学におけるスペクトラムの思想 村井俊哉/村松太郎
本書のテーマをめぐる、お茶の水の学士会館での対談である。印刷された記録を読むと対等の議論が展開しているような雰囲気が流れているが、実際の対談場面では村井教授の深い学識に感心させられるばかりであった。
■統合失調症におけるスペクトラムというメタファーの導入の意義と問題点
前田貴記/沖村宰/野原博
統合失調症の診断という、精神医学の根底に流れる大問題について新たな光を当てた力作。スペクトラムというと「連続」とイメージされることが多いが、本来的にはそれは不正確な捉え方であって、事物をある軸にそって並べ直したときに立ち現れたものこそがスペクトラムである。このような本質論に立脚して進める論はいかにも前田講師らしく迫力に溢れたものになっている。
■カテゴリー/デイメンジョンと精神鑑定 村松太郎
刑事事件・民事事件を問わず、法廷では精神疾患をかなり強引な手法でカテゴライズすることがしばしば見られている。それは、その場で善悪や勝ち負けの結論を出さなければならないという法的争いの性質に鑑みれば目的にかなっていると見ることも可能だが、精神医学の立場からはいかにも恣意的・非科学的な手法という感が免れない。しかし振り返ってみれば、精神医学界で行われている診断分類についても、実は水面下には同様の問題が潜んでいるのではないか。治療や、研究や、時には商売といった目的論によって、科学を、そして事実をも無視した恣意的なカテゴリー化がなされているのではないか。法廷という異界から精神医学を照射した論考である。
■スペクトラムの概念から考える精神科薬物療法 冨田真幸
スペクトラム概念の拡大は過剰診断の拡大につながりさらには過剰な薬物療法につながるという、現代の精神医療で進行しつつある問題に厳しい警鐘を鳴らしている。診断論が中心の本書にあって、診断の先にあるステップであり、かつ、医療で最も重要な目的である「治療」をテーマにした貴重な作品である。
■高次脳機能障害、特に前頭葉機能を抑制障害として捉える 鹿島晴雄
神経心理研究室の創始者である鹿島教授による巻頭エッセイである。神経心理学についての鹿島教授の思索の骨子が3ページに凝縮している。
(村松太郎、2016.11.30.)
インターネット依存の概念と治療
Muhammad ElSalhy (慶應義塾大学医学部大学院博士課程)
BRAIN and NERVE ----- 神経研究の進歩 2016年10月号
ムハンマド・エルサルヒ、村松太郎、樋口進、三村 將
本稿ではインターネット依存の定義から症状など細かい内容に加え、なぜインターネットに依存してしまうのか、その治療方法についてまとめた。
Ⅰ インターネット依存の概念
インターネット依存の定義だが、現状まだ統一されていない。今のところ、「インターネット使用の過剰あるいはコントロール困難なとらわれ促迫・行動で、結果として障害や苦悩が発生する」とされている。
インターネット依存は行動嗜癖の一種である。症状としては、Salience(オンライン活動が人生の最大の重要事項となり、他の思考・感情・行動を圧倒してしまう)や耐性(インターネット使用の時間、質などが増えてしまう)などの構成要素が当てはまる。
インターネット依存のリスクファクターとして、
①年齢と性別
②精神疾患
③欲望モデル
④家族内のコミュニケーションや家族機能の不全
⑤性格傾向
などが挙げられる。
Ⅱ ゲーム依存とSNS依存
インターネット依存のタイプとして、大きくゲーム依存とSNS依存のカテゴリーが挙げられる。
1.ゲーム依存
1990年代から現れたオンラインゲームはパソコン、ノートパソコン、スマートフォン、ポータブル ゲーム機など、様々な機械を通して、インターネット環境でさえあれば、どこからでもアクセスできるゲームであり、同時にたくさんの参加者がリアルタイムでコミュニケーションしながら、争う・協力するなどしつつゲームが進められていくもので、終了時点というものが存在しない。また、一人でできるタスクもあれば、チームで協力しなければならないタスクもあり、ソーシャルな要素がある点がオンラインゲームとオフラインゲームの最大の違いであるとも言える。このため、多くの人々にとってオンラインゲームの方が楽しく満足感が高く、そのため実生活を浸食するという結果になっている。
2.SNS依存
SNS (ソーシャルネットワークサイト)とは、現実の友人や見知らぬ人とコミュニケーションするバーチャルコミュニティを指す。 SNS依存で最も問題になっているSNSはFacebookである。オンラインゲームと違って、SNSは現実(オフライン)の友達との関係を維持するために使えるのが魅力だとされているが、時にはそのSNSを常に チェックしないとはみだし者になったり、周りのみんなについていけないと感じ、オンラインソーシャルネットワークに積極的に参加することに強いられるというパターンも少なくはない。
また、SNSでは、対面では言いにくいことも脱抑制的に言えるようになるため、友人関係の維持ではなく破壊につながることもしばしば認められている。
SNS依存には、SNS特有の原因もいくつかある。SNSは本質的に自己中心的な構造を有しているので、自己愛性格を満足させやすいという特性がその一つである。
Facebookが最も依存性が高いことの理由については仮説がいくつかあるが、他人と連絡できるだけでなく、電話、ゲームなどの様々な娯楽が内在しており、多様なモチベーションを満足させるという特性があるからという理由が根強い。
Ⅲ インターネット依存の予防・治療
インターネット依存に限らず、行動嗜癖の治療目標は「完全にやめる」ことではなく、使用のコントロールが目標になる。そして何より重要な最終目標は、本人の幸福である。依存に陥っている本人はインターネットをしている時が最も幸福だと思っているが、そもそもそれが本当に幸福であるかという問いを発する必要がある。
インターネット依存は、欲望が満たされることがないために、ずっとやり続けているのである。治療者の役割は本人にインターネットをやめるよう指示することではなく、本人とソーシャルネットワークやゲームについて、そしてなぜ彼らが依存に陥ったかを話し合うことである。
患者本人にとって重要なこととして、自身の強い点、弱い点、欲望についてよく知り、それらを踏まえた将来を考慮することも挙げられる。こうしたことによって本人とともに幸福を追求していくことこそが治療者の役割と言える。
適切なゲームを、適切な時間だけ行うのであれば、ポジティブな点はいくつもある。たとえば自尊心を高めたり、反射神経、反応時間、記憶力、論理的思考、戦略的思考、社交的スキル、コミュニケーションスキルなどを改善することができる。
(ムハンマド・エルサルヒ、 2016.10.10.)
解説 時を超え空間を超え
エジプトからの留学生であるムハンマド・エルサルヒ院生(Dr. Muhammad ElSalhy)は、アレキサンドリア大学医学部卒の医師である。流暢に日本語を話し、読み、書く。上記の紹介文もすべて彼が一人で書いたもので、日本人の手は一切加わっていない。ムハンマド院生はもちろん英語もできるし、ドイツ語もできる。母国語はアラビア語である。
そんな国際人そのものの彼の大学院での研究テーマは、インターネット依存の国際比較である。『インターネット依存の概念と治療』と題された本論文は『BRAIN AND NERVE --- 神経研究の進歩』の特集「アディクション ----- 行動の嗜癖として」に収載されている。もちろんすべて日本語で書かれている。
ムハンマド院生の上記第一文に記されている通り、インターネット依存にはまだ定義がない。それどころか、存在そのものさえ公式には認知されていない。2013年に出版されたDSM-5の「物質関連障害および嗜癖性障害群 Substance-Related and Addictive Disorders」の下位項目に「非物質性障害群 Non-Substance-Related Disorders」があるが、そこにはインターネットに関連する障害はない。DSM-5で唯一記載があるのは、付録的位置づけであるSection Ⅲの「4 今後の研究のための病態」の「インターネットゲーム障害 Internet Gaming Disorder」のみである。
しかし実際には、インターネットの急速な普及に伴い、インターネット依存は各国で深刻な問題になっている。そしてそれは、文化によって、ゲームよりむしろSNS依存が中心になるなど、様々な形を取る。ここでいう文化とは、インターネット環境を含む。たとえば通信速度の違いが依存形態に大きく影響する。一例を挙げれば、アクションゲームへの依存は、通信速度が一定以上に速い環境の国ではじめて成立する現象である。そしてインターネット環境とは、テクノロジーの進歩に伴い、また、各国の政治経済的事情により、刻々と変化していく。
DSM-5が如何なる扱いをしているかにかかわらず、インターネット依存は「行動嗜癖」の一つに位置づけられる病態である。行動嗜癖の脳科学がいま大いに注目されていることは、今回のBRAIN AND NERVE誌が特集として取り上げていることにも如実に表れている。
このように、インターネット依存の研究では、脳機能から文化歴史まで広大な領域を視野に入れることが求められる。それはムハンマド院生のような真の国際人にしてはじめて可能になるものである。彼が現在拠点を置くアジア、そしてホームグラウンドである中東・アフリカ、さらには西欧までの地球規模の空間に目を向け、また各国の環境の時間的変化を精密に把握しつつ進めているムハンマド・エルサルヒ院生の研究の大成が期待されるところである。
(村松太郎、 2016.10.29.)
有名人の顔が含まれる社会的出来事写真を用いた遠隔記憶検査作成の試み
江口洋子 (慶應義塾大学医学部精神神経科研究員・心理士)・穴水幸子・斎藤文恵
認知リハビリテーション, 21(1), 5-20, 2016
江口洋子1)、穴水幸子2)、斎藤文恵、阿部晶子2)、松田博史1)、3)、三村 將、加藤元一郎
1)埼玉医科大学 国際医療センター
2)国際医療福祉大学 保健医療学部 言語聴覚学科
3)国立精神・神経医療研究センター 脳病態統合イメージングセンター
記憶障害は大別すると、発症後に新しいことが覚えられないという前向性健忘と、発症以前の過去のエピソードに関する記憶を思い出すことができないという逆向性健忘に分類される。逆向性健忘が生じると、過去の思い出を家族や友人と共有できなくなり、そのことが周囲の者に失望や喪失感、心理的な拒絶を生み出し、また患者自身も周囲のそのような態度に接し、不全感や自己の不確実感を感じることがある(先崎ら、1997)。また、脳外傷後に家族内で取り決めていたルールを忘れ、日常生活で問題が生じる場合もある(八木ら、2013)。
逆向性健忘に関して、客観的に、かつ平易に評価できることは、患者本人と周囲の者が症状の程度を共有し、日常生活で生ずる問題点を予測して事前に対応策を立てたり、今後の認知リハビリの方略を考案したりするためにも重要である。
本研究では、近年の社会的出来事に関する記憶について、臨床的に有用な検査を作成することを目的として、従来の視覚性遠隔記憶検査(江口ら, 1996)をもとにして検査可能な期間を延長した遠隔記憶検査を作成した。さらにその信頼性と妥当性についても検討したので報告する。
本研究では、20歳代~80歳代の健常被検者199名に対して、有名人の顔が含まれる1970年から2010年までに生じた社会的出来事写真31枚を見せ、有名人の①名前の再生、②名前の再認、③出来事に関するキーワードの回答を求め、世代別の各得点率を調べた。作成のための調査は、従来の対面で調査する方法に加えて、インターネットを用いて広範囲に居住する者から簡便にデータを収集する方式を採用した。
検査の信頼性は、検査-再検査法により得点率の級内相関係数(interclass correlation coefficient ; ICC)を算出した。結果、合計得点率の1回目は76.3%、2回目は82.2%で、ICCは0.87となり、強い相関を認めた(p < 0.01)。
次に本検査を脳損傷患者の臨床評価に用いることの妥当性を検討するために、健忘症例3例に本検査を実施した。その結果、本人や家族の聴取から得られた健忘症患者の逆向性健忘の様態を、本検査の結果からも説明できた。
以上のことから、本検査が逆向性健忘を示す客観性指標として有用であることを示唆できた。
検査の問題点と限界として、本検査の項目に対する個人の社会的出来事に関する暴露の差の存在と、項目を追加して改正し続けなければならないという作成上の問題が挙げられる。さらには、近年の生活様式の変化と多様性が社会的出来事の記銘におよぼす影響についても、今後の検査の更新時には考慮する必要がある。
(江口洋子、2016.9.27.)
解説 シジフォスの岩を運び上げる
高次脳機能の中で、記憶研究の歴史は古い。その理由は複合的だが、一つの大きな要因は記憶という機能の測定のし易さであろう。呈示された情報をどれだけ覚えられるかを調べる。この単純な再生・再認パターンの検査で、記憶はかなり定量的に測定可能である。
だが遠隔記憶についてはそうはいかない。
記憶検査が単純と言えるのは、再生・再認課題の内容が単純な場合である。遠隔記憶検査のそれは決して単純ではない。ある意味いかなる検査課題より複雑である。遠隔記憶検査課題の内容は過去に獲得した情報になるが、一人ひとりの被検者についての詳細な過去は知り得ないからである。そこで有名な社会的出来事のリストを課題にするのが定法となっているが、ニュース等への曝露の程度は被検者によって大きく異なるという性質上、標準化するまでには繊細な作業が必要になる。また、いったん精密に標準化しても、社会的出来事は日に日に更新されるから、検査は日に日に古くなる。遠隔記憶検査の作成とは、永遠に改正を繰り返さなければならないという点で、シジフォスの岩を思わせる仕事なのである。江口研究員はこの困難な仕事を1996年に行い、「視覚性遠隔記憶検査」として完成させたが、今回、新たに作成したのが本研究「有名人の顔が含まれる社会的出来事写真を用いた遠隔記憶検査作成の試み」で発表された検査である。
現代の記憶研究は、脳画像研究から遺伝子研究や動物研究と多分野を横断するものに発展しており、臨床研究ではこうした分野とのクロストークが益々重要になっている。そのためには障害を正確に反映した定量化が必須であるところ、江口研究員が長年不断に取り組んでいる遠隔記憶検査はまさにそれに合致しており、 広大な学問領域と交流するためのツールとしても限りない意義を有している。
ギリシア神話のシジフォスの岩は、山頂に達する直前で転がり落ちることを繰り返すことから、徒労の象徴とされる。しかし江口研究員らの遠隔記憶検査は、完成・論文化という山頂に達した。それは日に日に更新される運命にある山頂であるが、そこに達して初めて見える風景は限りなく広い。最大限の活用が期待されるところである。
(村松太郎、2016.9.29.)
【1】Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test(RDST-J)数字変換課題に関する検討
森山泰 (駒木野病院精神科診療部長)
Yasushi Moriyama, Aihide Yoshino, Taro Muramatsu, and Masaru Mimura
Detailed analysis of error patterns in the number transcoding task on the Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test (RDST-J)
Psychogeriatrics. 27 JUN 2016 | DOI: 10.1111/psyg.12207 [Epub ahead of print]
【2】Japanese version of The Rapid Dementia Screening Test (RDST-J) スーパーマーケット課題のcluster数,switch数に関する検討
森山泰 (駒木野病院精神科診療部長)
Yasushi Moriyama, Aihide Yoshino, Taro Muramatsu, and Masaru Mimura
Detailed analysis of the Supermarket task included on the Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test
Psychogeriatrics. 2016 Jun 30. doi: 10.1111/psyg.12209. [Epub ahead of print]
【1】Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test(RDST-J)数字変換課題に関する検討
Japanese version of the Rapid Dementia Screening Testに含まれる数字変換課題は,漢字表記とアラビア表記による数表現の相互変換課題で以下の4課題からなる:209→二百九,4054→四千五十四, 六百八十一→681,二千二十七→2027
軽症アルツハイマー病(Alzheimer’s disease: AD)の患者さんに本検査を施行していく中で681を60801,600801などと間違えることが多い臨床的印象を持った.すなわちこれは人類の偉大な発明の1つである“アラビア数字の位取り”に関する障害であり,そこに本疾患の認知障害の本質に近いものを感じ,その他の誤りを含めまとめたいと思ったのが本研究の動機である(なおアラビア数字は0から9までの10の数字で全ての数が表現できる位取り記数法である一方で,漢数字は桁を表す漢字が存在する混合型記数法である).
本研究ではADの重症,軽症群で,そのさまざまな誤りパターンの出現頻度が異なるかを検討した. 対象は250例で, MMSE12~26点, CDR 0.5~3である.誤りの分類はこれまで本邦で報告されているもの15個と,それ以外の従来報告されていない誤りの計19種とし,その出現頻度を,軽症AD群(CDR0.5~1)・重症AD群(CDR2~3)で統計学的に比較した. 誤りパターンは以下の19種である:
1)209→二百九課題
数字の誤り(例:209→三百九); 桁語の誤り(例:209→二千九); shift error(保続的誤り;例:209→二0百九); 簡略化した表記(郵便番号表記時の記載法;例:209→二〇九); 従来報告されていない誤り
2)4054→四千五十四課題
数字の誤り(例:4054→五千五十四); 桁語の誤り(例:4054→四百五十四); shift error(保続的誤り;例:4054→四0千五十四); 簡略化した表記(郵便番号表記時の記載法;例:4054→四〇五四); 従来報告されていない誤り
3)六百八十一→681課題
数字の誤り(例:六百八十一→781); 複数積み重ね表記(位取り表記の誤り;例:六百八十一→60801); shift error(保続的誤り;例:六百八十一→6百81); 1の誤り(181を“いっひゃくはちじゅういち”と読まないなど日本語では“1”に関する独特の法則がある;例:六百八十一→680); 従来報告されていない誤り
4)二千二十七→2027課題
数字の誤り(例:二千二十七→3027); 複数積み重ね表記(位取り表記の誤り例:二千二十七→20207); shift error(保続的誤り;例:二千二十七→20千27); 従来報告されていない誤り
“Shift error”,“桁語の誤り”,“数字の誤り”は操作的に2字までとし,それ以上の場合は“従来報告されていない誤り”に含めた. また“従来報告されていない誤り”以外は複数の誤り分類を認めた.
その結果, 重症AD群では4課題全ての“従来報告されていない誤り”の出現頻度が有意に多い一方で, 軽症AD群では4054→四千五十四課題の“桁語の誤り”, “簡略化した表記”の出現頻度が有意に多かった.その他の13の誤りでは出現頻度に有意差を認めなかった.
以上, 位取りの誤りはAD重・軽症群においてその出現頻度に統計的有意差を認めなかったが,ADの重・軽症群では出現頻度の異なる誤りパターンが存在することが示された.
【2】Japanese version of The Rapid Dementia Screening Test (RDST-J) スーパーマーケット課題のcluster数,switch数に関する検討
Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test (RDST-J)に含まれるスーパーマーケット課題は1分間の制限時間内に「スーパーマーケットで買えるもの」をできるだけいってもらう言語流暢性課題である. 本検査をおこなっていく上で健常群では「野菜,えっと白菜,キャベツ,トマト,ニンジン」といったようにまず上位概念を想起したあとに下位概念を想起する戦略をとるのに対し,軽度認知症の患者さんでは下位概念を想起しにくいといった臨床的印象をもった.文献を調べるうちにこれらをより詳細に調べるツールとしてTroyerらの定義するCluster・Switch数があることを知った.すなわち回答をClusterと呼ばれるカテゴリーに分類する(表参照). Mean Cluster数は原本では各々の分類の回答数から1を引き,その総計をもとめ,それを回答されたカテゴリー数で割る.Switch数は1語以上のclusterの総数を求める.例えばスーパーマーケット課題での回答が「リンゴ,バナナ,ニンジン,トマト,鶏肉,豚肉」の場合,Mean Cluster数は1 (2 [リンゴ,バナナ]-1 + 2 [ニンジン,トマト] – 1 + 2 [鶏肉,豚肉] – 1=3, 3÷3=1). 一方Switch数は3 (3つのサブカテゴリーすなわち [果物, 野菜, 肉])となる.
ここでTroyerらが定義した各流暢性課題におけるカテゴリー数は言語流暢性課題(F,A,S)はいずれも4カテゴリーなのに対しスーパーマーケット・動物課題は14カテゴリーである.すなわちカテゴリー数が多いスーパーマーケット・動物課題はCluster,Switch数のより詳細な検討が可能であることが予測される.
またスーパーマーケット課題は14カテゴリー(上位概念)が多分野にわたり,それに属する下位概念に含まれる用語も多いため「上位概念を想起したあとに下位概念を想起する戦略」を頻用するのでより認知症の患者さんの認知障害をより鋭敏に検出できると考えた.そこで今回アルツハイマー型認知症(AD)の重症度とCluster,Switch数との関連を調べた.さらにCluster数とSwitch数は一方が減ると一方が増える(すなわちtrade off)の関係があると考えられこれについても調べた.
対象は very mild ~ severe AD250例で, MMSE12~26点,Clinical Dementia Rating 0.5~3と対照群49例である. スーパーマーケット課題の回答をTroyerらの原法をもとに,文化的違いなどを考慮し若干の改変をおこなった(表).
Cluster数は原法と同様果物といった上位概念語はりんご,バナナといった下位概念語が同時に回答された場合正解数に含めない一方で,原法と異なり統計学的検討をおこないやすくするため回答されたカテゴリー数で割ることをおこなわなかった.たとえばりんご,バナナ,果物, 鶏肉,豚肉が回答された場合,2[りんご,バナナ,すなわち果物はカウントしない]-1+2[鶏肉,豚肉]-1 =2 この2を2[果物,肉の2つのカテゴリー数]で割らないのでCluster数は2となる. Switch数は原法と同様1語以上のclusterの総数(たとえばりんご,バナナ,果物が回答された場合すべてcluster1に含まれるのでSwitch数は1となる)を求めた.
結果を以下に示す:1)Switch数とCluster数いずれもCDRが高値になるのに応じて低値となっていた;2)CDR0.5は健常群と比較してCluster数は低下していたが,Switch数は健常群と有意差を認めなかった;3) Switch数とCluster数は軽度の相関を示した(r=0.34, p<0.01)
以上1)ADのスーパーマーケット課題におけるCluster・Switch数は認知症の重症度に応じて低下していた;2) Hodgesらは意味記憶障害の立場から軽症ADにおいては上位概念が下位概念に比べて相対的に保たれているとしているが,本研究でも同様であった(すなわちCDR0.5では上位概念(Switch数)でなく下位概念(Cluster数)が障害されていた);3)Cluster数とSwitch数はtrade offの関係になく,むしろ共通する部分が多かった.
表:スーパーマーケット課題における14のcluster
1.果物:りんご,バナナ,マンゴなど
2.野菜:アボガド,豆,にんじんなど
3.乳製品:チーズ,卵,ヨーグルト,牛乳など
4.肉:ベーコン,鳥,魚,ハンバーガーなど
5.飲料:コーヒー,牛乳,ワインなど
6.調味料(完成した料理に使用する):ケチャップ,マーマレード,サラダドレッシングなど
7.香辛料(料理完成前に使用する):こしょう,塩,バニラなど
8.菓子類:キャンディー,ケーキ,アイスクリームなど
9.穀物:パン,マカロニ,米など
10.パン,ケーキを作る時の試料:ふくらまし粉,とうもろこし粉,塩など
11.弁当などの完成品:サラダ油,ケチャップ,スパゲッティーなど
12.雑貨:ティッシュ,雑誌,切手など
13.大豆加工品:納豆・味噌・豆腐など
14.魚類・海藻類:さしみ・魚・ちくわ・さつまあげ・こんぶ・わかめなど
(森山泰、2016.8.12.)
解説 検査の真価とは
結果がスコアとして得られる。それが検査の長所であることは言うまでもない。ではなぜスコアとして得られることが長所なのか。
スコアが客観的だからか。
そうではない。
スコアが臨床症状を反映しているからである。
より正確には、「臨床症状が、スコアという客観的なものに反映されているから」ということになろう。
このとき最も重要なのは、「スコアが臨床症状を反映している」ことであって、「スコアが客観的」というのは、そのスコアが臨床症状を反映しているという大前提あってのことである。当然すぎるくらい当然のことだ。
だがこの当然すぎるくらい当然のことはしばしば忘れられがちである。臨床症状から切り離されたスコアの解析のみが前面に出された研究論文がとても多いのが世の中の現状である。臨床症状とスコアの対応関係が精密でなければ、スコアをいくら統計的に精密に解析しても無意味だ。確かにスコアの解析に集中したほうが科学的な作業に見えるし、論文を多く生産しやすいであろう。しかしそれは明らかに本末転倒である。この愚行を避けるためには、臨床症状をスコアに反映させるべく、検査を不断に改良していくことが必要である。
まさにそれを実践した仕事が、森山博士の『Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test(RDST-J)数字変換課題に関する検討』と『Japanese version of The Rapid Dementia Screening Test (RDST-J) スーパーマーケット課題のcluster数,switch数に関する検討』である。森山博士がそもそもRDST-Jに着目したのは、汎用されている時計描画課題よりも、RDST-Jのほうが軽度認知症の臨床症状をよく反映しているという臨床的印象であった。(本サイト 2015.10. 「軽症アルツハイマー病の診断補助には,時計描画課題よりも日本語版Rapid Dementia Screening Testが有用である」参照)
RDST-Jは数字変換課題とスーパーマーケット課題から成る検査バッテリーである。森山博士はこの検査を認知症の臨床で施行していく中で、数字変換課題では位取りの誤りが多く、スーパーマーケット課題では、健常者では「野菜、えっと白菜、キャベツ、トマト、ニンジン」といったようにまず上位概念を想起したあとに下位概念を想起する戦略をとるのに対し、軽度認知症では下位概念を想起しにくいという印象を持ち、これらを実証的に示すことで上記2つの論文をまとめあげた。
当神経心理研究室創始者である鹿島晴雄前教授(現・国際医療福祉大学教授)は、神経心理学的検査を定量的アプローチと定性的アプローチに二分している。定量的アプローチとは、検査結果がスコアとして定量的に得られるものを指す。定性的アプローチについては次のように述べている:
定性的アプローチ
主として臨床家が開発、発展させてきたアプローチである。個々の被検者によりある程度の柔軟性、可変性をもった検査課題を用い、結果はスコアないし現象的な記述として得られる。結果は臨床所見を優先させそれに基づいて主観的、定性的に意味づけされ、判断される。臨床家が脳損傷者の診療経験を通じて工夫してきたいわば”直感的”検査であり、標準化は難しく、したがって基準もないものが多い。検査の妥当性は臨床的経験から保証される。検査手技は個々の被検者の状態に応じた柔軟な変更、修正を必要とするものが多く、厳密な定式化は困難である。検査の信頼性は検者の経験、能力に大きく左右される。
神経心理学的検査の理想は定量的アプローチと定性的アプローチの長所をあわせもつ、いわば”中庸的”アプローチであろう。
(神経心理学的検査 --- 定量的アプローチと定性的アプローチ.
現代精神医学大系 年刊版 ’88-A. 中山書店、東京. 1988.)
そして鹿島教授は、中庸的アプローチの実例としてウィスコンシンカード分類検査を挙げている。この検査は名前の通りウィスコンシン大学で開発された前頭葉機能検査だが、実際に多数の臨床例に施行してみると、前頭葉損傷者に特徴的な所見のいくつかがスコアに反映されないことが明らかになってきた。そこで当神経心理研究室で原法に改良を加えて完成したのが現在汎用されている48枚のカードを用いる方法(KWCST; 慶應式ウィスコンシンカード分類検査)である。
森山博士の手によるRDST-Jの改良・進化は、KWCSTの開発過程を彷彿とさせるものである。鹿島教授は「理想」と呼んだが、定量的アプローチと定性的アプローチの両方を併せ持つことこそが、検査の「真価」と言うべきであろう。森山博士の努力によって、RDST-Jが「理想」に接近し、「真価」が広く知られることが大いに期待される。
(村松太郎、2016.8.24.)
アルツハイマー病の妄想と神経基盤
仲秋秀太郎(慶應義塾大学医学部精神神経科特任准教授)Nakaaki S, Sato J, Torii K, Oka M, Negi A, Nakamae T, Narumoto J, Miyata J,
Furukawa TA, Mimura M. (2013) : Decreased white matter integrity before the onset of
delusions in patients with Alzheimer's disease: diffusion tensor imaging.
Neuropsychiatric Disease and Treatment, 9, 25-29.
アルツハイマー病の患者では、ものとられ妄想を認めることが多い。
「財布がないので、誰かに盗られた」という内容は、了解可能である。
統合失調症でしばしば出現する了解不可能な妄想とは異なる。認知症の妄想は認知機能低下による一種の誤認である。しかし、今のところ妄想という定義以外の適切な用語がないので、認知症の妄想を「妄想」と呼ぶ。この認知症の妄想には、認知症の認知機能低下の多様な特性を反映しているのかもしれない。
認知症(アルツハイマー病)で出現する妄想は出現頻度が高く、介護者の負担にもなるため、認知症における臨床研究において重要な課題である。アルツハイマー病の精神症状(妄想)には、年齢や性別、罹病期間などは関連しないといわれているが、その発現機序はいまだ不明な点が多い。著者らは、アルツハイマー病において精神症状が発病する患者では、その発病が顕在化する前から、皮質間の連合線維などの白質線維の微細構造異常を認める可能性が高いと推測した。しかし、現時点では、頭部MRI画像による白質線維束に着目した認知症の精神症状の出現予測に関する研究は、国内外で確立されていない。
本研究では、精神症状(妄想)が併発していない軽度のアルツハイマー病患者を1年間追跡調査し、ベースラインの時点で撮影した頭部MRI画像の拡散テンソル画像をFSLで解析した。
縦断的な経過で妄想の出現したアルツハイマー病患者は、妄想が出現しなかったアルツハイマー病患者に比較して、ベースラインでの拡散テンソル画像の左頭頂葉―後頭葉、脳梁体部などのFA(拡散異方向性)値が有意に低下していた。
左頭頂葉―後頭葉、脳梁体部のFA値の低下は、アルツハイマー病の精神症状出現の脆弱性と関連している。これらの部位の白質繊維の微細な構造異常を認める患者は、外界の情報の認識機能が低下し、情報の誤認がおきやすいと推測される。
本研究で、アルツハイマー病の精神症状への脆弱性とそれに関連した脳基盤を国内外で初めて検討し、明らかにした意義は重要である。アルツハイマー病の精神症状の発現に関与する新たな病態モデルを提供でき、発病前からの早期介入が可能になり、精神症状の発病予防や予後の改善が期待される。
アルツハイマー病で妄想が出現しやすい脳の脆弱性がある患者は、そこになんらかの誘因(心理社会的要因や環境要因)が加わり、妄想が出現するのかもしれない。本研究ではサンプルサイズも小さく、そのような誘因を明らかにできなかった。今後の検討課題である。
(仲秋秀太郎、2016.7.27.)
解説 妄想研究への新風
妄想といえば精神病症状の代表だが、では妄想とは何かと正面から問われると、回答は容易でない。妄想の端的な定義は「訂正不能の誤った確信」であるが、これに従えば、統合失調症の荒唐無稽な妄想も、妄想性障害のある程度了解できる妄想も、健常者に時おり見られる強い思い込みも、そしてアルツハイマー病のいわゆるもの盗られ妄想も、すべて妄想という言葉に包括されることになる。それはどう見ても不合理であろう。
そこで精神医学は古来から、妄想とは何かという問いについて様々な議論を重ねて来た。おそらく最もよく知られているのはカール・ヤスパースが挙げた、「並々ならぬ主観的確信」「訂正不能性」「内容がありえないこと」という三つの特徴であろう。このうち、「並々ならぬ主観的確信」は、輪郭が曖昧な印象を受けるが、これこそが妄想という症状の本質であるとする立場もある。それは換言すれば「主観と客観の混同」とも言うべき症状であり、妄想だけでなく、精神病性の症状(統合失調症や妄想性障害の症状)に共通する根本的な特徴であると見ることもできる。この線にそった妄想の定義としてシュピッツァーは「形式的には自己の心的状態に対する陳述のごとく話されるが、内容的には間主観的(客観的)に接近可能な事実についての陳述」を提唱している。ややわかりにくい定義であるが、言わんとするところは、「客観的な現象について、主観的な現象と同じ確信を持って述べる」ということである。
というふうに妄想という精神症状についての議論を始めると終わり無く延々と続くことになりがちである。それはそれで有意義な営みであるが、記述的な方法論のみに依拠する追究には限界があることもまた否めない。
この状況の打破が期待できるのが、本研究で仲秋特任准教授が採った方法論である。いわゆるもの盗られ妄想が外界の誤認に基づく症状であることは症候論からも推定されていたが、そこに本研究により、脳基盤という観点からのデータが新たに加えられたことになる。この結果は、アルツハイマー病についての理解を深めるという大きな意義があることはもちろん、精神医学で最重要とも言える症状である妄想についての伝統的な議論に新たな風を吹き込み活性化する可能性を包含する刺激的なものである。
(村松太郎、2016.7.29.)
前頭辺縁系神経回路における女性優位な世代間伝達パターン
山縣 文 (慶應義塾大学医学部精神神経科 助教)Yamagata B, Murayama K, Black JM, Hancock R, Mimura M, Yang TT, Reiss AL,
Hoeft F. Female-Specific Intergenerational Transmission Patterns of the Human
Corticolimbic Circuitry. J Neurosci. 2016;36(4):1254-60.
親は子供の認知、行動そして脳の発達に対し大きな影響を有しており、これを世代間伝達(Intergenerational transmission)と呼ぶ(Curley, 2011)。これは遺伝的要因や出生前の胎内での影響、さらに出生後の環境要因が相互的に関与していると考えられている。そのような親子における効果は統合失調症やうつ病といった精神疾患でもしばしば認められる。例えば、うつ病の親を持つ子供は健康な親を持つ子供に比べ2〜3倍うつ病を発症するリスクが高い(Lieb, 2002)。特に母親がうつ病の場合、息子ではなく娘の方がうつ病を発症するリスクが高い(Goodman, 1999; 2007)。つまり、うつ病には女性優位の世代間伝達があることが示唆されている。
一方、過去の脳画像研究より、情動制御に関与する脳神経基盤として扁桃体、海馬、前部帯状回、背外側前頭前野、腹内側前頭前野を含む皮質辺縁系神経回路の機能および構造異常がうつ病において一貫して指摘されている(Price, 2010)。過去の動物研究より、うつ病発症に関与する神経回路において女性優位な世代間伝達がある可能性が示唆されている(Weinstock, 1992; Zhu, 2004)。しかしながら、現在まで人間の脳におけるこの世代間伝達における性差について調べた研究はない。
そこで、我々は、健康な35組の生物学的な親子を対象に構造magnetic resonance imaging (MRI)を用いて皮質辺縁系における各親子ペアの灰白質体積の相関の程度の違いを調査した。Voxel-based correlation analysisを行なった結果、皮質辺縁系神経回路を構成する扁桃体、海馬、眼窩前頭前野、直回、前部帯状回において、母と娘の灰白質の体積が、他の3つの親子ペア(母と息子、父と娘、父と息子)と比較して、有意に高い正の相関を示した(P < 0.05, FWE-corrected)。
本研究より、母親がうつ病発症に関与する皮質辺縁系神経回路において脳構造異常を有している場合、息子ではなく、その娘が類似の脳構造異常を有している可能性が示され、うつ病における女性優位な世代間伝達に関与する生物学証拠が示唆された。
本研究の先には、精神疾患の発症リスクにおける性差の解明がある。うつ病は女性が男性より2〜3倍発症リスクが高い。統合失調症では、男性は若年発症で女性は30代前後の発症が多く、発症年齢に性差がある。さらに広汎性発達障害では男性の発症率が高い。このような精神疾患における性差の生物学的基盤を探求することは、病態解明への大きな前進に繋がると考える。
(山縣文、2016.6.1.)
解説 親と子、男と女
子は親に似る。これは事実である。ではなぜ似るのか。これは複雑である。遺伝か、それとも環境か。遺伝だとしたら、どの遺伝子か。環境だとしたら、どの環境か。胎内か。育て方か。おそらくはそれら膨大な因子が様々な率で寄与しているのであろう。顔や体型は遺伝の寄与率が大きそうである。職業選択は環境の寄与率が大きそうである。では性格はどうか。精神疾患はどうか。結局のところ、確実なのは「子は親に似る」という事実だけであって、すると親から子の世代に「何か」が伝達されているとまでしか言えない。これが世代間伝達という言葉の意味である。
親がうつ病だと子はうつ病になりやすい。これは事実である。だがなぜなりやすいのか。これは複雑である。この問いに挑むため古来から精神医学が採ってきた方法論は、双生児研究・養子研究であるが、その結果から言えるのは遺伝の要因と環境の要因のどちらが大きいかということまでであるし、研究デザインの性質上、独立した再検証はほぼ不可能だから、信頼性にもかなりの限界がある。結局のところ、精神疾患の世代間伝達のメカニズムについては、「遺伝も、環境も」という至極当然のことしか言えないというのがこれまでの状況であった。
この閉塞した状況を大きく揺さぶり、新たな道を開いたのが山縣博士の本研究である。山縣博士がまず注目したのは、特に母がうつ病だと娘がうつ病になりやすいという臨床的事実であった。父と母。息子と娘。誰が誰に似るか、その組合せは2x2の4通りある。山縣博士はこの4通りについて、脳の構造を精密に計測した。そして従来よりうつ病に密接に関連していることが示唆されている部位において、母と娘に有意な相関を見出した。母がうつ病だと娘がうつ病になりやすいという臨床的観察には、脳内にその基盤があることが示されたのである。
うつ病は女に多いといっても、うつ病発症率の男女差はそれほど顕著ではない。しかし精神疾患では、発症率にはっきりした男女差があるものがいくつもある。女に多いものは、摂食障害。境界性パーソナリティ障害。色情パラノイア。解離性同一性障害。クレプトマニア。男に多いものは、広汎性発達障害。反社会生パーソナリティ障害。アルコール依存症。フェティシズム障害。窃視障害。露出障害。これらの男女差を生んでいるものは何か。「脳」と答えればそれは普遍的な正解だが、真の問いは、その脳の違いを生んでいるものは何かということである。それは遺伝か環境か。両方であろう。では寄与の程度はどうか。そして遺伝子の中のどれが、環境の中のどれが、この違いを生んでいるのか。さらには脳の男女差を形成するまでの進化も考察しなければならない。そこには何万年という単位の生物的進化も、十年百年単位の社会文化的進化も含まれる。単なる脳の男女差だけでなく、世代間伝達という局面まで踏み込んだ山縣博士の本研究は、うつ病についての画期的な生物学的データであることにとどまらず、男と女の違いという人間にとって普遍的な関心領域に新たな光を当てたものでもある。
なお、この論文は国際社会からも注目を浴びており、2016年1月にはScientific AmericanにLike Mother, Like Daughter --- the Science Says No, Too.という見出しの下に紹介されている。
http://www.scientificamerican.com/article/like-mother-like-daughter-the-science-says-so-too/
さらに2016年2月にはReutersがMothers may pass daughters a brain wired for depressionとして配信している。
http://www.reuters.com/article/us-health-neuroscience-mothers-depressio-idUSKCN0VR2WN
(村松太郎、2016.6.29.)
妄想の医学と法学 中外医学社 2016年6月出版
著 村松太郎 (慶應義塾大学医学部精神神経科准教授)
解説 医と法は刑事裁判で出会い、脳に向かう
妄想を語るためには、事実を語らなければならない。
本書『妄想の医学と法学』で扱っているのは刑事裁判の判例である。そこには妥協は存在しない。どこまでも事実を語るのが裁判である。詳細な症例報告の開示が諸理由で難しくなっている現代において、判例は妄想を語るための最高の材料となっている。
犯行が妄想に基づくものであれば、刑は減軽される可能性がある。だから弁護人は、被告人の思考は妄想であると主張する。対して検察官は、妄想ではなく、単なる思い込みであると主張する。どちらが正しいかが精神医学に問われる。この時、精神医学の曖昧さが露呈する。精神医学では最重要とも言える症状であるにもかかわらず、「妄想とは何か」という問いに、精神医学は明確な答を呈示できないのである。
妄想とは何かという問いは、病気とは何かという問いに昇華する。
この時、医学の曖昧さが露呈する。
医の起源は、患者を苦悩から救うことである。そこで、苦悩を病気と名づけ、診断と治療を体系化し、医学が成立した。「すべては患者=本人=当事者のため」というヒポクラテスの誓いは、紀元前から現代まで、臨床医学の根本原理であり続けている。
だが刑事裁判には、反対当事者というものが存在する。当事者=患者=被告人を苦悩から救うことは、反対当事者=被害者の苦悩を深刻にするという事態が発生する。ここではヒポクラテスの誓いは、公正中立な判定を損なうヒポクラテスバイアスと化す。
バイアスから離れたとき、臨床とは全く別の風景が眼前に開ける。
脳機能が標準から逸脱していることを病気と定義するならば、殺人者はみな病気であろう。裁判所はそうは考えない。病気とみなして治療を命ずるのではなく、罪とみなして罰を命ずる。殺人者の心性を病気ではなく性格と認定するからである。しかし脳機能の標準からの逸脱という意味では、病気と性格を峻別する根拠は存在しない。では病気と性格はどこが違うのか。神経心理学に限らず、脳の研究は必ずこの問題にたどり着く。脳の病気を治療することは、性格・人格を改変することとどこが違うのか。
裁判は治療場面でこそないものの、病気と性格をめぐる問題は、他のどんな場面よりも生々しく顕現する。その場で答を出さなければならないからである。その答は、無罪から死刑まで最大限の振れ幅を持っている。妄想が論点となる刑事裁判では、特にこの問題が露わになる。『妄想の医学と法学』で取り上げたどの判例にも、この問題が底に流れている。そして最後の14ページでは、現代の医学と法学の到達点の明示を試みた。
妄想の医学と法学は刑事裁判の法廷で出会い、手に手を取って脳に向かう。いや、「手に手を取って」は著者の願望にすぎない。脳に向かう医と法の歩みは、両者を結びつけるのか、それとも接近を絶対的に阻む深い絶壁があることを示すことに終わるのか。それはこれからの刑事裁判の中に見えてくるであろう。『妄想の医学と法学』は、その道標となることを目指した書である。
(村松太郎、2016.5.31.)
共感 岩波書店 2014年9月出版
編集 梅田聡 (慶應義塾大学文学部教授)著 梅田聡 (慶應義塾大学文学部)
板倉昭二 (京都大学大学院文学研究科)
平田聡 (京都大学野生動物研究センター)
遠藤由美 (関西大学社会学部)
千住淳 (Birkbeck, University of London, Centre for Brain and Cognitive Development)
加藤元一郎 (慶應義塾大学医学部)
中村真 (宇都宮大学国際学部)
解説 共感を拡大する
現代社会でクローズアップされている、いじめ、DVなどの心の問題の根底には、共感不足というキーワードを見出すことができる。梅田聡教授が編集した本書『共感』は、岩波講座 コミュニケーションの認知科学の2巻としての配本で、現代社会の心の問題を科学的に読み解ける可能性を秘めた刺激的な書である。共感の科学 <認知神経科学からのアプローチ> / 共感の発達 <いかにして育まれるか> / 共感の進化 / 社会的文脈から共感を考える / 共感の自閉スペトクラム症 / 共感の病理 / 共感と向社会的行動 <集団間紛争の問題を通して考える> の各章から成り、当研究室の梅田聡教授が 第1章 共感の科学を、加藤元一郎教授が 第6章 共感の病理を、それぞれ執筆している。
第1章、梅田教授の「共感の科学」は、編者による冒頭の章にふさわしく、共感についての研究の動向の洗練されたまとめとなっている。さらには単なるまとめを超え、身体反応との関係という最新の視点が提示されている。最近の心理学は共感を認知的共感(cognitive empathy)と情動的共感(emotional empathy)に二分する。前者はいわば「クールな共感」で、「他者の心の状態を頭の中で推論し、理解する」ものである。後者はそこに身体反応を伴う、いわば「ホットな共感」である。前者は意図的にスイッチをオフにすることができるが(つまり、共感を抑制することができるが)、後者はそれができない。このように、共感を身体の反応という視点から捉えることは、神経科学の分野でよく知られているSomatic Marker 仮説と、Mirror Neuron仮説を繋ぎ、かつ、現代社会に広がる心の問題に迫るものである。
梅田教授は共感における身体反応性に特に深い関心を持ち、本書のほかに、
「心理学評論」 57巻1号 特集号 『感情と身体』
を編集し、同誌に
感情と身体の統合的理解に向けて
という簡明な論文を掲載している。
共感の身体反応性については、梅田教授によるさらに深く詳しい著書が期待されるところである。
第6章、加藤元一郎教授の「共感の病理」は、認知的共感の低下 / 保持・亢進と、情動的共感の低下 / 保持・亢進の 2 x 2 の表の各セルに、統合失調症・自閉症・境界性人格障害・素行障害・反社会性人格障害・ウィリアムズ症候群を整理し、さらには共感のダークサイドとも言うべきシャーデンフロイデ(本サイト 2015.3参照)にも言及されている。本章を読むと、精神科における実に多くの病態が、共感の病理という視点から捉えられることに気づかされる。そして直ちにいくつもの問いが生まれる。脳機能との関係はどうか。治療への発展性はどうか。加藤教授が特に関心を持っておられた認知進化からはどのように説明できるか。これらについては、加藤教授によるさらに深く詳しい著書が期待されるところである。それは知的興奮に溢れた名著になったことであろう。
(村松太郎、2016.4.27.)
治療に対する同意能力問題について
江口洋子(慶應義塾大学医学部精神神経科研究員・心理士)医療従事者のための同意能力評価の進め方・考え方 新興医学出版社 2015年9月出版
監修 三村將 (慶應義塾大学医学部精神神経科 教授)
監訳 成本迅 (京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学 准教授)
訳 富永敏行 (京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学)
仲秋秀太郎 (慶應義塾大学医学部精神神経科 特任准教授)
松岡照之 (京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学)
加藤佑佳 (京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学)
飯干紀代子 (志學館大学人間関係学部)
江口洋子 (慶應義塾大学医学部精神神経科)
小海宏之 (花園大学社会福祉学部)
成本迅 (京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学)
平成24年10月から27年9月にかけて科学技術振興機構/社会技術研究開発センター(RISTEX)で行われた「コミュニティで創る新しい高齢社会のデザイン」研究開発領域の「認知症高齢者の医療選択をサポートするシステムの開発」プロジェクトの参画メンバーにより本書を翻訳しました。
認知機能が低下すると治療方針に対する意思決定が困難なことがあります。日本では、独居で身寄りのない高齢者や認知症高齢者が増加し、精神科以外の診療科でも認知機能が低下した患者に遭遇することが稀なことではなくなりました。プロジェクトでは、本人の意思が反映された形で、認知症の人が適切な医療を受けられるようにするため、本人と家族・医療従事者(非専門医)・在宅支援者が参考にできる医療に関する意思決定支援ガイドを作成しました。
本書は、プロジェクトを進めるうえで、大いに参考になった資料の一つです。
ここでは、私が翻訳を担当した「6章 解釈」について、一部紹介いたします。
6章では、さまざまなツールで医療同意能力を評価した後、どのように解釈すべきかについて詳細に述べられています。
医療同意能力を正確に評価したとしても、ある治療に対する医療同意能力の有無を判定することは難しいとしています。それは、治療方法により予期されるリスクやベネフィットが異なり、自分の状況に照らし合わせて、いくつかの治療方法を比較しなければならないという状況の複雑さが存在するためです。治療方法ごとに医療同意能力がどの程度必要かという基準を決めておけば、その治療に対する本人の能力の有無を判定することが可能になりますが、実際の治療方法に対するリスクとベネフィットを比較衡量するための明確な方法は今のところありません。
著者はリスクとベネフィットのバランスを4つのカテゴリー(高リスク-低ベネフィット、中-中、低-高、低-低)に分類し、”Competence balance scale” (法的な判断能力の天秤)という概念を用いて理解しようとするGrisso T.とAppelbaum P.S.の試みについても紹介しています。本人の自律と保護を天秤にかけ、通常は自律の尊重のために天秤は自律に傾くように支点が位置していますが、カテゴリーを参照して支点の位置を考慮することにより、自律と保護のどちらが優先されるかを判断します。たとえば、複数の治療方法を比較して、自分にとって明らかに不利益な方法を選択した場合には、保護に傾くように支点を移動させた上で、本人の能力の有無を判定します。このように治療のリスクとベネフィットのバランスを参照して、天秤の傾きを考えれば、ある治療に対する医療同意能力の判定が可能になるということです。
本章では、その他に能力の判定が困難な例をいくつか挙げて解説しています。たとえば、簡易の認知機能検査の結果が良好な高齢者が、リスクは低くベネフィットが高い治療を拒否した例です。この高齢者は認知機能が保たれているために、治療拒否は本人の意思としてみなされる可能性がありました。しかし、難しい認知機能検査をして認知機能が低下していたという結果から、せん妄の影響を明らかし、治療拒否は医療同意能力が低下しているためであるためとされました。このように、医療同意能力について判定するには、本人の正しい病状や状況を把握することが重要とされています。
本章では、最後に能力判定に際の記録について、推奨している記載事項についても述べています。
このように、ある治療に対する医療同意能力の有無をどのように判定するのか、医療関係者や家族が最良と考える治療を本人が拒否した場合はどのように考えるかなど、臨床現場で医療従事者が判断に迷うときに、本章は役に立つことと思われます。
(江口洋子、2016.3.30.)
解説 大前提の崩れに対応する
人間社会は、一人一人が自由意思を持ち、自分についての重要事項について正しく決定できることを前提として成り立っている。だが本人が精神疾患や認知症に罹患しているとき、この大前提が崩れることがある。このとき、従来の医療倫理が単純には通用しない局面が立ち現れる。どこまでも本人の意思を尊重するというのは理想であるが、本人が自己にとって最良の医療を選択できない事態に直面したとき、それは理想であっても現実的でない。医療従事者には慎重なうえにも慎重な姿勢が求められる。しかしながら、いかなる医療行為もリスクとベネフィットのバランスの上に成り立つものであり、何が最善であるかを一義的に決定することが不可能である以上、慎重であるだけでは不十分で、何らかの基準か、あるいは基準には至らずとも、基本となる考え方が共有されていることが必要である。現代において大きくクローズアップされてきているこの問題に対し、『医療従事者のための同意能力評価の進め方・考え方』は臨床場面での有益な指針を示す書である。
原書は、
Scott Y.H. Kim:
“Evaluation of Capacity to Consent to Treatment and Research”
(Best practices in forensic mental health assessment series)
Oxford University Press 2009
で、当研究室からは仲秋特任准教授、江口研究員が翻訳を分担し、三村教授が監修している。
本書の前半である基礎編は、Appelbaum P.S. とGrisso T. が提唱した4つの能力モデル、すなわち「理解する力 understanding」「認識する力 appreciation」「論理的に考える力 reasoning」「選択を表明する力 expressing a choice」 を中心に展開し、同意能力 capacity to consent の概念の正確な把握に向けて構成されている。
そして後半の応用編は「評価の準備段階」「データ収集: 患者への面接」「解釈」「アセスメント後」と、臨床現場での時間的流れにあわせた実践的な記載の章が続き、最終章として「研究参加への同意能力」が設けられている。これは本書の原題、”Evaluation of Capacity to Consent to Treatment and Research”に対応している。
本書は新興医学出版社のホームページ
http://shinkoh-igaku.jp/mokuroku/data/859.html
にも紹介されている。
(村松太郎、2016.3.31.)
統合失調症患者の自己主体感における予測シグナルの遅れの行動学的エビデンス
是木明宏(慶應義塾大学医学部大学院博士課程)Koreki A, Maeda T, Fukushima H, Umeda S, Takahata K, Okimura T, Funayama M, Iwashita S, Mimura M, Kato M. Behavioral evidence of delayed prediction signals during agency attribution in patients with schizophrenia. Psychiatry Res. 2015. Nov 30;230(1):78-83.
この論文は2013年夏にASSC (Association for the Scientific Study of Consciousness)の学会でポスター発表した内容に、より詳細な考察を加えて形にしたものである。
統合失調症の病態は未解明だが、その中核症状は自我障害といわれている。この自我障害を認知神経科学の知見からどのように説明するかが近年活発に議論されており、特に自己意識(Self-consciousness)の研究に注目が集まっている。
自己意識には2つの側面がある。一つは自己所属感(Sense of Ownership)であり、この手は「私の」ものだといったような感覚を指す。もう一つが自己主体感(Sense of Agency:SoA)であり、例えば何か物が動いたときに、「私が」動かしているといったような、私がという感覚を指す。このSoAは統合失調症の症状にも非常に関連しており、例えば自分の行為が誰かに操られてしまうといった感覚はSoAが低下している状態であるといえる。逆に自分の行為が周囲へ過剰に影響を及ぼしてしまうという症状はSoAが過剰になっている症状といえる。実際に様々な神経心理学的な研究で統合失調症におけるSoAの異常が示されてきている。
SoAの成立機序はForward modelで説明される。人が何か行為をするとき、その行為の結果を予測する。この予測と実際の行為の結果とが一致していれば、「自分が」その結果を起こしたと感じることができる。これがSoAが生じる場合である。例えば、電気をつけようとしたとき、電気がつくと予測してスイッチを押し、思い通りに電気がつけば「自分が」電気をつけたと感じる。一方で予測に反してなかなか電気がつかず1分後に電気がついた場合、他人がどこかでスイッチを押して電気をつけたのだろうと感じるだろう。
このように「予測」はSoAの成立に非常に重要だが、この脳基盤は前頭葉から感覚連合野へと白質を通して伝わるシグナルだと考えられている(Efference copyやCorollary dischargeといわれる)。
統合失調症では予測シグナルの異常があることが示されており、またその神経基盤となりうる白質の異常も示されてきている。しかしこれら先行研究はSoA研究から得られたものではない。そのためSoAと予測シグナルの異常との関係を論じるにあたり、SoAパラダイムの中で予測シグナルの異常を示す必要性があった。
今回、健常者および統合失調症患者各30名に対してSoA task(Keio Method)を改変して行ったところ、統合失調症の予測シグナルの遅れを示す結果が得られた。さらにはその予測シグナルの遅れが過剰なSoAへと繋がる結果が示された。
この統合失調症における予測シグナルの遅れは、白質の異常との関係が想定され、Disconnection 仮説を支持するものと考えられる。統合失調症患者はこの遅れによって日常生活における様々な状況でSoAの異常を来たす可能性がある。予測シグナルが遅れている分、健常者とは違う状況でSoAを感じ、逆に通常ではSoAを感じる状況で患者はSoAを感じない。これは自我障害だけでなく幻聴や妄想など統合失調症の様々な症状にも繋がる可能性もある。さらにこの知見は予測シグナルの遅れを修正するようなリハビリテーションなど様々な治療技術の開発にも今後繋がると考えている。
(是木明宏、2016.2.22)
解説 自我障害を脳科学で語る
統合失調症の自我障害を科学の射程に引き寄せることを目指して前田貴記講師が開発したSoA task (本サイト2014.3.参照)を活用した一連の研究のひとつがKoreki et al: Behavioral evidence of delayed prediction signals during agency attribution in patients with schizophrenia. である。是木院生の解説文にある「改変」とは、trial-by-trial、すなわち、各試行ごとにSoA課題のdelay(遅れ)を延長していくことを指している。この改変を施した方法論により、統合失調症における自己主体感の遅れが客観的なデータとして可視化されたことが本論文の骨子である。
本研究で設定したdelayは50msecである。この50msecという数字は、統合失調症におけるcorollary discharge の測定値に由来する。本論文のタイトルにあるBehavioral evidence (行動学的エビデンス)は何気ない常套句に見えるが、実のところは統合失調症の自我障害を説明し得る唯一ともいえる神経生理学的な事象のcorollary dischargeをbehaviorのレベルに結びつけたという、世界初の行動学的エビデンスなのである。
Corollary dischargeの異常がさらに前頭葉白質の髄鞘化の異常と密接に関連することが示唆されていることとあわせ、本論文のデータの先には、統合失調症という脳の病気の巨大な姿が映し出されている。その姿はいまだ霧の中の巨人のように輪郭不明瞭だが、臨床症状から脳の解剖生理学までの連結部分を覆っていた霧を、巧妙な心理実験という一陣の風で吹き飛ばしたのが本研究である。
実験医学の領域ではしばしば from bench to bedside という表現が目にされる。基礎的な実験データを臨床所見に繋ぐことを意味する表現である。これまで記述のレベルでしか語られてこなかった統合失調症の自我障害を脳科学の言葉で語った本研究は、まさに精神医学におけるfrom bench to bedsideを具現したものと言えよう。
(村松太郎、2016.2.23.)
体位性頻脈症候群における脳構造の特殊性 <自律神経障害と精神症状の関連性を探る>
梅田 聡 (慶應義塾大学文学部教授)Umeda, S., Harrison, N. A., Gray, M. A., Mathias, C. J., & Critchley, H. D. (2015) Structural brain abnormalities in postural tachycardia syndrome: A VBM-DARTEL study. Frontiers in Neuroscience 9, 34.
William Jamesが情動における身体の重要性を訴えてから,120年以上の歳月が経つ.この間,抑うつや不安をはじめ,さまざまな情動や気分に関する神経生物学的・神経心理学的な研究が発展し,それらの背後にある脳内メカニズムに関する理解が深められた.特に近年になって見えてきたことの一つは,抑うつや不安などの精神症状の背景には,身体機能の特殊性,特に自律神経機能の異常が強く関与しているという事実である.
本論文は,自律神経障害の一種である「体位性頻脈症候群(postural tachycardia syndrome (PoTS))を対象としたMRIの構造画像研究である.PoTSは,起立時の著しい心拍上昇によって特徴づけられる自律神経病態であり,自律神経亢進型の障害と位置づけられる.原因に関してもさまざまな説が提案されているが,心臓自体の容積が小さいことが重要な要因であると考えられている.関連する事象として,多くの宇宙飛行士は,地球へ帰還後にPoTS症状を呈することが知られている.宇宙空間では,重力がないために,心臓が収縮してしまうことが背景にある.
MRI構造画像解析(VBM-DARTEL)の結果,健常群と比べPoTSにおいて,帯状回前部(anterior cingulate cortex)および島皮質(insular cortex)の容積が減少していることが明らかになった.この2つの部位は,近年,セイリエンスネットワークとして知られ,内臓や筋の状態,痛みや体温,体液循環,前庭感覚など,身体のホメオスタシスからの逸脱程度のモニター(内受容感覚),およびそれに対する身体調整機能の駆動に関わるとされる部位である.本研究の結果は,PoTSにおいて,身体のモニターおよび制御機能が低下していることを示唆するものと考えられる.
さらに,精神症状との関連を調べるため,抑うつおよび不安傾向との相関を調べたところ,島皮質の容積が小さいほど,抑うつ傾向および不安傾向が高いことが明らかになった.これらの成果は,抑うつや不安などの症状の生起に,身体機能の異常が深く関与することを示唆している.精神症状の生起メカニズムを探る上で,脳と身体との相互作用という視点から統合的に解析することが肝要であると考えられる.
(梅田聡、2016.1.20.)
解説 はたして人は、泣くから悲しいのか
「悲しいから泣くのではない。泣くから悲しいのだ」
19世紀の心理学者ウィリアム・ジェイムズのものとされるこの言葉は、人間において、生理学的反応(たとえば、「泣く」)が、心理学的情動体験(たとえば、「悲しい」)の原因であることを意味している。
人々の自然な常識的直感に反したこの言説は正しいのか。もし正しいとしたら、そこには如何なるメカニズムがあるのか。この心理学百年来の問いをめぐる議論を大きく前進させたのが、梅田教授がかつての留学先のロンドン大学認知神経科学研究所 / ロンドン大学 神経学・脳神経外科学病院 自律神経ユニット Institute of Cognitive Neuroscience, University College London / Autonomic Unit, National Hospital for Neurology and Neurosurgery University College London で行った本研究である。対象は自律神経症状と精神症状(不安等)を呈する疾患のPoTS (postural tachycardia syndrome; 体位性頻脈症候群)。主たる結果は、いわゆるセイリエンスネットワークSalience Networkを構成する帯状回前部と島皮質の容積減少である。
セイリアンスネットワークとは、その名の通り、Salient eventに対する生体の、いわばあらゆる反応に関与することが明らかになりつつある脳構造である。そして、統合失調症、気分障害、さらにはいわゆる神経症性障害にわたる多くの、おそらくはすべての、精神疾患でこのネットワークに何らかの異常があるという知見が蓄積されつつある。心の病と呼ばれてきた精神疾患にこのような所見が見出されたことを、伝統的な心と脳の二分法への強力かつ具体的な反証であるとする立場もある。より身体的色彩の強い疾患であるPoTSでもセイリアンスネットワークに所見があることを示した本研究は、心、脳、身体の関係の、さらにはそれらの境界の、見直しを迫るものであると言える。
そして本研究における特記すべき点は、「悲しいから泣くのか、泣くから悲しいのか」という問いとの深い関連性である。
この問いをPoTSに変換すれば、「不安だから頻脈になるのか、頻脈だから不安になるのか」となる。
精密に臨床観察を行えば、「不安」と「頻脈」の時間的前後関係までは明らかにすることができるかもしれない。「悲しい」と「泣く」についても同様である。しかし因果関係までは証明できない。そのためには脳内メカニズムの解明が必須である。PoTSの脳構造の特殊性を示した本研究は、この解明への歩を着実に進めるものである。同時に、より合理的で有効な治療法の開発にも繋がるであろう。精密な臨床観察と画像解析を駆使した梅田教授の本論文には、それを予感させる鳴動がある。
(村松太郎、2016.1.25.)
第39回 日本高次脳機能障害学会学術総会2015年12月10日、11日 ベルサール渋谷ファースト
テーマ 前頭葉
会長 故 加藤 元一郎
会長代行 三村 將
事務局長 船山 道隆
いかにも加藤元一郎教授らしい「前頭葉」という直球をテーマにした学会が、上記の通り開催され、本学会史上最多の約2400名にご参加いただいた。予想をはるかに超える人数であったため会場が手狭となり、参加者の皆様にご不便をおかけしたことをお詫び申し上げます。2日間にわたる熱心な討論は、前頭葉と高次脳機能障害学への関心の益々の高まりを実感させるものであった。
当研究室関連の演題は次の通り(研究室員が筆頭演者であったもののみを示す)。
1日目(2015年12月10日)
◇シンポジウム1: 発達障害と神経心理学
発達障害における顔認知
小西 海香
自閉スペクトラム症の嗅覚特性
熊崎 博一
◇教育講演 3
てんかん性健忘
田渕 肇
◇ワークショップ 1:情動 司会:梅田 聡
W1-1
情動を生み出す「脳・心・身体」のダイナミクス:脳画像研究と神経心理学研究からの統合的理解
梅田 聡
◇一般演題
・意味記憶障害が遷延した全生活史健忘の一例
是木 明宏 他
・注意障害の経過―トレールメイキングテストによる検討
稲村 稔 他
・計算論的精神医学によるワーキングメモリ障害と前頭前野の NMDA 受容体、D1 受容体機能の対応
沖村 宰 他
・病的収集活動の出現に明らかな契機がみられた右前頭葉損傷例
高田 武人 他
2日目(2015年12月11日)
◇シンポジウム 3:前頭側頭葉変性症と紛らわしい病態
司会:三村 將、池田 学
・前頭側頭葉変性症と類似する精神疾患
三村 將
◇ワークショップ2:sense of agencyパラダイムによる新たなリハビリテーション戦略―運動麻痺から高次脳機能障害まで
司会:前田 貴記
・自己意識の神経心理学の試み
前田 貴記
◇会長講演:前頭葉の臨床神経心理学
司会:鹿島 晴雄
前頭葉の臨床神経心理学
三村 將
◇教育講演 6
司法神経心理学
村松 太郎
◇一般演題
・右半球の広範な脳梗塞後にソマトパラフレニアとして体内に動物が出現したと考えられた一例
秋田 怜香 他
・抗てんかん薬で一部の健忘が改善したてんかん性健忘の一例
堀田 章悟 他
・顕著な視覚構成障害と漢字失書を呈した若年性アルツハイマー病疑いの 1 例
山縣 文 他
・顕著な漢字失書を呈したアルツハイマー病疑いの 1 例
堀込 俊郎 他
・物忘れ外来受診者に対するテレビ会議システムを用いた神経心理検査の実用性に関する検討
江口 洋子 他
・記憶障害を呈する脳損傷者が認定健康増進施設利用する意義(第 2 報)
先崎 章 他
なお、学術総会前日の2015年12月9日には、六本木の東京ミッドタウンホール&カンファレンスにおいて、各種委員会・役員会が行われ、2004年以来本学会理事長を務められた鹿島晴雄教授が退任され、新たな理事長として三村將教授が選ばれた。
そしてクリスマスのイルミネーションを見下ろす会場で、役員懇親会および加藤元一郎先生を偲ぶ会が行われた。
(村松太郎、2015.12.24.)
側頭-頭頂皮質の萎縮による進行性の超皮質性感覚失語および進行性の観念失行
船山道隆(足利赤十字病院 神経精神科 部長)Progressive transcortical sensory aphasia and progressive ideational apraxia owing to temporoparietal cortical atrophy
Michitaka Funayama and Asuka Nakajima
BMC Neurology (2015) 15:231 DOI 10.1186/s12883-015-0490-2
【背景】
前頭側頭葉変性症は、臨床的に以下の3つの下位分類がある、すなわち、行動障害型前頭側頭型認知症, 非流暢性/失文法型進行性失語, 意味型進行性失語である。一方で、後部脳の皮質に萎縮を認める変性疾患の臨床症状はまだ十分に解明されていない。現在までに、左シルビウス裂周囲の側頭-頭頂葉に萎縮/機能低下を認め、流暢であるが復唱の障害が目立つ失語を呈するlogopenic型進行性失語、両側の後頭-頭頂葉を中心とした萎縮/機能低下を認め、視空間障害を主症状とする後部皮質萎縮症、頭頂葉の萎縮/機能低下を認め、進行性の肢節運動失行を主症状とする原発性進行性失行が挙げられている。しかし、臨床症状がこの3群にうまく入らない患者群は以前から臨床現場では指摘されてきた。
【Logopenic型進行性失語と後部皮質萎縮症の中間】
本研究は、前2者、すなわち、logopenic型進行性失語と後部皮質萎縮症の中間に属し、発症が65歳以下の2症例の詳細な臨床症状を挙げ、logopenic 型進行性失語と後部皮質萎縮症がスペクトラムである可能性を示した。われわれの症例の病理所見を示すことはできなかったが、神経病理研究からはlogopenic型進行性失語と後部皮質萎縮症はアルツハイマー病の症例が多いと報告されている。すなわち、後部脳の皮質に萎縮を認めるアルツハイマー病は、logopenic型進行性失語と後部皮質萎縮症をプロトタイプとして、その両者の臨床像を持つ症例が少なくない可能性が示唆された。
【進行性の観念失行および概念失行】
また、今回のわれわれの症例は進行性の観念失行や概念失行を認めた。われわれは以前にも(Funayama M, Nakagawa Y, Yamaya Y, Yoshino F, Mimura M, Kato M. Progression of logopenic variant primary progressive aphasia to apraxia and semantic memory deficits. BMC Neurol. 2013;13:158. doi:10.1186/1471-2377-13-158.) 、logopenic型進行性失語において比較的発症早期から失行を伴った3症例を報告した。両報告の症例の失行は、原発性進行性失行に典型的に認められる肢節運動失行とは異なり、意味性の錯行為が目立つことなどから行為と意味のアクセスが不十分となる病態を示している。後部脳の皮質に萎縮を認めるアルツハイマー病では、この型の失行が出現することが多い可能性が示唆された。
(船山道隆、2015.11.12.)
解説 分類という道標
たとえば、虹は何色か?
七色。誰もがそう答えるであろう。
だが虹の色の数は、国や文化によって異なる。八色という国もある。六色という国もある。五色や四色もある。どれが正しいのか? どれも正しいといえば正しいし、正しくないといえば正しくない。
人間の目に見える波長は380nmから750nm。この範囲の様々な波長が混じった光が白色光である。白色光をプリズムで分離すると、様々な色が見えてくる。これが虹である。すなわち光とは元々は切れ目のない連続した波長として存在するのであって、それが人間の視覚、さらには色を表す言葉の数によって、有限の色数として認識されているにすぎない。虹の色の数は、知覚と言葉による制約を受けて定められているのである。
では、精神病は何種類か?
混沌の中から、クレペリンは早発性痴呆と躁うつ病を抽出した。この2つのカテゴリーへの分類を道標として、現代精神医学の発達が加速したと言っても過言ではない。
だが虹という自然界の現象と同様に、疾患という生物学的現象も、本来は連続的なものである。もちろん連続体であっても、その中のある群に他のものと一定以上の違いが見出されれば、その群はカテゴリーとして差し支えない。しかし本来が連続体である以上、どのカテゴリーにも分類できないものが必ず出て来る。だからクレペリンは分類体系を次々に改訂した。だが改訂をそう頻繁に行うわけにはいかない。ではどうするか。
第一の方法は、少々の矛盾は無視し、既存の項目の中に強引に分類してしまうということである。虹は七色であると固定し、一切疑わない姿勢がこれにあたる。実際に虹を見たとき、七色を見分けられる人はまずいないが、それでも虹は七色なのだ。
第二の方法は、「分類不能」というカテゴリーを作ることである。NOS (Not Otherwise Specified) だ。DSMはこの方法を採ることで、いかなるケースもどこかに必ず分類可能な形を維持している。
虹は七色式に既存の体系を墨守したり、NOS式にごみ箱を作ってすましていることが、ある時期には必要であり現実的でもあるが、知見が蓄積されてくるといつかは矛盾が臨界点に達し、新たな分類体系に脱皮せざるを得なくなる。脱皮すなわち進歩である。
その蓄積される知見はどのようにして生まれるか。
虹においては、知覚による制約は絶対的なものである。裸眼で見て何色見えるかが虹の色数というものの本質なのであって、機器で分析すれば可視光線は無限に近い色の数に分離できるなどと言っても意味はない。
一方、臨床とは、逆に裸眼では見えないものを追究する営みである。そのための武器の一つは画像診断などの機器の進歩であるが、そこに臨床家としての慧眼が加わって初めて、従来の分類体系を超えた視点が生まれる。
本論文、船山部長の「側頭-頭頂皮質の萎縮による進行性の超皮質性感覚失語および進行性の観念失行」は、そういう仕事である。
後部脳の皮質に萎縮を認める変性疾患は従来、(1) logopenic型進行性失語、(2) 後部皮質萎縮症、(3) 原発性進行性失行の3つに分類されていたが、(1)と(2)がスペクトラムである可能性を示した。本論文を要約すればそうなる。
それは表面的には分類学の進歩への貢献であるが、分類は手段であっても目的ではない。虹の色を追究すれば光という物理現象の本質に接近できるのと同様、臨床像の分類を追究すれば、疾患の本質に接近することができる。その先にあるのは疾患の重要な要素である神経病理や遺伝子である。
そして神経心理学で扱うことの多い脳器質疾患では、分類学においても、高次の神経症状とそれに密接に関連する脳局在部位を論ずることができるという大きな特長がある。本論文では失行が強調されている。これはいわば、船山部長という先駆者が示した道標であり、この道標に着目することで、誰もが精密な診断に向けて歩むことが可能になる。
本論文を精読すると、失行以外にも多くの臨床的道標が示されていることに気づかされる。どこまでも精密な臨床観察から生まれた論文なのである。その結果、本論文自体が、変性疾患の本質と全体像への道標となっている。
(村松太郎、2015.11.29.)
軽症アルツハイマー病の診断補助には,時計描画課題よりも日本語版Rapid Dementia Screening Testが有用である
森山泰 (駒木野病院精神科診療部長)Yasushi Moriyama, Aihide Yoshino, Kaori Yamanaka, Motoichiro Kato, Taro Muramatsu, and Masaru Mimura
Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test is effective for detecting patients with mild Alzheimer’s disease compared to the Clock Drawing Test
Psychogeriatrics. 2015 Jul 24. doi: 10.1111/psyg.12144.
日本語版 Rapid Dementia Screening Test(Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test: RDST-J)はKalbeらによって開発された認知症スクリーニング検査を酒井らが日本語に翻訳したもので,スーパーマーケット課題と数字変換課題の2題からなる.スーパーマーケット課題は1分間の制限時間内に「スーパーマーケットやコンビニエンスストアで買えるもの」をできるだけいってもらう言語流暢性課題である. 一方数字変換課題は,アラビア数字を漢数字に変換する2題(209→二百九,4054→四千五十四)と,漢数字をアラビア数字に変換する2題(六百八十一→681,二千二十七→2027)からなる. 本検査は3~5分で施行及び採点が可能であり,紙と鉛筆以外の用具を必要とせず,被検者からの受入れも良い. 本邦では酒井ら(2006)がその日本語版(Japanese version of the Rapid Dementia Screening Test: RDST-J)を作成している.
今回われわれはRDST-Jが時計描画課題より軽症認知症の評価に有用である臨床的印象をもち,それについて調査した. 対象はアルツハイマー病(Alzheimer’s disease: AD) 250例と健常群49例で,AD群のMMSEは12-26点,clinical dementia rating scale (CDR)は3-0.5である.患者群をCDRの値で4群に分け,健常群を含めた計5群における時計描画課題とRDST-Jの得点分布を統計学的に検討した.
その結果,認知症の重症度に応じてRDST-J,時計描画課題の成績は低下していた.また軽症AD群に注目するとRDST-Jは健常群とCDR 0.5で有意差を有したが,時計描画課題は有意差を有さなかった.そこでRDST-JにおけるCDR 0.5のスクリーニング検査としての妥当性を調べたところ,カットオフ値を7/8に設定した場合感度57.1%,特異度81.0%で,8/9とすると感度79.6%,特異度55.1% であった.
今回の検討からRDST-Jは時計描画課題と比較し,健常群と CDR0.5 の鑑別補助に有用であることが示された.
(森山泰、2015.10.3.)
解説 認知症疑いの最早期発見
日本社会の急速な高齢化に従い、認知症患者数も急増しつつある。折しもつい先日、当教室の佐渡充洋博士を中心とする研究班が、認知症による我が国の社会的費用は年間14.5兆円にのぼるというデータを発表した。このままいくと、2060年にはこの額は24兆円になると推計されるという。「このままいくと」日本社会は危ない。「このままいかない」ためには、認知症対策を加速しなければならない。そのためにはまず、認知症やその疑いの人々を、簡便な方法で発見しなければならない。母集団は膨大で、ターゲットも膨大であるから、特に簡便な方法でなければならない。
認知症のスクリーニング検査として広く用いられているのはMMSEである。だが、「広く用いられている」と言えるほどには、実際の臨床場面ではあまり使われていないというデータもある。MMSEは、多忙な日常臨床で用いるには、まだまだ簡便さにおいて不十分な検査なのである。
より簡便な検査としては時計描画課題がよく知られているが、森山博士の本論文は、その時計描画課題よりさらに簡便な検査で、軽症アルツハイマー病のスクリーニングが可能であることを示唆したデータを呈示している。結論をひとことで言うと、「健常群とCDR 0.5の鑑別に、RDST-Jが有用」ということである。CDR 0.5とは、「認知症疑い」である。我が国に膨大に存在するこの群を、簡便な検査で発見することの意義は非常に大きい。本論文にはさらに、RDST-J得点が認知症の重症度に応じて低下することも示されている。CDR 0.5からCDR 1、すなわち、「認知症疑い」から「軽度認知症」への移行についての研究は次の課題である。さらにその先へ、認知症の研究は限りなく続く。森山博士は、駒木野病院精神科診療部長という第一線で臨床に携わりつつ、研究論文も休むことなく生産し続けている。
(村松太郎、2015.10.26.)
アルツハイマー病患者におけるドネペジルからガランタミンへの切り替えのSPECTによる効果予測
岡瑞紀 (慶應義塾大学医学研究科大学院博士課程)Oka M, Nakaaki S, Negi A, Miyata J, Nakagawa A, Hirono N, Mimura M.
Predicting the neural effect of switching from donepezil to galantamine based on single-photon emission computed tomography findings in patients with Alzheimer’s disease
Psychogeriatrics.
Article first published online: 26 JUN 2015 | DOI: 10.1111/psyg.12132
本邦で初めて1999年にアルツハイマー病に関して承認されたコリンエステラーゼ阻害薬はドネペジルであるが、2011年にはさらに2種類のコリンエステラーゼ阻害薬が認可された。これまで多数の脳画像研究は、アルツハイマー病患者の前頭葉におけるコリンエステラーゼ阻害薬の治療効果に言及してきた。前頭葉が関与すると言われている、アパシーや遂行機能障害はアルツハイマー病患者及びその家族の生活の質を悪化させる。しかしながら、アパシーと遂行機能障害に対するコリンエステラーゼ阻害薬の神経学的効果はまだ明らかになっていない。そこで、SPECTを用いたベースラインにおける局所脳血流量を用いて、ドネペジルからガランタミンへの切り替えに反応するアルツハイマー病患者のアパシーと遂行機能障害への効果予測を検討した。
慶應義塾大学病院精神神経科外来において、ドネペジルによる治療に反応のなかった(12ヶ月以上ドネぺジル5mg/dayを服用していたがMMSEが1年間で 2点以上低下した)アルツハイマー病患者に対し、ガランタミンへの切り替え24週前向きオープン研究をおこなった。ベースラインの時点でSPECTを施行し、ベースラインおよびガランタミン切り替え後の12週と24週の3時点でMMSE(Mini-Mental State Examination)やADAS-J(the Japanese version of the Alzheimer’s Disease Assessment Scale-cognitive subscale)FAB(the Frontal Assessment Battery)、NPI-Q(the Neuropsychiatry Inventory Brief Questionnaire Form)、DEX(the Dysexecutive Questionnaire)を含む行動及び認知機能検査を施行した。
アルツハイマー病患者(78.6±5.6歳 教育歴 12.5±3.0年)の27名(男11:女16)の結果を検討したところ、ガランタミンへ切り替え後にNPI-Qにおけるアパシー、易怒性、異常行動と遂行機能を評価するDEX値が有意に改善した。いくつかの前頭葉領域(背外側及び腹外側前頭前野、前帯状回、眼窩部前頭野)の脳血流がベースラインで低いほど、ドネペジルからガランタミンへの切り替えを行った後に、NPI-Qにおけるアパシー(負担度)とDEX値がより改善することをSPECTの所見は予測した。
ガランタミンには、アセチルコリンエステラーゼ阻害作用に加え、ニコチン性アセチルコリン受容体への刺激作用を併せ持つ効果がある。この研究は、それらの効果がアパシーと遂行機能障害と関連する前頭葉に影響を与えることを示唆している。
(岡瑞紀、2015.9.19.)
解説 認知症の合理的治療戦略を目指して
病気には症状がある。症状には原因がある。原因を取り除ければ症状が消え、病気は治る。これがシンプルな治療論である。だが現実の病気はなかなかこうシンプルにはいかない。
岡瑞紀大学院生が専門としているアルツハイマー病も、シンプルにいかない病気の一つである。
アルツハイマー病の症状は、認知機能低下である。全般的な低下である。だが認知機能とは多種多様な現れ方をする。全般的な低下というのは、認知症の定義としてはそうであるということであって、低下のプロフィールは当然ながら一人ひとり異なる。病気のステージによっても異なる。
アルツハイマー病の原因論の中心となるのは、アミロイドカスケードである。だがそこから認知機能低下までのメカニズムの全容が解明されているわけではない。プロセスのどの段階を治療ターゲットにするのが最善かも不明である。
アルツハイマー病の薬はある。脳内のアセチルコリンの減少を抑える、コリンエステラーゼ阻害薬である。現在我が国にはドネペジル(アリセプト)、ガランタミン(レミニール)、リバスチグミン(イクセロンパッチ)の3種類があるが、どういう症状のときにどの薬が有効かはわかっていない。
このように、アルツハイマー病について現代の医学が持っている知見は断片的である。断片的だが、たくさんの断片がある。そして断片の数はどんどん増加しつつある。断片をピースとして組み合わせていけば、その先には病気の解明と、より効果的な治療があるはずである。
岡大学院生は、症状として、アパシーと遂行機能障害に着目した。原因論にかかわる客観的なデータとして、脳血流を測定した。薬として、ドネペジルとガランタミンを比較した。そして示唆に富む結果が得られた: アパシーと遂行機能障害は前頭葉の血流低下に関係しているかもしれない。それらの症状にはガランタミンの方が有効かもしれない。それはニコチン性アセチルコリン受容体刺激に関係しているかもしれない。
現時点では、どれも「かもしれない」にとどまる。本論文のデータは、壮大なパズルの1ピースにすぎない。1ピースだが、着実に未来に繋がる貴重な1ピースである。この仕事は岡大学院生の学位論文になった。
(村松太郎、2015.9.26.)
低酸素脳症者の実態、生活支援、社会支援についての多施設共同研究
先崎章 (東京福祉大学教授、埼玉県総合リハビリテーションセンター部長)平成23~26年度 研究報告書 全246ページ (科学研究費助成事業No.23530748、非売品、全国の高次脳機能障害者支援拠点機関に配布)
本冊子は、科学研究費を用いて行った「低酸素脳症とリハビリテーション」に関連する臨床研究と勉強の成果である印刷物を、研究代表者として一冊にまとめたものです。6名の分担研究者ならびに研究協力者による、28編の日本語の臨床論文(先崎章は16編を担当)と、それらの「まとめ(概略)」から成り立っています。
神経心理学研究会は臨床教室が会を主催し、臨床医が集っていることが特徴だと思います。今でこそ実験研究的な発表が多くなりましたが、一昔前は、鹿島晴雄先生、そして加藤元一郎先生の下、極めて日常臨床的なテーマ―をめぐって研究会が運営されていた時期がありました。本研究とこの研究報告書はその流れを受け継いでいるものです。
以下、報告書のまとめ(概略)を転記いたします。
Ⅰ 低酸素脳症者のリハビリテーション
低酸素脳症(anoxic brain injury)とは、心肺疾患などによる心肺停止、呼吸不全、溺水、高度の貧血、一酸化炭素中毒などにより、中枢神経系に一過性に酸素やグルコースの供給が途絶えることによって脳に生じる機能障害を総称したものである。その病態は、①酸素そのものが脳動脈血に供給されない低酸素性低酸素血症(hypoxic encephalopathy)②酸素を運搬するヘモグロビンの減少による貧血性低酸素血症(anemic hypoxia)③脳血流そのものが低下する低酸素性虚血性脳症(hypoxic ischemic encephalopathy)に分類される。
AED(自動対外式除動器)の普及や救命救急医療の発展に伴い、心肺停止後の蘇生率は向上している。そして救命・蘇生されたものの、後遺症が残る場合が多い。その症状は、麻痺や失調などの運動機能障害から、記憶障害を中心とする認知機能障害、発動性低下まで多彩である。回復は他の脳器質疾患と比べて緩慢であり、外傷性脳損傷者とは異なる経過をとる。ただし、リハビリテーション病院で診ている患者は心肺停止例全体の内のほんの一部の例である。
医学的リハビリテーションにおいては、回復期の直接的な機能回復訓練だけではなく、代償的・環境調整的な方法を用いて、患者のできる能力をひきだすことにより生活障害を改善することに重点をおいた、長期的な視点での対応が望まれる。入院から外来、外来から復職への移行期や、医療から介護・福祉、施設から在宅へ移行する等の適切な時期に医学的リハビリテーションの方法を用いて介入することが、社会参加を促進する。自殺企図による溺水、薬物中毒、縊首、練炭などによる一酸化中毒の場合は、発症前の適応状態や家族状況など社会的背景が複雑なことが多い。この場合に社会復帰を支援するためには、心理面の配慮や家族支援に加えて、福祉機関や保健センターなどとの長期的な連携が必要となる。
Ⅱ 低酸素脳症者の生活支援・社会支援
低酸素脳症者では、就労群と非就労群ともに高い抑うつ気分を示していた。気分状態や健康関連QOLは、記憶障害の重症度や、発症からの日数とは必ずしも関連していなかった。一方、記憶障害が重度でも気分が安定している場合もある。すなわち、とりまく環境や介入の方法により、社会活動水準が維持されている場合、「うつ」や「混乱」の尺度が低く、健康度自己評価も「良好」であった。できる能力をひきだし、社会活動水準を維持するような介入を工夫することが重要となる。発症から1年以上経過しても、「できる能力」をひきだすことで、日常生活活動を向上させることができる。社会参加支援のためには、低酸素脳症者においては少なくとも3年間はリハビリテーションが必要である。
身体障害(身体失調、構音障害、嚥下障害)、高次脳機能障害(記憶障害)、精神障害が併存している場合には、在宅生活では多方面にわたるマネジメントが必要となり、主介護者の介護負担が大きい。発動性が低下している場合には、訪問リハビリテーション、通所サービスへの導入が、主介護者の負担感を緩和させうる。ただし社会参加度が向上することで、自宅で家族の役割や責務が大きくなり、主介護者である家族の負担感が大きくなる場合もある。自殺未遂例では、リハビリテーション期間中に明らかな抑うつの再燃はなくとも、復職後に抑うつが再燃しうる。
Ⅲ リハビリテーションの現場におけるICF
外来通院中の低酸素脳症者を、ICF「活動と参加」48項目にて評価したところ、(1)記憶障害や発動性の低下が、ADL低下や社会参加の少なさに関連していること、(2)CAS日常生活行動、やる気スコアや流暢性で把握できる発動性の低下は、FAM運動や認知、ICFの一部の「活動と参加」のコードと相関していること、(3)ICFは低酸素脳症者の生活障害や支援すべき事柄を一部把握していること、が示唆された。
医療と福祉の共通語として、さらに家族も含めてICFを利用するためには、ICFコアセットを利用する方法がある。脳損傷者用に考案された脳外傷コアセット簡易版の「活動と参加」のいくつかの項目と、FAM認知、TBI-31、 Zaritの値との間に相関がみられた。家族でも簡便に使用できるICF脳外傷コアセット簡易版(質問紙版)は、家族の把握する「活動や参加」状況を医療者や福祉従事者が理解することに、ひいては家族支援に利用できる。
Ⅳ 低酸素脳症者の社会支援関連領域
発動性が低下し外界からの介入に拒絶もみられる低酸素脳症者では、社会参加の広がりがなされにくく、無為と拒否とが増強し、家族の心身的負担がさらに大きくなる。低酸素脳症者に特化した当事者の会は少ない。そんな中で、精神科リハビリテーションの基本原則の考え方を、脳損傷後の高次脳機能障害者の場合にも当てはめ支援していくことができる。三つの障害区分を区別することなく支援していく障害者自立支援法が2006年に施行され、2013年4月より、疾病や障害による支援システムの違いをよりなくしていく方向で、障害者総合支援法に変更された。精神科リハビリテーションが対象とする疾患・障害も、従来からの統合失調症、アルコールや認知症に加えて、発達障害、高次脳機能障害と広がりをみせている。
Ⅴ 高次脳機能障害者の医学的支援関連領域
低酸素脳症者の発動性の低下や注意障害、記憶障害に対して、外傷性脳損傷者の高次脳機能障害に対する薬物療法が一部参考になる。適切な時期に医学的リハビリテーションで行われている方法を用いて再評価や介入を行うことが、低酸素脳症者の生活の質を向上させ社会参加を促進する。
今後の課題
社会参加に至らない在宅生活者、施設入所者、就労しても適応障害を起こす者の長期的予後・支援が今後の課題である。記憶障害が特に重篤な者、身体能力が大きく損なわれている者、小児期発症の低酸素脳症者への支援も今後の課題である。
(先崎章、2015.8.22)
解説 低酸素脳症からの回復
脳への酸素供給が停止すると、人間は速やかに死亡する。常識である。
脳への酸素供給が一定時間停止すると、脳に不可逆的な障害が残る。医学常識である。
だがそこから先は? どういう障害が残るのか? それは回復するのか? どんなリハビリテーションが有効なのか?
海馬の神経細胞が低酸素状態に対して特に脆弱であることは神経生物学的にはよく知られているが、そこから臨床像までにはかなりの隔たりがある。低酸素脳症の実際の臨床例は、記憶障害以外にも様々な高次脳機能障害を呈するのが常だ。症状の把握から治療、認知リハビリテーション、そして社会的支援のあり方まで、低酸素脳症の臨床は課題が山積している。
それをどこまでも実践的に追究したのが先崎章教授(東京福祉大学社会福祉学部。埼玉県総合リハビリテーションセンター地域支援担当部長を兼ねる)を代表者とする研究班の本報告書『低酸素脳症者の実態、生活支援、社会支援についての多施設共同研究』である。
救命医療技術の進歩によって、かつてであれば生命を失っていた脳損傷から、多くの人々が生還できるようになった。その結果、後遺症としての高次機能障害を有する人々の数が急増しているのもまた厳然たる事実である。これに伴い、低酸素脳症に限らず、高次脳機能障害の認知リハビリテーションの需要は日々増大している。
先崎章教授は、外傷性脳損傷、低酸素脳症などの最も多くの臨床例と接し、リハビリテーションを実践している医師の一人である。本報告書は彼の仕事が形になった貴重な一冊で、臨床上示唆に富む多数の記述が含まれている。
なお、高次脳機能障害についての基礎知識から、治療・リハビリテーション・就労支援までを、先崎教授が実際のケースを紹介しつつまとめた著書として、
高次脳機能障害 精神医学・心理学的対応 ポケットマニュアル
(医歯薬出版、2009年)
がある。
世の中の「ポケットマニュアル」「ポケット事典」等には、一体どういうポケットに入れるんだと言いたくなるサイズの本も多いが、『高次脳機能障害 精神医学・心理学的対応 ポケットマニュアル』は、新書版で文字通りポケットに携帯できるハンディな名著である。
(村松太郎、2015.8.26.)
【1】Bálint症候群における視空間ワーキングメモリーの低下
船山道隆(足利赤十字病院 神経精神科 部長)
Funayama M, Nakagawa Y, Sunagawa K
Visuospatial working memory is severely impaired in Bálint syndrome patients
Cortex 2015: 255-264 (http:// dx.doi:10.1016/j.cortex.2015.05.023)
【2】Bálint症候群における電化製品のボタン操作
船山道隆(足利赤十字病院 神経精神科 部長)
Sunagawa K, Nakagawa Y, Funayama M
Effectiveness of Use of Button-Operated Electronic Devices Among Persons With Bálint Syndrome.
Am J Occup Ther. 2015 Mar-Apr;69(2):6902290050p1-9. doi: 10.5014/ajot.2015.014522.
【1】 Bálint症候群における視空間ワーキングメモリーの低下
両側頭頂葉の損傷のためにBálint症候群を生じている患者さまは、視覚が保たれているにもかかわらず、部屋の中でも迷ってしまったり、物体に視線を向けられなかったり、物体をつかみ損ねるなど、自分と周囲、あるいは、物体同士の位置関係の把握が困難となる視空間障害が生じることが知られています。視空間障害の原因のひとつには、視空間情報を脳内でイメージ化できない、あるいは、イメージがすぐに消えてしまうことが考えられています。しかしながら、今まではこれを証明する臨床研究はありませんでした。
筆者らはBálint症候群6名における脳内での視空間イメージの能力を検討するために、視空間イメージの保存時間やイメージ能力を測定することができる視空間ワーキングメモリーの検査を行いました。結果は、対照とした右頭頂葉損傷群(15名)と健常群(26名)と比較してBálint症候群では軽度Bálint症候群4名も含めて視空間ワーキングメモリーの成績が低下していました。これらの結果から、Bálint症候群の日常生活の困難さは、脳内の視空間イメージ能力が低下しているためである可能性が考えられました。
筆者らは、これらの結果を踏まえて、さらなる頭頂葉の機能の解明のみならず、頭頂葉損傷の患者さまたちの日常生活動作のリハビリに役立てていきたいと考えています。
【2】 Bálint症候群における電化製品のボタン操作
上記のBálint症候群は視空間障害のために多くの日常生活が困難となります。たとえ家庭内の入浴や洗面といったADLレベルは保たれていても、多くの患者さまで視空間障害のため複雑な道具を使うことが困難となっています。特にパソコン、銀行のATM、携帯電話など近年必須となった電子機器の使用はかなり難しくなっています。しかし、Bálint症候群での電子機器の使用能力に関する臨床研究は未だに行われていませんでした。
筆者らはBálint症候群(7名)の電子機器操作能力を研究するために、スマートフォン、旧式の携帯電話、電卓の3種類を用いて数字の入力能力(1桁から11ケタ)を検討しました。結果は、対照とした健忘群(8名)と健常群(8名)と比較してBálint症候群では軽度Bálint症候群4例も含めて数字の入力の成績が低下していました。ただ、色と高さが周囲と異なるボタンを持つ電卓では、重度Bálint症候群であっても桁数の少ない場合は数字の入力が可能でした。筆者らは、これらの結果をBálint症候群を含めた頭頂葉損傷の患者さまに対する電化機器のリハビリに応用していきたいと考えています。
(船山道隆、2015.7.12.)
解説 不思議な病態の解明から実効ある認知リハビリテーションへ
見えているのに見えていない。バリントBálint症候群とはそんな病態である。
教科書を開けば、精神性注視麻痺(視線を随意に移動できない)、視覚性失調(視覚刺激に応じた協調運動が悪く目の前の対象をつかめない)、空間性注視障害(注視している対象以外に注意が及ばない)の3つがバリント症候群の特徴である・・・と記されているが、このように定義にするとかえってわかりにくい。むしろ、「検査上は視覚は保たれているが、実生活では見えていないかのようである」「視覚的イメージがすぐに脳から消えてしまうようだ」という臨床的な描写のほうがわかりやすいであろう。
頭頂葉から後頭葉のある一定領域の損傷の際に発生するこの稀な症候群は、バリントが1909年に記載して以来、不思議な症候として注目されてきたが、メカニズムは不明のままであった。そんな中で、視覚的ワーキングメモリーの障害は、一つの有力な仮説となっていた。ワーキングメモリーとは、いわば「心の黒板」である。情報を一時的に保持する脳内のバッファーのような機能を指す。たとえば数列を即時に記憶して逆唱するのは、ワーキングメモリーの機能である。
バリント症候群の視覚的ワーキングメモリー障害仮説は、臨床症状からは首肯できるものの、そもそも「見えていない」と表現されるほどの視覚機能の障害があるバリント症候群で視覚的ワーキングメモリーを検証するのは至難の業である。
本論文【1】Bálint症候群における視空間ワーキングメモリーの低下は、足利赤十字病院神経精神科の船山道隆部長がバリント症候群のこの歴史的難題に挑んだ仕事である。それを可能にしたのは、この稀な症候群を複数例発見する臨床医としての手腕と、症状レベルに合った神経心理学的検査を選択する研究者としての慧眼であった。
船山部長による論文【1】の紹介文は
「筆者らは、これらの結果を踏まえて、さらなる頭頂葉の機能の解明のみならず、頭頂葉損傷の患者さまたちの日常生活動作のリハビリに役立てていきたいと考えています。」
と結ばれている。
この一文はある意味定型的な結びである。世の多くの論文はこのように、次のステップへの希望を語る形で結ばれている。そして世の多くの論文の著者はそこで歩みを止めている。論文の結びがそのまま仕事の結びになってしまうのが常だ。
船山部長はそうではなかった。希望の実現に向けて直ちに一歩踏み出した。それが本論文【2】Bálint症候群における電化製品のボタン操作である。
急速に日本社会に普及したIT機器は、高次脳機能障害の人々にとっては諸刃の剣である。IT機器は一方では「認知装具 cognitive orthoses」「認知義肢cognitive prosthetics」などの用語が示すように、認知リハビリテーションに活用できる有力なツールであるが(本サイト2015.5.25. 『認知リハビリテーション実践ガイド』第7章 外的エイド使用の訓練 参照)、他方では生活の自立を阻むバリアとなっている。たとえば単純なテンキー入力ができなければ、銀行のATMや携帯電話などを使用することができず、すると現代社会の生活においては深刻な障害となる。「見えているのに見えていない」バリント症候群では、テンキー入力は重要な課題である。
本論文【2】は、この問題に着目し、バリント症候群の人々の日常生活改善を目指した仕事である。スマホ、ガラケー、電卓は、テンキーという意味では同じでも、ボタンの視覚的形状が少しずつ違っている。健常者にとっては、言われてみれば違っているなと思いあたる程度であるが、バリントの人々にとっては操作の可否を決定的に左右する違いになり得る。本論文【2】はそれを実証的に示したもので、IT機器のリハビリテーションの計画立案に際しての重要な基礎データとなるものである。
船山部長の本論文【1】【2】は、バリント症候群という歴史的な病態について、そのメカニズムの解明にとどまらず、原著の記載から百年を過ぎた現代のIT機器のリハビリテーションに至る、雄大なスケールの仕事である。その根底には高次脳機能障害者の日常生活機能の改善という最終目標がある。認知のバリアフリーは、神経心理学の目指す重要なゴールの一つである。
(村松太郎、2015.7.26.)
統合失調症のワーキングメモリの障害に関するコンピューテイショナルアプローチ
沖村宰(慶應義塾大学医学研究科大学院博士課程)Okimura T, Tanaka S, Maeda T, Kato M, Mimura M
Simulation of the capacity and precision of working memory in the hypodopaminergic state: Relevance to schizophrenia.
Neuroscience, 295: 80-89, 2015.
統合失調症におけるワーキングメモリ(WM)障害の脳基盤は、前頭前野(PFC)でのD1受容体機能の低下であるという実験的アプローチからの仮説がある。実験的アプローチというのは、ヒトと動物を対象とした神経心理学的アプローチや神経生理学的アプローチである。この仮説をこれらのアプローチから検証し、詳細な病態メカニズムを解明し、治療戦略を開発することは現在のところ困難である。何故であろうか?この仮説に関する理想的な研究目標を考えてみると明らかになる。すなわち、未治療の統合失調症患者に対して、動物実験でのような神経生理学的アプローチによるPFCのD1受容体機能とWM障害の関連性を示し、脳神経回路レベルでの動的な測定によるWM障害の機序の解明という理想的な研究目標は現在のところ困難であるということである。しかし、統合失調症におけるWM障害が、この病の顕在発症前後から人生の終わりまで続き、患者の人生の負担になっていることを鑑みれば、何らかの進展が必要とされる。その1つの進展として、理論的アプローチであるComputational psychiatry(計算論的精神医学)というものが、近年、生物学的な妥当性をもちうるまでに発展し、統合失調症の病態メカニズムの理論的枠組みへの示唆を与えてきている。
聞きなれぬアプローチである計算論的精神医学について概要を述べる必要があろう。このアプローチは、実験物理学と理論物理学とのアナロジーでいえば、後者である。すなわち、精神疾患の研究において、実験的アプローチから得られた脳神経基盤や行動・症状の知見を数理モデルで表現し、数理モデルからもたらされる演繹的結果から、実験的アプローチの研究への予測を与えるという役割である。メリットとしては、①数理モデルが形成されれば、モデルに変化を加えることで簡単に障害モデルを形成、すなわち、未治療患者のモデルを作成できること、②モデルの動的振る舞いも簡単に表現できるので、詳細な病態メカニズムを追及できること、③障害モデルに対し、さらに数理的に変化を加えることで障害が健常化するかを簡単に検証できるので、治療戦略の仮説検証、例えば、薬物の機序からの治療効果の予測、これまで考えられなかったような治療戦略の示唆が可能であることが挙げられる。
このメリットが実験的アプローチに新たな視点を加え、統合失調症のWM障害の治療に光を投げかけられるようにするためには、計算論的精神医学が統合失調症の病態メカニズムの理論的枠組みへの示唆を与えるだけでは事足りず、実験的アプローチに直接リンクできるほどの詳細な描写をもって脳基盤のダイナミクスや症状の特徴を与えなければならず、その上で治療戦略への示唆が実験的アプローチで取込み可能となる。これまで、詳細に脳基盤とWM障害を対応付けた計算論的精神医学的研究は、著者の知る限りでは存在しない。
本研究の方法であるが、脳基盤として、NMDA、AMPA、GABAA受容体、Nap, Ca依存性Kイオンチャンネルをもった錐体細胞と抑制性介在ニューロンを数理モデル化し、相互作用をもつように全てつなげた。これら各受容体やイオンチャネルの機能は、D1受容体を介したドーパミン調節により増減できるようにした。この神経回路モデルによるWMの実験系として、円周上に10°毎離れた36個のスポットを用意し、4つのスポットに同時に100ミリ秒間キューを与え、キューが消えた後、2000ミリ秒間、与えられた4つのスポットの位置を保持しておけるかという系をたてた。ドーパミン濃度を枯渇状態から健常者レベル、飽和状態と7段階に変えて、WM保持の能力をWM容量(4つのスポットのうちいくつ保持できているか)とWM精度(保持されたスポットの位置がどれだけ正確であるか)をシミュレーションした。
結果として、WM容量は、ドーパミン濃度が健常者のレベルのときに最高となり、それより少なくても多くても低下した。これは、Goldman-Rakicらが示唆したD1受容体を介したドーパミン調節とWM機能のinverted-U特性を具体的にシミュレーションで再現化したことを意味する。また統合失調症ではWM容量が低下することが示されているが、これとも一致した。しかしWM容量はドーパミン濃度が低下しても増加してもWM容量が低下すること、他精神疾患でもWM容量の低下は認めることを考えると、WM容量低下だけを示すことでは統合失調症の特徴を描ききれていない。そこで、WM精度の結果の動的振る舞いを計算すると、ドーパミン濃度が低下しているときには、時間とともに保持されたスポットの位置がランダムに移動し、結果としてWM精度は低下した。ドーパミン濃度が増加しているときには、保持されたスポットの位置は健常者のときと同じ程度の正確さでもって維持された。統合失調症でのWM精度は低下しているか健常者と同じかは、先行研究では一致していない。実験系や測定方法の問題もあるが、薬物の影響もある。例えば、クロザピンの内服をしている患者が多かった患者群と健常者群の間でWM精度の差がなかったという研究がある。この研究について、本研究からの考察を試みると、まず、本研究から示唆された統合失調症におけるWM容量と精度の両方の低下の機序は、①D1受容体機能の低下は、NMDA受容体の機能の低下をもたらすので錐体細胞の発火が維持できなくなるためにWM容量が低下し、②D1受容体機能の低下は、NMDA受容体の機能の低下と抑制性介在ニューロンの発火の低下をもたらすことでランダムなノイズの影響が増加するためにWM精度が低下する、である。次に、クロザピンには、D1受容体機能以外への薬理学的特性もあり、直接的にNMDA受容体機能を増加させ、抑制性介在ニューロンの興奮性を高めるという報告がある。従って、上記本研究からの示唆とクロザピンの薬理学的特性を合わせると、クロザピンの内服患者では、WM容量よりもWM精度の方がより良く改善され、結果、WM精度のみが健常者と同じになるという例にあげた研究の結果が演繹的に説明される。このように、神経心理学と精神薬理学を包括したより詳細な考察がなされることは、計算論的精神医学の一つのメリットである。また、本研究では治療戦略に関してのシミュレーションも行った。D1受容体機能が軽度低下のときにNMDA受容体の機能のみを高めるとWMの機能は、容量と精度ともに改善した。このことは、NMDA受容体の機能を増強する薬物の臨床治験へのサポート、抗精神病薬との併用療法によりWM障害が改善するという治療戦略を示唆している。
本研究は、WMの保持の側面しかとらえていないこと、また数理モデルとして多数ある抑制性介在ニューロンを1つにしている点などの多くの限界があるが、計算論的精神医学というアプローチが統合失調症の病態メカニズムと治療戦略についての理論的示唆に大きな可能性を秘めていることが示されたと考える。本研究での数理モデルをさらに大規模かつ精巧にし、統合失調症の医療の一助になればと考える。
(沖村宰. 2015.6.15.)
解説 計算論的精神医学で統合失調症の謎に迫る
生物学的精神医学は、優れて実証的である。
臨床精神医学は、優れて実務的である。
計算論的精神医学は、この両者を橋渡しする新たな方法論である。
まさに待望の方法論と言えよう。なぜなら、生物学的精神医学の知見が近年ますます蓄積されているのにもかかわらず、生物学的なデータと臨床的な症候の間のギャップが依然として埋まらないからだ。
統合失調症に例を取れば、ドーパミンセオリーが提唱されてからの数十年間で、統合失調症の脳とドーパミンについての論文は膨大に出版されているが、統合失調症の臨床症状の大部分は、いまだ説明されるに至っていない。生物学的精神医学の知見と臨床精神医学の間の隔たりは大きく、そして深いのが現実なのである。このギャップを埋めるためには、従来からの精神医学や神経科学では不可能で、新たな方法論を大胆に取り入れなければならない。
そこで大きな期待が懸けられているのが計算論的精神医学 Computational Psychiatryである。
計算論的精神医学とは計算論的アプローチを手法とする精神医学である。計算論的アプローチでは、脳が外界といかに相互作用し情報を処理しているのかに着目する。いわば情報処理機構としての脳・神経システムの計算原理を探求する研究手法である。
東大で数理工学を学んでから医学に転じ精神科医となった沖村宰大学院生は、コンピューターを駆使し、統合失調症の脳内過程のシミュレーションを続けている。そこからの成果物の一つである本論文の圧巻は、いわゆる “inverted U” についての理解の深化である。Inverted Uは、Goldman-Rakicらが1995年のnature誌論文で初めて示唆したもので、「ワーキングメモリ容量は、ドーパミン濃度が健常者のレベルのときに最高となり、それより少なくても多くても低下する」という結果を、横軸をドーパミン濃度、縦軸をワーキングメモリ容量としたグラフに視覚化したものである。Inverted Uは、ドーパミンという物質と臨床症状のより実証的な接点を予感させる斬新で優れたものであったが、発表されて以来約20年が経過しても、統合失調症の症状への接近は遅々として進まない状態であった。沖村院生による本論文はこのギャップを埋める画期的なデータを示した研究である。
ワーキングメモリについて得られた本研究の結果は、より合理的な薬物療法戦略に繋がり得る。また、計算論的精神医学は、統合失調症の他の症状や認知機能の解明にも活用できる。Sense of Agency (自己主体感)もその重要なターゲットの一つで、沖村院生は現在、SoAタスク(本サイト2014.3. 前田講師「統合失調症の自我障害についての実証的研究」参照)への計算論的アプローチにも精力的に従事している。
「計算論的精神医学」が聞きなれぬ言葉から一般的な言葉となる頃には、統合失調症の病態理解も治療戦略も飛躍的に発展し、精神医学の臨床は現代とは異次元の風景になっているかもしれない。
(村松太郎、2015.6.22.)
認知リハビリテーション実践ガイド 医学書院 2015年6月1日発売監訳 村松太郎 (慶應義塾大学医学部精神神経科 准教授)
訳 穴水幸子(国際医療福祉大学 講師)
小口芳世(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)
小西海香(慶應義塾大学医学部精神神経科)
斎藤文恵(慶應義塾大学医学部精神神経科)
高畑圭輔(独立行政法人放射線医学総合研究所)
野崎昭子(東京武蔵野病院)
藤永直美(東京都リハビリテーション病院)
村松太郎(慶應義塾大学医学部精神神経科)
解説 エビデンスに基づく認知リハビリテーション
本書は
McKay Moore Sohlberg, Lyn S. Turkstra
Optimizing Cognitive Rehabilitation --- Effective Instructional Methods
The Guilford Press 2011
を、当研究室のメンバーが訳出したものである。
本書は邦題の通り、まさに「実践ガイド」である。この一冊があれば、認知リハビリテーションを実践できる。そのように断言しても差し支えないくらい、実地臨床がそのまま映し出された一冊である。臨場感溢れる臨床の実例がある。訓練の実際が記録されたワークシートがある。そのワークシートは本書の付表をコピーして、あるいはホームページからダウンロードして、すぐにも実地で使用可能である。そして本書に紹介されているリハビリテーションの技法にはすべて有効性のエビデンスがあることが、第Ⅰ部の基礎編に膨大な文献とともに示されている。認知リハビリテーションの臨床・研究両方における現代の第一人者であるSohlbergとTurkstraが著すことで初めて可能になった実践ガイドである。(あまりに実践的なため翻訳に困窮した部分もあった。著者らが臨床で用いていて、辞書には出ていないローカルな略語の意味がどうしてもわからなかった。そこでSohlberg先生に直接問い合わせたところ、” I am glad that our textbook will be useful to your people”というお言葉とともに、すぐに丁寧にご教示いただき、解決することができた)
構成が美しく、読みやすいことも本書の大きな特長となっている。全体を通してのキーワードはPIEである。数々の訓練技法が、
計画(P: Plan),
実行(I: Implementation),
評価(E: Evaluation)
という枠組みで整理されている。
認知リハビリテーションの実践とは、このPIEの流れにそって、次の問いに答えていくものであるというのが著者らの教えである:
WHO: 患者の特性
WHAT: ターゲットタスク (何を教えれば生活が改善するのか?)
WHERE: ターゲット環境 (どこでターゲットタスクが使われるのか?)
WHEN: ターゲットタスク実行のタイミング
WHY: ゴールの設定
HOW: 患者個別計画のデザイン
そして具体的な訓練法が、第Ⅱ部 実践編 に示されている。すなわち事実と概念(5章)、多段階ステップの訓練(6章)、外的エイド使用訓練(7章)、メタ認知的方略訓練(8章)、社会的技能訓練(9章)である。近年、認知リハビリテーションに急速に導入されてきている、IT機器を活用した訓練についての記載も豊富である。
原書には “Effective Instructional Method” と副題がつけられている。「効果的な教示法」。著者らの自信がこめられた副題だ。その自信には基礎と実践の両方からの裏づけがある。
まさに実践ガイドである。
なお本書は医学書院ホームページ
http://www.igaku-shoin.co.jp/bookDetail.do?book=86156
にも紹介されている。
(村松太郎、2015.5.25.)
高機能自閉スペクトラム症児における認知及び症状プロフィールの性差
熊崎博一(大阪大学連合小児発達学研究科 助教 福井大学子どものこころの発達研究センター 特命助教)Kumazaki H, Muramatsu T, Kosaka H, Fujisawa T, Iwata K, Tomoda A, Tsuchiya K, Mimura M. Sex differences in cognitive and symptom profiles in children with high functioning autism spectrum disorders . Research in Autism Spectrum Disorders 13-14: 1-7, 2015.
精神科外来において女児の高機能自閉スペクトラム症(Autism spectrum disorder: ASD)が二次障害を来たし受診となるケースをしばしば経験する。社会相互性の障害が一因となり、教育年齢ではいじめや不登校、青年期では職場不適応から暴力や犯罪などの様々な社会的破綻をきたし深刻な問題となっている。ケースに遭遇するたびに“何故もっと早く介入できなかったのか、健診では何故引っかからなかったのか”と悔しさを感じることもある。女児で高機能のケースは男児のケースと比べ幼少期には症状が見えづらいと言われており、女児の高機能ASDをいかに早期発見するかは喫緊の課題となっている。
我々はASDの性差について対象年齢を思春期前の狭い年齢範囲を対象として性差を調査した。WISCプロフィールについては各項目において有意な差を認めなかったが、CARS(Child Autistic Rating Scale)プロフィールについては女児で男児より嗅覚・味覚・触覚(近接感覚)について重症度が重いとの結果が出た。感覚過敏はASDの患者にとって実生活の中で抱く困難性の本質に近く、そのコントロールは社会性の獲得や対人関係の学習に重要な影響を及ぼすことからASDの核心部分との関連が深いとの見方もある。感覚の問題は低年齢においても特徴的であるが現在まで感覚の性差についての報告はほとんどない。ASDにおいて嗅覚特性が強いことがコミュニケーション能力や不適応行為の予後を示唆するとの報告があることからも嗅覚に着目する意義は大きい。今後嗅覚をはじめとした近接感覚に着目することで、女性のASD、とりわけ予後の悪い群への早期発見・早期介入につながるかもしれないと考えている。
(熊崎博一、2015.4.19)
解説 自閉スペクトラム症の診断精度を研ぎ澄ます
自閉スペクトラム症(ASD)は、男児のケースがはるかに多いことはよく知られている。それを説明する仮説として、Baron-Cohenによる有名なextreme male brain theory がある。ASDの認知機能の特徴はそのまま「男の脳」の特徴であり、それが女児のASDが少ない理由だとするのがこの仮説である。
この説明は納得しやすく、性差の生物学にも一致した合理的な理論に思える。だがあくまでも仮説にすぎないことには注意が必要である。納得しやすい仮説は、精密な検証がなされる前に受け入れられてしまうことがしばしばあり、その結果誤った道に迷い込む危険が生まれるのは、extreme male brain theoryも例外ではない。
その危険の一つが、女児のASDが見落とされやすくなることである。
熊崎博一助教は、児童精神科の豊富な臨床経験に基づき、多数の女児のASDが診断されないままに埋もれているのではないかという強い問題意識を持ち、本研究に着手した。そして女児ASDの近接感覚(嗅覚・味覚・触覚)の異常は相対的に重いというクリアな結果を得た。
ASDについての過去の研究論文によれば、IQによってその有病率の性差は異なる傾向が認められている。IQが高いと、男女比はより大きくなるのである(IQが高い女児ASDはより少ない)。これは、IQの高い女児は、自らのASD傾向を認識し、それを隠蔽することで適応しており、ASDであることが見えにくくなっているためであると考えられている。すると、認知機能に基づく評価は女児ASDの診断を混乱させることになり、正確な診断のためにはより生物学的な指標が求められる。
この意味でも、近接感覚(嗅覚・味覚・触覚)の測定が女児ASDの診断に役立つとすれば、臨床的に非常に有意義な知見であるといえる。
次のステップはこの結果をさらに洗練し、実臨床の診断に役立てることである。熊崎助教は、工学系の共同研究者が新たに開発した嗅覚測定機器を用いて、早速その仕事に着手している。治療に関しては、ロボットを用いた自閉スペクトラム症児への介入という先駆的な分野にも参入するなど、福井に拠点を置きつつ、国内外を精力的に飛び回り研究を続けている。
(村松太郎、2015.4.22)
他人の不幸は蜜の味
加藤元一郎 (慶應義塾大学医学部精神神経科教授)Takahashi H, Kato M, Matsuura M, Mobbs D, Suhara T, Okubo Y.
When Your Gain Is My Pain and Your Pain Is My Gain: Neural Correlates of Envy and Schadenfreude.
Science. 2009; 323: 937-939.
解説 その先へ
慶應の神経心理学研究室を創始当時から約30年間にわたり牽引されてきた加藤元一郎教授の代表作の一つが、Science誌に掲載されたこの論文である。タイトルにあるドイツ語のSchadenfreudeという単語には、英語にも日本語にも適切な訳語がない。あえて訳せば「恥知らずの悦び」とでもなろうか。意味するところは「他人の不幸は蜜の味」である。人は妬む。他人の不幸を喜ぶ。人間の感情の中で最も醜いとされるこれらに挑んだ野心的な研究がこの「他人の成功を妬み、他人の失敗を喜ぶ --- 妬みとシャーデンフロイデの脳基盤」である。
巧妙な心理課題とfMRIを組み合わせた本研究の結果は大きく三つある。第一に、妬みの感情には前部帯状回が関連していること。第二に、妬みの対象の人物に不幸が起こると、線条体が活動すること。いずれも重要なデータであるが、前部帯状回が葛藤を処理する部位であり、線条体が報酬に関連する部位であることに鑑みれば、ここまでは従来の研究を同一平面上に拡大した結果であるとも言えよう。
本研究の圧巻はここからである。妬みに関連する前部帯状回の活動が高い人ほど、他人の不幸に対して線条体が強く反応する。それが本研究の第三のデータである。「他人の不幸は蜜の味」と強く感じる人と、それほどでもない人はどこが違うのか、それについての脳内メカニズムの一端を明らかにしたこの結果は、人間の感情についての脳科学に、立体的に新たな次元を書き加えた画期的なデータである。
自分がより良く生きたいという気持ちを人間の光だとすれば、妬みやシャーデンフロイデはそれに伴う影である。向上心の進化に伴う影。この影は恥知らずの行為を形成し、影が伸びれば犯罪にもつながる。進化は人間の心に様々な影を作ってきた。攻撃性。嘘。独占欲。等々。こうした影は、時として人間の光の部分を真っ暗に覆い隠してしまう。しかしだからといってこれらを道徳論で抑え込もうとしても成功しないことは、人類の長い歴史が証明している。人間の醜い部分から目をそむけても、醜さが消滅するわけではない。否認の防衛機制はいつか破綻する運命にある。
妬みやシャーデンフロイデに代表される、人間の進化に伴う醜い部分。これらがモンスターのように成長し、人類を破滅に導くことを防ぐためには、直視して正体を見極めることから始めなければならない。「俺が物を書くとしたら進化の本だ」、あるとき加藤教授が口にした言葉である。
いかなる研究データも、より大きな問いに答えるためのステップである。本研究では、「他人の不幸は蜜の味」の脳内メカニズムの一端が解明された。それだけでは興味本位にさえ見える。だがその先には、人類の幸福への道が開けている。道は長く、ゴールははるか彼方に思えるが、その道は確かに光に溢れている。妬みやシャーデンフロイデの脳内メカニズムの解明は、これらの感情のより合理的な解決へのスタートラインである。データを理解すること、そして次のステップに生かすこと。それが、優れた研究論文への最大の敬意である。
(村松太郎、2015.3.30.)
非現実的な思考にとらわれて就職活動に困難をきたしている頭部外傷の1例
堀田章悟(慶應義塾大学医学部精神神経科 臨床心理士)第24回認知リハビリテーション研究会 2014年11月1日 東京
堀田章悟、元木順子、江口洋子、小西海香、三村將
認知機能が比較的保たれているが社会的行動障害を呈する患者には、リフレーミングを用いた心理的アプローチが有効であると考えられる症例を報告した。
症例は40歳代男性、X-8年に頭部打撲し、前頭葉出血、脳挫傷と右硬膜外血腫を認めた。他院により高次脳機能のリハビリテーションと経過観察を受けていたが、その後、通院は中断していた。X年より当院に受診。認知機能検査において明らかな低下は認めないが、社会的行動障害を呈していた。
受傷後、一時は受傷前の職場に復帰したが、以前の職種に戻るのが難しかった。前職から再び依頼の声がかかるという非現実的な思考、病識の低下などから再就職活動に困難を生じていた。
本症例は神経心理検査上では成績良好で認知機能は保たれていた。以前に高次脳機能のリハビリを受けており、現在は就労支援施設のプログラムに参加中である。したがって認知機能のリハビリよりも、心理的側面からのアプローチの必要性を考え、自己認識の変化の促進を目標にリフレーミングを援用した心理療法を実施した。
面接を重ねるにつれ、当初は「単純な作業ばかり」「もっと重度の人が受けるもの」と否定的な見方を示していた就労支援施設のプログラムへの参加について、「リズムづくりにはなっている」「高次脳機能障害を抱えつつ働いている人の話が聞けそう」など新しい受け取り方を獲得し、その点を自ら話すようになった。さらに、面接者の問いかけに対して「前職への復帰はブランクのために難しいかもしれない」と、以前の非現実的な答えから、現在の状況を客観的に答える場面も見られるようになった。これらのことからリフレーミングを援用した心理療法により、職業に関する自己認識の変化を促すことができたと考えた。
(堀田章悟、2015.2.23.)
解説 思い込みを正す
キーワードはリフレーミングである。リフレーミングとは、思い込みを解きほぐし、新しい視点を受け入れさせるという心理療法の技法である。
通常は脳損傷者を対象に用いるものではないこの技法を、脳損傷者の中でも特に認知リハビリテーションが困難な社会的行動障害に適用するという果敢な発想を実行に移し、根気良く続けることによって成果を挙げたのが、堀田章悟臨床心理士の本報告である。
果敢といっても、単に奇を衒ったわけでは決してない。この症例個人が、顕著な社会的行動障害を有しているにもかかわらず、通常の認知機能検査の成績は保たれていたことに堀田臨床心理士は着目し、リフレーミングが有効であろうと予測したのである。一見すると大胆な彼の治療計画は、緻密な神経心理学的検査の分析に裏打ちされている。
脳損傷が、脳の機能の一部を失わせるのは冷厳な事実である。そのため治療者は、失われた機能は取り戻せないという敗北主義に陥りがちである。そうした治療者の側の思い込みが、脳損傷者への積極的なかかわりを阻む傾向があることは否めない。堀田臨床心理士の本研究は、リフレーミングを患者の治療に応用したことにとどまらず、一般的な心理療法は脳損傷者には適用できないという治療者の思い込みを正すリフレーミングの必要性を示唆するものと言えるかもしれない。
(村松太郎、2015.2.26.)
ターナー症候群における白質異常
山縣文 (慶應義塾大学医学部精神神経科助教)Yamagata B, Barnea-Goraly N, Marzelli MJ, Park Y, Hong DS, Mimura M, Reiss AL. White Matter Aberrations in Prepubertal Estrogen-Naive Girls with Monosomic Turner Syndrome. Cereb Cortex 2012; 22:2761-2768.
ターナー症候群(Turner Syndrome; TS)は、正常女性の性染色体がXXの2本なのに対し、X染色体が1本しかないことによって発症する一連の症候群である(45XO)。低身長、心疾患、二次性徴の欠如といった身体的特徴と視空間構成、遂行機能また社会認知が同年齢の健常者と比べ障害されているという認知特性を有している。TSを対象とした脳画像研究は、女性において、X染色体の異数性が認知や脳の発達へどのように影響するのかを理解するために重要である。過去のMRI研究からTSにおける視空間構成や計算能力の障害が頭頂葉の灰白質の体積減少や前頭−頭頂葉の機能低下と関連していることが示唆されている。さらに近年、作動記憶課題遂行中の前頭葉と頭頂葉の機能的結合がTSにおいて障害されていることも報告されている。一方で、Diffusion Tensor Imaging (DTI)を用いてTSにおける白質構造異常を調べた研究は過去に2編しかないが (Molko et al., 2004; Holzapfel et al., 2006)、それらは、mosaicとnon-mosaic genotype(モザイク型と完全型)を含んだheterogeneousなsampleであり、またエストロゲン治療のよる認知機能や脳の発達への影響を考慮されていない。そこで、今回、我々はエストロゲン治療を受けていない思春期前のnon-mosaicなTSを対象にその白質の構造異常についてMRIを用いて検討した。
3〜12歳のTS群(26名)と健常対照群(20名)を対象にTract-based spatial statistics (TBSS)、Atlas-based ROI analysis、Fiber-trackingといった 3つの異なる DTI解析方法とVoxel-based Morphometry (VBM)を用いて群間における拡散異方性(Fractional anisotropy; FA)と白質の体積の違いを調査した。
その結果、TSは視空間構成、表情認知、感覚運動、社会認知に関与する脳領域の白質繊維において健常対照群と比較して有意なFA値の低下を示した。特に全ての解析方法において一貫して左の上縦束および紡錘状回においてTSのFA値が低下していることが示された。
今回の我々の結果より、TSの認知特性に関連する脳領域において白質構造異常が示された。特に前頭葉と頭頂葉を結ぶ白質繊維である上縦束において微細な白質構造異常がTSに認められたことは現在までに集積されている脳画像研究の知見をさらに支持するものとなった。今後、TSだけでなくKlinefelter’s syndrome (47 XXY)、XYY syndrome (47 XYY)といった性染色体の異数性を有する他の遺伝子疾患も含めた脳画像研究を進めていくことで、性染色体遺伝子と脳の発達、臨床症状の関係(Gene-Brain-Behavior)を知る機会をさらに我々に与えてくれると期待される。
(山縣文、2015.1.21.)
解説 遺伝子から脳へ、そして認知機能へ
人間存在の根源ともいうべき物質、遺伝子。現代の神経心理学では、人間の行動を、そして認知機能を、遺伝子まで遡って研究することが可能になっている。山縣文博士は、遺伝子検査・脳画像検査・認知機能検査を駆使して、ターナー症候群という昔から広く知られている疾患に新たな光をあて、その本質に迫るデータを得た。
ターナー症候群は、染色体異常の中では頻度の高いものであるが、遺伝子的にも臨床的にも決して均一でない。X染色体が1本欠けている「完全型 non-mosaic」と、正常染色体を持つ細胞の混在を認める「モザイク型 mosaic」では、臨床像がかなり異なり、したがって脳の所見も異なることが当然に推定される。また、治療として用いられるエストロゲンは、認知機能にも影響する。ターナー症候群についての過去の研究は、こうした点についての厳密さに欠くため、信頼性にはかなりの限界があった。山縣博士は、完全型 non-mosaicで、かつエストロゲン治療を受けていないターナー症候群のみに対象を厳選することによって、従来の研究を大きく超えた地点に到達した。山縣博士のデータは、遺伝子から臨床像に至るターナー症候群のメカニズムの解明と新たな治療のターゲットの開発に繋がるものであるのみならず、Gene-Brain-Behavior(遺伝子-脳-行動)についての人類の知識の貴重な1ページを綴るものであると言える。
本研究は、山縣博士が2010年から2012年まで留学していたアメリカのスタンフォード大学(Center for Interdisciplinary Brain Sciences Research, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine)で行った仕事である。現在山縣博士は、対象を発達障害に広げ、Gene-Brain-Behavior(遺伝子-脳-行動)のアプローチを継続している。
(村松太郎、2015.1.24.)
抗うつ薬ノルトリプリチンによる脳内ノルエピネフリントランスポーターの占有率
高野晴成 (放射線医学総合研究所 分子イメージング研究センター 臨床研究支援室 室長、分子神経イメージング研究プログラム)Takano H, Arakawa R, Nogami T, Suzuki M, Nagashima T, Fujiwara H, Kimura Y, Kodaka F, Takahata K, Shimada H, Murakami Y, Tateno A, Yamada M, Ito H, Kawamura K, Zhang MR, Takahashi H, Kato M, Okubo Y, Suhara T.
Norepinephrine transporter occupancy by nortriptyline in patients with depression: a positron emission tomography study with (S,S)-[18F]FMeNER-D₂.
Int J Neuropsychopharmacol 17(4):553-60, 2014.
Positron emission tomography (PET)は一つ一つの神経伝達系に特異的な放射性プローブを用いて、その機能を評価していくものである。計測の精度は放射性プローブの開発に大きく依存する。ノルエピネフリンはドーパミン、セロトニンと並ぶモノアミンの御三家の一つであり、その脳内トランスポーターは抗うつ薬の主要な標的でありながら、適切なPETプローブの開発は遅れていた。放射線医学総合研究所では世界に先駆けてF-18 FMeNER-D2を用いた脳内ノルエピネフリントランスポーター(NET)の人での測定方法を確立し、臨床応用を進めてきた。本研究ではNETに選択的な抗うつ薬ノルトリプリチンを服用中のうつ病患者の服薬量、血中濃度と脳内NET占有率を測定した。ノルトリプリチンは最小有効血中濃度が知られており、本研究のデータからその時の脳内NET占有率は約50%と推定された。すなわち、うつ病の治療においては50%以上の脳内NET占有率が必要であることが示唆された。ノルエピネフリン神経伝達は注意や意欲などの機能に関与しており、うつ病のみならず他の精神疾患においても検討が望まれる。このようにPETでは生きた人間で非侵襲的に脳内の生化学的な機能情報が得られるため、脳科学研究や精神神経疾患の臨床研究においてきわめて有用な道具である。
(高野晴成、2014.12.1)
解説 より洗練された抗うつ薬治療へ
抗うつ薬についての現代の精神医学が持っている知は、次のA, B, Cに要約することができる:
A. 抗うつ薬は、うつ病に有効である。これは、わかっている。
B. 抗うつ薬は、なぜうつ病に有効なのか。これは、よくわかっていない。
C. 抗うつ薬は、うつ病を有効に治療するためにはどのくらいの量を飲めばいいのか。これは、大体はわかっている。
すなわち、「このくらいの量の抗うつ薬を飲めば、うつ病はよくなるが、なぜその量が適切なのか、なぜうつ病がよくなるのかは、よくわかっていない」のが現状である。
ここには、「なぜその量が適切なのか」と「なぜうつ病がよくなるのか」という、二つの未解決の、そして重大な問いがある。この問いに対する答えが得られれば、うつ病のメカニズムについての理解は大きく進歩し、うつ病の治療法は大きく改善され、うつ病の人々の大きな恩恵になることは間違いない。
放射線医学総合研究所高野晴成室長の本研究は、この問いの解決に大きく貢献するものである。抗うつ薬に限らず、薬の適量は、最も単純には飲む薬の量、次の段階としては血中濃度の測定によって決めるのが一般的だが、最終的には人体内のその薬のターゲットにどれだけ有効に到達しているかが決め手になる。抗うつ薬ノルトリプリチン(商品名ノリトレン)のターゲットがノルエピネフリントランスポーター(NET)であることは、かなり以前から明らかにされていたが、薬がそこにどれだけ到達しているかを測定する方法がなく、適量は血中濃度のレベルで判定する以外にない状況が続いていた。それを打開したのが、本研究の原題に示されている(S,S)-[18F]FMeNER-D₂という化学物質である。放射線医学総合研究所で開発されたこの化学物質によって、ノルトリプチリンにおいて「なぜその量が適切なのか」を明らかにした本研究は、基礎と臨床の融合による見事な結実と言えよう。そして「なぜうつ病がよくなるのか」という問いの解明にも繋がることが大いに期待される。
高野室長は現在、国立精神・神経医療研究センター病院 第一精神診療部 医長として精神科臨床を行うとともに、脳病態統合イメージングセンター 臨床脳画像研究部に所属し、ニューロイメージングを駆使したさらなる研究を進めている。
(村松太郎、2014.12.18)
ドイツアーヘンでの留学手記 ---ブーメラン---
加藤隆(Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinik Aachen)臨床精神医学 43(11) 1675-1677, 2014.
MEG(Magnetoencephalography)とは、脳の神経活動に伴って生じる磁場変化を頭蓋骨に接したコイルで測定し、その活動源の時間的・空間的定位を行う脳機能画像研究である。空間定位のモデルには様々な方法が知られているが、基本的には個々人の脳に即した座標系を用いることがもっぱらであり、それ故MEG手技における最大の問題点は標準脳における活動への解釈が極めて困難な部分であると考えられる。統計学的な処理を極めて煩雑とさせ、fMRIと比較された場合の空間分解能の低下に繋がるこれらの問題は、新たな解析方法の開発と併せて是非とも解決されなければならない。近年Matlabをプラットフォームとして動作するSPM(Statistical Parametric Mapping)が、得られたMEGデータの統計的解析を可能としつつあり、著者はMatlabの習熟と併せて最新の解析手技をドイツ・アーヘンにて学んでいる。
(加藤隆 2014.11.19)
解説 充実のドイツ生活
慶應で学位取得後、さらなる躍進を目指してドイツに飛んだ加藤隆博士の留学記が『ドイツアーヘンでの留学手記 ---ブーメラン--- 』である。
ドイツ語という言語についての加藤博士自身の個人史と論評と現状から始まり、アーヘンという街と彼の勤務先であるアーヘン工科大学(ノルトラインヴェストファーレン州立の技術専門大学)の紹介、そして学生時代のヨットの経験を生かした流体力学理論と脳機能解析における統計の習熟についての論述、さらにはドイツ語学習とMatlab学習の深い関連性まで、簡にして要を得た流れるような文章に、原著論文さながらの注がつけられることで、学術的な深みも確保された短報となっている。難を言えば加藤博士が激務の合間に獲得されたと日本の我々に伝えられている休暇の量と質への言及がないことだが、そこまで追及するのは無粋というものであろう。他に例を見ない優れたこの留学記に、さらにここで解説をつけるのは蛇足と思われる。副題の謎めいた「ブーメラン」という単語の解読を含め、ぜひ原文をお読みください。臨床精神医学2014年11月号掲載。もちろん日本語で書かれている。
(村松太郎、2014.11.21.)
マキャベリ的知性と前頭葉眼窩面におけるドーパミンD2受容体
森口翔(慶應義塾大学医学研究科大学院博士課程)Dopamine D2 Receptors in the Orbitofrontal cortex and the Machiavellian intelligence
Moriguchi S, Yamada M, Mimura M, Suhara T
The 10th International Symposium on Functional NeuroReceptor Mapping of the Living Brain May 21 – 24, 2014, The Netherlands
神経心理学研究室所属の大学院博士課程2年目の森口です。
私は主にPET (positron emission tomography)を用いた研究をしており、現在は心理評価とPETを用いて脳のどの部位がその心理と関連しているかということについて研究しております。内容はといいますとマキャベリ的知性とドーパミン機能との関連です。マキャベリ的知性の測定はマキャベリの著書である『君主論』からリーダーとなる資質を備えた特徴を抽出しそれをもとに各被験者のマキャベリ度合いを測定します。そしてそのマキャベリ度合いと各被験者のドーパミン機能をPETにて測定したという内容です。こちらに関しましては、まとまり次第改めてご報告させて頂ければと思っております。
今回、この「マキャベリ的知性とドーパミン機能」をNeuro Receptor Mapping 2014という学会で発表してきました。
そこでは心理機能とPET研究で有名な先生と話をする機会もあり緊張しました。海外の学会だと旅費などでお金はかかりますが、世界の研究者の意見を聞けるという意味で国際学会への参加は有意義だと思います。大学院生ですと臨床を行っていた頃よりも休みが取りやすいため国際学会などへの参加も比較的しやすくなります。また、学会ではその学会自体も勉強になるのですが、学会前にセミナーやプレコースなどが開催される事が多く、基本的なことも体系的に学ぶことができます。臨床を常勤でやっていた頃には病棟を長期間あける事が出来ず、学会の一部に参加するのみでこのようなセミナーに参加することは中々出来ませんでした。
もちろん臨床は大切ですし、アイデアの基礎になる重要なものですが、一度大学院で自分の臨床経験を整理するということも貴重な経験だと思います。
もし興味がございましたら是非神経心理学研究室で一緒に勉強しましょう。
(森口翔、2014.10.14.)
解説 様々な知性の形
頭が良いとはどういうことか。知性的とはどういうことか。知能が高いとはどういうことか。そもそも知能とは何か。
「知能検査で測定されたもの、それが知能である」
無意味と言いたくなる答えだが、一面の真理である。つまりは今、知能を定義することは出来ず、知能検査とされている検査バッテリーの成績であるIQを、一応は「知能」と呼ぶという約束事があるにすぎない。
だからIQが低くても優れた能力を持っている人はたくさんいるし、逆にIQが高くても実社会での能力が優れていない人はたくさんいる。人間の能力は、知能検査では測定できない様々な認知機能から成り立っているのだ。
その一つがマキャベリ的知性である。
「マキャベリ」とは、「君主論」の著者であるニッコロ・マキャベリ(1469-1527)に由来する。「マキャベリ的知性」は、近年のパーソナリティ研究で注目を集めている概念で、主として人を操作するうえで必要な知性を指す。この操作とは、いわゆる非道徳的なものも含む。人を騙す、媚びるなどのテクニックを駆使してでも、人を操作し、自らの目的を達成しようとする、そうした能力に長けている人が「マキャベリ的知性が優れている」と呼ばれる。
非道徳的なものを含むということは、マキャベリ的とは悪い性格であるという解釈もできることになる。だが、「憎まれっ子世にはばかる」のは今も昔も同じであるし、君主とまではいかなくても、集団のリーダーには多かれ少なかれマキャベリ的な傾向がある。マキャベリ的知性がなければ、リーダーとしての適性は不十分ということになろう。平均人の「道徳」は、リーダーという立場の人にそのままは適用できないのである。
森口翔大学院生は、PETを用いて、マキャベリ的知性と脳内ドーパミン活動の関連を追究し、オランダで開催された国際学会で発表することによって、世界の研究者と交流する機会を得た。学会発表は登山でいえば中腹であり、この研究結果の国際的な一流誌への論文発表が待たれるところである。
(村松太郎、2014.10.21)
前頭前野損傷後の展望記憶障害
梅田聡 (慶應義塾大学文学部教授)Umeda, S., Kurosaki, Y., Terasawa, Y., Kato, M., & Miyahara, Y.(2011) Deficits in prospective memory following damage to the prefrontal cortex. Neuropsychologia, 49, 2178-2184.
未来に実行すべき予定や約束などの記憶は,展望記憶(prospective memory)と呼ばれる.展望記憶の障害は,健忘症,認知症および前頭葉損傷において顕著であり,記憶障害の重篤度や認知症の進行程度の把握においても重要な意味を持っている.
展望記憶の想起には,2つのタイプの処理要素が含まれる.
ひとつは「何か行うべき行為がある」ということの想起(存在想起)であり,想起の自発性やタイミングが必要とされる要素である.
もうひとつは,「具体的に何を行うか」ということの想起(内容想起)であり,手帳などの記憶補助に依存することのできる要素である.
これまでの研究から,内容想起の神経基盤については,海馬をはじめとするパペッツ回路内の脳部位の関与が指摘されている.一方,存在想起の神経基盤については,前頭葉の関与が指摘されてものの,詳細な部位については明らかにされていない.
そこで,74例の脳損傷例を対象として,番号札課題と呼ばれる課題を用いて,脳内のいずれの部位の損傷が存在想起のパフォーマンス低下を生み出しているかという点について検討した.
その結果,存在想起のパフォーマンスに影響を与える部位として,1) 右前頭前野背外側部,2) 右前頭前野腹内側部,3) 左前頭前野背内側部,の順に深い関与が認められた.これらの部位はいずれもブロードマンの10野に位置しており,前頭前野の先端部周辺が,自発的な意図の想起を可能にする処理を担っているものと考察された.
(梅田聡、2014.9.3.)
解説 未来の記憶
岡本太郎の『明日の神話』は、渋谷駅、井の頭線とJRの連絡通路にある巨大な壁画である。常に人々で溢れる場所に設置されたこの作品には、原爆の炸裂する瞬間が大胆な色彩と構図で描かれている。人類の悲劇をストレートに描いた芸術作品としては、ピカソの『ゲルニカ』が有名だが、この二つの作品の際だった違いは、そのタイトルにある。『明日の神話』とあえて逆説的なタイトルをつけた岡本太郎は、悲劇を悲劇としてだけ捉えるのではなく、未来に向かって燃え上がる人間の誇りをこの作品にこめたとされる。
「神話」という言葉には遠い過去のものというイメージがあるが、いかに神話とはいえ、それが作られた時点においては現代であり、これから作られる神話は未来の神話、明日の神話だ。
梅田聡教授(慶應義塾大学文学部心理学専攻)の論文のタイトルにある『展望記憶』とは、未来についての記憶である。
「記憶」とは、「思い出す」ことによって目に見えるものとなり、「思い出す」対象は過去のものに限ると考えがちであるが、人間には未来の記憶もある。予定を思い出すこと。まえもって予定していたことを、適切なタイミングで思い出し実行すること、そのための記憶が展望記憶である。社会で生活していくうえで、予定を正確にこなすことが大切なことは言われるまでもなく明らかで、事実、脳損傷者の社会復帰においては、過去の記憶よりもむしろ未来の記憶、すなわち展望記憶の障害がバリアになることはよく指摘されている。
展望記憶は、専門的にみるとかなり複雑な構造を持ち、非常に多くの要因がかかわっている認知機能であるが、「存在想起」(予定があったという事についての想起)と「内容想起」(その予定が具体的に何であったかという事についての想起)という二つの過程に分節するという発想が、展望記憶の研究を加速した。(梅田聡、小谷津孝明: 展望記憶の理論的考察. 心理学研究 69: 317-333, 1998)
本論文、『前頭前野損傷後の展望記憶障害』は、展望記憶の二つの要素のうちの一つである存在想起に前頭前野の先端部周辺が強くかかわっていることを、巧妙な神経心理学的検査とニューロイメージングの組み合わせによって示した研究である。
脳内の関連部位が明確に示されたことで、展望記憶の理論的研究、さらには認知リハビリテーションの方略は、さらに大きく発展するであろう。
一般に、過去の出来事をよく思い出せない人は「記憶力の悪い人」と呼ばれるが、約束などをすっぽかしてしまう人は「信頼できない人」と呼ばれる。認知機能の障害という観点からは、過去についての記憶障害も未来についての記憶障害も差異化することは出来ないはずだが、展望記憶障害は、このように不当ともいえる評価を受けがちである。同様のことは、多くの認知機能障害にも共通する事情である。神経心理学的研究の進歩によって、人間の認知機能の実像が明らかになっていくにつれて、障害者への偏見も解消していくことが期待される。
渋谷駅の雑踏の中にそびえる『明日の神話』のように、医学研究もすべての人に開かれたものになって初めて、その真価が発揮されると言うべきであろう。
(村松太郎、2014.9.24.)
統合失調症の「過大な自我」のSense of Agency タスクによる評価
是木明宏 (慶應義塾大学医学部大学院博士課程)The ‘Exaggerated Self’ in Schizophrenia evaluated using the Sense of Agency task (Keio method, trial-by-trial ver.)
Koreki A, Maeda T, Fukushima H, Okimura T, Takahata K, Umeda S, Iwashita S, Kato M, Mimura M
ASSC (Association for the Scientific Study of Consciousness) 17
San Diego, CA; July 12-15, 2013.
統合失調症ではsense of agency(SoA)の異常があることは当教室の研究を含めて今までに示されてきた。SoAの成立機序として、「予測」と実際の感覚フィードバックが一致するかどうかというForward model(一致すれば自分がやったと感じる)が提唱されているが、統合失調症では「予測」の異常があると先行研究で指摘されている。しかしその「予測」の異常がどのようなものか、またその異常がSoAにどのように関わってくるかは明らかではなかった。
今回の研究では、慶應独自のSoA課題を改変して行うことで、統合失調症患者の「予測」が「遅れている」可能性を示すことができた。さらにその「予測」の遅れが実験上での過剰なSoAに繋がる可能性も示された。この過剰なSoAは統合失調症の関係妄想を説明しうる。しかし一方で幻聴やさせられ体験は説明できない。「予測」が遅れる分、Forward modelに基づけば感覚フィードバックと一致しなくなりSoAが低下すると考えられ、これが幻聴やさせられ体験に繋がるとも考えられるが、今後はさらなる検証が必要である。
(是木明宏、2014.8.1.)
解説 統合失調症の自我障害を客観化する
タイトルの「過大な自我」とは、統合失調症の臨床症状として見られる、「中東で戦争が起きたのは自分が○○をしたからだ」など、自分が外界に影響を及ぼしているという形で体験される自我障害を指す。統合失調症では他方、させられ体験や幻聴による命令のように、外界から自分に影響が及んでいるという体験、いわば「過大な自我」に対して「弱化した自我」といえる自我障害もある。これら症状は自我の境界の異常という共通点はあっても、現象としては正反対の性質を持っている。このような自我障害は、統合失調症の症状の中核として、サイエンスの手の届かない難問中の難問としての地位を保ち続けて来ていた。
是木明宏大学院生はこの自我障害に切り込んだ研究をサンジエゴのASSC (Association for the Scientific Study of Consciousness)でポスター発表し、Student Poster Awardを獲得した。
ASSCは、精神医学のみならず、神経科学、認知科学、心理学、哲学など、様々な分野の専門家が参集する、「意識」に関する学会である。今回の受賞は、統合失調症の症状への学際的な注目という観点からも、大きな意義を有するものである。
この研究で用いられたツールは、当研究室の前田貴記講師が中心となって開発したSense of Agency Task (SoAタスク)(本サイト 2014.3 前田講師『統合失調症の自我障害についての実証的研究』参照)である。是木院生は前田講師の原法を改変し、一試行ごとに時間バイアスを調整するという巧みな手法を用い、統合失調症における「過大な自我」がどのように形成されるかについて行動実験的に示すことに成功した。
是木院生は、行動実験にとどまらず、ニューロイメージングも駆使しての統合失調症の神経基盤の解明を研究テーマとしており、現在、慶應の関連病院である駒木野病院(東京都八王子市)に併設されている精神医学・行動科学研究所にて、SoAタスクを用いた機能的MRI(fMRI)研究、DTI (Diffuse Tensor Imaging)研究が進行中である。さらなる発展と成果が期待される。
(村松太郎、2014.8.24.)
逆きつね検査を用いた、軽度アルツハイマー病における頭頂葉機能低下による視空間機能障害の検出について
田渕肇(慶應義塾大学医学部精神神経科講師)Tabuchi H, Konishi M, Saito N, Kato M, Mimura M.
Reverse Fox test for detecting visuospatial dysfunction corresponding to parietal hypoperfusion in mild Alzheimer’s disease.
Am J Alzheimers Dis Other Demen. 29 (2) :177-182, 2014.
アルツハイマー病では緩徐に進行する記銘力障害がよく知られているが、視空間認知機能の低下も病初期から認められる(記憶障害に先行して生じるとの主張もある)。今回我々は、模倣による新しい手指構成検査(逆きつね検査)により軽度アルツハイマー病患者の視空間認知機能を評価し、診断における有用性を検討した。
逆きつね検査は約1分程度の簡便な検査である。まず検査者は両手でそれぞれ、親指先を中指先・薬指先とくっつけ、人差し指と小指をまっすぐに伸ばし、いわゆる影絵で使われる「きつね」の形を示す。さらに検査者は片方の手をひねり、右手の人差し指と左手の小指、左手の人差し指と右手の小指をくっつけて、「逆きつね」の形を作り、被験者に模倣するよう指示する。
慶應義塾大学病院メモリークリニックに通院している65〜89歳の軽度アルツハイマー病患者47名(Clinical Dementia Rating 0.5ないし1、平均年齢77.9 + 5.2歳)、認知機能正常の対照群18名(平均年齢75.1 + 5.2歳)を対象とした。アルツハイマー群では逆きつね検査の成功率は31.9%、対照群では94.4%であった。またアルツハイマー群において、逆きつね失敗群15名(平均年齢78.7 + 5.1歳)は成功群32名(平均年齢77.6 + 5.2歳)と比べて記憶・遂行機能などに関する検査結果に差がみられなかったが、脳血流検査において後部帯状回・楔前部を含む頭頂葉領域および側頭葉領域での血流低下を認めた。
近年、アルツハイマー病に関する診断基準が四半世紀ぶりに改訂され、髄液検査やアミロイドイメージングなどの画像検査が推奨されている。しかしこれらの検査を実施できる施設は限られており、通常の診療現場での診断では、臨床症状や神経心理学的検査結果などが重要となる。特徴的な症状を簡便かつ効果的に捉えることができる検査は、特に外来診療などでは有用な診断補助ツールとなると考えられる。
(田渕肇 2014.7.2)
解説 ベッドサイドからニューロイメージングへ
両手でそれぞれ「きつね」を作る。誰でも知っている影絵のきつねである。そして一方のきつねをひねって反転させ、二つのきつねを逆につなぐ。これだけである。これが「逆きつね検査」だ。初期のアルツハイマー病を診断するための、昔からある検査である。ローテクといってもいい。伝統的といってもいい。シンプルといってもいいし、簡便といってもいい。施行には何もいらない。手があればできる。短時間でできる。誰でもできる。そして信頼度は高い。だがメカニズムは不明だった。
田渕講師はこの伝統的な検査のメカニズムを、美しい論文に仕上げて発表した。論文の図は二つのみ。逆きつね検査の写真と、SPECTの画像である。この二つの図の関係をストレートに示した、明快なメッセージを伝える論文である。
ベッドサイドのローテクから重装備のハイテクまでを駆使するのが、現代の精神科診断である。両者の結合が診断には不可欠である。脳の機能画像はそれ自体では単なる統計結果の描画にすぎず、精密な臨床症状の分析と結合した時はじめて命が吹き込まれる。逆に、伝統的なベッドサイドの検査も、脳内メカニズムとの関連性が示された時はじめて科学性を獲得する。逆きつね検査というローテクとSPECTというハイテクを綺麗に結合させたこの仕事は、田渕講師の学位論文となった。
フィールドとなったメモリークリニックは、2008年、神経内科と精神神経科との共同運営で慶應義塾大学病院に開設された完全予約制のクリニックである。初診は、初期認知症、あるいは発症前の認知症が主で、これら対象者の早期診断・早期介入に大きく貢献するとともに、近未来の高齢化社会に向けての貴重な研究データが次々に生まれている。
なお、メモリークリニックの解説書として
『メモリークリニック診療マニュアル
鹿島晴雄/鈴木則宏 (監修), 田渕肇/伊東大介 (編集) 南江堂 (2011年発刊)』
がある。
(村松太郎、2014.7.21.)
日常生活上の行動障害と健忘を合併した広範な前頭葉挫傷の1例
— 追報告 受傷後24年 —
猪股裕子 (平川病院 言語聴覚士)第23回認知リハビリテーション研究会 2013年10月5日 東京
猪股裕子、平川淳一、浪岡政美、森山泰、梅田聡、加藤元一郎
【症例】50歳代、男性。X-22年、3階から転落し脳挫傷受傷、開頭血腫除去術実施される。以後、健忘、乱費、借金、アルコール乱用、暴言、片付けができないなどの行動異常あり。X-14年、生活の破綻とアルコールの問題でK病院 に入院し、入退院を繰り返しながら治療。X年当院受診し、アルコール治療と認知リハビリテーション開始。当初知的機能は比較的保たれていたが、前向性記憶(近時記憶、時間的序列、展望記憶など)の問題、及び言語性ワーキングメモリー容量の低下、注意障害(分配性・転換、転導性の問題)、遂行機能障害、前頭葉症状(固執傾向、柔軟性低下、被刺激性亢進、判断力低下、問題解決能力低下、脱抑制的、病識低下など)、顕著な日常生活上の行動障害がみられていた。MRI T2強調画像で、両側前頭葉広範囲に渡る低吸収、軽度の萎縮、脳室拡大を認めた。
地域関連機関と連携しながら、約2年に渡り記憶訓練(基礎訓練、アラーム訓練、外的補助手段活用)、注意力訓練、問題解決訓練、遂行機能訓練、生活面の支援プログラム(金銭管理訓練、問題行動に対するアプローチ他)を実施、経過中‘気づき’が増加し、僅かながらも社会生活におけるスキルや行動変容が図れてきた。神経心理学的検査上14年前の評価に比し、知的機能や記憶は大きな改善はみられなかったが、注意、前頭葉機能、遂行機能で若干変化が得られ、行動面にも変化がみられたため、X+2年、リハビリを終了した。
気づきに関しては、前頭葉機能の改善が自己認識力や日常活動の改善に寄与していることが考えられた。また、行動の変容が図れたことから、慢性期でも介入した意味があったと考えた。
(猪股裕子、2014.6. 20)
解説 24年間のフォローアップ
超慢性期における脳損傷者の認知機能や認知リハビリテーションの効果についてのデータは文献中にもほとんど存在しない。一つのケースを20年以上にわたってフォローアップすることは現実的には非常に困難なのである。しかもこのケースでは、前頭葉損傷の症状としての脱抑制が乱費や暴言やアルコール問題として顕在化しており、認知リハビリテーションのプログラムにのせること自体に大変な苦労が要求され、治療者の消耗によるフォロー中断の危機が常に存在する。
猪股裕子言語聴覚士は、このような数々の悪条件を乗り越えて熱心にケースに接し、超慢性期においても認知リハビリテーションが一定の有効性を持つことを示した。さらに神経心理学的検査成績を14年前と比較し、改善する機能と改善しない機能を峻別して日常生活機能との関係を論じた。
このケースの14年前のデータは、駒木野病院の森山泰博士が1999年の神経心理学会で発表したものである。森山博士も当研究室のメンバーであり、慶應神経心理学研究室の層の厚さと協力体制があって得られた貴重なデータであるといえよう。
様々な脳損傷によって障害された認知機能を回復させんとする試みが認知リハビリテーションである。実効果ある認知リハビリテーションのためには、精密な神経心理学的評価によって、その対象者において失われている機能と残存している機能を正確に把握することが必要条件で、現在では認知リハビリテーションは臨床に直結した応用神経心理学の一分野となっている。
猪股言語聴覚士がこの研究を発表した認知リハビリテーション研究会http://reha.cognition.jp/は、一般演題の発表時間が20分と他の学会に比して2倍以上に長く、認知リハビリテーションの実践について広く深い議論が可能な設定になっている。
1995年、当時慶應神経心理学研究会を主宰していた鹿島晴雄客員教授(現)を中心に設立された、まさに臨床家・実践家のための研究会である。会員の内訳は医師が25%、コメディカルが75%で、現在事務局は当教室内に置かれている。
次回すなわち第24回認知リハビリテーション研究会は2014年11月1日、東京の研究社英語センター大会議室で開催される。
(村松太郎、2014.6.21)
logopenic型進行性失語から失行および意味記憶障害への展開
船山道隆(足利赤十字病院 神経精神科 部長)Funayama M, Nakagawa Y, Yamaya Y, Yoshino F, Mimura M, Kato M.
Progression of logopenic variant primary progressive aphasia to apraxia and semantic memory deficits.
BMC Neurol 13: 158, 2013.
近年、脳画像の発展や相次ぐ新しい病理所見の発見によって変性疾患に伴う進行性失語は注目を集めている。進行性失語は、非流暢性/失文法型進行性失語、意味型進行性失語、logopenic型進行性失語の3類型に分類できる。病初期には失語が中核症状であるが、変性疾患であるため徐々に失語以外の症状も呈するようになる。非流暢性/失文法型は経過とともにアパシー、対人関係の問題、脱抑制、常同行為、共感の乏しさ、自己洞察の乏しさなどが、意味型は意味記憶障害、共感の乏しさ、興味の狭小化および特定の事柄への没頭などと、両者とも主に社会行動面での問題が出現してくる。一方で、近年概念化されたlogopenic型の長期予後については、今までに報告はほとんどなされていなかった。
今回われわれは、発症から8年以上経過したlogopenic型進行性失語の3例(男性2例、女性1例)を報告した。3例とも50代発症であり、SPECTでは左側を中心とした側頭-頭頂葉接合部を中心に相対的血流量の低下を認めた。3例とも初期にlogopenic型進行性失語を呈し、数年後から観念運動失行、さらに概念失行が出現し、発症後5~9年後には家族や親戚が認知できない人物認知の障害や異食症が出現した。エピソード記憶障害は3~4年ほど経過してから出現したが、本3症例の中核症状ではなかった。この経過は、失語から失行、さらに意味記憶障害に至ったとまとめることができた。
近年の神経病理研究からは、logopenic型進行性失語の約2/3がアルツハイマー病であることが判明している。われわれの症例は、昔から言われている失語・失行・失認を伴いやすく経過が早い若年発症のアルツハイマー病であった可能性が高い。本研究から推察すると、logopenic型進行性失語の一部は、このタイプのアルツハイマー病である可能性が高い。
(船山道隆、2014.5.8.)
解説 精神疾患解明の真髄
Logopenic型進行性失語。聞き慣れない病名だ。まず “logopenic”。ロゴ・ペニック。logo-は「言葉」、penicは「不足」を表すギリシア語である。「進行性失語」とは、何年もかけて徐々に症状が進んで行く失語症である。失語症といえば脳血管障害によるものが典型的だが、脳血管障害によるものでなく、かといって脳炎や脳腫瘍などでもなく、徐々に言葉が失われていく経過を取るケースがある。最初の報告は1892年のピック Pick によるものだが、20世紀後半になってこうした症例が続々と報告されるようになった。これが進行性失語である。原因は不明だ。不明の原因により、脳のある部位から萎縮が始まるのだ。始まりは、言語にかかわる部位のごく一部から。そして徐々に言語中枢を侵す。さらには脳全体に萎縮が及ぶこともある。
Logopenic型進行性失語は、第三の進行性失語と呼ばれる新しい概念である。言語症状としては、特に復唱の障害が目立つのが特徴だ。加えて高度に専門的な言語症状分析により、一つの疾患単位としてまとめられた。21世紀に入ってからのことだ。だが経過は不明であった。徐々に進行するというが、どのくらいの速度で進行するのか。言語以外の症状はどのように推移するのか。最終像はどうなるのか。既存の変性疾患の中に分類できるのか。これらはすべて不明であった。「logopenic型進行性失語から失行および意味記憶障害への展開」と題された船山論文は、8年間という長期にわたって3症例を綿密に観察し、この問いに対する答えを提示したものである。
長期経過の研究がなぜ必要なのか。もちろん一つには、患者さん本人や家族のためである。そしてもう一つは、疾患の本質の洞察のためである。症状とは、点と線である。点とは横断面、すなわち、ある一時期を切り取った時に、そこに見られる症状。線とは縦断面、すなわち長期経過だ。操作的診断基準が席捲している現代の精神医学では、点だけが過剰に重視されている。もちろん点も重要である。点の把握だけでも、容易なことではない。失語症の言語症状分析と同等の高度な診断技術が、どんな精神疾患の横断面の症状の把握においても求められる。しかし如何に精密に分析しても、点だけを見ていたのでは限界は明らかだ。点と線が揃って初めて、疾患の本質に接近することができる。脳器質疾患の症候を精密に分析するという、神経心理学で綿々と継承されている方法論は、精神医学の本来の診断学そのものである。
船山部長は、logopenic型進行性失語症の症状を精密に分析し、さらには長期経過を明らかにすることにより、この疾患の原因論としてのアルツハイマー病との繋がりを示した。「logopenic型進行性失語症の少なくとも一部は、若年型アルツハイマー病である」
結論として示唆されているのは、あくまでも淡々とした事実だ。だがそれを示した船山論文は、精神疾患の真の解明方法はこうあるべきだというモデルを見事に実践してみせた仕事である。
(2014.5.27. 村松太郎)
脳損傷後にみられた芸術的能力の開花に関する研究
高畑圭輔 (放射線医学総合研究所 博士研究員)Takahata K, Saito F, Muramatsu T, Yamada M, Shirahase J, Tabuchi H, Suhara T, Mimura M, Kato M.
Emergence of realism: Enhanced visual artistry and high accuracy of visual numerosity representation after left prefrontal damage.
Neuropsychologia 57: 38-49, 2014.
精神医学においては、疾患による認知機能の低下や異常など、主に障害としての側面が強調されています。これは、医学として当然のことですが、一方で、脳損傷や前頭側頭葉変性症(FTLD)を発症した後に、特定の能力が向上する例が稀ながら存在することが、神経心理学の分野で古くから報告されてきました。このような、精神神経疾患によって引き起こされる、逆説的とも言える現象は「獲得性サヴァン症候群」と呼ばれており、優位半球の前頭葉の局在病変によって生じることが多く、絵画や造形などの視空間認知に関連した芸術的技能で開花する例が多いことが知られています。近年、獲得性サヴァン症候群に関する報告が、国内外で相次ぐようになりましたが、脳局在機能の障害により芸術的技能が向上する機構は長らく不明のままでした。特に、芸術的技能の中でも写実能力が向上した症例が多いという点は、獲得性サヴァン症候群にまつわる謎とされていました。
本研究は、加藤元一郎先生のご指導の下、大学院時代に行われたもので、左前頭前野の損傷後に絵画能力が亢進した症例においてサヴァン様の機能亢進の背景機構を探った研究です。以前から、我々は「優位半球の前頭葉が損傷することにより、同部位が抑制していた非優位半球の後部脳の機能が解放されることによって写実能力が亢進する」のではないかと考えておりました。今回、幸いにも患者さんにご協力して頂けることになり、神経心理検査、認知心理課題、脳血流シンチ、専門家による絵画技能の評価などの複数の手法を組み合わせることによって仮説の検証を行いました。詳しい結果については、論文を参照して頂ければと思いますが、患者さんにおいて前頭葉機能の低下にも関わらず写実的な描画技術が高まっていたこと、健常対照群よりも正確な数量弁別能を示したこと、非優位半球の頭頂葉の血流が亢進していたことなどが確認され、我々の仮説が支持されることが示されました。
本研究の成果は、獲得性サヴァン症候群の病態解明につながるだけでなく、脳損傷や認知症患者さんのリハビリテーションにも役立てられるのではないかと考えています。今後、症例を積み重ねてさらなる検討を加えていきたいと考えています。
(高畑圭輔、2014.4.9.)
解説 覚醒する才能
脳が損傷されれば、脳の機能は損われると思うであろう。
多くの場合はその通りである。ところが、稀ではあるが、脳損傷によって逆に特定の脳機能が活性化することがある。眠っていた才能が開花するといってもよい。それが獲得性サヴァン症候群と呼ばれる現象である。
サヴァン症候群とは、一種の天才である。19世紀に、先天的な知能低下を持ちながら特定の領域(たとえば記憶力)に突出した能力を持っている複数のケースが「idiot-savant(白痴の天才)」と名づけられて発表されたのが最初である。有名なサヴァンとして、映画『レインマン』のモデルとなったキム・ピークを挙げることができる。彼は深刻な中枢神経系の異常が存在するにもかかわらず、過去に読んだ約9,000冊の書物の内容を正確に暗記しているという驚異的な記憶力を具えたサヴァンとして知られている。
サヴァン自体、稀な疾患であるが、獲得性サヴァン症候群はさらに稀である。獲得性サヴァンとは、成人になってから何らかの脳損傷を被った結果、何らかの優れた機能が現われるケースを指す。なぜこのような現象が起きるかは謎であった。これまでLancetなどにごくわずかな症例報告があるが、いずれも「獲得性サヴァン症候群というケースが存在する」という記述のレベルを超えるものではなかった。
高畑博士が2014年にNeuropsychologiaに発表したこの論文は、獲得性サヴァンの謎に挑んだものである。提示されているのは、脳損傷の一例についての詳細な検討で、この男性は脳血管障害で左前頭葉に損傷を負った後、見事な絵が描けるようになった。そこで、
・脳血流の測定
・前頭葉機能、視覚的数量認知課題等の神経心理学的検査
・脳損傷前に描いた絵と脳損傷後に描いた絵の質の比較(東京藝大の27人の専門家に定量的評価を依頼。結果は、「写実性」「色彩」の項目が、脳損傷後に改善)
などを行った結果、右前頭葉、楔前部、頭頂間溝の血流増加が、描画能力等に関連することが証明された。長年にわたり謎であった獲得性サヴァンの脳基盤の解明に明るい光が差したのである。
この高畑博士の論文は、
The human species is the sole animal that can draw a picture.
(人類は、絵を描く唯一の動物である)
という一文から始まっている。
人間だけが持つ、絵を描くという機能。高度に複雑化した人間の脳が可能にした機能は、ほかにも数限りなくある。その脳の奥底にあった機能が、左前頭葉の損傷によって開花したというのが、この高畑論文の主旨である。
進化の過程で静かに眠りにつき、タイムカプセルのように覚醒を待っている才能が、おそらく人間の脳にはまだまだあるに違いない。
(村松太郎、2014.4.23.)
統合失調症の自我障害についての実証的研究
前田貴記(慶應義塾大学医学部精神神経科講師)Maeda T, Takahata K, Muramatsu M, Okimura T, Koreki A, Iwashita S, Mimura M, Kato M.
Reduced sense of agency in chronic residual schizophrenia with predominant negative symptoms.
Psychiatry Research, 209(3): 386-392,2013
統合失調症において、自我障害は中核的な症状と考えられている。近年、認知科学において自己意識を研究するパラダイムとして、sense of agency (SoA)が発展してきており、その側面から、統合失調症の自我障害についても検討されてきている。我々も、統合失調症におけるSoAについて実証的に評価するために独自のタスクを考案し研究をすすめてきた。本論文では、慢性期で陰性症状が前景の統合失調症において、SoAが低下していることを示したものであり、臨床的にはとらえにくいものの、陰性症状が強い患者においても自我障害が潜在していることが、実験的には示された点で重要である。慢性期で陽性症状が前景の統合失調症においてもSoA異常がみられるものの(Maeda et al., 2012)、異常パターンは陰性症状群とは異なっている。以上より、SoA異常は、統合失調症のtrait & state markerとしての意義があるかもしれず、今後、急性期、さらには前駆状態(schizotypal personality disorderを含む)について検証していきたい。
(前田貴記, 2014.3.12.)
解説 統合失調症の謎を解く: 精神病理学と脳科学の出会い
幻聴、妄想、思考障害、・・・統合失調症の症状として挙げられるものは数多くあるが、それらの基底にあるとされるものが自我障害である。従来、記述的な精神病理学の領域だけに棲息していたこの自我障害をサイエンスの対象とし、統合失調症の本質に迫るのが前田貴記講師のテーマで、そのために彼が中心となって開発したツールがSense of Agency Task (SoAタスク)である。
Sense of Agencyとは日本語では自己主体感と呼ばれており、健常者にとっては自分の思考や行動の主体(agency)が自己であると認識されるのは当然すぎるほど当然であるが、統合失調症ではこの認識が崩れたり、さらには外界の現象の主体が自己であると認識されたりする。これがSense of Agencyの異常である。
たとえば、統合失調症の症状であるさせられ体験は、自己の行動が他者にコントロールされると感じられるもので、まさにSense of Agencyの異常である。また、統合失調症の最も代表的な症状ともいえる幻聴も、元々は自らの脳内に発生したものであるはずの思考や声が、他者のものとして感じられるものととらえれば、やはりSense of Agencyの異常であるといえる。
前田講師が中心となって開発したSoAタスクは、ベッドサイドで簡便に行える検査で、パソコンのディスプレイ上の光点の動きが、自分自身のキー操作によるか否かの主観的判断を問うことによって、Sense of Agencyをみるものである。このタスクのデビューは2012年の論文:
Maeda T, Kato M, Muramatsu T, Iwashita S, Mimura M, Kashima H.
Aberrant sense of agency in patients with schizophrenia: forward and backward over-attribution of temporal causality during intentional action.
Psychiatry Res. 2012 Jun 30;198(1):1-6.
である。
本論文 Reduced sense of agency in chronic residual schizophrenia with predominant negative symptoms. はそれに続く第二弾に位置づけられるもので、統合失調症におけるSoA減弱を実証的に示した世界初の論文である。
一方で、SoAタスク施行時の脳内活動をfunctional MRIで示した論文、
Fukushima H, Goto Y, Maeda T, Kato M, Umeda S.
Neural substrates for judgment of self-agency in ambiguous situations.
PLoS One. 2013 Aug 19;8(8):e72267.
も2013年に刊行している。
SoAタスクを用いたこれら一連の研究は、自我障害という、統合失調症の中核ともいえる症状、しかし従来はサイエンスの対象になりにくかった症状を、実証的研究の射程に捉えたという点ひとつをとってみても、非常に大きな意義を有するものである。近い将来には、統合失調症の前駆状態の正確な評価への応用も期待される。
なお、統合失調症の自我障害の現在を前田講師が解説したものとして、
日本統合失調症学会監修『統合失調症』
第24章統合失調症の自我障害の認知科学
がある。(2013.6 発刊)
(村松太郎, 2014.3.30.)